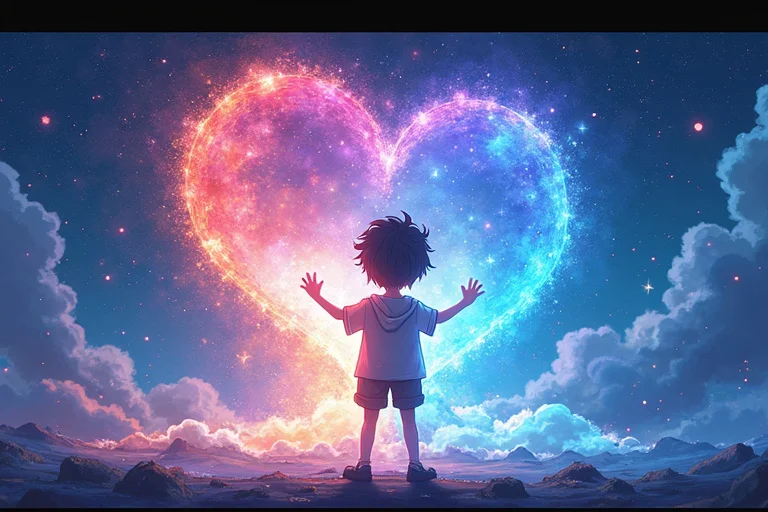「で、結局、出し物は『可もなく不可もなきタピオカ屋』に決まりそうだけど、異議ある人ー?」
退屈が凝固したような放課後の教室で、やる気のない級長が死んだ魚のような目で言った。誰も手を挙げない。僕、高槻蓮も、窓の外を流れる雲を眺めながら、まあそんなもんだよな、と心の中でため息をついた。高校二年の秋。僕らの青春は、どうやらタピオカミルクティーの甘ったるさと共に、平坦に過ぎていくらしい。
その沈黙を切り裂いたのは、一人の転校生だった。
「断固、反対します!」
凛とした声が響き、全員の視線が一点に集まる。教室の後ろの席で、転校してきたばかりの天野ミライがすっくと立ち上がっていた。腰まである黒髪、意志の強そうな瞳。非の打ち所のない美少女だが、その言動は初日から少し、いや、かなりズレていた。
「このままでは、未来が、世界が、取り返しのつかないことになります!」
ぽかんとするクラスメイトたち。級長が面倒くさそうに「天野さん、大げさだって」と呟く。だがミライは構わず、僕の方をまっすぐ見て言った。
「高槻蓮くん。あなたに協力してほしいんです。この『歴史上最も退屈な文化祭』を、『伝説の文化祭』に変えるために!」
名指しされた僕に、好奇と憐憫の視線が突き刺さる。勘弁してくれ。僕はただ、平穏に過ごしたいだけなんだ。
放課後、僕は親友の翔太と、なぜか文句を言いに来たクラス委員長の橘さんと一緒に、ミライによって物理準備室に連行されていた。
「単刀直入に言います。私は未来から来ました」
開口一番、ミライはそう言ってのけた。翔太が「おっ、そういう設定? 面白いじゃん!」と茶化し、橘さんはこめかみを押さえている。
「信じられないのも無理はありません。ですが、証拠はあります」
ミライが手のひらから小さな金属球を取り出すと、それはふわりと宙に浮き、ホログラムのスクリーンを投影した。そこに映し出されたのは、僕らの高校の、百年後の歴史書とされるデータだった。
『西暦2024年、〇〇高校の文化祭は、後世に『グレート・ボーリング・フェス』と揶揄されるほど無気力なものだった。この出来事は、人々の娯楽に対する情熱を著しく低下させ、後の『エンタメ禁止法』制定の遠因となった』
「……マジかよ」翔太が絶句した。
「そんなバカな話があるわけないでしょ!」橘さんは当然、信じていない。
僕も半信半疑だった。だが、目の前で浮遊するホログラムは、どう見ても現代の技術じゃなかった。
「だから、この文化祭を革命的に面白くして、歴史を修正する必要があるんです」ミライの瞳は真剣そのものだった。「私の計画はこうです――『校舎まるごと、メモリー・ギャラクシー計画』!」
彼女の計画は壮大だった。来場者から思い出の写真を提供してもらい、それをデータ化。僕らの教室がある校舎の壁面すべてをスクリーンに見立て、無数の写真を星のように投影し、巨大な銀河を作り出すというのだ。
「そんなの無理に決まってる!」と叫ぶ橘さんをよそに、翔太は「最高じゃん! やろうぜ、蓮!」と目を輝かせている。僕は、ミライの無謀な計画と、彼女自身の持つ不思議な引力に、抗うことができなかった。こうして、僕らのありえない文化祭準備が始まった。
まず問題になったのは機材だ。校舎全体に投影するなんて、プロジェクターが何台あっても足りない。ミライは「未来のジャンクパーツから自作します」と言い、どこからか持ってきたガラクタを半田ごて片手に改造し始めた。出来上がったのは、手のひらサイズの浮遊型プロジェクター。デザインもどこか有機的で、まるで生きているかのようだった。
最初は「どうせ無理だ」と遠巻きに見ていたクラスメイトたちも、準備室から漏れ聞こえる奇妙な音や、宙に浮かぶテスト映像を見て、一人、また一人と集まってきた。「何これ、すげえ!」「私にも手伝わせて!」気づけば、クラス全員がこの無謀な計画に夢中になっていた。
反対していた橘さんも、その熱気に巻き込まれ、いつの間にか教師や生徒会を説得するための完璧なプレゼン資料を作り上げていた。僕は記録係として、みんなの姿をカメラで追い続けた。徹夜で作業して笑い合う顔、うまくいかずに悩む横顔、そのすべてがキラキラと輝いて見えた。ファインダー越しに見るミライは、時々、遠い未来を思うような、少し寂しげな表情をすることがあった。
そして、運命の文化祭当日。
僕らの教室は、来場者の写真を受け付けるステーションとして大盛況だった。夕暮れ時、いよいよメインイベントの投影が始まる。僕らは固唾を飲んで校庭から校舎を見上げていた。
ミライがデバイスを操作する。「投影、開始します!」
しかし、何も起こらない。校舎は静まり返ったままだ。
「どうして……? システム、オールグリーンのはずなのに……」
ミライの顔から血の気が引いていく。その時、放送室から悲鳴が上がった。「機材が! 何者かに妨害電波を……!」
最悪の事態だった。ざわめく来場者、絶望するクラスメイトたち。僕らの革命は、始まる前に終わってしまうのか。ミライが「ごめんなさい……私の計算が……」と震える声で呟いた。
その瞬間、僕の中で何かが弾けた。
「まだだ! まだ終わってない!」
僕は叫んでいた。
「手動でやろう! アナログで!」
僕は自分のカメラを掲げた。この数週間、僕が撮りためた、みんなの写真があった。
「プロジェクターは一台だけ無事だ! あの壁に、僕らの物語を映し出すんだ!」
僕の言葉に、みんなの顔が上がる。翔太が「それだ!」と叫び、橘さんがマイクを掴んで来場者に事情を説明し始めた。クラスメイトが走り出す。即席のステージが作られ、壁に白い布が張られる。
そして、僕が撮った写真が、一枚、また一枚と壁に映し出された。
ハンダごてを握るミライ。難しい顔で資料を読む橘さん。バカみたいにはしゃぐ翔太。ペンキだらけで笑う女子たち。夜食のカップ麺をすする男子たち。計画通りの「記憶の銀河」ではなかった。でもそこには、僕らだけの、かけがえのない「青春の銀河」が広がっていた。
気づけば、校庭は静まり返り、誰もが壁に映る僕らの物語に見入っていた。最後の一枚が映し終わった時、割れんばかりの拍手が沸き起こった。
片付けが終わった屋上は、心地よい疲労感と達成感に満ちていた。夕焼けの空を見上げながら、ミライが僕の隣で言った。
「ありがとう、蓮くん。未来、変わったみたい」
彼女は自分のデバイスを見せてくれた。そこにあった『グレート・ボーリング・フェス』の記述は、綺麗に消えていた。
「どんな歴史になったかは、もう私にも分からない。ここからは、あなたたちが作る未来だから」
そう言うと、ミライは悪戯っぽく笑った。「じゃあね、またいつか、どこかの時間線で」
彼女の体が淡い光に包まれ、透き通っていく。僕は何も言えず、ただその光景を見つめていた。光が消えた後には、秋の風が吹くだけだった。
あれから半年。僕は写真部の部長になった。僕らの文化祭は、なぜか『手作り感あふれる感動のライブショー』として学校の伝説になっている。
時々、あの不思議な転校生のことを思い出す。
未来は変わったんだろうか。エンタメは守られたんだろうか。
確かなことは分からない。でも、ファインダーを覗くと、世界はあの頃よりずっと、ワクワクするものに見える。僕らの文化祭は、たぶん、歴史上なんかじゃなく、僕らの心の中で最高だった。それで十分じゃないか、と僕は思うんだ。