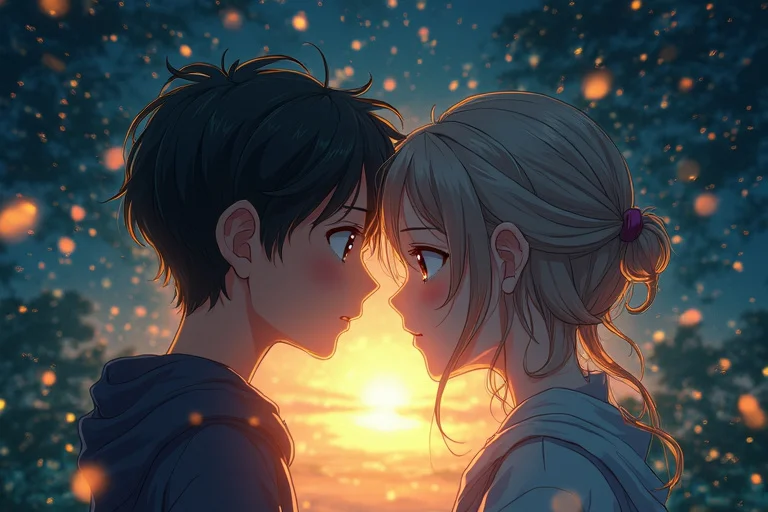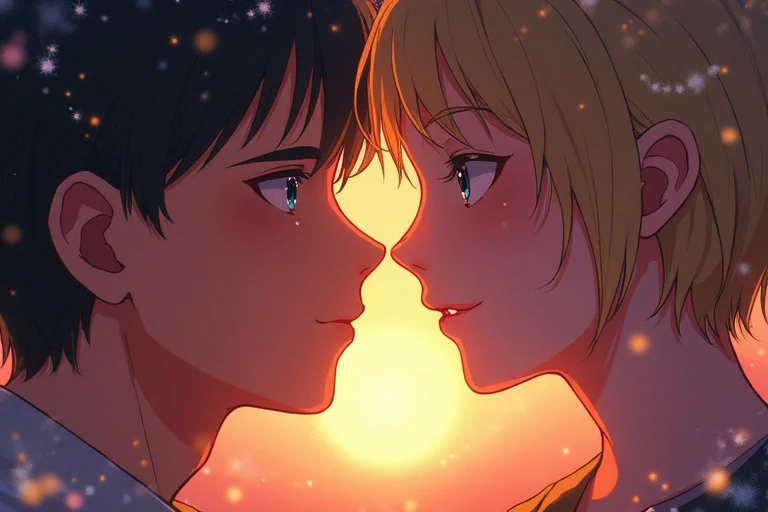第一章 未来を写すカメラ
高校二年の夏、俺、高宮蓮は死んでいた。もちろん、比喩的な意味でだ。心臓は動いていたし、呼吸もしていたが、魂は灰色の靄に包まれて動かなかった。所属する写真部の活動も、ただ惰性でシャッターを切るだけ。ファインダー越しに見える世界は、どれもこれも色褪せて、平板に見えた。
そんな俺の灰色の日々に、七瀬陽菜は突然、色の奔流のように現れた。
蝉時雨が降り注ぐ午後だった。錆びた鉄の匂いが立ち込める廃線跡は、俺のお気に入りの撮影場所だ。誰にも邪魔されず、世界の終わりみたいな静けさに浸れるから。三脚を立て、古びた枕木にレンズを向けていると、背後から鈴を転がすような声がした。
「面白いものが撮れる?」
振り返ると、麦わら帽子をかぶった少女が立っていた。同じクラスの七瀬陽菜。いつも教室の隅で、楽しそうに友達と笑っている、俺とは世界の違う住人。その手には、使い込まれた銀色のフィルムカメラが握られていた。
「別に。ただの暇つぶし」
素っ気なく答える俺に、彼女は気にもせず隣にしゃがみ込んだ。「ふぅん」と相槌を打ちながら、俺のデジタル一眼レフを覗き込む。
「すごいカメラだね。私のは、おじいちゃんのお下がり」
そう言って彼女は、宝物みたいに自分のカメラを掲げて見せた。そして、悪戯っぽく笑い、こう言ったのだ。
「でもね、これ、ただのカメラじゃないんだ。未来が写るの」
「は?」
思わず間抜けな声が出た。未来が写る? 馬鹿げている。俺の訝しげな視線を受け止め、陽菜はにっこりと笑った。
「信じてないでしょ。じゃあ、撮ってあげる」
言うが早いか、彼女は俺にカメラを向けた。カシャ、という乾いたシャッター音が、蝉の声に吸い込まれていく。
「うん、見えた」
「何がだよ」
「一年後の君の姿。大丈夫、ちゃんと笑ってたよ。今よりずっといい顔してた」
陽菜はそれだけ言うと、「じゃあね」と手を振り、風のように去って行った。残されたのは、錆びた線路と、俺の心に引っかかった小さな棘のような言葉だけ。未来が写るカメラ。くだらない。そう頭では分かっているのに、その日から俺の世界は、七瀬陽菜という鮮やかな光に侵食され始めた。
第二章 永遠の輪郭
陽菜の嘘に付き合うつもりはなかった。だが、彼女はまるで俺の行く先々を知っているかのように現れた。図書室で、通学路の踏切で、そして廃線跡で。いつもその手には、例のフィルムカメラがあった。
「ねえ、高宮くん。ひまわり畑、撮りに行こうよ」
「なんで俺が」
「だって、未来の君は写真家になってるかもしれないじゃない? その練習!」
彼女の理屈はいつも滅茶苦茶だったが、なぜか断れなかった。太陽の匂いをいっぱいに吸い込んだひまわり畑。じりじりと肌を焼くアスファルト。突然の夕立に駆け込んだバス停。二人で食べた、すぐに溶けてしまう安っぽいアイスキャンディー。陽菜は、俺が今まで見過ごしてきたありふれた日常の欠片を、次々と宝物に変えていった。
カシャ。カシャ。彼女は夢中でシャッターを切る。ファインダーを覗くその横顔は、真剣で、どこか神聖ですらあった。
「何をそんなに撮るんだ?」
「全部だよ。今、ここにあるもの全部。光も、風も、匂いも、ぜんぶ永遠に閉じ込めておくの」
彼女の撮る写真は、確かに不思議な力を持っていた。現像された写真を見せてもらうと、ただの風景なのに、そこに写る光や影がまるで呼吸しているように感じられた。俺もいつしか、彼女につられるようにシャッターを切っていた。ファインダー越しの陽菜は、よく笑った。その笑顔を撮るたび、心臓の奥がぎゅっと掴まれるような、甘くて苦い感覚に襲われた。
夏休みの終わりが近づいた頃、市の写真コンテストのポスターが目に留まった。テーマは『永遠の一瞬』。
「これ、一緒に出そうよ」
陽菜が俺の袖を引いた。
「俺はいい」
「どうして? 高宮くんの写真、すごくいいよ。優しいもん」
優しい、と言われたのは初めてだった。俺の写真は、冷たくて、乾いているとばかり思っていた。
「最高の写真を撮って、世界をびっくりさせてやろうよ」
陽菜の瞳は、夏の夜空に打ち上げられた花火のようにきらめいていた。その引力に、俺はもう抗えなかった。俺は、陽菜を撮ることに決めた。彼女こそが、俺にとっての『永遠の一瞬』だと思ったから。
第三章 ファインダー越しの嘘
コンテストの締め切り三日前。俺たちは、あの廃線跡に来ていた。西日が世界を茜色に染め上げる、一日のうちで最も美しい時間。
「笑ってくれ」
カメラを構え、俺は言った。陽菜はこくりと頷き、ふわりと微笑んだ。それは、今まで見たどの笑顔よりも儚く、そして完璧な笑顔だった。俺は息を止め、シャッターを切った。全身の血が逆流するような高揚感。これだ。これ以上の写真はもう撮れない。
急いで家に帰り、暗室に籠った。現像液のツンとした匂いの中で、ゆっくりと像が浮かび上がる。光の中に立つ、陽菜の笑顔。俺は、震える手でその写真を掲げた。
その時だった。けたたましくスマートフォンの着信音が鳴り響いたのは。ディスプレイには、知らない番号が表示されていた。
「高宮蓮くんの携帯かい? 七瀬陽菜の兄です」
硬い声だった。嫌な予感が背筋を走る。
「陽菜が、倒れたんだ。病院に来てほしい」
病室のドアを開けると、そこには俺の知らない陽菜がいた。白いベッドの上で、たくさんの管に繋がれ、静かに眠っている。血の気の引いた顔は、まるで精巧な人形のようだった。
「進行性の網膜色素変性症なんだ」
陽菜の兄と名乗る青年が、廊下のベンチで静かに語り始めた。
「徐々に視野が狭まって、最後は光を失う。それだけじゃない。あいつは、もっと厄介な病気も抱えてる。医者からは…持って、あと一年くらいだろうって」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。言葉が出ない。
「あいつが持ってたカメラ、ただの古いフィルムカメラだよ。親父の形見だ。未来なんて写りっこない」
兄は、自嘲するように笑った。
「あいつは、自分の未来がないことを知ってた。だから、嘘をついたんだ。失われていく自分の『今』を、誰かの記憶に『未来』として残してほしかったんだ。君に撮ってもらった写真の中に、未来でも笑っている自分を見たかったんだよ」
陽菜の言葉が、脳内で稲妻のように駆け巡った。
『一年後の君の姿が見えた』
それは、俺の未来を予言したのではなく、俺の未来が続くことを願う、彼女の祈りだったのだ。
『見たくない未来もあるんだよ』
そう言って寂しげに笑った日があった。それは、自分の姿が消えてしまう未来のことだった。
俺が切り取っていたのは、彼女の笑顔ではなかった。笑顔の裏に隠された、絶望と、それでも懸命に輝こうとする、魂の叫びだった。
惰性で生きていた俺。有り余るほどの時間と未来を持ちながら、それをドブに捨てていた俺。そんな俺が、彼女の『永遠の一瞬』を撮る資格など、どこにあったというのだろう。手の中にあったはずのコンテスト用の写真が、急にひどく陳腐で、薄っぺらなものに思えた。
第四章 君のいない夏光
俺はコンテストへの応募をやめた。代わりに、陽菜のためだけの写真展を開くことにした。兄に頼み込み、殺風景な病室の壁を、俺たちの夏で埋め尽くした。
俺が撮った陽菜の写真。陽菜が撮ったひまわり畑や錆びた線路の写真。一枚一枚、壁に貼っていく。陽菜は、ほとんど見えなくなった目で、ぼんやりと壁を眺めていた。
「きれい…」
か細い声だった。俺は彼女のベッドの横に座り、一枚ずつ写真の説明をした。
「これは、夕立に降られたバス停。陽菜、髪がびしょ濡れだった」
「…うん」
「これは、ひまわりの写真。陽菜が撮ったやつ。太陽の匂いがする」
「…うん」
陽菜は、おぼつかない手つきで、壁の写真にそっと触れた。指先で、夏の輪郭を確かめるように。俺は、涙がこぼれないように、奥歯を強く噛みしめた。
「高宮くん」
陽菜が俺の方を向いた。もう焦点の合わない瞳が、俺を探している。
「私の未来、見えたよ」
彼女は、あの夏の日と同じように、ふわりと微笑んだ。
「高宮くんの写真の中に、私がいる。ずっと笑ってる。これが、私の見たかった未来だよ。ありがとう」
その言葉を最後に、陽菜はゆっくりと眠りに落ちていった。
季節が巡り、再び夏が来た。
俺は一人、あの廃線跡に立っていた。首から提げているのは、陽菜の兄から譲り受けた、あの銀色のフィルムカメラだ。ずしりとした重みが、彼女の存在を伝えてくる。
ファインダーを覗くと、去年と同じ、世界を焼き尽くすような強い光が満ちていた。蝉の声も、錆びた鉄の匂いも、何もかもが同じだ。ただ、隣に陽菜はいない。
カシャ。
乾いたシャッター音が響く。
このカメラは、未来を写さない。
けれど、俺は知っている。シャッターを切るたびに、ファインダー越しの世界を愛おしいと思うこの心が、陽菜が俺に残してくれた未来そのものなのだと。
俺はもう、灰色の日々には戻らない。陽菜が教えてくれた光の中で、彼女が見たかった未来を、俺が生きていく。一枚、また一枚と、この夏光を永遠に刻み込みながら。