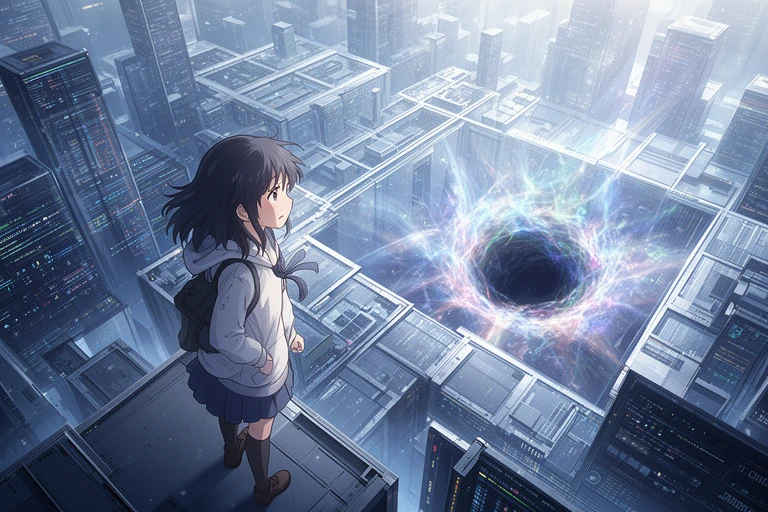第一章 錆びついた訃報
高橋健太の日常は、限りなく無菌室に近かった。都心の高層ビル、その三十階にあるオフィス。モニターが放つ青白い光だけが、彼の世界のすべてを照らしていた。合理性。効率。それが健太の信条であり、彼の構築するシステムそのものだった。人付き合いは最低限。飲み会は時間の浪費。故郷からの電話は、不在着信のリストに沈んでいくだけの無意味な文字列。そう、昨日までは。
「……高橋健太さんの、ご自宅でしょうか」
受話器の向こうから聞こえてきたのは、知らない男の、抑揚のない事務的な声だった。故郷の市役所の福祉課を名乗るその声は、健太の日常に、まるでインクを垂らしたようにじわりと染みを作った。
「祖母の、フミが?」
「はい。本日、ご自宅で亡くなられているのが発見されまして。検死の結果、死後一週間ほど経過しているかと。いわゆる、孤独死という形で……」
孤独死。その言葉は、健太の鼓膜を鈍く打ったが、心までは届かなかった。八十をとうに超えた祖母。もう何年も顔を見ていない。最後に電話で話したのはいつだったか。記憶の引き出しは、錆びついて開かなかった。
「そうですか。……それで、私は何をすれば?」
感情を排した声で尋ねると、男は少し間を置いてから、遺体の引き取りと遺品整理について説明を始めた。面倒だ、というのが正直な感想だった。仕事が立て込んでいる。プロジェクトの締め切りも近い。だが、社会的な体裁という、彼が最も軽蔑しながらも従わざるを得ないルールが、彼の背中を押した。
「それから、一つ奇妙な点が」と、男が付け加えた。「お祖母様の枕元から、これが見つかりまして」
「これ、とは?」
「最新型のタブレットです。電源も入ったままでした。ご高齢の方がお一人で……どうにも不自然でして」
タブレット。その単語は、健太の無菌室の壁に、初めてはっきりとした亀裂を入れた。祖母のフミは、固定電話の子機の使い方すら怪しいような、デジタルとは無縁の人間だったはずだ。なぜ、そんなものが。
健太の脳内で、無数のコードが絡み合うような、不快な感覚が走った。それは、彼の信条とする合理性では解けない、初めてのバグだった。彼は重い溜息をつき、数年ぶりに故郷行きのチケットを予約した。窓の外では、東京のネオンが、まるで遠い世界の出来事のように、無機質に瞬いていた。
第二章 不在の人のざわめき
新幹線を降り、ローカル線に乗り換えると、車窓の風景は急速に色褪せていった。健太が逃げるように飛び出した故郷の町は、記憶の中よりもさらに寂れ、空き家が虫歯のように点在していた。潮の香りが、錆の匂いと混じり合って鼻をつく。
祖母の家は、時が止まったまま、静かに健太を待っていた。埃っぽさの中に、微かに線香と、懐かしい醤油の匂いが混じる。畳を踏むたびに、ぎしり、と床が軋む音は、不在の主の重みを語っているようだった。
問題のタブレットは、福祉課の男が言った通り、小さな文机の上に置かれていた。指紋ひとつない、真新しいガラス面。健太はそれを手に取ったが、画面にはパスワードの入力が求められた。思いつく数字をいくつか試したが、無情にも弾かれるだけだった。
遺品整理を始めると、ひっきりなしに弔問客が訪れた。隣家の佐々木さん、向かいの魚屋の店主、ゲートボール仲間だという老人たち。彼らは一様に、健太の知らない祖母の顔を語った。
「フミさんには、本当にお世話になってねえ。うちの孫が熱を出した時、夜中に薬を届けてくれたんだよ」
「最近じゃあ、町の誰よりもスマホに詳しかったぞ。わしらの先生だったんだ」
健太は、曖昧な相槌を打ちながら、心の中に広がる違和感に戸惑っていた。自分の知る祖母は、もっと寡黙で、世間から一歩引いたような人だったはずだ。
その夜、一人の若い女性が訪れた。彼女は、町の集会所でボランティアをしているという美咲と名乗った。彼女の手には、祖母が好きだったという菊の花が抱えられていた。
「フミさん、うちの『デジタル寺子屋』で、一番の生徒さんだったんですよ」
美咲は、そう言って微笑んだ。彼女の話によれば、祖母は半年ほど前から、美咲が主催する高齢者向けのスマホ・タブレット教室に、雨の日も風の日も通い詰めていたという。
「どうして、あんなに熱心に?」健太は、思わず尋ねていた。
「『東京にいる孫と、顔を見て話がしてみたい』って。それが、フミさんの口癖でした。健太さんのために、ビデオ通話の使い方を、何度も何度も練習されて……」
美咲の言葉が、健太の胸に突き刺さった。タブレットは、祖母が自分に向けて伸ばした手だったのだ。疎んじていた自分へ、何とかして繋がろうとした、必死の試み。罪悪感が、冷え切っていたはずの心臓を、じりじりと灼いた。
その夜、健太は眠れずに、祖母の部屋を漁った。そして、桐の箪笥の奥から、一冊の古い大学ノートを見つけ出した。それは、祖母の日記だった。拙い文字で綴られていたのは、日々の些細な出来事と、健太への尽きない想い。
『健太は、元気にしているだろうか。ちゃんとご飯を食べているだろうか。ばあちゃんは、お前の声が聞きたいよ』
ページをめくるたびに、涙が視界を滲ませた。そして、最後の日付のページに、こんな一文があった。
『あの子が生まれた日を、忘れるはずがない。私の、一番の宝物だ』
健太の誕生日。その数字が、まるで啓示のように、彼の脳裏に浮かび上がった。
第三章 最後のメッセージ
震える指で、健太はタブレットに自分の誕生日を四桁で入力した。カチリ、と軽い音を立てて、ロックが解除される。待ち受け画面は、健太が幼い頃、祖母と一緒に撮った色褪せた写真だった。
ホーム画面には、アプリが一つもなかった。ただ一つ、『健太へ』と名付けられた、動画ファイルがあるだけだった。健太は息を呑み、再生アイコンをタップした。
画面に映し出されたのは、見慣れた祖母の家の縁側だった。そして、そこに座る祖母の姿。死後一週間が経過していたとは思えないほど、その顔色は良く、穏やかな笑みを浮かべていた。
『健太、かい?』
懐かしい声が、スピーカーから響いた。まるで、すぐそこに祖母がいるかのような錯覚に陥る。
『これを見ているということは、ばあちゃんはもう、この世にいないんだね。驚いたかい? 役所の人には、孤独死だって言われたんじゃないか?』
祖母は、悪戯っぽく笑った。健太は、何が起こっているのか理解できず、ただ画面を凝視した。
『ごめんよ。少し、芝居を打たせてもらった。でもね、こうでもしないと、お前はきっと、この家に帰ってこなかっただろうから』
動画の中の祖母は、ゆっくりと言葉を続けた。彼女は、半年前に末期の癌だと宣告されていた。治療法はなく、余命は幾ばくもない。しかし、彼女は入院も、延命治療も拒んだ。誰にも迷惑をかけたくない。そして何より、愛する孫に、自分の死に際の無様な姿を見せたくなかった。
『だからね、これは、ばあちゃんが自分で計画した、自分だけのお葬式なんだよ』
彼女は、自分の死期を悟っていた。体が動くうちに、このビデオメッセージを撮り、信頼する美咲にだけすべてを打ち明け、後のことを託した。美咲は、祖母の固い決意に折れ、計画に協力したのだという。タブレットは、健太をここに呼び寄せるための、壮大な計画の鍵だったのだ。
孤独死。それは、世間が貼ったレッテルに過ぎなかった。祖母の死は、孤独などでは断じてなかった。それは、自らの生を全うし、愛する者への想いを残すための、気高く、覚悟に満ちた「孤高」の死だった。
『健太。ばあちゃんは、この町で、たくさんの人に支えられて、本当に幸せだった。デジタル寺子屋のおかげで、新しい友達もできた。画面越しだけど、世界中の景色も見ることができた。だけどね、一番大事なのは、やっぱり隣にいる人だよ。画面の向こうばかり見ていちゃ、いけないよ。ちゃんと、隣にいる人の顔を見て、手を取って、温もりを感じなさい』
祖母の目から、一筋の涙がこぼれた。
『お前は、私のたった一つの誇りだ。達者でな』
映像が途切れ、画面が暗転した。静寂が部屋を支配する。健太は、タブレットを胸に抱きしめ、嗚咽した。凍てついていたはずの心が溶け、熱い何かがとめどなく溢れ出した。それは、祖母の最後の、そして最大の愛情だった。
第四章 つながりの在り処
翌日、健太は町の人々と共に、祖母のささやかな、しかし本当の葬儀を執り行った。そこには、孤独死という言葉がもたらす陰鬱な雰囲気は微塵もなかった。参列者は皆、フミさんとの温かい思い出を語り合い、涙し、そして笑った。健太は、一人ひとりに頭を下げ、祖母が生前お世話になった礼を述べた。彼らの皺の刻まれた手が健太の手を握り返すたびに、温かい何かが流れ込んでくるのを感じた。これが、祖母が言っていた「温もり」なのだと、健太は知った。
東京へ戻る日、健太は集会所に美咲を訪ねた。
「これ、使ってください」
彼はそう言って、会社から支給されていた予備のノートパソコンを差し出した。
「もしよければ、今度帰って来た時、何か手伝わせてもらえませんか。プログラミングの初歩とか、セキュリティの話とか。俺、それしかできないんで」
照れくさそうに言う健太に、美咲は満面の笑みで頷いた。「フミさん、きっと喜んでますよ」
東京に戻った健太の世界は、以前とはまるで違って見えた。オフィスの青白い光は、どこか温かみを帯びているように感じられた。彼は、隣の席でいつも黙々と作業をしている同僚に、「今日、昼飯でもどうですか」と声をかけた。驚いた顔をした同僚が、やがて嬉しそうに頷く。それは、健太にとって、人生の新しいプログラムを起動させる、最初のワンクリックだった。
その夜、健太は自室のベランダに出て、故郷の方角の夜空を見上げた。手には、祖母の形見のタブレット。彼は、その中に新しいフォルダを一つ作った。フォルダ名は、『つながり』。
社会の片隅で静かに消えていく、名もなき死。しかし、その一つ一つに、語られることのない物語と、誰かを想う深い愛情が隠されているのかもしれない。祖母が残したサイレント・ブルーの画面は、もう何も映さない。だが、健太の心には、確かに届いていた。決して消えることのない、温かいメッセージが。彼はこれから、そのメッセージを胸に、自分の手で、新しいつながりを紡いでいくのだろう。空には、シリウスが青白く、しかし力強く輝いていた。