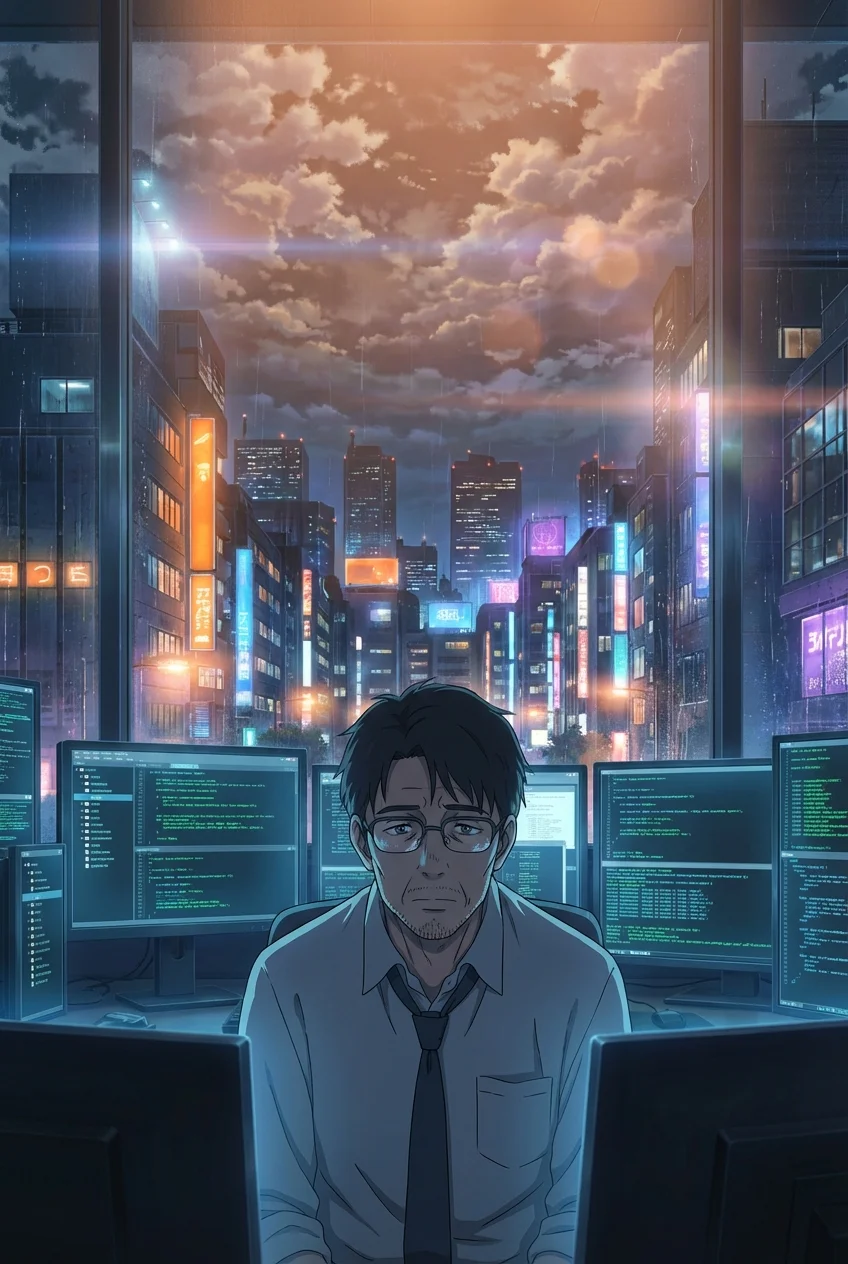第一章 静寂のアーカイブ
ガラスとクロムで構成されたオフィスは、まるで巨大なサーバー室のようだった。桐島朔(きりしま さく)の指先から放たれる微かなタイピング音だけが、完璧な静寂に周期的な波紋を広げている。彼は、総合記憶管理公社、通称『メモリーバンク』の特級査定官だ。彼の仕事は、人々が売りに出す「記憶」の価値を査定すること。喜び、悲しみ、興奮、後悔──あらゆる感情はここでデジタルデータに変換され、エンターテインメントや臨床心理学の素材として商品化される。
朔の前に、新たな査定案件がディスプレイに表示された。クライアント名、永井千代。82歳。持ち込まれた記憶は、彼女の人生の最後の10年分。膨大なデータ量だったが、朔の眉はわずかにひそめられた。AIによる一次評価は『カテゴリーD-マイナス』。市場価値、ほぼゼロ。
朔はヘッドセットを装着し、千代の記憶へとダイブした。
そこは、縁側に陽光が差し込む古い日本家屋だった。庭には名も知らぬ草花が咲き乱れ、一匹の三毛猫がひなたぼっこをしている。千代は、その猫に話しかけたり、庭の草むしりをしたり、編み物をしたりしている。BGMのように流れるのは、古びたラジオから聞こえるクラシック音楽だけ。食事は質素で、会話する相手もほとんどいない。劇的な出来事は何一つ起こらない。ただ、穏やかで、単調で、どこまでも平凡な日常が、10年分、延々と繰り返されるだけだった。
「ひどいな…」
朔は無意識に呟いていた。これは商品にならない。他人が追体験したいと思うような刺激的な要素が皆無だ。彼は、査定報告書に「価値計測不能。データ廃棄を推奨」と打ち込み始めた。それが最も効率的で、合理的な判断だった。
しかし、送信ボタンを押す直前、指が止まる。数時間前、オンライン面談で対面した永井千代の顔が脳裏をよぎったのだ。深い皺の刻まれた顔で、彼女は穏やかに、しかし確かな光を宿した瞳でこう言った。
「私の人生には、派手な物語はありません。でも、この陽だまりの匂いや、土をいじった後の指先の感触、あの子…猫のゴロゴロいう喉の音。それこそが、私の全てなんです。誰かにとってはガラクタでも、私にとっては宝物。だから、どうか、この記憶を遺してほしいのです」
その言葉が、朔の心に小さな棘のように引っかかった。効率と数値だけが支配するこの世界で、彼女は価値ゼロの記憶に「全て」だと言った。日常を覆すような出来事ではない。むしろ、日常そのものが静かに朔の価値観を揺さぶり始めていた。彼は報告書の送信を保留し、もう一度、あの退屈なはずの記憶の海へと思考を沈めていった。
第二章 色褪せた日々のノイズ
朔は規定を逸脱している自覚があった。本来、Dランク以下の記憶に査定官が時間を割くことは、生産性の低下と見なされる。だが、彼は千代の記憶から離れられなくなっていた。同僚の佐藤が、コーヒーを片手に彼のデスクに立ち寄り、モニターを覗き込んだ。
「まだその老婆の記憶と睨めっこか? 桐島らしくないな。そんなガラクタ、さっさと廃棄しちまえよ」
「…少し、気になる点がある」
朔は短く答えた。佐藤は肩をすくめ、興味を失ったように去っていく。
朔が気になっていたのは、記憶データに混じる微細なノイズだった。それは、映像の隅に一瞬だけ映り込む、意味不明な幾何学模様や、穏やかな日常の音に紛れて、かろうじて聞き取れる高周波のパルス音。システムの劣化によるバグか、あるいは単なる記録エラーだろう。AIもそう判断していた。だが、朔の研ぎ澄まされた感覚は、そのノイズが不自然なほど周期的に、そして特定の場面でだけ現れることに気づいていた。千代が庭のスミレに水をやる時。彼女が古いアルバムをめくる時。ラジオがある特定の周波数を受信する時。
彼は、仕事という名目を忘れ、まるで難解なパズルを解くようにノイズの解析に没頭した。千代の記憶を何度も追体験するうち、奇妙な感覚が彼を包み始めた。最初は退屈でしかなかったはずの縁側の陽だまりが、どこか懐かしい暖かさを帯びて感じられる。土の匂いが、幼い頃に祖母の家で遊んだ記憶を微かに呼び覚ます。三毛猫の柔らかな毛の感触が、画面越しに伝わってくるような気さえした。
感情を切り離し、客観的なデータとして記憶を処理してきた朔の心に、小さな変化が生まれつつあった。彼は、自分が査定しているのが単なるデータではなく、一人の人間が生きてきた時間の結晶なのだという、当たり前の事実を思い出し始めていた。そして、あのノイズは、この穏やかな記憶の世界にそぐわない、異質な意志の欠片のように思えてならなかった。
ある夜、朔は自宅の解析システムを使い、ついにノイズのパターンを特定した。それはランダムなエラーではなかった。高度なステガノグラフィー技術によって隠された、別のデータ層への入り口だった。彼はゴクリと唾を飲み込み、パスワード解析プログラムを起動した。画面に無数の文字列が流れ始める。千代の記憶の奥深くに、一体何が隠されているというのか。
第三章 スミレの暗号
解析プログラムが甲高い音を立てて停止した時、窓の外は白み始めていた。画面に表示された一つの単語。
『VIOLA』──スミレ。
朔ははっとした。千代が庭で、特に丹精込めて育てていた花の名前だ。彼は震える指でその単語を入力する。すると、ロックが外れ、隠されていたデータが滝のように展開された。
そこに現れたのは、千代の穏やかな日常とは似ても似つかぬ、冷徹で無機質な設計図と、膨大な量の監視記録だった。
朔は息を呑んだ。それは、政府が国民の生活を管理するために極秘裏に運用している超巨大情報監視システム『アーカイヴ』の根幹に関わるデータだった。そして、永井千代は、そのシステムの初期開発者の一人だったのだ。
データには、彼女自身のものと思われるテキストログも含まれていた。
『私は、人々の記憶を永遠に保存する夢の箱舟を造るつもりだった。だが、彼らが造り上げたのは、魂を分類し、管理し、不要なものを切り捨てるための牢獄だった』
『アーカイヴは、社会の安定という名目で、基準から外れた思考や感情を持つ人間を静かに社会から抹殺する。彼らの記憶は「ノイズ」として処理され、存在しなかったことにされる。私は、取り返しのつかない過ちを犯した』
朔は全身の血が凍るのを感じた。彼が毎日行っている「記憶の査定」という仕事は、まさにそのシステムの一部だったのだ。価値のある記憶とない記憶を選別し、社会にとって「不要」な人間の痕跡を消していく作業。自分は、ただの会社員ではなく、巨大なシステムの末端で、魂の仕分けをしていたに過ぎなかった。
千代の計画の全貌が見えた。彼女は、アーカイヴの目から逃れるために、自らの記憶を「最も価値のない、平凡な日常」でコーティングしたのだ。そして、その巨大なカモフラージュデータの中に、システムの設計図と、政府が隠蔽してきた数々の非人道的な行為の証拠を暗号化して隠した。彼女の狙いは、メモリーバンクの査定システムに「価値なし」と判断させること。なぜなら、「価値なし」と判断されたデータは、厳重な監視下にある保管サーバーではなく、セキュリティの甘い廃棄サーバーへと送られる。その廃棄プロセスに乗じて、外部の協力者へデータを転送する仕組みが仕組まれていたのだ。
朔が「価値なし」と判断し、廃棄ボタンを押すことこそが、この壮大な告発計画の最後の引き金だった。千代の「この記憶こそが、私の全てなんです」という言葉が、全く違う意味を帯びて朔の胸に突き刺さった。彼女は、自らの人生の最後の10年を、この計画のためだけに生きてきたのだ。
第四章 価値ゼロの未来
朔は数分間、身動きもせずディスプレイを見つめていた。報告すれば、会社始まって以来のスクープとなり、特級査定官としての地位は不動のものになるだろう。だが、それは千代の命がけの告発を握り潰し、システムの一部として生き続けることを意味する。彼の脳裏に、縁側で穏やかに微笑む千代の顔と、彼女の記憶に触れて呼び覚まされた自分自身の温かい記憶の断片が交互に浮かんだ。
もう、記憶を単なる商品として見ることはできなかった。
朔は、深呼吸を一つすると、キーボードに向かった。彼はまず、自分がアクセスした全てのログを完璧に消去した。そして、永井千代の査定報告書を開き、最終判断の欄に、簡潔にこう書き込んだ。
『総合評価:D-マイナス。市場価値、ゼロ。規約に基づき、データ廃棄を実行する』
彼は、震える指で送信ボタンを押した。それは、彼のキャリアの終わりを意味すると同時に、巨大なシステムに対する、一人の人間としてのささやかな、しかし決定的な反逆だった。ボタンが押された瞬間、廃棄サーバーへと送られた千代のデータは、内部のプログラムを起動させ、世界中のジャーナリストや人権団体へ向けて、その身を裂くようにして真実を拡散し始めたはずだ。
数日後、世界は激震した。『アーカイヴ』の存在が白日の下に晒され、社会は混乱の渦に巻き込まれた。メモリーバンクは当然のごとく調査対象となり、朔は「査定ミス」の責任を問われる形で、静かに会社を去った。
職を失い、全てを失った朔は、目的もなく街を歩いていた。雑踏の中で、彼の目は小さな花屋の店先に引き寄せられた。そこには、千代の記憶の中で見たのと同じ、小さな紫色のスミレの鉢植えが並んでいた。
彼は、その一鉢を手に取った。小さな花弁に触れた指先に、土のひんやりとした感触が伝わる。それは、データではなかった。価値を示す数値も、市場価格もついていない。だが、彼の心には、これまで感じたことのないほど確かな温もりと、重みが満ちていた。
社会がこの先どうなるかは分からない。システムが崩壊するのか、あるいは形を変えて存続するのか。だが、朔は知っていた。たとえ誰かにとって価値がゼロであろうと、一つ一つの記憶には、その人の人生の全てが詰まっている。そして、その尊さを知った自分は、もう二度と、魂に値段をつけることはないだろう。
彼はスミレの鉢植えを抱え、陽光が差し込む坂道を、ゆっくりと登り始めた。その足取りは、未来へと向かう、新たな一歩だった。