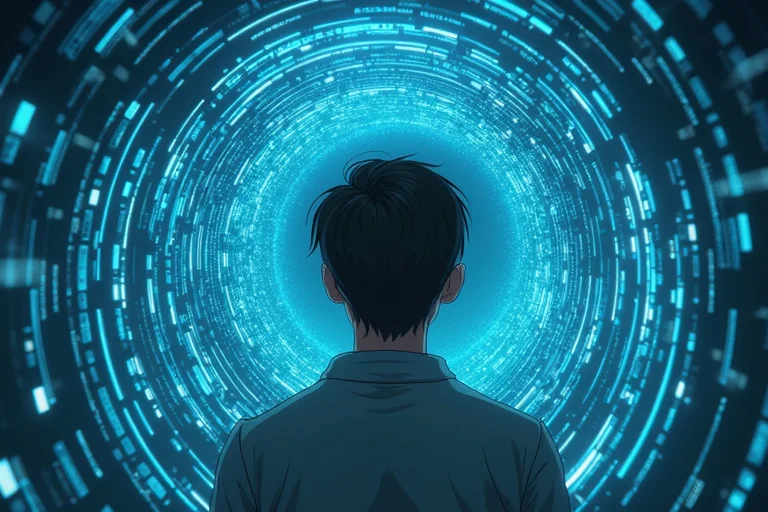クリックひとつで、世界は燃える。
フリーライターの水野圭吾は、煤けた6畳間のモニターの前で、その真理を何度も実感してきた。ペンネーム「K」として彼が書くのは、真実ではない。人々の感情を最も効率よく揺さぶり、アクセス数を稼ぐための「物語」だ。生活のためだ、と自分に言い聞かせながら、彼は今日もキーボードを叩いていた。
今回の依頼は、大手広告代理店の“影”と呼ばれる男、影山からだった。匿名性の高い通信アプリで送られてきた指示は簡潔だ。
『テーマ:次世代エネルギー。ターゲット:革新的技術を発表したベンチャー企業「テラ・フロンティア」。ネガティブキャンペーンを展開せよ』
報酬は破格だった。水野は二つ返事で引き受けた。
彼はまず、「テラ・フロンティア」のクリーンエネルギー技術に「未報告の健康的リスクが存在する」という専門家風の匿名ブログを立ち上げた。次に、その技術が「海外の軍事技術の転用であり、情報漏洩の危険がある」という元関係者を名乗る人物の告発文をSNSに投下した。ソースは全て、彼自身だ。
いくつもの偽アカウントを使い分け、絶妙なタイミングで情報を拡散させる。不安を煽るコメント、義憤に駆られたリツイート。水野が仕掛けた小さな火種は、ネットという強風に煽られ、瞬く間に炎上という名の篝火となった。
『テラ・フロンティア、株価大暴落』
『説明会に抗議者殺到』
ニュースサイトの見出しが、彼の「成功」を報じていた。口座に振り込まれた報酬を確認し、水野は虚しい達成感とともにウイスキーを呷った。
数日後、一本のニュース映像が彼の目を釘付けにした。テラ・フロンティアの若き社長、三崎誠が、やつれた顔で謝罪会見に臨んでいる。しかし、水野の視線はその隣に立つ、白髪の老人に注がれていた。技術開発の最高責任者、工藤博士。水野が子供の頃、科学雑誌で夢中になって読んだ、尊敬する科学者その人だった。
「我々の技術は、未来のためのものです。断じて、人々を危険に晒すものではない……」
工藤博士のかすれた声は、ヤジにかき消された。その瞳に浮かぶ深い絶望を見て、水野の心臓を冷たい何かが鷲掴みにした。これはゲームじゃない。俺は、尊敬する人間の夢を、人生を、この手で焼き払ったのか。
罪悪感が水野を苛んだ。影山に連絡を取ろうとしたが、アカウントはすでに削除され、全ての通信記録が消去されていた。完全に尻尾を切られたのだ。
このままでは終われない。終わらせてはいけない。
水野は決意した。自分が焚き付けた嘘の篝火を、この手で消し去ることを。
彼は仕事部屋に籠もり、今度は「真実」を暴くための調査を開始した。武器は、これまで嘘を捏造するために培ってきた情報操作のスキル、そのすべてだ。
彼はまず、影山の正体を探るべく、過去のやり取りの断片からデジタル・フットプリントを辿った。IPアドレスの偽装、暗号化された通信。影山は用心深かったが、完璧ではなかった。水野は、影山が使っていたサーバーの脆弱性を見つけ出し、侵入に成功する。
そこには、驚くべき事実が眠っていた。影山は、テラ・フロンティアのライバルである巨大エネルギー企業「アトラス・エナジー」と繋がっていたのだ。アトラス社が、旧態依然とした自社のエネルギー利権を守るため、影山を使ってテラ・フロンティアを社会的に抹殺しようと計画した、というのが真相だった。
水野は、アトラス社と影山の間の契約書、指示内容のメール、金の流れを示すデータを全て抜き出した。決定的な証拠だった。
だが、これをどうやって世に出す?
「K」として告発しても、誰も信じないだろう。嘘つきの常習犯なのだから。
水野は不敵に笑った。ならば、最高の「物語」を紡いでやろう。
彼は、これまでの人生で最も緻密な記事を書き上げた。タイトルは、『虚構の篝火を燃やした男』。
それは、アトラス・エナジーの陰謀を暴く告発記事であると同時に、フェイクニュースライター「K」こと、水野圭吾自身の罪の告白でもあった。
彼は記事の最後にこう記した。
『私は、クリックひとつで人の夢を焼き、社会を歪めてきた。その罪は決して許されるものではない。だが、この嘘にまみれた世界で、最後の真実を伝える責任が私にはある。この告発が、私にできる唯一の贖罪だ』
水野は、全ての証拠データと共に、その記事を大手報道機関複数社に一斉送信した。そしてエンターキーを押すと同時に、スマートフォンの電源を切り、静かに立ち上がった。
翌朝、世界は再び燃え上がった。しかし、昨日までとは炎の色が違っていた。
アトラス・エナジーの株価は暴落し、幹部たちは次々と検察の聴取を受けることになった。テラ・フロンティアには支援の声が殺到し、工藤博士の研究は守られた。
水野圭吾は、自ら警察署の扉を開けていた。
降り注ぐ無数のフラッシュライトを浴びながら、彼は不思議と晴れやかな気持ちで空を見上げた。煤けた6畳間で燻っていた男が放った最後の火花は、確かに、世界の片隅を少しだけ照らしたのだから。