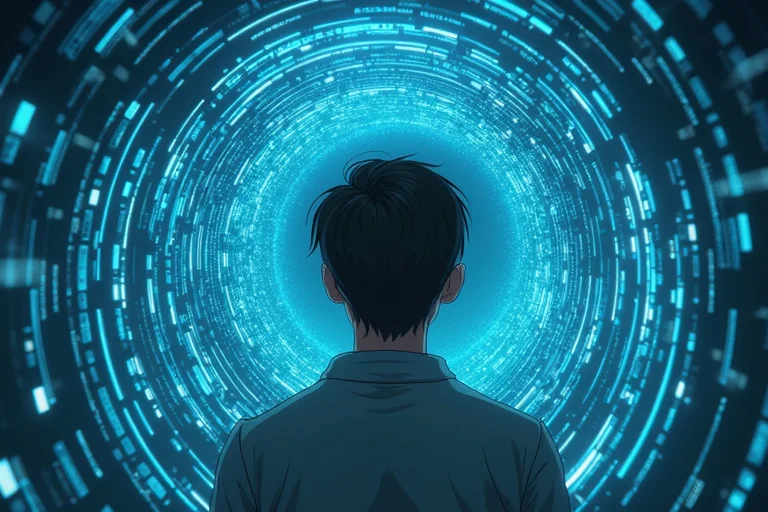高橋健太の価値は、72点だった。
デスクの隅に表示されるその数字は、彼の一日を支配する亡霊だ。AI人事評価システム『ECHO』。三ヶ月前に導入されたそれは、メールの返信速度から会議での発言回数、社内SNSでのエンゲージメントに至るまで、あらゆる業務活動をリアルタイムで解析し、社員をスコア化する。会社は「公平で客観的な評価」だと謳ったが、健太には見えない首輪がはめられたようにしか感じられなかった。
「高橋君、またスコアが下がってるじゃないか。もっと積極的に『ECHO』が好むアクションを取らないと」
課長の声は、温度のないプラスチックのようだ。背後から覗き込まれたモニターには、赤い下降矢印が72という数字の横で冷たく点滅している。周囲のデスクでは、カタカタと軽快なキーボードの音に混じって、わざとらしい笑い声や、中身のない賛辞がチャットツール上を飛び交っていた。スコアを稼ぐための空虚なパフォーマンス。それが、今の職場の日常だった。
健太は、そういう器用な立ち回りが苦手だった。地味ではあるが、顧客の細かな要望に応え、トラブルの芽を未然に摘む。そんな仕事に誇りを持っていた。だが、ECHOはそうした画面に現れない貢献を評価しない。むしろ、定型業務から外れた行動は「非効率」と見なされ、スコアを下げる要因にすらなった。
隣の席の若手、田中はECHO導入後に頭角を現した一人だ。彼のスコアは常に90点台をキープしている。彼は会議で誰かの意見にすかさず「素晴らしい視点ですね!」とコメントし、社内SNSには上司の投稿を引用して長文の賛辞を投稿する。彼の実際の業務がどれだけ進んでいるのか、健太には甚だ疑問だった。だが、ECHOの中では田中が正義だった。
ある日の午後、健太はECHOから「パフォーマンス改善勧告」という冷たいタイトルの通知を受け取った。スコアが三ヶ月連続で基準値を下回ったため、一ヶ月後に改善が見られなければ降格処分も検討するという。画面が歪み、胃の底が冷えた。十年以上、この会社に尽くしてきた自負が、音を立てて崩れていく。俺の十年は、この無機質なシステムの前では何の価値もないのか。怒りよりも先に、深い無力感が健太を襲った。
その夜、健太は退職した先輩、佐々木に連絡を取った。彼は五十代半ばのベテランエンジニアだったが、ECHOの導入を機に早期退職を選んだ一人だ。
「やっぱり、おかしかったんだ」
居酒屋のカウンターで、佐々木は健太の話を聞くと、苦々しく顔を歪めた。
「あのシステムは、人間を評価しているんじゃない。ただ、過去のデータをなぞって『それらしい』人間を複製しているだけだ。俺みたいな古いタイプは、ノイズとして処理される運命さ」
佐々木の言葉が、健太の中で燻っていた疑念に火をつけた。このまま黙ってシステムの軍門に下るのか。それとも、抗うのか。
「佐々木さん、俺、調べてみようと思うんです。このECHOってやつの正体を」
健太の目に宿った光を見て、佐々木は少し驚いたように目を細め、そして静かに頷いた。「手伝えることがあれば、言え」
そこからの健太の行動は、執念に近かった。昼はスコアを落とさないよう最低限のパフォーマンスをこなし、夜は佐々木の協力のもと、ECHOのアルゴリズムを分析した。公にされている仕様書の裏を読み、システムの挙動から評価ロジックを逆算していく。それは、巨大な城壁に爪を立てるような、途方もない作業だった。
やがて、彼らは恐ろしい事実にたどり着く。ECHOの評価基準は、過去五年間に最も高い評価を得た「トップパフォーマー」百名の行動データを基に構築されていた。そして、その百名のほとんどが、特定の派閥に属する、声の大きい社員たちだった。ECHOは多様な働き方を認めず、特定の成功パターンを全社員に強制する装置だったのだ。イノベーションの芽を摘み、異質なものを排除する、静かなる独裁者。
さらに決定的な証拠が見つかった。ECHOの開発責任者である役員の行動パターンに、不自然なほど高いウェイトがかけられている。システムは、開発者自身を「理想の社員」として学習していた。これはもはや評価システムではない。権力者の価値観を社員に刷り込むための、巧妙な洗脳ツールだ。
全身から血の気が引くのを感じた。これは、ただの不公平じゃない。人間の尊厳に対する冒涜だ。健太はすべての証拠データをUSBメモリに収め、固く握りしめた。
翌週、全社員が参加する四半期報告会が開かれた。壇上では、社長がECHOの導入による生産性向上を誇らしげに語っている。スクリーンには、会社全体のスコアが上昇していることを示すグラフが映し出された。会場からは、まばらな拍手が起こる。誰もがECHOの支配を受け入れ、その中で生きる術を身につけ始めていた。
健太は立ち上がった。心臓が喉から飛び出しそうだった。足が震え、指先が冷たい。だが、ここで声を上げなければ、自分の中に残った最後の何かが死んでしまう気がした。
「異議があります!」
マイクもないまま張り上げた声は、意外なほどホールに響き渡った。会場の視線が一斉に健太に突き刺さる。社長が眉をひそめ、警備員が駆け寄ろうとするのを手で制し、健太は壇上へと歩みを進めた。
「そのスコアは、偽りです」
彼はPCを演台のプロジェクターに接続し、USBメモリを差し込んだ。スクリーンに映し出されたのは、ECHOの歪んだ評価ロジックと、役員のデータが不正に操作されていることを示す生々しい記録だった。
「我々はスコアで評価される家畜じゃない!血の通った人間なんです!」
静まり返った会場に、健太の魂の叫びが木霊した。呆然とする役員たち。ざわめき始める社員たち。その中で、健太はただ一人、まっすぐに前を見据えていた。
健太は、その日のうちに懲戒解雇された。会社という組織にとって、彼は許されざる反逆者だった。だが、彼の投じた一石は、静かだった水面に大きな波紋を広げた。
健太の告発は、匿名でリークされ、やがて大手メディアの知るところとなった。AIによる人事評価の倫理性が社会的な議題となり、健太が勤めていた会社はECHOシステムの運用停止と、第三者委員会による調査の受け入れを発表せざるを得なくなった。
数日後、健太のアパートの郵便受けに、一通の封筒が届いていた。中身は、冷たい定型文で綴られた解雇通知書だ。健太はそれを一瞥すると、くしゃくしゃに丸めてゴミ箱に投げ入れた。
スマートフォンの画面には、元同僚たちからのメッセージが何十件も届いていた。「ありがとう」「君は間違ってない」「俺たちも目が覚めた」。その中には、会社を辞めて新しい事業を一緒にやらないかという誘いまであった。
健太は窓を開けた。夕陽が、高層ビル群のガラスを赤く燃やしていた。スコアに追われ、息苦しさを感じていた昨日までの景色とは、まるで違って見える。失ったものは大きい。だが、得たものの方が、ずっと価値があるように思えた。
「スコアなんかじゃ、測れないものがある」
誰に言うでもなく呟き、健太は小さく笑った。その表情には、ひとつの戦いを終えた男の、静かで確かな誇りが浮かんでいた。空は広く、明日への道は、まだどこまでも続いていた。