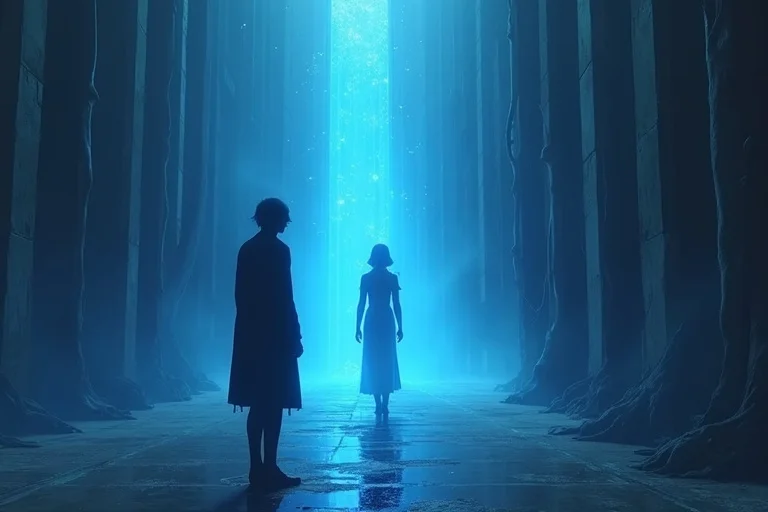第一章 不協和音の街
俺の名はカイ。この世界で、おそらく最も静かな場所に生きている。俺の耳には、他人の「社会的な期待値」が微弱な共鳴振動として届く。期待が大きければ大きいほど、それは甲高い不協和音となって鼓膜を苛む。そして、期待がゼロに近づくほど、世界は心地よい静寂に包まれるのだ。
俺が暮らす「労働奉仕区画」は、常に静かだった。ここは社会から見捨てられた者たちの掃き溜め。誰も誰かに期待などしない。だから俺は、この灰色にくすんだ街の静寂を愛していた。古びた配管が軋む音、遠くで響く金属の打撃音、そして人々の諦観に満ちた吐息。それらは俺の世界の背景音楽であり、決して俺の心を乱すことはなかった。
だが、空を見上げると、その静寂は破られる。雲の上、遥か天蓋に築かれた「管理監督区画」。そこからは、絶えず耳障りなノイズが降り注いでくる。成功への期待、他者からの承認欲求、権力への渇望。それらが混じり合った不協和音は、まるで巨大な金属板を無数のかぎ爪で引っ掻くような音となって、俺の頭蓋に響き渡る。
この世界は「感謝」によって成り立っている。人々が交わす感謝の表明が物理的な生命エネルギーに変換され、我々が呼吸するための空気を生成するのだという。だが、俺たちの区画の空気はいつも薄く、金属の味がした。皆が互いを労り、乏しい食料を分け合う時に生まれるささやかな感謝では、この淀んだ空気を浄化するには足りないらしかった。上層の連中が振りまく、けたたましい感謝の言葉だけが、この世界の空気を支配していた。
第二章 共鳴石の囁き
奉仕区画の中央広場には、黒曜石のような滑らかな石が鎮座している。感謝管理システムの末端装置、「共鳴石」だ。本来なら、感謝のエネルギーを吸収し、生命の息吹を象徴する美しい光を放つはずの石。しかし、ここの石はいつも沈黙していた。鈍い光を宿すこともなく、ただそこに在るだけの、巨大な墓石のようだった。
ある日の夕暮れ、俺はいつものようにその石の前を通りかかった。空気がひときわ薄く感じられ、誰もが肩で息をしている。その時だ。
――キィン……。
耳の奥で、微かな音が鳴った。それは上層から降ってくる不協和音とは違う、もっと低く、地の底から響いてくるような、鈍い金属音。俺は思わず足を止め、音の源を探った。それは、目の前の共鳴石から発せられていた。
石にそっと手を触れる。ひんやりとした感触が伝わると同時に、脳を直接揺さぶるような振動が駆け巡った。俺の能力が増幅されている。上層のノイズがさらに鋭利になり、頭痛が走る。だが、それ以上に俺の心を捉えたのは、石そのものが発する悲鳴のような音だった。それは「飢え」の音だった。感謝に、本物の感謝に飢えている石の慟哭。
なのに、なぜだ? この区画には、確かに感謝がある。隣の老婆が焼いてくれた硬いパン。友人が分け与えてくれた水。そのやり取りの中に生まれる温かい感情は、俺には音として聞こえないが、確かに存在しているはずだ。なぜ、この石はそれを感知せず、飢えを訴えているのか。そして、なぜ上層の、心にもない感謝の言葉が飛び交う場所では、生命エネルギーが満ち溢れているように見えるのか。
この世界の仕組みは、どこか根本的に歪んでいる。その直感が、冷たい確信となって俺の胸に突き刺さった。
第三章 管理監督区画の虚構
友人の幼い妹が、淀んだ空気に肺を病んだ。特効薬は管理監督区画にしかない。危険を承知で、俺は貨物用の昇降機に忍び込み、初めて上層の世界に足を踏み入れた。
昇降機の扉が開いた瞬間、俺は凄まじい音の洪水に襲われ、その場に膝をついた。
「素晴らしいプレゼンだった、感謝するよ!」
「こちらこそ、ご尽力に感謝します!」
耳を劈く不協和音。期待と見返りを前提とした感謝の言葉が、ガラスの破片のように降り注ぐ。白亜のビル群、清潔な大通り、きらびやかな衣服をまとった人々。彼らの身体からは、絶えず高周波の共鳴振動が発せられ、互いにぶつかり合い、狂乱のオーケストラを奏でていた。空気は濃く、甘ったるい香りがする。だが、それは生命力に満ちた匂いではなかった。人工的に生成された、虚ろな芳香だった。
薬局で高価な薬を手に入れ、逃げるように路地裏に駆け込む。そこで俺は見た。二人の役人が、恭しく頭を下げ合っている。
「先日の件、誠に感謝申し上げる」
「いやはや、こちらこそ。今後とも良き関係を」
彼らの口から紡がれる感謝の言葉とは裏腹に、俺の耳に届く振動は、嫉妬と侮蔑、そして互いの地位に対する値踏みの音だった。心がこもっていない。ただの形式。義務。それなのに、彼らの足元にある監視用の小型共鳴石は、眩いばかりの光を放っている。
この時、俺は理解した。システムが求めているのは、真の感謝ではない。「感謝の表明」という、記号化された行為そのものなのだ。心の底から湧き出る温かい感情ではなく、社会的なポーズとしての感謝。それこそが、この歪んだ世界のエネルギー源だった。
第四章 流れの源流
俺は奉仕区画に戻り、中央広場の共鳴石の前に立った。増幅された能力を使い、石が発する鈍い悲鳴の奥にある、エネルギーの流れを追う。それは、か細い糸のように地下深くへと伸びていた。
真夜中、俺は石の台座をこじ開け、地下へと続くメンテナンス用の通路に侵入した。錆びた梯子を降りていくと、ひんやりとした空気が肌を撫でる。やがて、広大な空間に出た。
そこは、世界の心臓部だった。無数のケーブルが巨大な中央共鳴石へと接続され、石は脈打つように禍々しい光を放っていた。壁面のモニターには、各区画から集められた感謝エネルギーの数値が表示されている。管理監督区画の数値は天文学的な数字を叩き出しているのに対し、労働奉仕区画の数値は、限りなくゼロに近かった。
俺はシステムの構造を読み解いた。このシステムは、特定の周波数――つまり、義務や形式として表明された感謝の振動――のみを効率的に吸い上げるように設計されていたのだ。そして吸い上げられたエネルギーは、全てがこの中央石に集められ、濾過された後、その大半が管理監督区画へと再分配されていた。上層の富と権力、そして彼らが吸う甘い空気は、こうして作り出されていた。
では、俺たちの区画を支える、あのささやかな感謝はどこへ消えたのか? 俺が意識を集中させると、システムの集計から漏れた、全く別のエネルギーの流れが見えた。それは、システムには認識されない、あまりにも純粋で微弱な振動。無形のエネルギー。それが亡霊のように区画内を漂い、人々が完全に窒息するのを、かろうじて防いでいたのだ。
真の感謝は、見えざる盾となって、俺たちを細々と守っていた。
第五章 静寂の決断
真実を知った俺は、中央共鳴石の前に立ち尽くした。これを破壊すれば、世界は変わる。上層の欺瞞は崩れ落ち、エネルギーの独占は終わる。だが、同時に世界は深刻な生命エネルギー不足に陥るだろう。システムが供給していた偽りの空気さえも失われ、多くの人々が苦しむことになる。特に、俺が守りたいと願う奉仕区画の仲間たちが、真っ先に犠牲になるかもしれない。
俺の背後で、静かな足音がした。いつの間にか後をつけてきていた、診療所の女医、エナだった。
「カイ……あなた、何をしようとしてるの?」
彼女の声には、俺の能力に反応する不協和音が一切混じっていなかった。ただ純粋な心配だけが、穏やかな微振動となって俺の心を撫でた。
俺は全てを話した。この世界の偽りの構造を。彼女は静かに聞き終えると、俺の震える手を取った。
「怖い。もちろん、怖いわ。でも……偽りの空気を吸って、ゆっくりと死んでいくのが、本当に生きていることなのかしら」
彼女の瞳には、絶望ではなく、未来を見据える強い光が宿っていた。
「私たちは、自分たちの息で、生きていかなきゃ」
彼女の言葉が、俺の最後の迷いを断ち切った。俺は、足元に転がっていた太い鉄パイプを握りしめる。これが俺の、この世界へのたった一つの、そして最大の「表明」だった。
第六章 世界の沈黙
俺は鉄パイプを振り上げ、力の限り中央共鳴石に叩きつけた。
甲高い破壊音と共に、石に亀裂が走る。次の瞬間、世界から一切の音が消えた。上層から降り注いでいた不協和音が止み、システムが発していた低い駆動音も沈黙した。そして、俺の頭の中から、他人の期待値を感じ取る共鳴振動が、綺麗さっぱり消え失せていた。
共鳴石の崩壊と共に、俺の能力は失われたのだ。
世界は、生まれて初めて体験する、完全な静寂に包まれた。それは、俺がずっと求めてきた「期待されない静寂」とは違う、何もかもが停止してしまったかのような、死の静寂だった。同時に、空気が急速に薄くなっていくのがわかった。息が苦しい。エナも胸を押さえ、苦しげに喘いでいる。俺は彼女の手を強く握りしめ、地上へと向かって走り出した。
地上に出ると、奉仕区画は混乱の渦にあった。誰もが息苦しさに倒れ込み、空を見上げていた。天蓋にある管理監督区画の輝きも、今は嘘のように消え失せている。世界は平等に、窒息しかけていた。偽りのシステムに依存しきっていた世界の、当然の末路だった。
第七章 息吹の夜明け
どれくらいの時間が経っただろうか。死の淵をさまよう人々の間を、俺はエナと二人、水を配り、互いを励まし合いながら歩き続けた。
その時だった。倒れていた老婆が、震える手で幼い子供に一切れの乾パンを差し出した。
「さあ、お食べ……」
子供はそれを受け取ると、か細い声で言った。
「……ありがとう、おばあちゃん」
その瞬間、ほんのわずかに、空気が震えた気がした。能力を失った俺には何も聞こえない。だが、心で感じた。それは、システムを介さない、人と人との間に直接生まれた、純粋な感謝の息吹だった。
その小さな感謝は、連鎖した。あちこちで、人々が互いを助け合い、ささやかな言葉を交わし始める。
「大丈夫か?」
「ああ、君のおかげだ。ありがとう」
「ありがとう」
「ありがとう」
一つ一つの感謝は、あまりに小さく、か弱い。だが、それらが寄り集まり、ゆっくりと、しかし確実に、世界に新しい空気を満たしていく。それは上層が作り出した甘ったるい偽りの空気ではない。少し冷たくて、土の匂いがする、本物の生命の味だった。
俺は深く、深く、その新しい空気を吸い込んだ。もう俺の耳に不協和音が響くことはない。誰からも期待されない静寂の中にいるわけでもない。世界は音で満ちている。人々の本当の声、風の音、そしてこれから生まれるであろう新しい世界の産声。
俺は隣にいるエナの顔を見つめ、微笑んだ。静寂の中で、俺は確かに、真の希望を抱きながら、新たな一歩を踏み出していた。