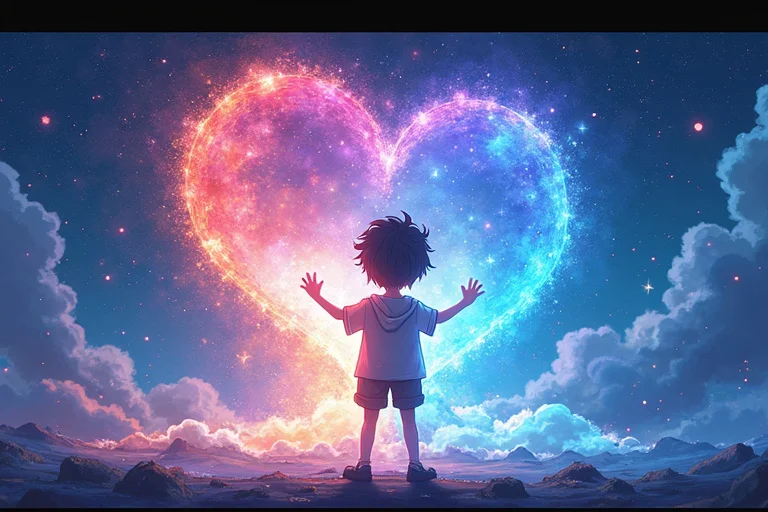第一章 色なき観身者
僕、蒼(アオ)の見る世界は、いつも少しだけ色褪せていた。
13歳から18歳までの青春期。人々は感情の熱量に応じて、身体から「輝度」と呼ばれる物理的な光を放つ。喜びは黄金に、悲しみは藍色に、怒りは深紅に。教室は常に、無数の光が混ざり合うプリズムのようで、その中心にいる友人たちの時間は、僕の知らない法則で流れていく。
「見て、アオ! この前のテスト、満点だったんだ!」
振り返った陽菜(ヒナ)の身体から、弾けるような檸檬色の輝度が溢れ出す。隣に立つ蓮(レン)が冗談めかして彼女をからかうと、その輝度はさらに増し、二人の周囲の空気が蜂蜜のように甘く、そして濃密に揺らめいた。輝度の高い者同士が共鳴し、時間の流れを加速させるのだ。彼らにとって、楽しい放課後の一時間は、僕にとっての数分に過ぎない。
僕には、輝度がなかった。生まれつき、感情の熱量を光に変えることができない。だから僕は、彼らの時間の共鳴に加われない。ただ一人、正常な時間の流れに取り残される観測者。それが僕の立ち位置だった。
陽菜が僕に笑いかける。彼女の輝きは眩しすぎて、いつも少し目を細めてしまう。その眩しさから零れ落ちた光の粒子が、僕の指先に触れた。僕は誰にも気づかれないよう、そっとそれを手のひらに掬う。僕の唯一の能力。他者の輝度を、その熱量と色彩ごと、一時的に「保存」する力。手のひらの中に、小さな太陽が宿ったような、微かな温もりだけが残った。
第二章 歪む放課後
その異変は、取り壊しが決まった旧校舎で起きた。肝試しだと騒ぐ陽菜と蓮に引きずられ、埃っぽい廊下を歩いていた時だ。
突然、世界から音が消えた。
陽菜と蓮の輝度が、遊び心から強く共鳴した瞬間だった。彼らの周りの空間がぐにゃりと歪み、夕陽が差し込む窓の外の景色が、まるで熱せられたガラスのように揺らめく。
「……あれ?」
陽菜が呟いた言葉が、何度も繰り返される。割れた窓ガラスの破片が床に落ちる音が、永遠に反響する。時間のループ。世界各地で頻発する「時間の飽和地帯」そのものだった。
陽菜の檸檬色の輝度が、急速に色を失っていく。ループする時間に輝度を吸い取られているのだ。彼女の顔から血の気が引き、蓮もまた苦しげに膝をついた。
「陽菜! 蓮!」
僕の声は届かない。彼らは、閉じられた時間の牢獄にいる。このままでは、彼らの青春そのものが喰い尽くされる。
僕は覚悟を決めた。右の手のひらに意識を集中する。そこには、数日前に保存した、陸上部のエースが自己ベストを更新した瞬間の、爆発的な歓喜の輝度が眠っている。僕はそれを、目の前の歪んだ空間に向かって解放した。
――迸る、灼熱のオレンジ色の光。
僕の身体から放たれた他人の輝きは、ループする時間に強引に割り込み、均衡を破壊した。ガラスが砕けるような鋭い音と共に、時間の牢獄が砕け散る。正常な時の流れが戻り、陽菜と蓮は、ぜえぜえと肩で息をしながら床に座り込んでいた。
「今のは……アオ、お前から……?」
蓮が信じられないものを見る目で僕を見つめる。陽菜はただ、輝きを失いかけた瞳で、僕の手のひらを見つめていた。
第三章 結晶の伝説
「お主のその力、あるいは世界を救う鍵かもしれん」
学校の古びた図書館。司書の渡会(わたらい)先生は、埃をかぶった分厚い本を開きながら静かに言った。彼は、この世界の輝度と時間の法則を密かに研究している変わり者として知られていた。
僕が旧校舎での出来事を話すと、彼は深く頷いた。
「『時間の飽和地帯』は、巷で噂されるような『世界の病』などではない。ワシは、あれを過去の青春が遺した『祝福の残響』だと考えておる」
「祝福……ですか?」
「強すぎる輝度は、時にあふれ、未来の時間を侵食する。それはまるで、コップからあふれた水が床を濡らすようにな。そして、そのあふれた輝度が凝縮されたものが存在する」
渡会先生が指し示したのは、本の挿絵に描かれた半透明の結晶だった。
「ルミネッセンス・クリスタル。青春の感情が極限まで高まった瞬間に、ごく稀に生成される輝度の化石じゃ。飽和した時間を元に戻すには、この結晶に封じられた純粋な時間のエネルギーが必要になる」
最初のクリスタルの在り処は、この学校にある可能性が高いという。一年前の学園祭。閉鎖された旧体育館のステージで、ある生徒が放った輝きが、夜空を焦がすほどだった、と。
その生徒の名を、僕は知っていた。
第四章 君の記憶、僕の真実
旧体育館のステージの床板を一枚剥がすと、それは静かにそこにあった。夜空の色を閉じ込めたような、小さな青い結晶。埃の中で、自ら淡い光を放っている。
陽菜が生み出したクリスタルだ。一年前、学園祭のステージで、彼女はたった一人で歌ったのだ。緊張と、喝采への期待と、歌うことへの純粋な喜び。それらが混ざり合った感情が、この結晶を生んだ。
僕がそっと指で触れた瞬間、奔流が僕の意識を襲った。
陽菜の視界。陽菜の感情。スポットライトの熱さ、観客の息遣い、心臓の早鐘。そして、歌い終えた瞬間に全身を駆け巡った、雷のような達成感と歓喜。凝縮された時間の断片が、僕の中に流れ込んでくる。
同時に、僕は理解した。僕自身の存在の真実を。
僕に輝度がないのは、欠落ではなかった。他者の輝度を受け入れ、世界の均衡を保つための『器』として、僕は『空っぽ』である必要があったのだ。僕の能力は『保存』じゃない。『吸収』だ。強すぎる輝度が時間を飽和させてしまわないように、僕という存在が、その過剰なエネルギーを吸い上げる防波堤だった。
僕が今まで感じていた、世界からの疎外感。それこそが、僕が世界を守っている証だったのだ。
第五章 黄昏の選択
世界の終わりは、美しい黄昏の姿でやってきた。
空が、悲鳴を上げるように茜色と群青色のまだら模様に引き裂かれ、街中の時間が一斉に停止しかけた。世界規模の時間の飽和。過去の青春の輝きが、現在という時間を完全に喰い尽くそうとしていた。
校庭では、輝度の高い生徒たちが次々と意識を失い、その身体から光が急速に失われていく。陽菜も、蓮も、膝から崩れ落ちた。
もう、猶予はない。
僕は決意した。ポケットから集めた数個のルミネッセンス・クリスタルを取り出す。陽菜がくれた歌の結晶。蓮がくれた悔しさの結晶。僕が今まで吸収し、溜め込んできた無数の名もなき輝き。これら全てを解放し、飽和した時間に叩きつけ、未来への道をこじ開ける。
倒れている陽菜のそばにしゃがみこみ、僕は彼女の冷たくなった手をそっと握った。彼女の記憶に残ることはない、最初で最後の言葉を紡ぐ。
「君の輝きは、色のなかった僕の世界の、唯一の光だった」
ありがとう、陽菜。
僕は立ち上がり、天を仰いだ。手のひらに全てのクリスタルと、僕自身という『器』に満たされた全エネルギーを集める。身体が内側から灼けるように熱い。これが、僕のたった一度の、僕だけの輝き。
第六章 新しい朝
僕の身体は、純白の光の粒子となって霧散した。
解放されたエネルギーは、飽和し淀んでいた世界の時間を洗い流し、停滞した歯車を再び未来へと回し始めた。引き裂かれた空は一つに繋がり、失われた輝度は人々の元へ戻る。
世界の時間軸は、修復された。
――陽菜は、保健室のベッドで目を覚ました。
窓の外からは、新しい朝の光が差し込んでいる。なぜ自分がここで眠っていたのか、思い出せない。ただ、胸にぽっかりと穴が空いたような、温かい喪失感が残っていた。
教室に戻ると、友人たちが昨日と変わらない笑顔で迎えてくれた。でも、何かが違う。自分の隣の席。そこは空席で、誰も気にしていないのに、陽菜はそこにかつて誰かがいたような気がしてならなかった。
ふと窓の外を見る。空は、昨日までとは比べ物にならないほど、澄み切った青色をしていた。
その、あまりに深く、優しい青さに、なぜか涙がこぼれた。
誰も、蒼という少年を覚えていない。彼の存在した記録も記憶も、世界を修復する代償として、時の流れに溶けて消えた。
しかし、彼がいた証は、確かに世界に残された。
新たな世代の少年少女たちが、これから放つであろう青春の輝き。その一つ一つが、彼という防波堤の上に築かれる、未来そのものだった。空の青さに、風の匂いに、友の笑顔の中に、彼の残光は、いつまでも静かに揺らめき続ける。