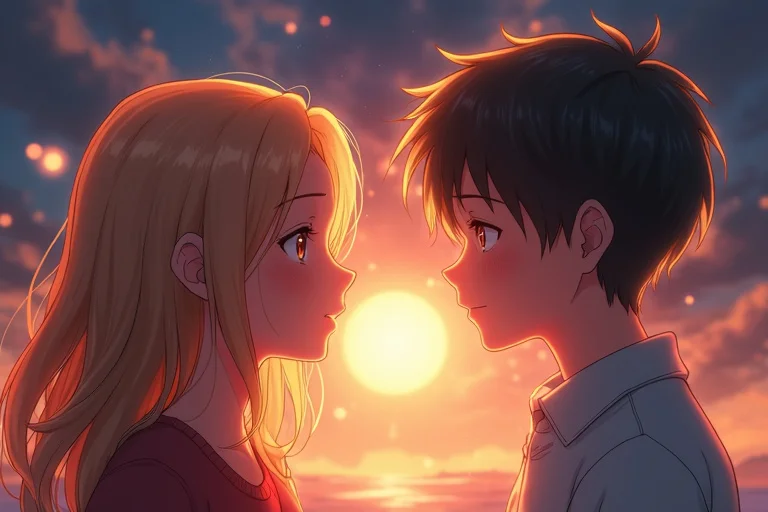第一章 亡霊との対話
半年前、親友の海斗が死んだ。
夏の終わりの、空が高すぎる青だった日。ニュースキャスターは、高波にさらわれた遊泳中の高校生、と無機質な声で伝えた。俺、杉浦樹の世界から、その日を境に音が消えた。色彩が褪せた。心臓のあたりにぽっかりと穴が空き、そこから絶えず冷たい風が吹き込んでいるような、そんな日々が続いた。
海斗の四十九日を過ぎた頃、俺は彼のおばさんに頼まれ、誰も足を踏み入れなくなった海斗の部屋を片付けていた。窓の外では、季節外れの蝉が力なく鳴いている。彼の部屋は、まるで持ち主がふらりとコンビニにでも出かけたかのように、時間が止まっていた。読みかけの漫画、脱ぎっぱなしのジャージ、そして、勉強机の隅に埃をかぶって積まれた、無数のカセットテープの山。
「何だ、これ」
手に取ると、白いラベルに海斗の走り書きのような文字が並んでいた。『7月10日、雨。』『7月14日、期末テスト最悪。』『7月22日、花火。』――音声日記。あいつ、こんな古風なことをしていたのか。ラジカセなんて、今どきどこに。見回すと、ベッドの下から古びたポータブルカセットプレーヤーが見つかった。ヘッドフォンを耳に当て、一番上のテープをセットする。再生ボタンを、祈るような気持ちで押し込んだ。
カシャン、という硬質な音。数秒のノイズの後、鼓膜を震わせたのは、紛れもない海斗の声だった。
『――マジで暑すぎ。アイス食いてえ。樹のやつ、今日部活サボりやがったな。あとでケツ蹴り上げに行かねえと』
息が、止まった。すぐそこに、海斗がいる。ひまわりの匂いがするような、からりとした太陽みたいな声。俺は無意識に、掠れた声で応えていた。
「……サボってねえよ。熱が出ただけだ」
当たり前だが、返事はない。テープは回り続け、その日の夕飯の文句や、新曲のギターリフが上手く弾けないというぼやきが流れてくる。俺は、その一つ一つに相槌を打ち、茶々を入れた。まるで、半年前まで当たり前だった放課後の会話のように。
その日から、俺の奇妙な習慣が始まった。学校から帰ると、まっすぐ海斗の部屋へ向かい、彼の音声日記を聞く。そして、テープの向こうの彼に話しかける。それは、死者との対話。俺だけの、秘密の儀式だった。穴の空いた心に、海斗の声が麻酔のようにじんわりと染み渡っていく。俺は、この禁断の慰めに、溺れるようにのめり込んでいった。
第二章 停止した時間
テープの中の海斗は、生きていた。当たり前だ。去年の夏、彼は確かに生きて、笑い、怒り、悩んでいた。
『美咲がさ、また図書室で寝てんの。あいつ、マジで本の匂い嗅ぐと眠くなる体質なのか? 今度、寝顔に落書きしてやろうぜ、樹』
「やめとけよ。絶対怒られる」
俺はヘッドフォン越しに苦笑しながら、現実の教室にいる美咲の顔を思い浮かべた。彼女は、俺と海斗の共通の友人だ。最近、心配そうに俺の顔を覗き込んでは、「大丈夫?」と繰り返す。大丈夫なわけがない。だが、それを説明する術を俺は持たなかった。「親友の遺した音声日記と会話してるんだ」なんて、言えるはずもない。
俺の世界は、海斗の部屋の六畳間に凝縮されていった。現実の時間は、もはやどうでもよかった。教室の喧騒も、教師の退屈な授業も、すべてがすりガラスの向こう側の出来事のように感じられた。俺にとってのリアルは、このヘッドフォンの中にだけあった。
カセットテープは、俺を過去へと誘うタイムマシンだった。海斗が語る夏の日々は、鮮やかな色彩を伴って脳裏に蘇る。二人で自転車を飛ばした海岸線。アスファルトの匂い、肌を焼く日差し、そして隣で笑う海斗の白い歯。テープを聞きながら目を閉じれば、今でも潮の香りがするような気さえした。
俺は幸福だった。そして、絶望的に孤独だった。
この「対話」は、完全な一方通行だ。俺がどれだけ叫んでも、質問しても、テープの中の海斗は脚本通りに喋り続けるだけ。その事実が、時折、鋭いナイフのように胸を刺した。俺は、彼の声のこだまが響くだけの、エコー・チェンバーに閉じ込められているに過ぎない。
「樹、あんた、最近ずっとあの子の部屋にいるんだって?」
ある日、廊下で美咲に呼び止められた。彼女の瞳には、心配と、わずかな苛立ちが浮かんでいる。
「……別に」
「別に、じゃないでしょ。顔色悪いよ。みんな心配してる。……そろそろ、前を向かなきゃ」
前を向け、か。簡単に言うな。お前に、俺の何がわかる。喉まで出かかった言葉を、俺は飲み込んだ。美咲は何も悪くない。悪いのは、過去という名の沼から抜け出せない、俺自身だ。
俺は彼女から逃げるようにその場を立ち去り、また海斗の部屋へ向かった。早く、彼の声が聞きたかった。現実の面倒な人間関係から、俺を守ってくれる、優しい声が。
第三章 ノイズの向こうの真実
テープの山も、残りわずかになってきた。日付は、事故のあった八月の最終週に近づいていく。俺は、その周辺の日付のテープを再生するのが、怖かった。そこに、彼の死の予兆が記録されていたら? 何も知らずに、最後の時へ向かう彼の無邪気な声を聞くことになったら?
だが、聞かないという選択肢はなかった。これは、俺が最後まで見届けなければならない、海斗の人生のエピローグなのだ。
そして、ついにそのテープを見つけてしまった。『8月28日』。事故の前日だ。俺は震える指で、それをプレーヤーにセットした。
いつもの陽気な声とは、まるで違った。ノイズの向こうから聞こえてきたのは、押し殺したような、切迫した声だった。
『……クソ、なんであんなこと言っちまったんだろ。でも、引けねえよな。樹のこと、馬鹿にされて黙ってられるかよ』
樹? 俺のことか? 心臓が嫌な音を立てて脈打つ。
『「お前の大事なダチ、根性なしの絵描き野郎だろ」って。……カッとなっちまった。あいつら、いつもそうだ。自分たちが一番偉いと思ってやがる』
声の主は、俺たちのクラスを牛耳っている、高城たちのグループだとすぐに分かった。彼らは、文化部で絵ばかり描いている俺を、昔から見下していた。海斗は、いつも俺の前に立って、盾になってくれていた。
『「そんなに言うなら、賭けるか?」って。言っちまった。「明日の夜、嵐が来るらしい。あの荒れた海で、沖の灯台まで泳いでタッチして帰ってこれたら、お前らの勝ちだ。そしたら、もう樹には手を出さねえ」って』
待て。何だ、それは。事故じゃ、なかったのか? 遊泳中なんかじゃなく、無謀な賭けだったというのか?
『もし俺が勝ったら、高城は俺に土下座して謝る。……バカな賭けだ。分かってる。でも、あいつらの鼻を明かしてやりてえ。樹が、あんな奴らに怯えずに、好きな絵を描けるようにしてやりてえんだよ』
全身の血が凍りつくようだった。俺の、せいだ。俺が弱かったせいで、海斗は無茶な賭けをして、そして――。
だが、衝撃はそれだけでは終わらなかった。テープの最後に、海斗は絞り出すような声で言った。
『……美咲には、悪いことしたな。あいつ、必死で止めてくれたのに。「そんな賭けをけしかけた高城くんも、最低だよ!」って泣かせて……。俺、あいつのこと、多分、好きだったんだけどな。まあ、いいか。樹のためだ』
美咲……?
美咲が、賭けのことを知っていた? そして、高城を庇うような、いや、違う。違う。これは……。
頭の中で、パズルのピースが、最悪の形で組み合わさっていく。美咲が、俺に「前を向け」と言った時の、あの苛立ちの混じった瞳。高城と美咲が、最近、一緒に下校しているのを何度か見かけたこと。
まさか。
いや。
海斗の声は、こう続いた。
『高城が賭けに乗ったのは、美咲が煽ったからだ。「海斗くんならできるんじゃない?」って。あいつ、俺が美咲のこと好きなの知ってて、高城にいい顔したかったのか……? 分かんねえよ。もう、何もかも』
カシャン。テープが終わり、静寂が訪れた。俺はヘッドフォンを床に叩きつけた。裏切り。それは、死んだ親友からのものではなく、生きている人間からの、冷たくて残酷な裏切りだった。俺が逃げ込んでいた過去は、美しい思い出なんかじゃなかった。そこにあったのは、俺の知らない、嫉妬と打算と、そして友の優しさが招いた、救いのない悲劇だった。
第四章 潮騒のエピローグ
数日間、俺は抜け殻のようになった。何も手につかず、ただ天井の染みを眺めて過ごした。海斗の声を聞くのが怖かった。最後のテープが一本、机の上に残っている。事故当日の、『8月29日』。それを聞けば、すべてが終わる。そして、俺は本当の独りになる。
意を決してヘッドフォンを手に取ったのは、雨が窓を叩く夜だった。プレーヤーに最後のテープを入れる。
再生ボタンを押す。ザーッという激しいノイズ。それは、雨音か、それとも、嵐の海の音か。
『……樹、聞こえるか』
海斗の声は、風の音に混じって、不思議と穏やかだった。
『これを、お前がいつ聞くか分かんねえけど。多分、俺が死んだ後なんだろうな。……もし俺が帰れなかったら、樹、お前はちゃんと前を向けよ』
遺言だった。それは、俺が今まで聞いてきた日常の断片とは違う、明確に俺に向けられた、最後のメッセージだった。
『俺のせいで、お前が自分のせいだなんて思うなよ。これは、俺が自分で決めたことだ。お前を守りたかったのは本当だけど、それだけじゃねえ。俺自身の、意地だったんだ。……だから、お前は、俺が守りたかったお前の未来を、ちゃんと生きろ。いっぱい絵を描け。笑って、泣いて、誰かを好きになれ。俺の分までなんて言わねえ。お前の人生を、全力で生きろ。……じゃあな、親友』
そこで、声は途切れた。あとには、荒れ狂う潮騒の音だけが、永遠に続くかのように響いていた。
涙が、止まらなかった。罪悪感も、裏切られた怒りも、喪失の悲しみも、すべてが涙に溶けて流れ落ちていくようだった。海斗は、俺に「生きろ」と言った。過去に囚われるなと、最後に教えてくれた。
俺は、カセットプレーヤーの電源を切り、ヘッドフォンをそっと外した。もう、彼の声に逃げるのは終わりだ。
翌日、俺は学校へ行くと、まっすぐ美咲のところへ向かった。彼女は俺の顔を見て、怯えたように目を伏せた。俺は、何も言わなかった。ただ、彼女を見つめた。彼女を責める言葉は、一つも浮かんでこなかった。彼女もまた、自分の過ちという名の地獄の中で、ずっと苦しんできたのかもしれない。それで十分だった。
俺は踵を返し、自分の席に戻った。そして、鞄からスケッチブックと鉛筆を取り出した。半年ぶりに開いたページは、真っ白だった。
窓の外には、あの日のような、突き抜ける青空が広がっている。
もう、ヘッドフォンの中から海斗の声は聞こえない。けれど、目を閉じると、今も耳の奥で潮騒の音が聞こえる気がした。それは、彼が生きた証。彼が俺に託した、未来へのプロローグ。
俺は、真っ白なページに、震える線で、水平線を描き始めた。彼のいない世界で、俺の物語を、ここから始めるために。