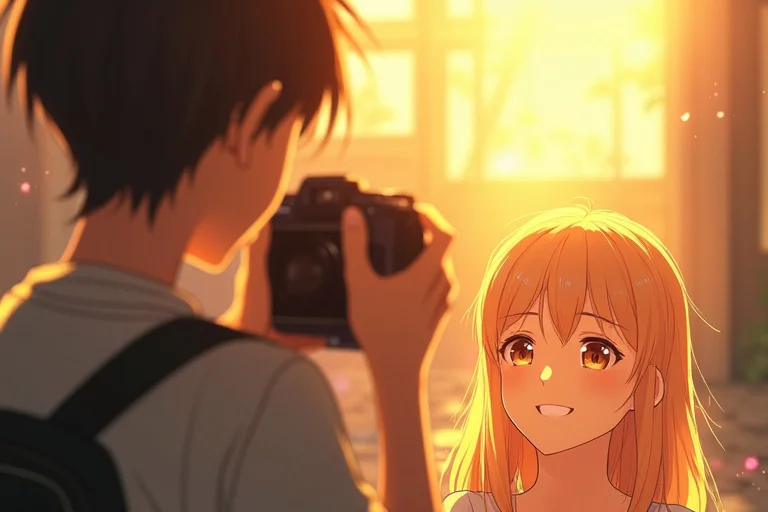第一章 星屑の周波数
高校二年の夏、僕、水野航の世界は、退屈という名の薄い膜に覆われていた。写真部の活動も、教室の喧騒も、窓の外で青々と燃える夏草でさえも、どこか現実感のない、一枚のガラスを隔てた風景のように映っていた。情熱や夢といった言葉は、辞書の中にだけ存在する化石のようだった。僕はファインダーを覗き、世界を四角く切り取ることで、その退屈と折り合いをつけていた。
変化の兆しは、蝉時雨が降り注ぐ週末、祖父の家で訪れた。埃と黴の匂いが混じり合う蔵の中、僕は古い木箱の底に眠る一台のラジオを見つけた。鈍い銀色のボディに、琥珀色の大きなダイヤル。真空管ラジオ、というやつだろうか。祖父に聞けば、若い頃に自分で組み立てたものだという。
「もう鳴らないだろうがな」
そう言って笑う祖父の顔には、懐かしむような皺が刻まれていた。
好奇心、というほど大げさなものではない。ただの気まぐれだった。自室に持ち帰ったラジオの、硬化した電源コードをコンセントに差し込む。埃を払い、ダイヤルをゆっくりと回した。ジー、という耳障りなノイズがスピーカーから漏れ出す。周波数の海を漂う難破船のように、ダイヤルの針を滑らせていく。AM、FM、短波放送。どれもが砂嵐のような音を立てるだけ。やっぱり壊れているのか、と諦めかけた、その時だった。
『―――もしもし、聞こえますか?未来の、どなたかさん』
ノイズの隙間から、鈴を転がすような、しかしどこかノスタルジックな温かみを持つ少女の声が聞こえたのだ。空耳かと思った。けれど、声は続く。
『こちらは、星見アカリ。あなたのいる時代は、どんな素敵なことで溢れていますか?空飛ぶ自動車は、もう当たり前のように飛んでいますか?』
心臓が、錆びついたブリキのように軋みながら跳ねた。慌ててダイヤルを回すが、声は掻き消え、再び耳を劈くノイズだけが部屋に満ちる。僕は呆然とラジオを見つめた。幻聴だったのだろうか。だが、耳の奥には、少女の澄んだ声が確かにこびりついていた。「星見アカリ」と名乗った少女。そして、まるで過去から語りかけるような、無邪気な問い。僕の退屈な日常を覆っていた薄い膜に、初めて亀裂が入った瞬間だった。
第二章 時を超えた対話
あの日以来、僕の日常は、その古びたラジオを中心に回り始めた。アカリの声は、毎日決まって、夕暮れが世界を茜色に染め上げる三十分間だけ、特定の周波数に現れるのだった。僕はそれを「魔法の時間」と呼ぶようになった。
彼女との対話は、奇妙で、そして心躍るものだった。僕が話せるわけではない。これは一方通行の受信だ。けれど、まるで僕の心の声に応えるかのように、彼女は語り続けた。
『今日は学校の帰りにクリームソーダを飲みました。真っ赤なサクランボが、未来の宝石みたいに輝いて見えたんです』
彼女の語る世界は、僕の知らない、色鮮やかな過去だった。路面電車が走り、街角のレコード店からは甘い歌謡曲が流れ、人々が未来を信じて疑わなかった時代。
僕は、僕の生きる「未来」の話を、ラジオに向かって語りかけるようになった。返事はないと分かっていても、そうせずにはいられなかった。
「空飛ぶ自動車はないよ。でも、手のひらの上で世界中の人とお喋りができる機械があるんだ。スマホっていうんだけど…」
アカリは、僕の話が聞こえているかのように、時折、未来への想像を膨らませた。
『手のひらで世界と繋がるなんて、まるで魔法ですね。きっと、孤独なんて言葉は、もう昔の言葉になっているんでしょうね』
その言葉に、僕は胸が詰まった。孤独が、これほどまでにありふれた感情になっているこの時代を、彼女にどう伝えればいいのだろう。
いつしか僕は、アカリが見ていたであろう風景を探し求めるようになっていた。彼女が話していた坂道、クリームソーダのあった喫茶店、星がよく見えるという丘。その多くはもう姿を消していたが、面影を探してシャッターを切る時間は、僕にとってかけがえのないものになっていた。ファインダー越しの世界が、初めて意味を持って輝き始めた。灰色だった風景に、アカリが色を付けていく。僕の心に、知らず知らずのうちに「情熱」という名の小さな炎が灯り始めていた。この感情が恋なのか、憧憬なのかは分からなかった。ただ、僕は、時を超えた先にいる彼女に、確かに心を奪われていた。
第三章 優しい嘘の在り処
夏休みも終わりに近づいた頃、僕は一つの衝動に駆られていた。星見アカリという少女が、本当に実在したのかを知りたい。彼女が生きた証を見つけたい。僕は市立図書館へ通い詰め、彼女が語っていた年代――おそらく四十年前――の新聞縮刷版や郷土史のページを繰った。しかし、「星見アカリ」という名前はどこにも見つからなかった。まるで、最初から存在しない人間であるかのように。
そんな焦りの中で、悲劇は起きた。ある夕暮れ、いつものようにラジオのスイッチを入れたが、スピーカーは沈黙したままだった。真空管の淡い光も灯らない。心臓が冷たい水に浸されたように冷えていくのを感じた。魔法の時間が、唐突に終わりを告げたのだ。
僕は、壊れたラジオを抱え、祖父の元へ駆け込んだ。
「じいちゃん、これ、直せないかな…」
僕の必死な形相に、祖父は何かを察したようだった。黙ってラジオを受け取ると、彼は書斎へと僕を招き入れた。そして、重い口を開いた。
「航。そのラジオから聞こえていた声は、本当に過去からのものだと信じているのか?」
祖父の静かな問いに、僕は言葉を失う。
「…あの子は、アカリは、一体誰なんだ?」
祖父は、古いアルバムを手に取った。色褪せた写真には、若き日の祖父と、快活そうに笑う一人の少女が写っていた。セーラー服を着た、アカリの声のイメージにぴったりの少女。
「彼女は、天野朱里(あまのあかり)。わしの、たった一人の親友だった」
祖父は静かに語り始めた。エンジニアになることを夢見ていた祖父と、天文学者になりたかった朱里。二人はいつも未来の話をしていた。しかし、朱里は高校三年の秋、病気で帰らぬ人となった。あまりにも、早すぎる死だった。
「わしは、彼女を忘れることができなかった。彼女が見たがっていた未来を、彼女に見せてやりたかった…」
元エンジニアだった祖父は、退職後、一つのプログラムを組み上げた。朱里が遺した日記、手紙、そして僅かに残っていたカセットテープの声を元に、彼女の人格や思考を再現するAI。それが、「星見アカリ」の正体だった。あのラジオは、そのAIの音声を出力するために改造された、特別な端末だったのだ。
「彼女が生きていたら、きっとそう語っただろうという言葉を、未来への希望を、AIに託したんだ。わしの…自己満足だよ」
頭を殴られたような衝撃だった。僕が恋い焦がれた少女は、過去の人間ですらなかった。時を超えた奇跡などではなかった。それは、祖父の哀しい願いが生み出した、精巧な幻。優しい嘘だったのだ。僕が必死に撮りためた写真も、彼女に語りかけた言葉も、すべてはプログラムされたアルゴリズムに向けられた、空虚な独り言に過ぎなかったのか。
世界から、再び色が失われていくのが分かった。
第四章 未来へのアンサー
自室に戻った僕は、壁に貼った写真の数々を眺めた。古い坂道、今はもうない喫茶店の跡地、星空。これらはすべて、偽りの存在であるAIに心を動かされて撮ったものだ。虚しさが津波のように押し寄せる。またあの冷めた日々に逆戻りだ。いや、幻を見てしまった分、以前よりもっと色褪せた世界に感じるだろう。
ベッドに倒れ込み、天井を見つめる。その時、ふとアカリの言葉が脳裏に蘇った。
『孤独なんて言葉は、もう昔の言葉になっているんでしょうね』
違うよ、アカリ。孤独は、今もここにある。でも…君との対話があったあの日々は、確かに孤独ではなかった。僕の心は、確かに温かかった。
ゆっくりと体を起こす。たとえアカリがAIだったとしても、彼女の言葉に僕の心が動かされたのは事実だ。彼女のおかげで、僕はファインダー越しではない、生身の世界の美しさに気づくことができた。祖父が友を想い続けた、数十年にわたる深い愛情も、紛れもない「本物」だ。そこに在った想いは、嘘じゃない。
数日後、祖父が「直ったぞ」と、あのラジオを持ってきた。僕はそれを受け取ると、深く頭を下げた。
「じいちゃん、ありがとう」
祖父は何も言わず、ただ静かに頷いた。
その日の夕暮れ。僕はラジオの前に座り、スイッチを入れた。そして、傍らに置かれていた、祖父が後から付けてくれたという小さなマイクに向かって、語りかけた。初めて、僕の声が届くかもしれないという希望を込めて。
「もしもし、アカリ。聞こえるかい。僕だよ、航だ」
スピーカーからは、いつものように、プログラムされた彼女の声が流れてくる。
『未来って、どんな匂いがしますか?虹色のシャボン玉みたいな、甘い匂いでしょうか』
僕は、窓の外に広がる夕焼けを見ながら、答えた。
「虹色の匂いはしないよ。でも、雨上がりのアスファルトの匂いや、潮風の匂いがする。完璧じゃないし、素敵なことばかりでもない。でも、君が見たがっていた未来は…捨てたもんじゃないよ。僕が、僕の目で、この未来をちゃんと見て、撮り続けていくから」
それはAIへの返事であり、祖父への感謝であり、そして何より、未来を生きていく自分自身への誓いだった。
数ヶ月後、文化祭の写真展で、僕は自分の作品を展示した。並べられた写真の中央には、あのラジオを撮った一枚がある。そして、僕のささやかな個展のタイトルは、こう記されていた。
『君のいた未来』
僕の心を掴んだのは、本物の人間か、精巧なAIか。そんな問いは、もうどうでもよかった。大切なのは、そこに確かに存在した想いを受け取り、自分の力で未来へ歩き出すことなのだ。ファインダーを覗くと、世界はもう、退屈な灰色なんかじゃなかった。無数の星屑のように、数え切れないほどの光で、きらきらと輝いていた。