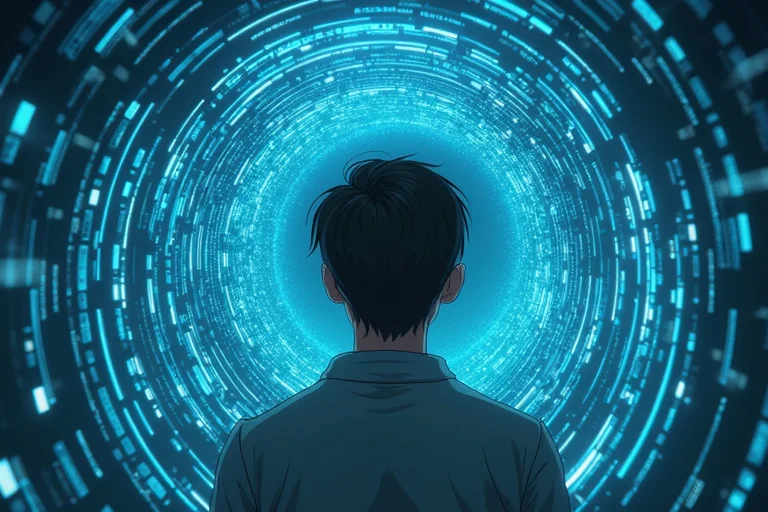第一章 コンクリートの王国
柏木修一の腕時計が示す時刻は、午後七時。彼の世界では、まだ一日の折り返し地点に過ぎない。都心の一等地に聳え立つガラス張りのオフィスビル、その三十階から見下ろす夜景は、彼が築き上げてきた王国の版図そのものだった。無数の光の粒は、彼が率いる大手建設会社「帝都建設」が手掛けたビルやマンション。光は富であり、力だった。
「部長、例の『ひだまり食堂』の件ですが、最終通告の期限が明日です」
部下の報告に、修一はモニターから目を離さずに頷いた。
「予定通り進めろ。感傷に付き合っている暇はない」
湾岸エリアの再開発プロジェクト。その最後の障害が、時代に取り残されたような木造家屋で営まれる、小さな「こども食堂」だった。立ち退きを拒む老婆が一人。法的には、こちらの完全な勝利だ。だが、メディアが嗅ぎつければ「弱者イジメ」と騒がれかねない。だからこそ、修一は自ら現地に赴くことにした。最短距離で、終わらせるために。
翌日の午後、修一は黒塗りのハイヤーを路地に待たせ、その古びた家の前に立った。錆びたトタン屋根に、傾きかけた木の看板。「ひだまり食堂」。ガラス戸の向こうから、醤油と出汁の混じった温かい匂いが漏れてくる。彼の世界には存在しない、非効率で、感傷的な匂いだった。
「ごめんください」
声を張り上げると、奥から現れたのは、腰の曲がった小柄な老婆だった。高遠ハツ。資料で見た通りの顔だ。
「柏木と申します。帝都建設の者です」
修一は、一切の感情を排した声で言った。
「明日が期限です。ご理解いただけましたか」
ハツは、深い皺の刻まれた目元を和らげ、静かに首を横に振った。
「ここは、なくすわけにはいかないんですよ」
その穏やかだが、揺るぎない声に、修一は苛立ちを覚えた。食堂の中では、五、六人の子供たちが、一つのテーブルを囲んで宿題をしたり、小声で笑い合ったりしている。その光景が、修一には現実感のない芝居のように見えた。
「法的な手続きは完了しています。我々は正当な権利を行使するだけです」
「権利、ですか」
ハツは、ふっと息を吐いた。「あなた方の正しさは、この子たちの晩ごはんより、重いものですかねぇ」
戯言だ、と修一は思った。これはビジネスだ。個人の感傷が、数十億規模のプロジェクトを停滞させることなどあってはならない。彼は冷たく言い放った。
「では、明日、執行官と共に参ります」
背を向けた修一の耳に、子供たちの屈託のない声が届く。その声は、彼の築き上げたコンクリートの王国に響く、不協和音でしかなかった。
第二章 見えない亀裂
自宅のドアを開けても、「おかえり」の声はない。広々としたリビングは、モデルルームのように整然としているが、生活の匂いがしなかった。数年前に妻を病で亡くして以来、この家はただの箱になった。
「美咲、いるか」
高校生の娘の部屋をノックする。返事はない。ドアを開けると、美咲はヘッドフォンをしてベッドに寝転がり、こちらに背を向けていた。食卓に用意した夕食には、ラップがかかったままだ。
「飯は食べたのか」
「……いらない」
くぐもった声が返ってくる。いつからだろう。娘との間に、こんなにも分厚い壁ができてしまったのは。
翌日、修一は高校の担任教師に呼び出された。会議室で向き合った若い教師は、言いにくそうに口を開いた。
「お嬢さん、最近、学校で孤立しているようです。成績も……正直、かなり落ちています」
修一は絶句した。成績優秀で、友人も多かったはずの娘が?
「何か、ご家庭で変わったことは?」
「いや、特に……」
何も答えられない自分がいた。娘が何を悩み、何に苦しんでいるのか、全く知らなかった。自分の王国を広げることに夢中で、足元にできた深い亀裂に気づいていなかったのだ。
その夜、美咲は帰ってこなかった。午後十時を過ぎても連絡一つない。焦燥感に駆られた修一は、コートを羽織って家を飛び出した。塾か、友人の家か。心当たりのある場所に電話をかけても、誰も美咲の行き先を知らなかった。
冷たい夜風が頬を打つ。無意識に、車で湾岸エリアを彷徨っていた。煌びやかな高層マンション群と、再開発を待つ古い街並みが、境界線のように隣り合っている。その境界に、ぽつんと灯る小さな明かりを見つけた。
『ひだまり食堂』。
なぜだか分からない。磁石に引かれるように、修一は車を停め、その灯りに近づいた。
ガラス戸の隙間から中を覗き込み、修一は息を呑んだ。
見覚えのある制服。俯き加減に、黙々とご飯をかき込んでいるのは、紛れもなく美咲だった。その隣には、見知らぬ子供たち。そして、そんな彼らを、ハツが優しい目で見守っている。
裕福な家庭で、何不自由なく育ててきたはずの娘が。なぜ、こんな場所で、施しのような食事を受けているのか。怒りと混乱で、頭が真っ白になった。
第三章 ひだまりの告白
「美咲!」
修一は、勢いよく戸を開けた。彼の怒声に、食堂の穏やかな空気が凍りつく。美咲はビクリと肩を震わせ、顔を上げた。その目には、怯えと、見つけてくれるなと願っていた絶望の色が浮かんでいた。
「何をしているんだ、こんな所で!帰るぞ!」
修一が娘の腕を掴もうとした瞬間、細い腕が、しかし力強くその手を制した。ハツだった。
「お待ちください。この子を、追い詰めないでやってください」
「黙れ!あんたが娘を唆したのか!」
「お父さん、やめて!」
美咲の悲鳴のような声が響いた。その声に、修一は初めて娘の心の叫びを聞いた気がした。
ハツは、静かに修一を見据えた。その瞳は、怒りでも非難でもなく、深い悲しみに濡れていた。
「この子が、初めてここに来た日のことを、覚えてますよ」
ハツはゆっくりと語り始めた。ひと月ほど前、美咲は偶然この食堂の前を通りかかった。学校にも家にも居場所がなく、心の置き場を探して彷徨っていたのだという。
「この子はね、お腹が空いていたんじゃない。心が、ずっと飢えていたんですよ」
修一の完璧主義と高い期待。亡き母の不在。誰も、彼女の心の飢えに気づいてやれなかった。友人たちとの間にも、裕福な家庭という見えない壁があり、本当の自分を晒せなかった。この小さな食堂だけが、何も問わず、ただ温かいご飯を出してくれる唯一の場所だったのだ。
修一は言葉を失った。娘の孤独に、全く気づいていなかった自分を恥じた。
「……なぜ、こんなことをしているんだ。たかが子供に飯を食わせるために、巨大なプロジェクトを邪魔してまで」
絞り出すような修一の問いに、ハツの瞳から一筋の涙がこぼれ落ちた。
「三十年前、私にも息子がいました」
その告白は、思いがけないものだった。
「あの子は、とても優秀で、自慢の息子でした。一流大学を出て、誰もが羨むような大企業に就職して……」
ハツは言葉を切り、修一の目を真っ直ぐに見た。
「帝都建設、という会社でした」
雷に打たれたような衝撃が、修一の全身を貫いた。
「息子は、過労とプレッシャーで心を病んでいきました。それでも、弱音一つ吐かなかった。周りの期待に応えようと、必死だったんでしょう。そしてある朝、あの子は……自分で自分の人生を、終わらせてしまったんです」
食堂に、沈黙が落ちる。時計の秒針の音だけが、やけに大きく響いた。
「遺書もありませんでした。ただ、部屋の机に、コンビニのおにぎりが一つ、手付かずで置いてあった。あの子は、きっと最後の最後まで、誰にも『助けて』と言えなかった。お腹は満たされていても、心はずっと飢えていたんです。私が、一番近くにいた母親が、その飢えに気づいてやれなかった……」
ハツの言葉は、鋭い刃となって修一の胸に突き刺さった。効率。成果。利益。彼が信奉してきた全てが、音を立てて崩れ落ちていく。自分が追い求めてきた「正しさ」が、誰かの命を追い詰め、そして今、自分の娘をも同じ淵に立たせていたのかもしれない。
目の前にいるのは、立ち退きを拒む頑固な老婆ではない。自分と同じように、愛する者を守れなかった、一人の母親の姿だった。
第四章 瓦礫の上の食卓
オフィスに戻った修一は、別人になっていた。
「湾岸プロジェクト、一度凍結できないか。住民との合意形成に、根本的な問題がある」
役員会議での彼の発言に、周囲は凍りついた。これまで誰よりも計画推進を叫んでいた男の、百八十度の転換だった。当然、彼の意見は一蹴された。だが、修一は諦めなかった。彼は初めて、利益のためではなく、守るべきもののために頭を下げ、かつて築いた人脈を駆けずり回った。
強制執行の日は、刻一刻と迫っていた。会社の決定は覆らない。ならば、と修一は別の道を探し始めた。彼は、再開発エリアの図面を広げ、自分の知識を総動員して、代替地を探した。近隣の商店街にある、シャッターが下りたままの古い惣菜屋。所有者を突き止め、何度も足を運んで交渉した。
執行日の前夜。ひだまり食堂には、最後の灯りがともっていた。修一は、美咲と共にその戸をくぐった。
「高遠さん」
修一は、一枚の契約書をテーブルに置いた。「新しい場所です。ここより少し狭いですが、家賃は私が保証します」
ハツは驚いたように目を見開き、やがて、深く、深く頭を下げた。
その夜、取り壊しを待つ古い食堂で、三人は食卓を囲んだ。ハツが作った、何の変哲もない肉じゃが。だが、その一口が、修一の乾ききった心にじんわりと染み渡っていくのがわかった。ぎこちない沈黙の中で、美咲がぽつりと言った。
「……おいしい」
その言葉に、修一も、ハツも、静かに微笑んだ。
数ヶ月後。新しい『ひだまり食堂』には、以前と変わらず子供たちの声が響いていた。その片隅で、慣れない手つきで野菜の皮を剥いているのは、スーツを脱ぎ、エプロンをつけた修一の姿だった。時折、隣で配膳を手伝う美咲と、ぎこちない会話を交わす。失われた時間を取り戻すのは、簡単ではないだろう。だが、父と娘の間には、確かな雪解けの気配が満ちていた。
修一は思う。自分は今まで、たくさんの高層ビルを建ててきた。だが、本当に価値があったのは、冷たいコンクリートの城ではなく、この小さな食堂に灯る、温かい光だったのではないか。社会という巨大な構造を、一人で変えることなどできない。しかし、目の前の一人の、声なき「飢え」に気づき、そっと手を差し伸べることはできる。
窓の外では、解体された古い食堂の跡地で、巨大なクレーンが動き始めている。瓦礫の中から、また新しい王国が生まれようとしていた。だが修一はもう、空を見上げることはなかった。彼の視線の先には、湯気の立つご飯を頬張る子供たちの笑顔と、その隣で静かに微笑む娘の横顔があった。本当の豊かさとは何か。その答えの欠片が、確かにここにあると信じられた。