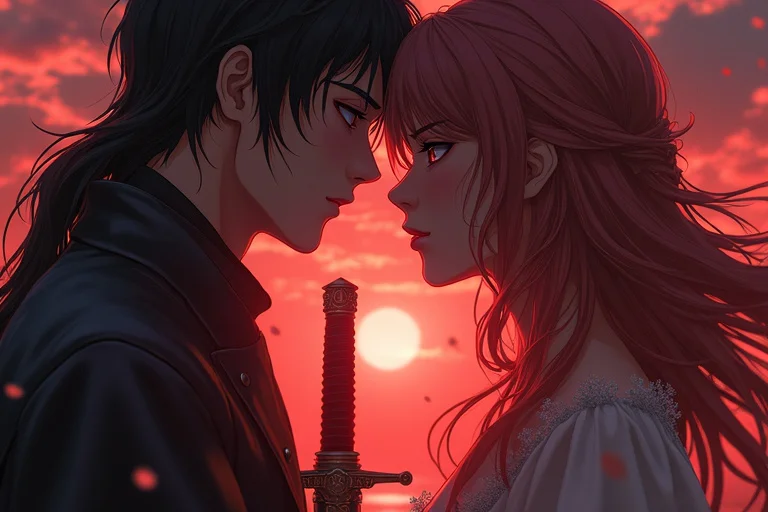第一章 奇妙な依頼人
橘伊織(たちばな いおり)の仕事場は、油と古い木の匂いがした。江戸の片隅、陽の当たらぬ長屋の一室で、彼は「繕い屋」を営んでいる。欠けた茶碗を漆で継ぎ、骨の折れた番傘を直し、鼻緒の切れた下駄を蘇らせる。その手は驚くほど器用で、どんな壊れた物も、まるで最初からそうであったかのように元通りにしてしまうのだった。
だが、伊織の手がかつて握っていたのは、鑿(のみ)や槌(つち)ではない。人を斬るための、冷たい鉄の塊であった。ある藩で剣術指南役まで務めた男が、今では血の匂いを嫌い、刃物といえば小刀一本を商売道具にするだけの、静かな暮らしに埋もれていた。その背中には、拭い去れぬ過去が錆のようにこびりついている。
ある雨の日の午後だった。降りしきる雨音が仕事場の静寂を支配する中、戸口に小さな影が立った。十歳になるかならぬか、痩せた体躯に襤褸(ぼろ)をまとった少女だった。その腕には、同じくらいみすぼらしい、しかし作りは精巧な一体の絡繰り人形が抱かれている。少女は何も言わない。ただ、大きく潤んだ瞳で、じっと伊織を見つめている。
「どうした、嬢ちゃん。何か直してほしいのか」
伊織が声をかけると、少女はこくりと頷き、おずおずと中へ入ってきた。そして、大切そうに抱えていた人形を畳の上にそっと置く。それは、美しい着物を着た童子の姿をしていたが、片腕はだらりと垂れ、顔には深い亀裂が走っていた。見るからに、もはや動きそうにない。
「……これは、ひどいな。直せるかどうか」
伊織が人形に手を伸ばそうとした、その時だ。少女は小さな紙切れを差し出した。震える指で書かれた、拙い文字。そこに記されていた言葉に、伊織は息を呑んだ。
『これを、斬ってください』
斬る? 繕い屋の俺に、斬れと? 伊織は眉をひそめ、少女の顔を見返した。少女は言葉を発せないのか、ただ必死の形相で頷くだけだ。その瞳の奥には、懇願と、そして奇妙なほどの覚悟が宿っていた。
「冗談じゃない。俺は物を直すのが仕事だ。壊すのはごめんだ」
伊織は冷たく突き放した。過去の残像が脳裏をよぎる。剣を振るった時の、肉を断つおぞましい感触。二度と味わいたくない感覚だった。しかし、少女は動かない。雨に濡れた体から、か細い湯気が立つ。その姿は、まるで雨に打たれる地蔵のように、哀れで、そして頑なだった。
伊織は深いため息をつき、頭を掻いた。この少女の瞳は、知っている。かつて自分が斬り捨てた男の、最後の瞬間の瞳に似ていた。何かを託し、何かを訴える、忘れようとしても忘れられない光。
「……分かった。わけは聞かん。だが、斬るかどうかは、俺がこれを調べてからだ。それでいいな」
少女の顔に、ぱっと安堵の色が浮かんだ。彼女は深く、深く頭を下げると、人形を伊織に託し、雨の中へと消えていった。残されたのは、言葉を失った絡繰り人形と、伊織の胸に生まれた、解けぬ謎の染みだけだった。
第二章 絡繰り人形の記憶
少女は、名を小夜(さよ)といった。翌日から毎日、彼女は伊織の仕事場に現れ、隅の方で膝を抱え、伊織が人形を調べる様子をじっと見守った。言葉はなくとも、その存在は伊織の日常に静かな波紋を広げていった。
伊織は人形を『時雨(しぐれ)』と名付けた。雨の日にやってきた、不思議な客だったからだ。彼はまず、時雨の外装を丁寧に外し、内部の絡繰りを検分し始めた。それは、息をのむほど精緻な仕事だった。幾百もの歯車と発条(ばね)が、まるで人体の臓腑のように複雑に絡み合い、一つの宇宙を形成している。
「……大したもんだ。これを作った奴は、きっと稀代の絡繰り師だろうな」
伊織の呟きに、小夜の肩が小さく揺れた。伊織が時雨の壊れた腕を手に取ると、その指先が微かに動いた。まるで、何かを掴もうとするかのように。その仕草に、伊織はふと、己の過去を重ねていた。剣を握り、型を稽古する日々。指先に伝わる柄の感触、切っ先が空気を切り裂く音。繕う手と、斬る手。正反対の行為が、指先の記憶を通じて奇妙に交錯する。
その頃、伊織の住む界隈に、柄の悪い浪人たちの姿が見え隠れするようになった。彼らは何かを探しているようで、鋭い目つきで道行く人々を品定めしていた。伊織はただならぬ気配を感じ取り、戸締りを一層厳重にした。
ある夜、伊織は一人、酒を煽っていた。傍らには、まだ修復途中の時雨が横たわっている。月光が仕事場に差し込み、道具の影を長く伸ばしていた。彼は、なぜ自分が剣を捨てたのかを思い出していた。藩の権力争いに巻き込まれ、無二の親友を、上意討ちという名目で斬らなければならなかった日。友は「お前は悪くない」と笑って死んだ。その笑顔が、今も伊織を苛む。以来、彼の剣は錆びつき、心と共に鞘の奥深くで眠っている。
不意に、時雨の顔の亀裂が、月光の下で涙の痕のように見えた。伊織はそっとその頬に触れる。冷たい陶器の肌。だが、その奥に、作り手の温かい魂が宿っているような気がした。この人形を、本当に斬ってしまっていいのだろうか。小夜の願いと、この人形に込められたであろう作り手の想い。二つの間で、伊織の心は大きく揺れていた。
「お前は、何を伝えたいんだ……」
問いかけに、時雨は答えない。ただ、静かな闇の中で、伊織の過去と現在を、じっと見つめているかのようだった。
第三章 時雨の涙
数日後、伊織はついに時雨の絡繰りの中枢に辿り着いた。心臓部にあたる最も複雑な機構。そこを修理すれば、あるいは再び動き出すかもしれない。彼は慎重に、小さな歯車を一つ、また一つと調整していく。その時だった。指先に、カチリ、という微かな感触があった。それは、通常の絡繰りの動きとは明らかに異なる、隠された仕掛けの音だった。
興味を惹かれた伊織が、その部分をさらに探ると、胸部の内側に偽装された小さな空洞が現れた。中には、油紙で厳重に包まれた一巻の書状が収められている。伊織は息を殺してそれを取り出し、灯りの下で開いた。
そこに記されていたのは、伊織がかつて仕えた藩――その重役たちによる、幕府への献上品の横領と、不正な蓄財の克明な記録だった。藩の財政を蝕む巨悪の証拠。書状の最後には、一人の男の名が署名されていた。
『絡繰り師・玄斉(げんさい)』
伊織の脳裏に、電光が走った。玄斉。その名は、当代随一と謳われた伝説の絡繰り師だ。数ヶ月前、不慮の事故で死んだと噂されていた男。
全てが繋がった。玄斉は藩の不正を知り、この密書を最も安全な場所――自身の最高傑作である絡繰り人形の胎内に隠したのだ。そして、追っ手に気づかれる前に、娘である小夜に人形を託し、口封じのために殺された。小夜が「斬ってくれ」と頼んだのは、父の最後の遺言だったに違いない。この人形を壊し、中の密書を取り出せ、と。少女のあの必死な瞳は、父との最後の約束を果たすための覚悟の光だったのだ。
伊織が愕然としていると、外が急に騒がしくなった。戸板を乱暴に叩く音。
「開けろ! この中にいるのは分かっているんだ!」
あの浪人たちだ。彼らは藩が放った刺客。ついにこの場所を突き止めたのだ。伊織は咄嗟に密書を懐に隠し、小夜の手を引いて仕事場の奥へと下がった。小夜は恐怖に体を震わせ、伊織の着物の袖を固く握りしめている。
次の瞬間、木っ端微塵になる音と共に、戸板が蹴破られた。鋭い眼光を放つ三人の男が、抜き身の刀を手に、ずかずかと上がり込んでくる。
「娘と、その人形を渡してもらおうか。大人しくすれば、命だけは助けてやる」
頭目らしき男が、下卑た笑みを浮かべた。伊織は小夜を背にかばい、静かに男たちと対峙する。仕事場には繕いの道具しかない。対する相手は、殺意に満ちた真剣。絶体絶命だった。
「……断る」
伊織の声は、自分でも驚くほど落ち着いていた。
「その子も、人形も、俺の客だ。手出しはさせん」
その言葉は、もはや単なる繕い屋のものではなかった。錆びついたはずの魂の奥底で、何かがカチリと音を立てて動き出す。それは、時雨の絡繰りが見せた、希望の仕掛けの音によく似ていた。
第四章 夜明けの太刀音
「ほざけ!」
浪人の一人が、怒号と共に斬りかかってきた。伊織は小夜を突き飛ばして身をかわし、傍にあった手頃な樫の木の角材を掴む。キン、と鈍い音を立てて刃を受け止めるが、木材は無惨にも半ばまで断ち切られた。多勢に無勢、武器もない。このままでは嬲り殺しにされるだけだ。
小夜の怯えた顔が視界の隅に入る。あの瞳。守ると決めたのだ。過去の亡霊に囚われ、逃げ続けてきた自分は、もうここにはいない。
伊織の脳裏に、親友の最後の言葉が蘇る。『お前の剣は、人を活かすこともできるはずだ』。あの時は、その意味が分からなかった。だが、今なら分かる。守るべき者のために振るう時、剣は命を奪うだけの道具ではなくなる。
伊織は決意した。彼は角材を投げ捨て、部屋の隅に立てかけてあった、長い布に巻かれた棒状の物へと走った。刺客たちが訝しむ中、伊織は布を解く。現れたのは、埃をかぶった、一振りの刀。何年も抜かれることのなかった、彼の魂そのものだった。
鯉口を切り、刀身を抜き放つ。月光を浴びた刃は、錆びてなどいなかった。手入れこそされていないが、その輝きは少しも失われていない。伊織が柄を握りしめると、まるで血が通うかのように、刀が手に馴染んだ。
「……来るがいい」
空気が変わった。さっきまでの繕い屋の男ではない。そこに立つのは、修羅場をくぐり抜けてきた、本物の剣士だった。刺客たちの顔から笑みが消え、緊張が走る。
三方からの同時攻撃。しかし、伊織の動きは彼らの予測を遥かに超えていた。一歩踏み込み、一人の喉元を峰で打つ。体を翻し、二人目の突きを紙一重でかわしながら、その腕を柄頭で強打し、刀を落とさせる。最後の頭目の斬撃を、刀身で受け流す。火花が散り、甲高い金属音が夜の静寂を切り裂いた。
伊織の剣に、殺気はない。ただ、相手の力をいなし、戦意を削ぐための、正確無比な太刀筋。それは舞のように美しく、そして恐ろしいほどに完成された剣技だった。やがて、三人の刺客はことごとく打ち倒され、畳の上に呻き声を上げて転がっていた。誰一人、命を奪うことなく。
伊織は刀を納め、静かに息を吐いた。肩に浅い切り傷を負っていたが、不思議と心は晴れやかだった。夜が明け始め、東の空が白み始めていた。
密書は、伊織の手によって無事、町奉行所の信頼できる役人の手に渡った。藩の悪事は白日の下に晒され、巨悪は裁かれることとなる。
数日後、小夜との別れの日が来た。彼女は役人に保護され、安全な場所で新しい生活を始めることになっていた。伊織の仕事場の前で、小夜は深々と頭を下げた。そして、顔を上げると、小さな唇を震わせ、か細く、しかしはっきりとした声で言った。
「……ありがとう、ございました」
失われていたはずの、少女の声。それは伊織の心に、どんな名刀の響きよりも強く、深く沁み渡った。小夜は伊織の手に、小さな木彫りの鳥を握らせると、名残惜しそうに振り返りながら去っていった。
伊織は一人、仕事場に戻った。油と木の匂いがする、彼の居場所。窓辺に、小夜がくれた木彫りの鳥を置く。その傍らには、再び布に巻かれた刀が立てかけられている。
斬ること。繕うこと。そして、守ること。全ては、一つの手の内にある。錆色の月が沈み、暁の光が世界を照らし始める。伊織は、その光の中で、ただ静かに、己の剣が指し示す道を、見つめていた。その顔には、かつてないほどの穏やかな微笑みが浮かんでいた。