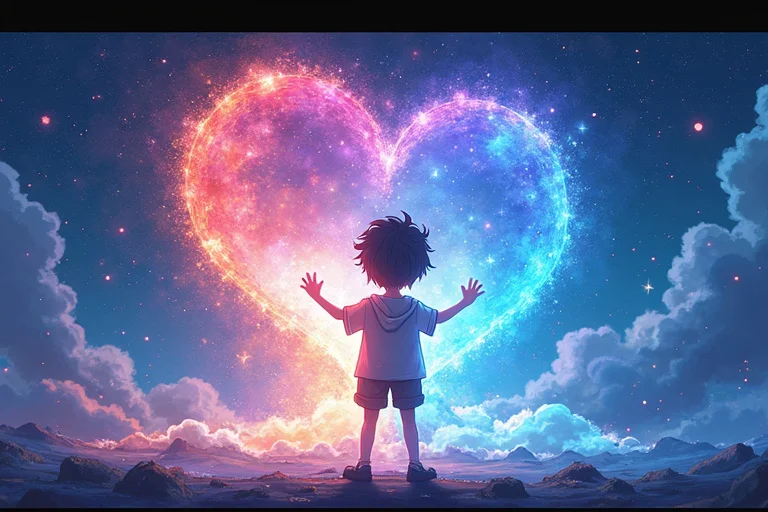第一章 消えない残像
水無月湊(みなづき みなと)の周囲には、常に季節の断片が漂っていた。
彼が未来の大学生活に胸を膨らませれば、湿ったアスファルトの上に桜の花びらが幻のように舞い落ちる。逆に、締め切り間近の課題を思って憂鬱になると、足元から色褪せた落ち葉がカサリと音を立てて湧き上がってくるのだ。人々が「多重季節現象」と呼ぶそれは、感情の振れ幅が大きい青春期に頻発する、ありふれた現象だった。
だが、湊のそれは少し違った。彼の感情は、時折、物理的な「残像」としてこの世界に形を残す。
「また出してる」
教室の窓際、夕暮れの光を浴びて半透明に揺らめく人影を指して、幼馴染の日向夏帆(ひなた かほ)が呆れたように言った。それは湊自身の姿をした、淡い光の彫刻。三日前に、進路指導の面談で「まだ何も決まっていない、でも何かすごいことができる気がする」と漠然とした期待を語った瞬間に生まれたものだ。
「ごめん。でも、すぐ消えるはずだ」
湊が言う通り、普段なら残像は数分もすれば空気中に溶けていく。だが、その日に限って、残像は消えなかった。授業が終わっても、日が落ちても、それは湊の隣に佇み、まるで未来の可能性を値踏みするかのように、じっと彼を見つめているのだった。
第二章 季節が混じる街
「消えない残像」が現れてから一週間、街の様子は明らかにおかしくなっていった。
湊が通う高校の中庭では、雪柳が白い花を咲かせる隣で、向日葵が力なく首を垂れている。夏の入道雲と秋のうろこ雲が空をまだらに覆い、人々は原因不明の眩暈や倦怠感を「季節酔い」と呼んで眉をひそめた。
そして、その中心には常に、湊の「消えない残像」がいた。
それは日に日に輪郭を濃くし、今や湊から少し離れて勝手に歩き回るまでになっていた。残像が通り過ぎた場所では、春の土の匂いと冬の氷の匂いが混じり合い、人々を混乱させる。まるで、まだ形にならぬ期待だけが暴走し、世界に無責任な季節を振りまいているかのようだった。
「湊、あれはもうアンタじゃない。別の何かだよ」
放課後の帰り道、夏帆が不安げに呟いた。彼女の周囲だけは、いつも真夏の太陽のように空気が澄んでいる。その力強い季節感が、湊の心をいつも少しだけ落ち着かせてくれた。
「わかってる。でも、どうすればいいんだ……」
湊が俯いたその時、ふと視界の端に、古びたショーウィンドウが映った。埃をかぶった品々の中に、一つだけ、微かな光を放つものがある。
それは、小さな砂時計だった。
湊の心臓が、どくん、と大きく鳴った。ショーウィンドウの向こうで、彼の「消えない残像」がぴたりと足を止め、まるで引き寄せられるかのように、その光を見つめていた。
第三章 光る砂時計
古道具屋の老店主は、埃っぽい空気の向こうで「それは『季節の砂時計』と呼ばれてる代物でね」と語った。
湊が手に取った砂時計は、くびれた硝子の中に、まるで砕かれた水晶のような透明な砂が封じ込められていた。彼の「消えない残像」が近づくと、共鳴するように砂が淡い光を放ち、さらさらと内側で流れ始める。
「誰かの強い感情が、閉じ込められているらしい。未来への希望、だったかな」
店主の言葉に、湊は息を呑んだ。
砂時計にそっと指で触れた瞬間、脳内に無数のイメージが洪水のように流れ込んできた。
──真っ白なキャンパスに絵筆を走らせる自分。見知らぬ国の雑踏を歩く自分。喝采を浴びてステージに立つ自分。それは、彼が幼い頃から心の片隅で夢想してきた、「ありえたかもしれない未来」の断片だった。
この砂時計は、過去の誰かが抱いた、あまりにも純粋で、形のない「期待」そのものを封じ込めているのだ。そして、それは今、湊の「消えない残像」と全く同じ性質を持っていた。
第四章 歪む世界と君の声
砂時計を手に入れてから、湊は残像の正体に近づいた気がした。だが同時に、世界の歪みは加速していく。
ある朝、街には季節外れの濃霧が立ち込め、その中を歩くと肌に触れる空気が数秒ごとに入れ替わった。灼けるような熱風の次に、肌を刺すような冷気が襲う。人々は家に閉じこもり、街はゴーストタウンのように静まり返った。
「もうやめてよ、湊!」
学校の屋上で、夏帆が湊の胸ぐらを掴んだ。彼女の頬は青ざめ、いつも力強い夏の気配が揺らいでいる。
「未来ばっかり見て、夢ばっかり見て! アンタのそのフワフワした期待が、今を壊してるのがわからないの!?」
彼女の言葉は、鋭い刃のように湊の胸を抉った。
夏帆は正しい。この残像は、彼の無責任な夢の成れの果てだ。具体的な努力もせず、ただ「いつか何者かになれるはずだ」と信じてきた、その傲慢さの結晶なのだ。
「僕は……」
何も言い返せない湊の前で、屋上のフェンスの向こう、霧の中に佇む残像が、ゆっくりとこちらを振り向いた。その顔には、何の感情も浮かんでいなかった。ただ、無限の可能性を秘めた空虚な瞳が、湊を射抜いていた。
第五章 約束の丘で
残像が向かった先は、湊にとって忘れられない場所だった。街を見下ろす小さな丘。幼い頃、夏帆と二人で寝転がり、他愛もない未来を語り合った場所だ。
「僕は小説家になって、カホちゃんは世界一のパン屋さんだ!」
「じゃあ、湊の小説が売れたら、私のお店で記念パーティーね!」
あの頃の期待は、もっと具体的で、温かかった。
湊が丘にたどり着くと、残像は丘の真ん中に立ち、天を仰いでいた。その体から溢れ出す光が、空に渦巻く季節の雲をさらにかき乱す。春雷が轟き、真夏の陽光が突き刺さり、秋の冷たい雨と冬の吹雪が同時に地上に降り注ぐ。「破滅的な季節の混濁」が、始まろうとしていた。
湊は覚悟を決めて、残像と対峙する。手に握った砂時計が、心臓の鼓動と同期するように激しく明滅した。
「お前は、誰だ」
問いかけると、残像は初めて口を開いた。それは湊自身の声でありながら、何百、何千という声が重なったような、奇妙な響きを持っていた。
『我々は、お前が捨てた可能性だ』
『お前が選ばなかった、すべての未来だ』
その言葉と共に、砂時計が砕け散るほどの光を放った。湊はついに理解する。この残像は、特定の未来などではない。彼がこれまで抱いてきた、あまりにも漠然としすぎた「まだ見ぬ期待」そのものの集合体。行き場を失い、どの未来にもなれなかった純粋なエネルギーの塊が、世界の理を歪めていたのだ。
第六章 未来の輪郭
空は砕けた万華鏡のように、あらゆる季節の色を混沌と映し出していた。残像は湊に向かって手を伸ばす。その手を取れば、無限の可能性と引き換えに、湊という個人の「現在」は消滅するだろう。
無限の未来か、唯一の現在か。
湊の脳裏に、夏帆の悲痛な顔が浮かんだ。彼女が望んだのは、輝かしい未来の湊ではない。「今、ここにいる」湊だ。
彼は残像の手を取らなかった。代わりに、懐から一冊のノートを取り出す。それは、誰にも見せたことのない、彼が書き綴ってきた物語の断片だった。
「僕は、小説家になる」
かつて丘の上で誓った、幼い夢。それは無数の可能性の中から選び取るには、あまりにささやかで、不確かで、地味な選択かもしれない。
「すごい何者かになんてなれなくてもいい。僕は、僕が選んだ物語を、今、ここから始めたいんだ」
湊がそう宣言した瞬間、残像の体が眩い光の粒子に変わり始めた。漠然とした期待が、初めて具体的な「意志」という輪郭を得たのだ。
肥大化した可能性は、もはや世界を歪める脅威ではない。たった一つの未来へ向かうための、道標へと変わる。光の粒子は、吸い込まれるように湊の体へと統合されていった。
第七章 現在(いま)という季節
光が収まった時、丘の上には湊が一人だけ立っていた。空を覆っていた季節の混濁は嘘のように晴れ渡り、高く澄んだ秋の空が広がっている。彼の足元に転がる砂時計は、光を失い、ただの硝子のオブジェに戻っていた。
世界は、穏やかな「現在の季節」を取り戻したのだ。
だが、湊は一つの変化に気づいていた。これまで彼の周りに常に漂っていた、季節の断片がどこにもない。未来を思っても桜は舞わず、過去を悔やんでも落ち葉は現れない。漠然とした未来を夢想する、あの胸のときめきが、ごっそりと抜け落ちてしまったかのようだった。
彼はたくさんの可能性を失ったのだ。その代わりに、たった一つの現実を選び取った。
「おかえり、湊」
背後から、聞き慣れた声がした。夏帆が、少し泣きそうな顔で笑っている。
「……ただいま、夏帆」
湊は、少しだけ寂しげに、でも確かに微笑み返した。
失った未来への期待は、もう戻らないかもしれない。だが、彼の胸には、目の前のノートと、隣で微笑む幼馴染と、これから始まる物語への、静かで確かな熱があった。
湊は空を見上げた。そこには、ただ一つの季節を示す、穏やかな雲が静かに流れていくだけだった。