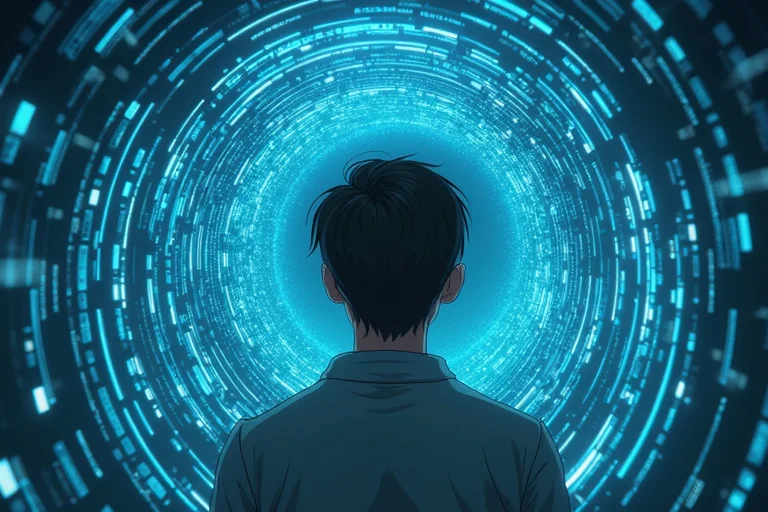第一章 消された告発
アスファルトに染み込んだ夏の熱気が、夜になっても靄のように立ち上っていた。ウェブメディア『オルタナティヴ・アイ』の記者である真宮蓮は、目的のマンションを見上げ、固くこぶしを握りしめた。三ヶ月に及ぶ追跡の末、ようやく掴んだ巨大複合企業「ネオ・ライフ」の不正会計疑惑。その最後のピースを握る男、元経理部長の高坂渉が、この一室にいる。
インターホンを鳴らす指が、微かに震えていた。応答はない。もう一度、強く押す。諦めかけたその時、ゆっくりとドアが開いた。そこに立っていたのは、蓮が資料写真で見た精悍な面影などどこにもない、抜け殻のような男だった。虚ろな瞳、覇気のない声。
「……どちら様でしょうか」
「真宮と申します。ネオ・ライフの件で、お話を伺いに」
蓮が核心を突くと、高坂の瞳がほんの一瞬、怯えたように揺らいだ。だが、それだけだった。彼は力なく首を振り、壊れた人形のように同じ言葉を繰り返した。
「申し訳ないが、何も覚えていないんです。ネオ・ライフ……ええ、勤めていましたが、もうずいぶん昔のことのようで。何も、思い出せない」
その言葉は、蓮の全身から力を奪った。嘘をついている人間の目ではない。そこにあるのは、記憶という土台を根こそぎ奪われた人間の、底なしの空虚だけだった。ふと、高坂の捲られたシャツの袖口から、手首の内側にある微かな痣が目に入った。レーザー治療痕のような、直径五ミリほどの円形の痣。見間違えるはずもない。それは、公共精神医療サービス『メモリー・デリート・サービス(MDS)』、通称「忘却処理」を受けた者の証だった。
政府が国民の精神衛生向上を掲げて導入したこのシステムは、トラウマや深刻な苦悩の原因となる記憶を選択的に消去するものだ。公式にはPTSD治療や犯罪被害者のケアが目的とされているが、その利用は年々拡大していた。辛い失恋、仕事の失敗、愛する者との死別。人々は、痛みを乗り越えるのではなく、痛みそのものを消し去る安易な道を選び始めていた。
蓮は、このMDSというシステムに、生理的な嫌悪とジャーナリストとしての強い疑念を抱いていた。人間から記憶というアイデンティティの根幹を奪う行為が、果たして「治療」と呼べるのか。そして今、そのシステムが、社会正義の追求を阻む巨大な壁として目の前に立ちはだかっている。
「高坂さん、あなたは忘れたんじゃない。忘れさせられたんだ」
蓮の言葉は、男の空虚な瞳に何の波紋も描かなかった。ドアが静かに閉められ、蓮は蒸し暑い廊下に一人、取り残された。不正の証拠は、公的な手続きによって、この世から「合法的に」消去されてしまったのだ。彼の正義感は、行き場を失ってじりじりと焦げていくようだった。
第二章 忘却の聖域
ネオ・ライフの不正を暴く道が絶たれた蓮は、調査の矛先をMDSそのものへと転換した。だが、政府管轄のMDSは、鉄壁の要塞だった。施設は厳重なセキュリティで守られ、内部情報は国家機密として扱われている。正面からの取材など、門前払いされるのが関の山だ。
蓮は、別の角度から核心に迫ることにした。SNSの片隅で細々と運営されている、「MDS被害者の会」と名乗るオンラインコミュニティ。そこに集うのは、MDSによって家族や恋人が「別人になってしまった」と訴える人々だった。記憶を消した当事者は、その喪失感にさえ気づかない。苦しむのは、取り残された側なのだ。
蓮は身分を偽り、そのコミュニティのオフライン会合に参加した。都心から離れた公民館の和室には、十数人の男女が、それぞれの胸に抱えた見えない傷をいたわるように集っていた。そこで、蓮は伊織と名乗る初老の男と出会った。穏やかな物腰だが、その瞳の奥には、深い後悔と恐怖が澱のように溜まっている。
「あなたは……ここの人たちとは少し違う匂いがする」
伊織は、鋭い観察眼で蓮の正体を見抜いていた。観念した蓮がジャーナリストだと明かすと、伊織は意外にも安堵したような表情を見せた。彼は、元MDSのシステムエンジニアだったのだ。
「あの場所は、聖域なんかじゃない。魂の墓場だ」
伊織は震える声で語り始めた。彼によれば、MDSは単に記憶を消去するだけではないという。
「消された記憶は、どこかへ消えてなくなるわけじゃない。……すべて、保管されているんだ。巨大なデータバンクに、永遠に」
「何のために?」蓮は息を飲んだ。
「わからない。だが、恐ろしいことだと思わないかね。人の最も無防備な、魂の記録だ。それを、誰かが密かに収集している。私はそれに気づいて、怖くなって辞めたんだ」
伊織の告白は、蓮の疑念を確信へと変えた。MDSは、国民を精神的に支配するための、壮大なシステムなのではないか。消去された記憶データの中には、高坂が消したネオ・ライフの不正の証拠も眠っているはずだ。
「伊織さん、そのデータバンクにアクセスする方法は?」
蓮の問いに、伊織は顔を曇らせた。
「危険すぎる。私のような元職員でさえ、一度外に出れば二度と近づけない」
「それでも、やるしかないんです。この国の『忘却』という名の病を、止めなければ」
蓮の瞳に宿る、狂気にも似た正義の炎を見て、伊織はしばらく逡巡していた。やがて、彼は重い覚悟を決めたように、一つのUSBメモリを蓮に手渡した。「これは、私が辞める時に持ち出した、古いバックドアのアクセスキーだ。使える保証はない。だが、君の覚悟に賭けてみよう」
冷たい金属の感触が、蓮の掌に重くのしかかった。それは、真実への扉の鍵であると同時に、決して引き返せない道への切符でもあった。
第三章 私という名の罪人
深夜、蓮は自室のPCの前で、伊織から託されたUSBメモリを握りしめていた。画面には、MDSのデータバンクへのログインプロンプトが静かに明滅している。伊織が教えてくれた手順通りにキーを認証させると、無機質な文字列の羅列が流れ、やがて巨大なデータベースの入り口が開いた。心臓が早鐘のように鳴る。
蓮はまず、「高坂渉」の名前で検索をかけた。ヒットした。暗号化されたデータパッケージをクリックすると、解凍が始まる。この中に、ネオ・ライフの不正を証明するすべてがあるはずだ。
データの解凍を待つ間、蓮の心にふと、悪魔的な好奇心が芽生えた。このバンクには、一体どれだけの「消された過去」が眠っているのだろうか。彼は、まるで禁断の果実に手を伸ばすように、検索窓に自分自身の名前――『真宮蓮』――を打ち込んでみた。
ありえない。ヒットするはずがない。自分はMDSなど利用したことはないのだから。
しかし、画面には無情にも一件のデータが表示された。
対象者: 真宮蓮 / 処理年月日: 5年前 / 担当医: 安川 / キーワード: 交通事故、妹、葵
――葵。
その名を見た瞬間、蓮の世界から音が消えた。蓮には、5つ年下の妹がいた。名前は葵。花のように笑う、快活な少女だった。5年前、心臓の持病が急に悪化して、帰らぬ人となった。そう、病死だったはずだ。蓮はずっとそう信じて生きてきた。
震える指で、自分のデータパッケージを開く。再生ボタンをクリックすると、モニターに鮮明な映像が映し出された。それは、蓮自身の視界の記憶だった。
雨の夜。車のハンドルを握る自分の手。助手席には、楽しそうに大学の話をする葵がいる。連日の徹夜取材で、蓮の体は鉛のように重かった。一瞬、強烈な眠気に襲われ、意識が途切れる。次に目を開けた時、世界はスローモーションになっていた。対向車のヘッドライトが網膜を焼き、葵の短い悲鳴が耳をつんざく。そして、すべてを砕く轟音と、ガラスの割れる音――。
映像はそこで途切れていた。
蓮は、椅子から崩れ落ちた。忘れていたのではない。忘却処理によって、消していたのだ。自分が過労運転で事故を起こし、最愛の妹を死なせてしまったという、耐えがたい罪の記憶を。MDSでその記憶を消し、妹は「病死だった」という都合のいい偽りの記憶を上書きして、自分は被害者の顔をして生きてきたのだ。
社会の欺瞞を暴くと息巻いていた自分こそが、最大の欺瞞の塊だった。他者の罪を断罪する資格など、どこにもなかった。正義の仮面の下に隠されていたのは、罪から目を逸らし続けた、醜く弱い一人の男の姿だった。高坂を、MDSを利用した権力の手先をあれほど憎んでいたのに、自分もまったく同じ穴の狢だったのだ。
「ああ……ああ……っ」
声にならない嗚咽が、暗い部屋に漏れた。彼の信じてきた正義も、アイデンティティも、すべてが音を立てて崩壊していく。足元が消え、底なしの暗闇へと落ちていく感覚。彼は、自分という名の罪人だった。
第四章 痛みと歩む夜明け
どれくらいの時間、床に蹲っていたのだろうか。蓮のPCからは、解凍の終わった高坂のデータが、静かに彼を待っていた。だが、もうどうでもよかった。ネオ・ライフの不正も、社会の欺瞞も、今の彼には遠い世界の出来事に思えた。ジャーナリストを辞めよう。すべてを捨てて、どこかへ消えてしまいたい。
その時、スマートフォンの着信音が鳴った。伊織からだった。
「……真宮君か。無事かね」
「伊織さん……僕は……」蓮の声は、ひどくかすれていた。「僕は、あなた方が言う『被害者』の家族なんかじゃなかった。僕自身が、利用者でした。自分の罪を……消すために」
すべてを告白する蓮の言葉を、伊織は静かに聞いていた。そして、電話の向こうで深く息を吸う音がした。
「そうか……。忘れたいほどの痛みを、君も抱えていたんだな。だがな、真宮君。忘れることが救いになると本気で信じている人間など、あの施設には一人もいやしない。皆、痛みに耐えきれなかっただけだ。問題は、忘れたという事実にどう向き合うかだ。君が暴こうとしていたのは、社会の欺瞞だけじゃない。君自身の欺瞞でもあったんだ。今、君は真実の入り口に立った。そこから逃げるのか、それとも向き合うのか。決めるのは君自身だ」
伊織の言葉が、砕け散った蓮の心に、小さな光を灯した。そうだ。逃げてはいけない。この痛みから、この罪から、もう二度と目を逸らしてはいけない。
蓮は、ふらつく足で立ち上がると、再びPCに向かった。そして、一心不乱にキーボードを叩き始めた。それは、ネオ・ライフの不正を告発する記事だった。だが、単なる暴露記事ではない。
記事の冒頭で、蓮は自らのすべてを晒した。自分がMDSの利用者であり、運転事故で妹を死なせた罪の記憶を消していたこと。偽りの正義感に酔っていたこと。その上で、彼は社会に、そして読者一人ひとりに問いかけた。
『忘却は、本当に私たちを救うのでしょうか。痛みや後悔、罪悪感は、人間が人間であることの証ではないでしょうか。私たちは、辛い記憶と共に生き、それを乗り越えようともがき、時に赦し、赦されることでしか、本当の意味で前に進むことはできないのではないでしょうか。忘却という安易な安寧の先に、真の未来はありません』
記事を公開するボタンを、蓮は静かにクリックした。職を失うだろう。社会的な非難も浴びるに違いない。だが、彼の心は不思議なほど穏やかだった。
翌朝。蓮は、何年かぶりに見たような、澄み切った朝の光の中で目を覚ました。窓を開けると、ひんやりとした空気が頬を撫でる。心の中には、消えることのない罪の意識と、5年間忘れていた妹への愛おしさが、確かな痛みとして存在していた。それは重く、苦しい。けれど、紛れもなく彼自身の一部だった。
この記事が、社会をどう変えるかはわからない。MDSがなくなることもないかもしれない。だが、蓮は一つの答えを見つけていた。
忘却の安寧ではなく、記憶の痛みと共に生きていくこと。
それこそが、罪人である彼が、これから歩むべき唯一の道であり、彼が見つけた真の「再生」だった。空には、薄い雲が流れていたが、その向こうには、どこまでも続く青空が広がっているのが見えた。蓮は、その空をただ、じっと見つめていた。