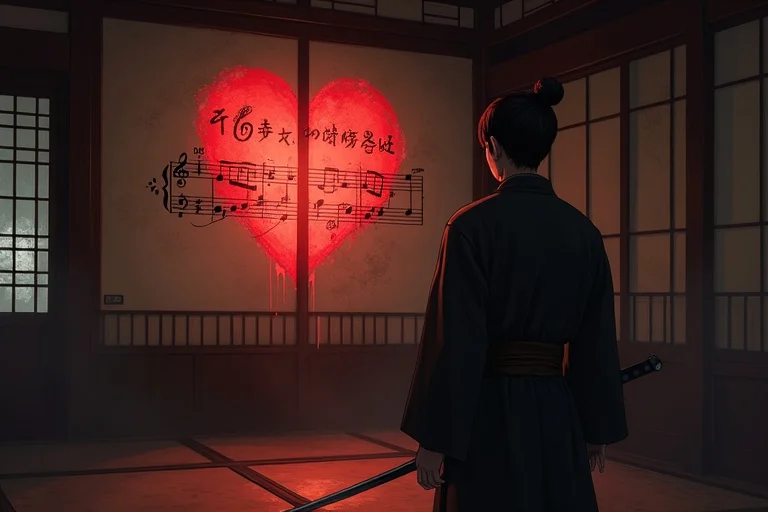第一章 残響の依頼
江戸の町は、音で満ちていた。行き交う人々の下駄の音、物売りの威勢の良い声、遠くで響く鍛冶の槌音。それら無数の音の奔流の中で、俺、響(ひびき)は生業を立てている。音記録師。そう名乗ってはいるが、この稼業を理解する者はほとんどいない。
俺の仕事は、音を記録することだ。特殊な鉱石を溶かし込んで作られた瑠璃の椀に清水を張り、音叉に似た調律具で空間の震えを拾う。すると、かつてその場で鳴り響いた音が、水面にさざ波となって蘇るのだ。それは過去の残響、音の幽霊のようなものだった。大抵は、祝いの席での謡や、今は亡き名人の芸の記録といった依頼が主だった。俺にとって音は記録すべき対象であり、そこに込められた感情など、仕事の対価である銭の重さには及ばない。そう、思っていた。あの日、あの奇妙な依頼を受けるまでは。
依頼主は、薬種問屋『遠州屋』の大旦那、宗右衛門と名乗る老人だった。深々と皺の刻まれた顔には、拭い去れぬ悲しみが影を落としていた。通された奥座敷はしんと静まりかえり、庭のつくばいが水を打つ音だけが、やけに大きく聞こえた。
「響殿に頼みたいのは、亡き娘、お琴(こと)が最後に奏でた琴(こと)の音だ」
宗右衛門の声は、乾いた葉が擦れるようにか細かった。俺は眉をひそめる。
「お亡くなりになった方の音を?それはいつ頃のことで?」
「…三年前だ」
三年前。いくら俺の技術が特殊だとはいえ、時の流れは音の残滓を薄れさせる。三年も前の音を拾うのは至難の業だ。
「大旦那。失礼ながら、それはほとんど不可能かと。それに、琴そのものがなければ…」
「琴は…ない」宗右衛門は目を伏せた。「娘は、病の末に起きた火事でな。部屋も、愛用していた琴も、すべて焼けてしもうた」
絶望的な条件だった。断ろうと口を開きかけた俺を、宗右衛門のすがるような目が射抜いた。
「だが、音は物に宿ると聞く。娘が暮らした部屋は、火事の後もそのままにしてある。どうか、あの部屋に残る品々から、娘の最後の音色を拾い上げてはくれまいか。あの子が生きた証を、もう一度この耳で…」
老人の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。その涙に、俺は一瞬、心を揺さぶられた。だが、それ以上に心を動かしたのは、彼が卓上に滑らせた分厚い桐の箱だった。中には、俺の稼業の数年分はあろうかという小判が鈍い光を放っていた。
非現実的な依頼。だが、この報酬は魅力的だ。俺は、仕事は仕事と割り切り、乾いた声で答えた。
「…分かりました。やってみましょう。ただし、必ず記録できるという保証はできかねます」
「それでいい。頼む」
こうして俺は、音のない部屋で、聞こえるはずのない音を探すという、前代未聞の仕事を引き受けることになった。その先に、人の心の最も暗い深淵が待ち受けているとも知らずに。
第二章 物言わぬ部屋
遠州屋の離れにあるお琴の部屋は、時が止まっていた。火事の痕跡は生々しく、柱や壁は黒く煤けている。焦げた木の匂いが、三年の時を経てもなお鼻をついた。陽光が障子の破れ目から差し込み、宙を舞う埃をきらきらと照らし出している。まるで、無数の小さな魂がさまよっているかのようだった。
俺は部屋の中央に座し、持参した道具を広げた。瑠璃の椀に、革袋から汲んだ清らかな水を注ぐ。次に、長さの違う数本の調律具を取り出した。これは、特定の周波数に共鳴するよう作られた特別な金属棒だ。
「さて、どこから始めるか」
まずは、燃え残った衣桁(いこう)に掛かる着物に、一番短い調律具をそっと近づけた。目を閉じ、全神経を耳に集中させる。…キィン、と金属の震えが空気を伝わり、椀の水面が微かに揺れた。
―――サ、サ……
絹の衣擦れの音。優雅な所作で立ち居振る舞う、若い娘の姿が目に浮かぶようだ。だが、それは日常の断片に過ぎない。
次に、文机の焼け焦げた引き出しに残っていた文箱。調律具を変え、再び集中する。
―――カリ、カリ……サラサラ……
筆が紙を走る、せわしない音。何かを書き綴っている。恋文か、日記か。音だけでは内容は分からない。鏡台に向かえば、若い娘のか細いため息が聞こえた。どの音も、確かにお琴という娘が生きていた証ではある。だが、宗右衛門が求める「琴の音」には程遠い。
数日が過ぎた。俺は毎日この部屋に通い、音の欠片を拾い集めては、その無力さに苛立っていた。宗右衛門は、毎日俺の元を訪れ、静かに茶を差し出すだけだった。彼の沈黙は、期待と焦燥が入り混じった重圧となって俺の肩にのしかかる。
そんなある日、お琴のかつての許嫁だったという若侍、庄太夫が訪ねてきた。彼は、俺が奇妙な仕事をしていると聞きつけ、お琴の思い出を語りに来たのだ。
「お琴殿は、ただ美しいだけの方ではなかった。芯の強い、真っ直ぐなお方でした。…ただ、時折、遠くを見るような、何かを諦めたような目をされることがあった」
庄太夫の話は、俺の中でバラバラだった音の断片を、少しずつつなぎ合わせ始めた。衣擦れの音は彼女の優雅さを、筆の音は内に秘めた情熱を、ため息は誰にも言えぬ苦悩を表しているのかもしれない。
俺は、いつの間にか単なる「音」としてではなく、お琴という一人の人間の人生の断片として、その残響を聴くようになっていた。最初は金のためと割り切っていたはずの仕事に、奇妙な熱がこもり始めていた。この部屋に散らばる音のパズルを完成させたい。彼女が最後に伝えたかったのは、本当に美しい琴の音色だけだったのだろうか。
疑念が芽生え始めた俺の目に、ふと、部屋の隅に転がっているものが留まった。それは、ほとんど黒焦げになった小さな木片。よく見ると、繊細な彫刻が施されている。椿の柄の、古い櫛だった。
第三章 櫛が奏でる真実
その櫛を手に取った瞬間、なぜか胸がざわついた。これまで試してきたどの品とも違う、強い存在感を放っているように感じられた。火事でほとんどの品が失われた中で、なぜこれだけが比較的形を保って残っていたのか。まるで、何かを伝えるために燃え尽きるのを拒んだかのように。
俺は唾を飲み込み、瑠璃の椀を櫛のそばに置いた。一番長い、最も繊細な音を拾う調律具を慎重に構える。指先が微かに震えていた。
調律具を、櫛の焦げた表面に触れるか触れないかの距離まで近づける。
キィィィィン――――。
これまでとは比較にならない、鋭く澄んだ金属音が響き渡った。その瞬間、瑠璃椀の水面が激しく波立ち、渦を巻いた。そして、音が、溢れ出した。
―――ベンッ、ベベンッ! ギャギャッ!
それは、俺が想像していたような、優雅で美しい琴の音ではなかった。弦をかきむしるような、不協和音。何かに叩きつけられ、壊れる音。悲鳴のような弦の断末魔。
そして、その激しい音に混じって、声が聞こえた。
『おやめください、父上! 私の心は、もう…!』
若く、しかし凛とした娘の声。お琴の声だ。彼女は病で気力を失っていたのではなかったのか。その声には、強い抵抗の意志が満ちていた。
だが、衝撃はそれだけでは終わらなかった。彼女の声に応えるように、もう一つ、聞き覚えのある声が響いたのだ。低く、抑圧された、怒りに震える男の声。
『黙れ! あのような身分の低い男のもとへなど、行かせるものか! これは遠州屋のため、お前のためなのだ!』
俺は息を呑んだ。全身の血が凍りつくのを感じた。この声は…紛れもなく、依頼主である宗右衛門のものだった。
全ての断片が、恐ろしい形で一つにつながった。
火事は、不慮の事故などではなかった。お琴は病死したのではない。彼女は、許嫁ではない、身分の低い男と駆け落ちしようとしていた。それを知った父・宗右衛門が、家の名誉を守るために実力行使で止めようとしたのだ。もみ合いになり、お琴が抵抗する中で琴が倒れ、燭台の火が燃え移った。あれは、無理心中を図った末の、惨劇だったのだ。
宗右衛門は、娘の最後の音色を聴きたいと言った。だが、彼が本当に聴きたかったのは、このおぞましい真実の音ではなかったはずだ。彼は、自らが犯した罪の記憶に蓋をし、病で亡くなった美しく儚い娘、という幻想を作り上げた。そして、その幻想を完成させるために、娘が奏でたであろう「美しい最後の琴の音」を俺に求めに来たのだ。
俺の手には今、一つの家族を崩壊させた、あまりにも重い真実が握られていた。瑠璃椀の水面は、静けさを取り戻している。だが、俺の心は激しい嵐に見舞われていた。この音を、どうすればいい? 依頼通り、美しい音色だけを切り取って偽りの慰めを与えるのか。それとも、この残酷な真実を、罪の記憶から逃れようとする老人に突きつけるのか。
音記録師として、ただ音を記録するだけのはずだった。だが、俺が記録してしまったのは、一人の人間の魂の叫びそのものだった。
第四章 聞こえなかった言葉
俺は数刻、煤けた部屋で身じろぎもせずに座り続けていた。手の中の櫛が、まるで鉛のように重い。瑠璃椀に記録された音は、ただの音波の記録ではない。それは、葬られたはずの真実であり、父親に殺された娘の最後の抵抗だった。
俺に何ができる? 金のためと割り切っていたはずの仕事が、今や俺自身の良心を鋭く問うていた。偽りの安らぎを与えることは、優しさなのか? それとも、真実から目を背けさせる、より残酷な行為なのか?
日が傾き、部屋に差し込む光が赤く染まる頃、俺は静かに立ち上がった。心は、決まっていた。
遠州屋の奥座敷。再び宗右衛門と向き合った俺は、彼の前に瑠璃椀を置いた。宗右衛門の顔には、期待の色が浮かんでいる。
「響殿…もしや、記録できたのか」
「はい」俺は短く答えた。「お琴様の、最後の音が」
俺は調律具を手に取り、椀の縁を軽く叩いた。再生の合図だ。宗右衛門は目を閉じ、神妙な面持ちで耳を澄ます。
最初に聞こえてきたのは、お琴の凛とした声だった。
『おやめください、父上!』
宗右衛門の肩が、びくりと震えた。彼の顔から血の気が引き、薄く開かれた目に恐怖の色が宿る。続く、弦をかきむしる不協和音と、物が壊れる音。そして、決定的な一言が、静かな座敷に響き渡った。
『…あのうような身分の低い男のもとへなど、行かせるものか!』
それは、三年前の彼自身の声だった。
再生が終わっても、音の残響が部屋を満たしているかのような錯覚に陥った。宗右衛門は、石のように固まったまま動かない。やがて、その皺だらけの顔がくしゃりと歪み、堰を切ったように嗚咽が漏れ始めた。
「あ…ああ…お琴…」
それは、悲しみというよりも、罪の重さに押し潰された男の、獣のような呻きだった。
「わしは…ただ、お前を守りたかっただけじゃ…家の名誉を…。こんなことには…なるはずでは…」
彼は、真実の音によって、自らが作り上げた幻想の壁を打ち砕かれたのだ。記憶の奥底に封じ込めていた罪と、ようやく向き合わざるを得なくなった。
俺は、卓上に置かれていた報酬の桐箱には目もくれず、静かに立ち上がった。もう、ここに用はない。俺の仕事は終わった。
遠州屋の門を出ると、夕暮れの江戸の喧騒が俺を包み込んだ。だが、その音は、以前とは全く違って聞こえた。威勢のいい物売りの声の裏には、家族を養う男の必死さが聞こえる。子供たちのはしゃぎ声には、無垢な生命の喜びが聞こえる。すれ違う人々の囁きの一つ一つに、それぞれの人生の物語が織り込まれているように感じられた。
俺は空を見上げた。茜色に染まる空を、一羽の鳥が鳴きながら横切っていく。その鳴き声すらも、今は一つの確かな意味を持つ、記録されるべき物語のように思えた。
音を記録する。それは、ただ技術を弄ぶことではない。その音に込められた人の想い、喜び、悲しみ、そして時に残酷な真実を、自らの魂で受け止めることなのだ。
俺はこれからも音記録師として生きていくだろう。だが、もう二度と、音を単なる音として聴くことはない。心を傾け、耳を澄ます。世界は、語られるべき声で満ちている。俺はその声なき声を拾い集め、時に誰かの心に届け、時に静かに歴史の澱に沈める。それが、この重い真実を記録してしまった俺に課せられた、新たな稼業の意味なのかもしれない。
風の音が、まるで新しい物語の始まりを告げるように、俺の頬を撫でていった。