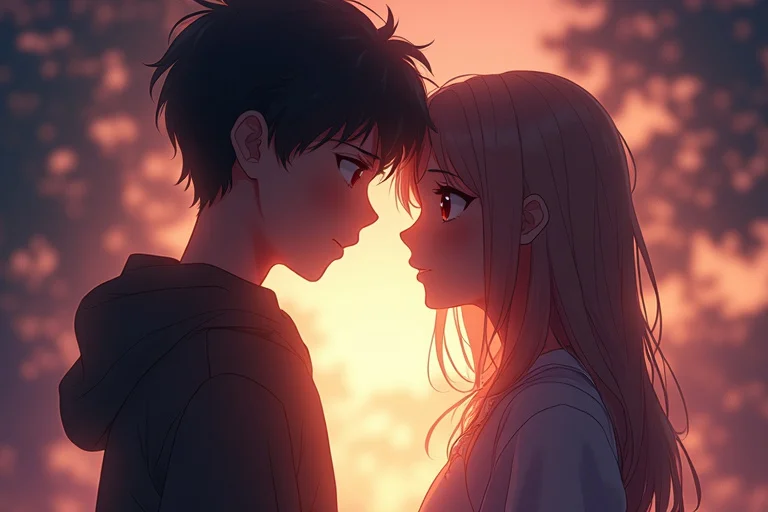「……以上、昼の放送を終わります」
七瀬莉子の涼やかな声が、校内に設置された古びたスピーカーから響き渡る。俺、水島蓮は、目の前のミキサーのフェーダーをゆっくりと下げた。放送室の窓から見える空は、退屈なほど青く澄み渡っていた。
「今日も平和、平和。あまりに平和すぎて、あくびで顎が外れそうだぜ」
隣で椅子にふんぞり返っていた高槻翔太が、大げさに伸びをしながら言った。サッカー部のエースだったこいつは、去年の怪我でフィールドを去り、なぜか俺のいる放送部に入り浸っている。
「平和が一番だろ」
「蓮はそれでいいのかよ? 高校生活最後の文化祭だぜ? 思い出、作りたくねえの?」
翔太の目が、悪戯っぽく光った。こういう時のこいつは、ろくなことを考えていない。
「例えば、だけどな。俺たちの声で、この学校をジャックする、とか」
その言葉が、俺の心の、退屈という名の分厚い壁に小さなヒビを入れた。
計画は「文化祭最終日、後夜祭の直前、全校生徒に向けたゲリララジオを放送する」という、あまりにも無謀なものだった。番組名は『アフタースクール・ジャック』。発案者はもちろん翔太だ。
「馬鹿じゃないの!?」
案の定、放送部長の七瀬は柳眉を逆立てた。「校則違反よ。停学じゃ済まないわ。放送部だって廃部にされかねない!」
正論だ。あまりにも正しい。でも、翔太は引き下がらなかった。
「なあ七瀬。あんた、いつも言ってるよな。『放送は、誰かの心に何かを届けるためにある』って。今の俺たちの放送、誰かの心に届いてるか? 先生の連絡事項と、当たり障りのない音楽だけだぜ」
「それは……」
言葉に詰まる七瀬に、俺も続いた。
「やってみたいんだ。たった一度でいいから、俺たちの言葉で、俺たちの音楽で、この学校を揺らしてみたい」
俺の目を見た七瀬は、何かを堪えるように唇を噛み、放送室を飛び出していった。
俺と翔太は、二人だけの共犯者になった。放課後、俺は機材の改造に取り掛かった。普段は使わない予備のミキサーとマイクを、先生たちに見つからないよう、体育館裏の倉庫に運び込む。翔太は、番組の構成と原稿を考え始めた。夜の学校に忍び込み、校内スピーカーの配線に直接繋がる秘密のラインを確保した時は、心臓が飛び出るかと思った。見つかれば即アウトのスリルが、錆びついていた日常を鮮やかに塗り替えていく。
文化祭当日。校内は浮かれた熱気に満ちていた。だが、俺たちの頭の中は、今夜決行する計画のことでいっぱいだった。
後夜祭の準備が始まる夕暮れ時。体育館裏の倉庫に機材をセッティングしていると、息を切らした七瀬が現れた。
「……馬鹿なことはやめて。今ならまだ間に合うから」
その声は、震えていた。
「ごめんな、七瀬。でも、もう止められない」
翔太がまっすぐに彼女の目を見て言った。
すると七瀬は、俺たちが書き溜めた原稿の束を、どこからか取り出した。
「これ、読んだわ。……最低よ。先生のモノマネとか、くだらない恋愛相談とか」
「だよな。わりぃ」
「でも……」
七瀬は一枚の原稿を指さした。それは、翔太が怪我で辞めたサッカー部の仲間たちへ宛てた、不器用な感謝のメッセージだった。
「……でも、少しだけ、羨ましいって思った。こんな風に、自分の気持ちを、誰かに真っ直ぐ伝えられることが」
俯いていた彼女が顔を上げる。その瞳には、決意の光が宿っていた。
「……五分だけよ。私が先生たちの足止めをする。その間に、やりなさい」
俺と翔太は、顔を見合わせた。最高の共犯者が、もう一人増えた瞬間だった。
後夜祭のキャンプファイヤーに火が灯る直前。俺はスイッチを入れた。全校のスピーカーから、割れるようなノイズが響く。ざわめく生徒たち。
『―――全校生徒に告ぐ! 聞こえるか! これは、俺たち放送部による電波ジャックだ!』
翔太のシャウトが、学校中に轟いた。
『今から数分、この時間は俺たちがもらった! 題して、アフタースクール・ジャック!』
翔太の軽快なトークが炸裂する。くだらない学校あるあるネタで笑いを誘い、事前にこっそり募集した恋の悩みに無責任なエールを送る。校庭に集まった生徒たちから、爆笑と歓声が上がるのが倉庫まで聞こえてくる。
『次は、俺からの個人的なメッセージだ。サッカー部のみんな、聞いてるか?』
翔太の声色が少しだけ変わる。
『怪我した時、お前らにきついこと言っちまった。本当は、一緒に戦えなくて、めちゃくちゃ悔しかった。……すまん。そして、ありがとう。お前らは、俺の最高のチームメイトだ』
きっと、フィールドのどこかで聞いている仲間たちに、その声は届いているはずだ。
「蓮、お前も何か言えよ!」
翔太がマイクを突き出す。俺は息を吸い込んだ。
「えー…いつも翔太に振り回されてる水島です! でも、お前と馬鹿やってる今が、最高に楽しい! それから、七瀬部長! あんたが一番、ロックだぜ!」
放送室から先生たちが飛び出してくるのが見えた。もう時間がない。その時、俺たちのヘッドフォンに、凛とした声が割り込んできた。七瀬だ。彼女は放送室のマイクを乗っ取ったらしい。
『――この放送が、退屈な毎日を送る誰かの、ほんの小さな火種になりますように。以上、たった一度きりの、アフタースクール・ジャックでした!』
俺たちは機材の電源を落とし、倉庫から駆け出した。後ろで先生たちの怒鳴り声が聞こえる。でも、不思議と怖くはなかった。
隣を走る翔太と目が合う。二人で馬鹿みたいに笑った。
後日、俺たちはこっぴどく叱られ、山のような反省文を書かされた。だが、俺たちのゲリラ放送は学校の伝説になった。
あの日の夕焼けを、俺は一生忘れないだろう。退屈な日常を突き破って、自分たちの声で世界を揺らした、あの数分間。俺たちの青春は、あの電波ジャックと共に、本当の意味で始まったのだ。