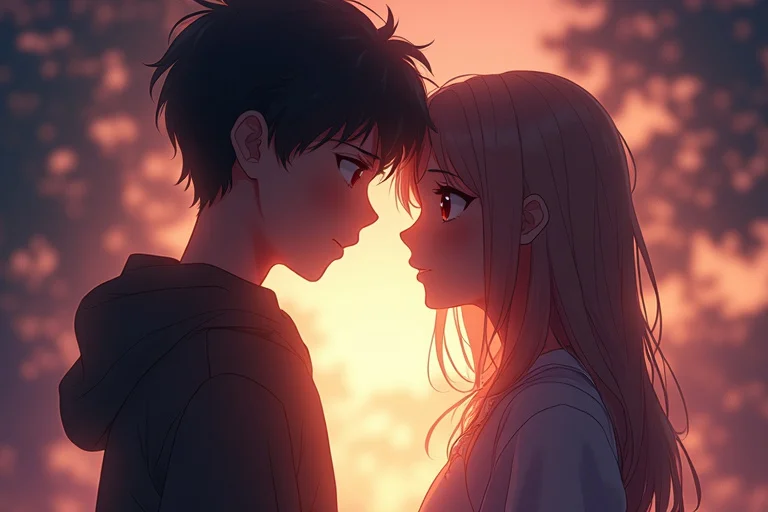第一章 幽霊とファインダー
高槻樹(たかつき いつき)にとって、世界は常に一枚のガラスを隔てた向こう側にあるものだった。感情の彩度を落とし、物事を斜に構えて眺める。それが、いつしか身についた彼の処世術だった。趣味は写真。だが、そこに情熱はない。ただ、ファインダーという四角い窓を通して世界を切り取る行為が、彼と世界の間に心地よい距離を生んでくれた。
その日も、樹は放課後の校舎の屋上で、手すりに寄りかかりながら愛用の古いフィルムカメラを構えていた。レンズが捉えるのは、誰もいないグラウンドと、西日に長く伸びる校舎の影。静かで、退屈で、だからこそ安心できる光景。カシャ、と乾いたシャッター音が響く。
「……あの」
不意に背後からかけられた声に、心臓が跳ねた。振り返ると、そこに一人の少女が立っていた。セーラー服の襟を風にはためかせ、色素の薄い髪が夕陽を透かしてきらきらと光っている。水瀬凪(みなせ なぎ)。同じクラスに在籍しているはずだが、その姿を見るのは入学式以来かもしれない。病弱でほとんど学校に来ないことから、いつしか「屋上の幽霊」なんて不名誉なあだ名で呼ばれている、実在さえ疑わしい存在。
彼女は、噂とは裏腹に、驚くほど確かな輪郭を持ってそこにいた。凪はまっすぐに樹の目を見つめ、りん、と澄んだ声で言った。
「高槻くん、だよね。写真、撮ってるんでしょ」
「……まあ」
「お願いがあるの」
凪は一歩、樹に近づいた。その瞳は、何かを渇望するように、それでいて諦めるように、不思議な色をたたえて揺れていた。
「私の、最後の夏を撮ってくれない?」
最後の夏。その言葉が、樹の心に小さな棘のように引っかかった。ガラスの向こうにあったはずの世界が、不意に、目の前の少女を通して生々しい手触りをもって迫ってくる。それは、彼の退屈な日常が終わりを告げる、最初のシャッター音だった。
第二章 色づく世界
凪の依頼を、樹は断ることができなかった。「最後の夏」という言葉の真意を問いただすこともできず、ただ彼女の不思議な引力に導かれるように、週末ごとにカメラを手に凪と会うようになった。
彼女が指定する撮影場所は、いつも決まって、世界の喧騒から切り離されたような場所だった。夜明け前の、空と海の境界が溶け合う海岸。錆びたレールだけが残る廃線跡。町を見下ろす、星屑が降り注ぐ丘。凪はそんな静寂の中で、まるで水を得た魚のように、のびのびと振る舞った。
「見て、樹くん。夜が明ける前のこの色、世界で一番好き」
水平線の向こうが白み始めると、凪は砂浜に座り込んで、うっとりと空を眺めた。樹は、そんな彼女の横顔にレンズを向ける。ファインダー越しに見る凪は、儚く、美しく、そして強烈に「生きて」いた。カシャ。シャッターを切るたびに、凪の一瞬が永遠に焼き付けられていく。
最初は義務感でしかなかった撮影は、いつしか樹のすべてになっていた。どうすれば彼女の持つ空気感を捉えられるか。光は、角度は、絞りは。凪という被写体は、樹に初めて「表現したい」という欲求を教えた。凪を通して見る世界は、これまで彼が見ていた無機質な風景とは違い、驚くほど豊かで、鮮やかな色彩に満ちていた。風の匂い、波の音、肌を撫でる光の粒。五感が開かれていく感覚。
「樹くんの撮る写真、好きだな。静かだけど、すごく優しい音がする」
ある日、撮りためた写真を見せると、凪はそう言って微笑んだ。その笑顔は、樹が今まで撮ってきたどんな風景よりも、彼の心を強く揺さぶった。友情だろうか。あるいは、もっと別の感情か。名前のつけられない気持ちが、胸の中でゆっくりと育っていくのを感じていた。
しかし、凪は時折、ふっと遠くを見つめて、触れることのできない寂しさをその瞳に宿すことがあった。そのたびに、「最後の夏」という言葉が現実味を帯びて樹の胸を締め付ける。だが、彼は怖くて聞けなかった。この穏やかで、宝物のような時間が、答えを知ることで壊れてしまうのが、何よりも怖かった。
第三章 花火のあとさき
夏が盛りを迎え、町は祭りの喧騒に包まれた。樹は凪を誘った。人混みが苦手な彼女が断るかもしれない、と半ば覚悟して。しかし、凪は「行く。浴衣、着てみたいな」と、はにかみながら頷いた。
祭りの夜。紺地に白い撫子の柄の浴衣を着た凪は、昼間見るよりずっと大人びて見えた。普段は結ばない髪を結い上げ、少しだけ差した紅が、夜の闇に白く浮かぶ彼女の肌を際立たせる。樹は心臓の音がうるさいのを自覚しながら、何度もシャッターを切った。りんご飴を頬張る姿。金魚すくいに夢中になる横顔。そのすべてが愛おしい。
「樹くん、ありがとう。今日、すごく楽しい」
境内へと続く石段の途中で、凪が振り返って言った。背後で、ヒュルル、と打ち上げ花火が空に昇る音がする。樹はカメラを構えた。花火が夜空に大輪の花を咲かせる、その光に照らされた凪の笑顔を撮る。この夏、最高の、一枚を。
ドン、という轟音と共に、色とりどりの光が弾けた。凪が息を呑むほど美しい笑顔を見せた、その瞬間。
ふ、と彼女の体から力が抜けた。
「……え?」
樹の腕の中に、凪の体が崩れ落ちる。手から滑り落ちたカメラが、石段を転がり、ガシャン、と鈍い音を立てた。人々の歓声と、鳴り止まない花火の音が、やけに遠く聞こえる。腕の中の凪は、糸が切れた人形のようにぐったりとして、浅い息を繰り返していた。
病院の、殺風景な白い廊下。樹は、駆けつけた凪の両親からすべてを聞かされた。凪は生まれつき重い心臓の病を抱えていたこと。何度も手術を繰り返したが、もう手の施しようがないこと。そして、この夏を越すのは難しいだろうと、医者から告げられていること。
「最後の夏」は、比喩でも感傷でもなく、残酷な事実だった。「幽霊」の噂も、彼女が人との関わりを断ち、限られた命を静かに過ごそうとしていたからだった。
頭を殴られたような衝撃。凪が必死に一瞬一瞬を生きようとしていた理由。彼女の儚げな美しさの根源。そのすべてを、樹はようやく理解した。そして同時に、何も知らずに、ただ無邪気に彼女の「最後の時間」を消費していた自分を呪った。ファインダー越しに見ていたはずの世界が、ガラスを突き破って、どうしようもない現実の重さとなって彼にのしかかってきた。
第四章 君が生きた夏
数日後、樹は凪の病室を訪れた。窓から差し込む光が、ベッドに横たわる凪の顔を白く照らしている。以前よりもずっと痩せてしまった彼女は、それでも樹の姿を認めると、穏やかに微笑んだ。
「驚かせた? ごめんね」
「……謝るなよ」
喉の奥が詰まって、声が震えた。樹は堪えるように唇を噛み締め、カバンから一冊のアルバムを取り出した。それは、この夏に撮りためた凪の写真で埋め尽くされていた。夜明けの海で笑う凪。廃線跡を歩く凪。星空を見上げる凪。そして、祭りの夜、花火の光に照らされた、あの笑顔。
「君は、ちゃんとここにいた。生きてた」
写真の中の凪は、生命力に満ち溢れ、輝いていた。凪はゆっくりとページをめくり、一枚一枚を愛おしそうに指でなぞった。その瞳に、じわりと涙が滲む。
「……きれい。私、こんな顔して笑ってたんだ」
彼女は顔を上げ、樹を見た。
「ありがとう、樹くん。樹くんの写真の中でなら、私、ずっと生き続けられる気がする。私の夏はね、最高に楽しかったよ」
その言葉が、樹にとっての救いだった。
その夏が終わる頃、凪は、まるで眠るように静かに息を引き取った。
三年後。
都内のあるギャラリーで、一人の若手写真家の個展が開かれていた。高槻樹、初の個展。タイトルは、『君が生きた夏』。
会場の壁には、凪の写真が並んでいた。様々な表情の、様々な季節を生きる凪。訪れた人々は皆、その生命感あふれる写真に足を止め、見入っていた。
会場の中央、一番大きなパネルに引き伸ばされているのは、あの夏祭りの夜の写真だ。花火の光を浴びて、人生で最も輝いていたであろう、凪の笑顔。樹はその写真の前に立ち、静かに目を閉じた。悲しみは、今も胸にある。けれど、それ以上に、凪が与えてくれたものが、彼の内側を温かく満たしていた。本気で何かを追い求めることの喜び。誰かを心から大切に思うことの切なさ。そして、限りある時間の中で、今を生きることの尊さ。
ふと、隣で写真を見ていた小さな女の子が、母親に話しかける声が聞こえた。
「ママ、この人、すごく綺麗に笑ってるね」
樹は、薄く目を開けた。そして、写真の中の凪に向かって、誰にも気づかれないくらい、小さく微笑み返した。
君の時間は止まってしまったけれど、君が生きた証は、こうして確かに光の中に在り続ける。そして、これからもずっと、僕の進む道を照らし続けてくれるだろう。樹はそう確信しながら、未来へと続く、新たなファインダーを覗き込んだ。