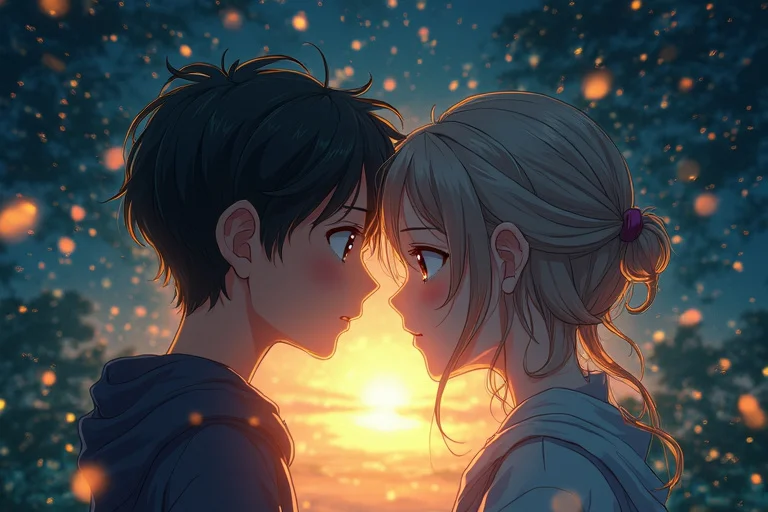「文化祭のテーマは『未来への飛躍』です! 皆さん、頑張りましょう!」
生徒会長のキラキラした声が体育館に響く。俺、高槻湊は、その声をBGMに欠伸を噛み殺した。高校二年の秋。周囲が文化祭の熱気に浮かされる中、俺はどこか冷めていた。所属する写真部の展示だって、去年の使い回しでいいとさえ思っていた。青春なんて、誰かが作った幻想だ。
「湊、聞いてる? 今年はうちのクラス、お化け屋敷なんだからね! ちゃんと脅かし役やりなさいよ!」
幼馴染の橘栞が、パンフレットで俺の頭を軽く叩く。太陽みたいに笑うこいつの隣は、昔から俺の定位置だった。
「へいへい。どうせなら、もっとクリエイティブなことしたいねぇ」
「文句ばっかり! じゃあ、何か面白いこと見つけてきなさいよ!」
その言葉が、まさか予言になるとは思ってもみなかった。
数日後、俺はお化け屋敷で使うボロ布を探して、誰も寄り付かない旧資料室にいた。埃っぽい書棚の奥、床に転がっていた木箱に足を引っかけたのが始まりだった。中に入っていたのは、羊皮紙のような古びた一枚の紙。そこには、万年筆で書かれたであろう、謎の文章と奇妙な図形が描かれていた。
『百年の星霜を経て、我が学び舎の礎を継ぐ者へ。七つの鍵を集めし時、未来への扉が開かれん。第一の鍵は、沈黙の歌姫が唇を開く場所なり』
「なんだこれ……」
胸が、ほんの少しだけ高鳴った。まるで、ゲームのプロローグだ。俺は無意識にシャッターを切っていた。
教室に戻り、隣の席の栞に現像した写真を見せると、彼女は目を輝かせた。
「なにこれ! 宝の地図!? 面白そう!」
「ただのイタズラだろ」
「『沈黙の歌姫』って、絶対音楽室のベートーヴェンの肖像画だよ! あそこのピアノ、夜中に鳴るって七不思議にもなってるし!」
栞の行動力は光速だ。その日の放課後、俺たちは完全に人気がなくなった校舎に忍び込んでいた。月明かりが差し込む音楽室は、昼間とは全く違う顔をしていた。
「ほら、やっぱり!」
栞が指差したベートーヴェンの肖像画。その裏の壁に、引っ掻いたような小さな傷があった。爪でなぞると、カチリと音がして小さな蓋が開き、中から真鍮の鍵が出てきた。鍵には『Ⅱ』という数字と、『天を映す水盤』という文字が刻まれている。
「やった! 次だ!」
「おい、これマジなのかよ……」
退屈だった日常が、急に色鮮やかな冒険に変わった瞬間だった。
『天を映す水盤』は屋上の雨水タンク、『古の知恵者の寝床』は図書室の司書席。俺の観察眼と栞の突拍子もない閃きは、面白いように噛み合った。次々と鍵を見つけ出すうちに、俺たちの宝探しに、思わぬライバルが現れた。
「君たち、何をコソコソしているんだい?」
現れたのは、生徒会長の西園寺蓮。完璧な笑顔の裏に、鋭い光を宿していた。
「それは僕が探していたものだ。我が曽祖父……この学園の創設者が残した、西園寺家の『遺産』だからね」
西園寺は、俺たちと同じ暗号文の写しを持っていた。どうやら彼は、創設者の子孫として、家宝を探していたらしい。こうして、俺たち平民ペアと、エリート生徒会長との、奇妙な宝探しレースが始まった。
時にヒントを奪い合い、時に協力して仕掛けを解き、時にくだらないことで笑い合う。西園寺が意外とドジで、高いところにある鍵を取ろうとして脚立から落ちそうになったのを、俺と栞で助けたこともあった。
「……ありがとう。君たちといると、調子が狂うな」
ぶっきらぼうに礼を言う彼の横顔は、いつもの完璧な生徒会長とは少し違って見えた。
そして、文化祭当日。六つの鍵を集めた俺たちがたどり着いた最後の暗号は、こうだった。
『祭りの中心にて、百年の喝采が未来を照らす時、最後の扉は開かれん』
「祭りの中心……メインステージだ!」
栞が叫んだ。ちょうどステージでは、軽音部のライブが最高潮に達している。
俺たちは観客をかき分け、ステージの袖へ滑り込んだ。西園寺も既に来ていた。
「ステージの真下だ!」
三人でステージ下の狭い空間に潜り込む。そこには、古びた石板があった。石板には、これまで集めた六つの鍵を差し込む穴が空いている。
「早く!」
ライブの最後の曲が始まった。振動で、天井から埃がぱらぱらと落ちてくる。俺たちが鍵を差し込むと、石板が静かに沈み、下から金属製のタイムカプセルが現れた。
「これか……!」
西園寺がゴクリと息を飲む。俺と栞も固唾を飲んで見守る。蓋を開けた西園寺の顔が、みるみるうちに驚きに変わった。
「金銀財宝じゃ……ない?」
栞が覗き込む。カプセルの中にあったのは、黄金でも宝石でもなかった。それは、無数の紙の束。未来の素材や技術について書かれたメモ、見たこともない校舎の設計図、そして、一枚の手紙。
『これを見つけた未来の君たちへ。本当の宝とは、黄金ではない。それは、君たちがこれから創り出す未来そのものだ。この設計図は、私の夢の青写真(ブループリント)。だが、これはただの叩き台に過ぎない。君たちの手で、これを越える最高の未来を設計してほしい。青春を、世界を、思い切り楽しんでくれ』
ライブが終わり、割れんばかりの拍手と歓声が、ステージ下の俺たちにも届いた。まるで、百年前の創設者からの喝采のようだった。
「なんだ……そういうことかよ」
俺は、思わず笑っていた。退屈な日常なんて、どこにもなかった。宝物は足元に、すぐ隣に、そして未来に転がっていたんだ。
俺たちはタイムカプセルを抱えてステージに上がり、事の経緯を話した。創設者の壮大な夢は、その日一番の喝采を浴びた。
文化祭の片付けも終わった夕暮れの教室で、俺は窓の外を眺める栞に声をかけた。
「なあ、栞」
「ん?」
「俺たちの宝探し、まだ始まったばっかりだよな」
振り向いた栞は、夕日に照らされて、今まで見たどの写真よりも綺麗に輝いていた。
「当たり前でしょ!」
ファインダー越しではない、このキラキラした世界。俺は、ようやく自分の『青春』のシャッターを切った。