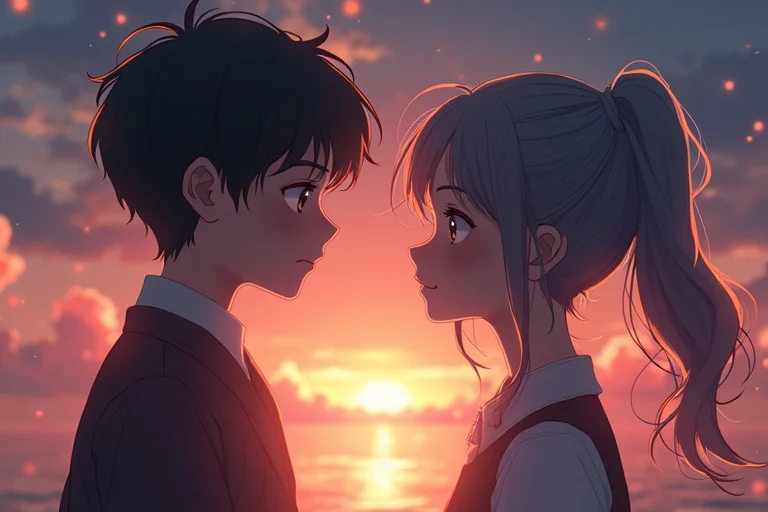第一章 青い砂時計の町
その夏、僕はまた、失われた過去の自分と対峙していた。古い木造りの机に広げた日記帳。真新しい夏の始まりを告げる最初のページには、いつも決まって同じ言葉が綴られている。「この夏こそ、僕はすべてを記憶する」。しかし、その下のページは、どれも空白か、あるいはインクの薄れた走り書きで埋め尽くされているばかりだ。僕が住むこの町には、奇妙な「病」がある。夏の終わりが近づくと、青春時代の鮮やかな記憶が、まるで砂時計の砂が落ちるように、少しずつ、しかし確実に曖昧になっていくのだ。誰もがそれを「夏の記憶喪失」と呼び、抗うことのない自然な現象として受け入れている。だが僕は、それに抗いたかった。
僕の名はユウ。十八歳の夏を迎えようとしていた。窓の外では、蝉時雨が容赦なく降り注ぎ、アスファルトの匂いがむせ返る。隣町から引っ越してきたアオイは、古いフィルムカメラを片手に、この町のすべての風景を焼き付けようとしていた。「忘れるくらいなら、撮り尽くしてやるさ!」彼女の明るい声は、どこか諦めにも似た響きを持っていた。もう一人の親友、カケルは、いつもギターを爪弾き、刹那のメロディを紡ぐ。「言葉よりも、音の方が記憶に残りやすいって、そう思わないか?」彼の作る曲は、いつも青く、そしてどこか物悲しい。僕らは、それぞれのやり方で、薄れていく夏の記憶を必死に繋ぎ止めようとしていた。
この町には「忘れ草」と呼ばれる花が、至る所に咲いている。深い瑠璃色の花弁は、まるで時間を閉じ込めたかのように静かで、見る者の心を掴んで離さない。古老たちは、この花が町の記憶を司っているのだと囁いた。触れると、過去の記憶が泡のように弾けて消える、そんな迷信めいた話もある。僕は日記をつけ、アオイは写真を撮り、カケルは歌を歌う。しかし、去年の夏、その前の夏、そしてもっと前の夏の思い出は、もうほとんど残っていない。覚えているのは、親友たちと過ごした漠然とした楽しさだけだ。それが、僕らの青春だった。
ある日の午後、僕は古い本棚の奥から、一年前に書いたはずの日記帳を見つけ出した。表紙には、僕の拙い字で「去年の夏」と書かれている。パラパラとページをめくる。最初の数ページには、たしかに去年の夏の出来事が綴られていた。花火大会、夏の祭り、アオイとカケルとの些細な冒険。しかし、読み進めるうちに、僕は奇妙な違和感を覚えた。ページの中ほどに、見慣れない、しかしどこか懐かしい文字で書かれた一節があったのだ。
「時の丘、忘れ草、螺旋の記憶。繰り返される問い。ここには、何かがある。」
そして、その一節の隣には、古びた地図のようなスケッチが描かれていた。それは、町の外れにある、今は使われていない古い観測所を示しているようだった。僕は震えた。これは、一体誰が書いたものなのだろうか。僕の、失われた去年の記憶の中に、こんな手がかりがあったのだろうか。僕の胸に、抗い難い好奇心と、これまで感じたことのない切迫感が湧き上がった。この夏は、何もかもが違う。僕はそう直感した。
第二章 記憶の影を追いかけて
僕が見つけた謎の日記の一節は、僕らの「夏の記憶喪失」の裏に隠された真実があることを示唆していた。僕はアオイとカケルにそのページを見せた。アオイは目を丸くし、カケルはギターを弾く手を止めて深く眉根を寄せた。「ユウ、これ、お前の字じゃないよな?」「いや、それが…どうやら僕の字なんだ。記憶が薄れても、文字の癖だけは残るのかもしれない。」僕の声は少し震えていた。
地図の示す「時の丘」は、町から少し離れた場所にある、忘れ草が一面に咲き乱れる小高い丘だった。そこには、錆びついたドーム型の屋根を持つ、使われなくなった古い観測所がひっそりと佇んでいた。夏の日差しが容赦なく降り注ぐ中、僕らは汗だくになりながら丘を登った。忘れ草の群生が風に揺れ、深い青色が波のように広がる。その美しさは、どこか人を惑わすような妖しさを秘めていた。
観測所の中は、ひんやりとして、独特の黴臭さが漂っていた。窓は割れ、計器類は朽ち果てている。埃まみれの床に、いくつかの資料が散らばっていた。その中に、古びた革表紙のノートを見つけた。まるで植物図鑑のようなそのノートには、「忘れ草の生態と時空への影響に関する考察」というタイトルが手書きで書かれている。筆跡は、日記の謎の記述と同じ、僕の、しかし僕ではない誰かのもののように思えた。
ノートを読み進めるうちに、僕らの背筋に冷たいものが走った。そこには、忘れ草が単なる花ではないことが記されていた。
「忘れ草は、その根を通じて地脈から微弱な時空エネルギーを吸収し、その地域一帯の記憶を再構築する能力を持つ。特に人間の感情や記憶が活発な若年層のそれを、特定の『期間』で反復・収束させることで、一種の『記憶の砂時計』を形成する。」
僕らは顔を見合わせた。つまり、僕らが経験している「夏の記憶喪失」は、忘れ草の自然な作用であり、そしてそれは、意図的に仕組まれたものかもしれない、ということだ。さらにノートには、「この現象を停止させることは可能である。ただし、それはこの町そのものの時間の流れに干渉し、極めて危険な結果をもたらす可能性がある」という警告が記されていた。
ノートの最後には、古めかしい装置の設計図が描かれていた。それは、観測所の中央に設置されていた、錆びついた機械に酷似していた。その装置は、忘れ草のエネルギーを増幅・制御し、記憶の再構築の範囲と周期を調整するためのものらしい。僕は、去年の僕が、いや、過去の夏の僕が、この場所で、僕らと同じように真実を探し、このノートを発見し、そして記憶を失い、また次の夏に同じことを繰り返していたのだと、漠然と理解し始めていた。僕たちは、まるで巨大な螺旋階段を、延々と登り続けているような気分だった。
「この町って、一体何なんだ…?」アオイが震える声で呟いた。
カケルは、ギターケースを抱きしめるようにして、ノートの最後のページを凝視していた。そこには、まるで血で書かれたかのように赤いインクで、こう記されていた。
「この螺旋を断ち切るには、記憶の根源にある『悲しみ』と向き合わねばならない。」
「悲しみ?」僕らの記憶が薄れるのは、悲しみを忘れるためなのか?それとも、何か別の、もっと深い意味があるのか?夏の終わりの足音が、今までになく、不吉な響きを帯びて聞こえ始めた。
第三章 時を縛る花
僕らは、ノートの記述と観測所の装置、そして忘れ草の謎に、頭を悩ませた。一体、この町の「悲しみ」とは何なのか。そして、なぜ「夏の記憶喪失」が繰り返されているのか。僕が去年の日記に書き残した「螺旋の記憶」という言葉が、まるで僕らの状況を正確に言い当てているように感じられた。
アオイが、ノートの片隅に挟まっていた古い新聞の切り抜きを見つけた。それは、数十年前の地元紙の小さな記事だった。「大規模地滑り発生、町の中心部に壊滅的被害」。記事には、当時のこの町を襲った未曾有の災害のことが書かれていた。多くの犠牲者が出たこと、そして、町が復興に途方もない時間を要したこと。しかし、僕らの記憶には、そんな悲惨な出来事は一切残っていなかった。いや、そもそも、この町にはそんな災害があったことを知っている大人もいない。僕たちは、半信半疑で、町役場の古い資料を漁った。そして、そこで、さらに衝撃的な事実を知ることになる。
町役場の最下層にある、厳重に施錠された資料室。そこに収められていたのは、忘れ草の生態を研究していたとされる、今は亡き植物学者の日誌だった。その日誌には、僕らが観測所で発見したノートの記述を補完する、恐るべき内容が書かれていた。
「地滑り災害後、町は絶望に包まれた。人々は深い悲しみに囚われ、町全体が死んだように沈黙した。そんな中、私は忘れ草の持つ、記憶を再構築する能力に注目した。しかし、それは記憶を消すだけでなく、特定の期間の記憶を循環させることで、時間の流れそのものを『安定したループ』の中に閉じ込めることも可能だと判明したのだ。」
僕らは息を呑んだ。この町は、過去の悲劇から立ち直るために、忘れ草の力を使って、意図的に時間をループさせていたのだ。悲しみを忘れるため、新しい記憶が上書きされるたびに、悲劇の記憶は薄れ、町の人々は、永遠に「災禍のない夏の終わり」を繰り返す。そして、そのループは、青春時代に特化して強く作用する。つまり、僕らが経験している「夏の記憶喪失」とは、この町が悲劇を乗り越えるために選び取った、残酷な「安定」の代償だったのだ。
「待ってくれ…僕らの青春は、幻だったのか?」カケルが絞り出すような声を上げた。
アオイは、これまで撮りためた写真の山を眺め、涙を流していた。「写真に写っているのは、本物の私たちなのに…でも、その写真が意味する記憶は、何度でも消されてしまうなんて…」
僕の日記に書かれていた「見覚えのない文字」の正体も、これで全て繋がった。それは、過去の夏の僕が、この真実に辿り着くたびに、次の僕のために残した「警告」であり「手がかり」だったのだ。僕たちは、何度もこのループの中で、同じ夏を過ごし、同じようにこの真実を追い求めていた。そして、夏の終わりには、すべてを忘れ、また新しい「初めまして」の夏を迎えていた。僕たちの青春は、螺旋を描くように、永遠に繰り返されていたのだ。僕らの価値観は根底から揺らいだ。これまで信じてきた、刹那の輝きを追いかける「青春」が、実は誰かの手によって作られた、巨大な箱庭の中の幻だったなんて。この事実は、僕らの胸に、激しい怒りと、深い虚無感を同時に植え付けた。
第四章 それでも、夏の終わりに
真実を知った僕らは、重い選択を迫られた。このまま、永遠に繰り返される「忘れられた夏」の中で、薄れていく記憶と共に生きるのか。それとも、このループを断ち切り、過去の悲劇と向き合い、未来へと進むのか。後者を選べば、町は再び混乱に陥るかもしれない。失われた記憶が戻ることで、人々は新たな悲しみや絶望に直面する可能性がある。それでも、僕たちは幻ではなく、本物の青春を生きたかった。
「僕は、この夏の記憶を、鮮明に残したい。アオイとカケルと過ごしたこの瞬間を、忘れずにいたい!」僕の声は、決意に満ちていた。
アオイは、握りしめたカメラを強く見つめ、静かに頷いた。「私、忘れたくない。もう、何も失いたくない。」
カケルはギターを背負い、僕らの目を見て言った。「このループ、ぶっ壊してやろうぜ。本物の音を、刻みつけるんだ。」
僕らは、再び時の丘の観測所へと向かった。古びた装置の設計図を頼りに、その機能を再構築する。忘れ草の力を停止させ、町の時間のループを断ち切る。それは、町の過去と現在、そして未来を賭けた、無謀な挑戦だった。観測所の錆びついたレバーを、僕は震える手で引いた。ゴトン、と重い音を立てて、装置が起動する。地中から微かな振動が伝わり、忘れ草の群生が、まるで悲鳴を上げるかのように、青い光を放ち始めた。
装置の作動と共に、町の空気が一変した。遠くから、人々のざわめきが聞こえる。これまで、どんな夏が来ても、常に穏やかだった町が、ざわつき始めた。忘れ草は、徐々にその色を失い、深い青色から白く枯れ、風に舞い散っていく。それに連動するように、町の人々の表情に、困惑や悲しみ、あるいは怒りといった、これまで見たことのない複雑な感情が刻まれていくのが感じられた。彼らの失われた記憶が、一斉に戻ってきたのだ。
町の風景も少しずつ変化を見せた。崩れた石垣、ひび割れたアスファルトの隙間から顔を出す、かつての災害の痕跡。それは、僕らが初めて目にする、この町の「本物の姿」だった。人々は混乱し、悲嘆に暮れる。しかし、その混乱の中にも、どこか力強い、新しい生命の息吹が感じられた。それは、幻の平和ではなく、真実と向き合うことで得られる、本物の希望の光だった。
僕たちの記憶は、鮮明なままだ。夏の終わりは来たが、僕らは何も失わなかった。アオイは、枯れた忘れ草の写真を撮り、カケルは、その光景を歌に乗せる。僕もまた、新しい日記のページに、この夏に起こったすべての出来事を書き記した。僕らの選択が本当に正しかったのか、それが町に新たな悲しみをもたらすのではないか、という不安は、確かに胸の奥にある。それでも、僕たちは、失われることのない「本物の記憶」という、かけがえのない宝を手に入れたのだ。
次の夏、僕らは、記憶を持ったまま新しい季節を迎えるだろう。町は、以前とは違う姿になるかもしれない。人々は、混乱の中から、新しい秩序を見出すために苦悩するだろう。それでも、僕たちは、この夏を忘れない。僕らの青春は、幻の中で終わるのではなく、この町の真実を刻み込み、未来へと続いていく。僕は日記の最後のページに、希望と、そして記憶の重みを刻んだ。青春は終わらない。形を変えて、無限に、続いていくのだと。