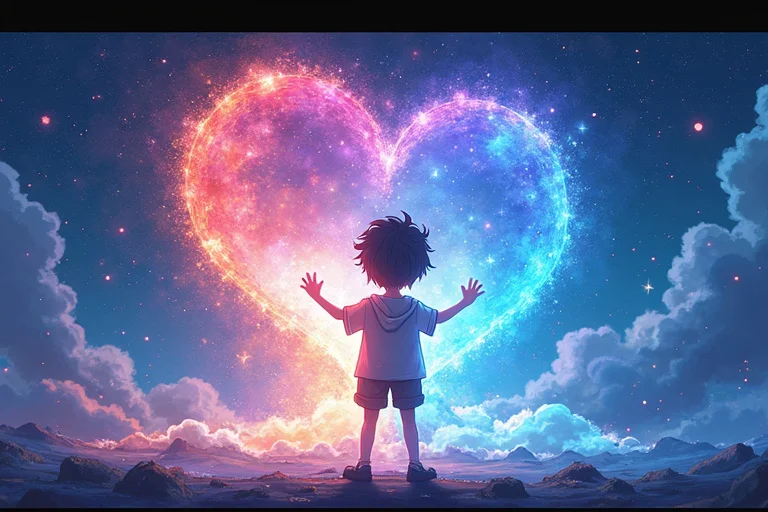第一章 色を失くした街角
僕、アオイの言葉は、いつも宙に迷子になる。
街ゆく人々が交わす挨拶は、柔らかな若草色や快活な橙色の粒子となって互いの胸に吸い込まれていく。恋人たちが囁く愛の言葉は、燃えるような深紅や甘い薔薇色の光の帯となり、二人の間を溶け合うように行き交う。この世界では、感情は色を持ち、言葉は心を繋ぐ架け橋だった。人々は十六の歳を迎えると、その架け橋を渡る術を身につける。
けれど、僕の言葉だけは違った。
「ヒカリ、待って」
放課後の雑踏の中、僕は彼女の名前を呼んだ。僕の口からこぼれたのは、澄み切った空の色を映したかのような、鮮烈な蒼の粒子。それは僕の本心の色。けれど粒子は彼女の背中に届くことなく、まるでシャボン玉のようにふわりと宙を舞い、誰に触れることもなく、ただそこに漂うだけ。
足を止めたヒカリが振り返る。彼女の周りには、友人たちから贈られたであろう色とりどりの粒子がオーラのように揺らめいていた。人気者の彼女は、いつもたくさんの色をその身に纏っている。それが少し、眩しかった。
「どうしたの、アオイ? 顔色が悪いよ」
心配そうに紡がれた彼女の言葉は、温かな陽だまりのような黄金色をしていた。その粒子が僕に向かって飛んでくる。けれど、僕の心の手前で見えない壁に弾かれるようにして、するりと逸れて消えてしまう。僕は誰の色も受け取ることができない。そして、僕の色もまた、誰にも与えることができない。
「ううん、何でもない。今日の君は、特に綺麗だなって」
僕が微笑むと、今度は淡いラベンダー色の粒子が生まれた。賞賛と、少しの憧れ。それもまた、彼女の纏う華やかなオーラの周りを衛星のように旋回するだけで、決して彼女自身には届かない。ヒカリは寂しそうに眉を寄せたが、すぐに笑顔を作って見せた。
「ありがとう。でもね、最近少し疲れるんだ。いろんな色が混ざりすぎて、自分の色がどんなだったか、忘れちゃいそう」
その言葉に、僕は胸が締め付けられるのを感じた。街では「色彩混濁症」の噂が囁かれ始めていた。他者の色を受け取りすぎた結果、心が混濁し、自我が曖昧になるという病。ヒカリの纏うオーラも、よく見ればいくつかの色が濁り、淀んだ色合いを生み出している箇所があった。
僕は彼女を救いたかった。僕のこの純粋な蒼を、そっと彼女の心に届けたかった。だが、僕の言葉はいつだって無力だった。誰とも繋がれない、色のない孤独。それが僕の世界の全てだった。
第二章 混濁する心象
季節が巡るにつれて、街の色は加速度的に濁っていった。人々はより強く、より鮮やかな色を求め、まるで飢えた獣のように他者の感情を貪り合った。友情の証として交わされる緑は濃すぎ、愛情を示す赤はどす黒く、喜びの黄色は目に痛いほどぎらついていた。街角では、自分の名前すら思い出せなくなった色彩混濁症の患者が、虚ろな目で立ち尽くす姿が珍しくなくなった。
ヒカリの症状も、日に日に悪化していった。あれほど豊かだった彼女の表情は乏しくなり、言葉から生まれる粒子の色も、鈍い灰色が混じるようになっていた。僕がどんなに声をかけても、彼女の反応は薄く、その瞳は僕の向こう側の何かを見ているようだった。
「自分の色を、見失わないで」
ある雨の日、僕は傘もささずに彼女の家の前でそう懇願した。僕の喉から絞り出された言葉は、悲痛なインディゴブルーの雨となり、アスファルトを濡らした。ヒカリはただ、窓の内側からぼんやりと僕を見つめるだけ。彼女の心には、もうどんな言葉も届かないのかもしれなかった。
無力感に苛まれながら、僕は古い図書館の片隅で答えを探し続けた。なぜ僕だけが特別なのか。この悲しい病の本当の原因は何なのか。古い文献を紐解くうち、僕は一つの仮説に辿り着く。色彩混濁症は、単なる「受け取りすぎ」が原因なのではない。人々が、他者の色で自分を彩ることに慣れすぎた結果、自分自身の心から言葉を紡ぐことを忘れ、内なる泉を涸らしてしまったことが、真の原因ではないだろうか。
自室に戻ると、窓辺に置いた小さな石が目に入った。それは僕が幼い頃に河原で拾った、何の変哲もない、ただの透明な石。けれど、その周りには、僕が部屋で独り呟いた言葉の粒子たちが、まるで雪のように静かに降り積もっていた。誰にも届かなかった僕の言葉たち。喜びのスカイブルー、悲しみのインディゴ、怒りのスカーレット。それらの粒子は消えることなく、長い時間をかけてこの石に吸い寄せられ、その内部に蓄積されているようだった。
僕はそっと石を手に取った。ひんやりとした感触。普段はただ透明なだけのそれは、僕の指先から伝わる微かな体温に反応したのか、ほんの一瞬、内側から虹色の光を放ったように見えた。
第三章 純粋なる蒼の奔流
その知らせは、冷たい冬の風のように突然僕の耳に届いた。
ヒカリが、倒れた。
病院に駆けつけると、彼女は白いベッドの上で静かに横たわっていた。彼女を包んでいた色とりどりのオーラは完全に消え失せ、代わりにどす黒い泥のような靄が、その全身からゆらゆらと立ち昇っている。瞳は固く閉じられ、呼吸だけが、彼女がかろうじて生きていることを示していた。
「色彩混濁症の末期です。もう、我々には……」
医者の言葉が、遠くで響いていた。周りでは、ヒカリの両親が泣き崩れている。僕はただ、立ち尽くすことしかできなかった。僕の無力さが、彼女をここまで追い詰めたのだ。他者の色を受け入れず、自分の色も与えられない、欠陥品。それが僕だ。
絶望が、僕の心を黒く塗りつ潰そうとした。
だが、その時だった。ヒカリの指が、ほんのわずかに動いた気がした。
「……ア、オ……イ……」
か細い、色のない声。それは粒子にすらならなかった。けれど、確かに僕の名を呼んでいた。
僕の中で、何かが弾けた。絶望の底から、熱いものが込み上げてくる。それは、諦めきれない想い。彼女を取り戻したいという、ただ一つの純粋な願い。
「ヒカリッ!」
僕は叫んだ。それはもはや、ただの言葉ではなかった。僕の魂そのものの咆哮だった。
僕の全身から、これまで見たこともないほどに眩い、純粋な蒼色の光の奔流がほとばしった。病室の空気が震え、光の粒子が嵐のように吹き荒れる。そして、その奔流は、僕が握りしめていた胸ポケットの石へと、一斉に吸い込まれていった。
次の瞬間、僕の手の中で、その石は太陽のように輝き始めた。
それは「無色の結晶」だった。どんな色にも染まらず、僕の純粋な本心だけを蓄え続けた、僕の心の結晶。その結晶が、眩い虹色の光を放ちながら、僕に真実を教えてくれた。
僕の能力は、欠陥なんかじゃなかった。他者の影響を受けず、常に自分自身の「本心の色」を保ち続けるための、聖域だったのだ。人々が混濁したのは、他人の色に頼り、自分の色を見失ったから。ならば、救う方法は一つしかない。
僕は光り輝く結晶を手に、ヒカリのベッドへと一歩踏み出した。
第四章 世界が色を取り戻すとき
僕は震える手で、虹色に輝く結晶をヒカリの胸の上にそっと置いた。温かい光が、彼女の身体を優しく包み込む。
僕はもう、言葉を「与えよう」とは思わなかった。ただ、僕の心を、この世界に響かせようと決めた。祈るように、歌うように、僕は静かに言葉を紡ぎ始める。
「思い出して、ヒカリ。君だけの色を」
僕の口から生まれた純粋な蒼の粒子は、もう彼女の体内に入ろうとはしなかった。代わりに、結晶を触媒として、彼女を蝕むどす黒い靄に触れていく。すると、魔法のように、靄の中から他人の色――見栄のための赤、偽りの笑顔の黄色、媚びへつらいの茶色――が、次々と剥がれ落ちていった。
そして、全ての不純な色が浄化された後、彼女自身の心の中から、淡く、しかし確かな光が生まれ始めた。それは、誰にも汚されていない、優しくて温かい、桜色の光だった。ヒカリ自身の、本当の色。
奇跡は、病室の外へ、そして街へと広がっていった。結晶から放たれる虹色の光と、僕の言葉の響きが共鳴し、色彩混濁症に苦しむ人々の心に届いていく。彼らは、他者の色を求めることをやめ、自分自身の内なる泉に目を向け始めた。
街は、以前のようなけばけばしい色彩を失った。しかし、そこには多種多様な、穏やかで優しい、本物の色が静かに輝いていた。誰もが、自分だけの色を誇らしげに纏っている。それは、色を「交換」する世界ではなく、互いの色をありのままに「尊重」し、照らし合う世界の始まりだった。
ゆっくりと、ヒカリが目を開けた。その瞳には、確かな光が宿っている。
「アオイ……」
彼女の唇からこぼれた言葉は、美しい桜色の粒子となり、僕の周りを優しく舞った。それは僕の心には入らない。けれど、僕の蒼と彼女の桜色は、互いに触れ合うことなく、ただそこに在るだけで、完璧に調和していた。僕たちは、確かに繋がっていた。
もう、僕は孤独ではなかった。空を見上げると、僕が紡いだ言葉が、柔らかな蒼色の粒子となって、新しい世界へと静かに溶けていくのが見えた。