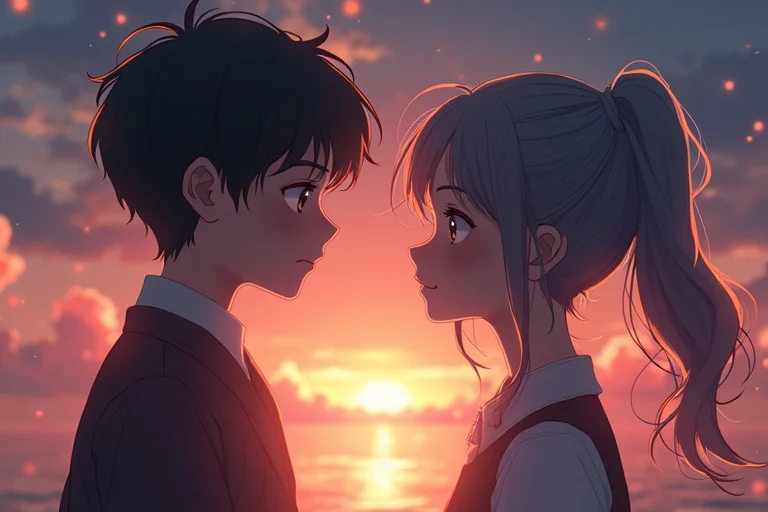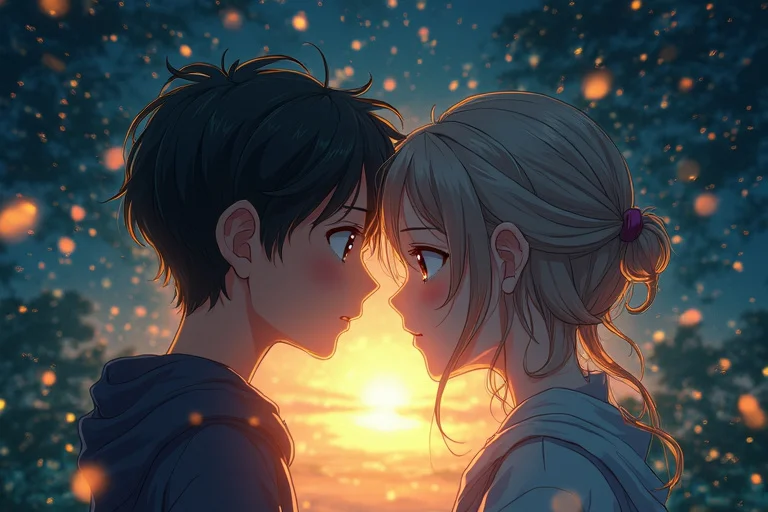第一章 色褪せたプレビュー
僕の住む街、識港市(しきこうし)は、記憶で動いている。
街灯の柔らかな光も、滑るように走る路面電車も、その動力源はすべて、市民が十八歳の誕生日に供出する「最も輝かしい記憶」から抽出されるエネルギーによって賄われているのだ。供出は義務であり、街への貢献の証とされた。供出された記憶は、持ち主の脳から綺麗に消え去る。まるで、初めからそんな出来事はなかったかのように。
高校三年生の夏。僕、水野蒼(みずの あお)の十八歳の誕生日まで、あと一ヶ月を切っていた。写真部に所属する僕は、日々ファインダー越しに世界を切り取っている。光、影、人々の刹那の表情。それらを印画紙に焼き付けることで、不確かな世界に確かな輪郭を与えようと足掻いていた。僕にとって、記憶とはカメラに収めるべき被写体だった。
しかし、供出すべき「最も輝かしい記憶」が、僕には見つけられずにいた。これまでの十七年間、僕の人生はまるで露出アンダーの写真のように、どこか薄暗く、決定的な瞬間に欠けているように思えた。
「ねぇ、蒼。本当に供出しなきゃ、だめなのかな」
放課後の暗室。赤いセーフライトの光が、隣で現像液を揺らす幼馴染、月島陽菜(つきしま ひな)の横顔を妖しく照らしていた。不意に発せられたその言葉は、現像液の酸っぱい匂いの中に、不穏な響きを伴って溶けていく。
「陽菜? 当たり前だろ。街のルールなんだから」
「でも、もし……一番大事なものを失くしちゃったら、どうするの? 人は、それでちゃんと生きていけるのかな」
陽菜の声は、水面を揺らす小石のように、僕の心の平穏をかき乱した。彼女の兄は三年前に記憶を供出した。それ以来、優秀で快活だった彼は、どこか感情のピントがずれてしまったように、虚ろな微笑みを浮かべるだけの人になってしまったと、陽菜は時々寂しそうに話していた。
「大丈夫だよ。みんなそうしてるんだから」
僕は根拠のない言葉を返すことしかできなかった。セーフライトの赤い光の中で、陽菜の瞳が潤んでいるように見えたのは、きっと気のせいだ。僕の胸の中で、これまで感じたことのないシャッターチャンスを逃したような、奇妙な焦燥感が芽生え始めていた。僕たちの最後の夏は、そんな不確かな予感を孕んで静かに始まろうとしていた。
第二章 焦がれたシャッターチャンス
「最高の記憶がないなら、これから作ればいいんだよ!」
翌日、陽菜はまるで昨日の憂鬱を振り払うかのように、そう言って笑った。彼女の提案で、僕たちは残された夏休みを「最高の記憶」作りのために費やすことになった。
蝉時雨が降り注ぐ中、浴衣姿で歩いた夏祭り。綿菓子の甘ったるい匂い。夜空に大輪の花を咲かせる花火を、僕はずっと陽菜の横顔と一緒にフレームに収めていた。打ち上がる光に照らされるたびに変わる彼女の表情は、どんな花火よりも僕の心を捉えて離さなかった。
潮風が頬を撫でる海辺では、砂浜にはしゃぐ陽菜にレンズを向けた。波と戯れ、太陽の光を全身に浴びて笑う彼女は、まるでこの世界の輝きを独り占めしているかのようだった。ファインダーを覗く僕の心臓が、絞りを開けすぎたレンズのように、どうしようもなく光を取り込んで高鳴るのを感じた。
二人きりの図書室、西日に染まる教室、誰もいない屋上。僕のカメラのメモリは、陽菜との記憶で急速に満たされていった。一枚、また一枚と写真が増えるたびに、僕の中で確信が生まれていく。僕が供出すべき記憶は、他のどれでもない。この、陽菜と過ごした夏。この焦がれるような、切なくて、どうしようもなく愛おしい時間だ。
しかし、その確信は同時に、鋭い痛みとなって僕の胸を抉った。これを供出するということは、この感情も、陽菜が僕に見せてくれた笑顔のディテールも、すべてを失うということだ。彼女の兄のように、僕もまた、何か大切なものを失い、虚ろになってしまうのだろうか。陽菜は、そんな僕を見ても、今まで通り笑いかけてくれるのだろうか。
「蒼は、どの記憶にするか決めた?」
夕暮れの帰り道、陽菜が尋ねた。僕は言葉に詰まる。
「……まだ、かな」
「そっか。……ねぇ、蒼。もし私が、いなくなったらどうする?」
「え?」
「ううん、なんでもない!」
彼女は悪戯っぽく笑って駆け出した。その背中を追いかけながら、僕は強烈な不安に襲われた。まるで陽菜が、僕の記憶から消えてしまう未来を予言しているかのように聞こえたからだ。僕はこの夏を、永遠に手放したくない。その思いが、僕をある行動へと駆り立てた。
第三章 現像された真実
識港市には、供出された記憶が保管される「中央アーカイブ」という施設がある。供出された記憶はエネルギーに変換されるだけでなく、個人情報を削除された上でデータとして保存され、市民は教養目的でそれを閲覧することができた。ただし、自分の記憶や、近親者の記憶を直接検索することは固く禁じられている。
僕は、陽菜の兄が供出した記憶の正体を知りたかった。彼をあんなにも変えてしまった記憶とは、一体どんなものだったのか。そこに、僕たちがこれから迎える未来へのヒントが隠されているような気がしたのだ。司書の目を盗み、禁止されている親族検索のプロテクトを、ハッキングの知識を総動員して解除する。検索窓に「月島 拓海」と打ち込むと、たった一つのデータがヒットした。
タイトルは『妹の死』。
僕は息を呑んだ。再生ボタンを押すと、ノイズ混じりの映像が流れ始める。それは、商店街の交差点だった。自転車に乗った幼い陽菜。信号を無視して猛スピードで突っ込んでくるトラック。悲鳴。衝撃音。アスファルトに広がる、赤い、赤い染み――。それは、陽菜が小学三年生の時に遭ったとされる、軽傷で済んだはずの自転車事故の光景だった。だが、アーカイブの記憶の中で、彼女は明確に命を落としていた。
どういうことだ? 陽菜は、今、生きている。混乱する僕の目に、データの注釈が飛び込んできた。
『記憶分類:高エネルギー値/カテゴリ:現実改変適用済み』
――現実、改変?
僕はアーカイブのシステム深層へとさらに潜り込んだ。そして、この街の根幹を揺るがす、恐ろしい真実を発見してしまった。
識港市のシステムは、単に記憶をエネルギーに変えるだけではなかった。特に強い感情――悲しみ、喜び、後悔――が込められた記憶は、稀に「現実を書き換える」ほどの莫大なエネルギーを放出するというのだ。陽菜の兄は、妹を失った耐え難いほどの悲しみの記憶を供出することで、事故が起こらなかった、あるいは軽傷で済んだという「あり得たかもしれない現在」へと、世界線を強制的に上書きしたのだ。
その代償として、彼は妹を失った記憶も、彼女を救ったという実感も、それに伴うすべての感情を失った。だから彼は、あんなにも虚ろなのだ。
全身から血の気が引いていく。陽菜が言っていた言葉が、脳内でリフレインする。
『一番大事なものを失くしちゃったら、どうするの?』
『もし私が、いなくなったらどうする?』
彼女は、このシステムの真実に薄々感づいていたんだ。だから、記憶の供出を恐れていた。もし僕が、陽菜と過ごしたこの幸せな夏の記憶を供出したら? その強すぎる幸福感が、システムに「現実改変」のトリガーを引かせてしまったら? この幸せだった夏そのものが、「なかったこと」にされてしまうかもしれない。陽菜の存在ごと、僕の世界から消えてしまうかもしれない。
暗室のセーフライトよりも濃い、絶望的な暗闇が僕を包んだ。僕が手にした「最も輝かしい記憶」は、同時に世界を壊しかねない、危険な爆弾でもあったのだ。
第四章 僕が選んだ一枚
十八歳の誕生日当日。僕は供出の儀式が行われる市庁舎のホールに立っていた。純白の空間の中央に、記憶をスキャンする装置が静かに鎮座している。隣には、同じく今日誕生日を迎えた陽菜が、固い表情で立っていた。
僕の選択肢は二つ。
一つは、陽菜との夏を供出すること。それは、僕たちの世界が消滅するリスクを伴う危険な賭けだった。
もう一つは、当たり障りのない、例えば中学の修学旅行のような、凡庸な記憶を供出すること。そうすれば、この夏は僕だけのものとして残り続ける。だが、それは街への、そして何より僕の気持ちへの裏切りだ。
僕はこの数日間、眠れぬ夜を過ごし、考え抜いた。陽菜との写真を何度も見返し、その一枚一枚に込められた感情の粒子を確かめるように指でなぞった。そして、たった一つの答えに辿り着いた。
「水野 蒼さん。供出する記憶を、心に強く思い描いてください」
係員の声が響く。僕は目を閉じた。
僕が選んだ記憶。それは、陽菜と過ごした輝かしい夏の日々ではない。アーカイブで街の真実を知ってしまったあの日から、今日この場所に立つまでの、苦悩に満ちた数週間の記憶だ。
陽菜を失うかもしれない恐怖。世界が壊れるかもしれない不安。どうすれば彼女を守れるのか、答えの出ない問いに苛まれ続けた、暗くて、痛くて、みっともない時間。それは、およそ「輝かしい」とは言えない記憶だった。
けれど、その苦悩のすべては、陽菜を大切に思う心から生まれたものだ。彼女の未来を案じ、必死で考え抜いた、僕の青春そのものだった。これ以上に純粋で、強い感情が込められた記憶を、僕は他に知らない。
装置から光が放たれ、僕の意識が一瞬、白に染まる。
……儀式が終わった。僕はぼんやりとした頭で目を開ける。街のシステムに関する複雑な知識や、アーカイブで見た衝撃的な映像は、靄がかかったように思い出せない。ただ、何かとても大切な決断をした、という確信だけが胸に残っていた。陽菜との夏の思い出は、色鮮やかなまま僕の中にあった。
「蒼!」
心配そうな顔をした陽菜が駆け寄ってくる。
「……大丈夫だった?」
「ああ。……陽菜、俺、覚えてるよ。君と過ごした夏。全部」
僕の言葉に、彼女の瞳がみるみるうちに潤んでいく。
「よかった……。私、怖かった。蒼が、私のこと忘れちゃったらどうしようって……」
僕は無意識に、首から下げたカメラを構えていた。
「忘れるわけないだろ」
ファインダーを覗くと、泣きそうな顔で、でも最高に嬉しそうに微笑む陽菜がいた。僕は静かにシャッターを切る。
カシャッ。
供出した記憶の詳細は、もう思い出せない。でも、それでいい。記憶は失われても、感情は残る。この胸に深く刻まれた、陽菜を想う切ないほどの温かさは、決して消えたりしない。
僕たちの青春は、不確かな記憶と、一枚の写真、そしてこの確かな温もりとして、これからも続いていく。ファインダー越しの彼女の笑顔が、僕にとっての新しい「最も輝かしい記憶」になった。