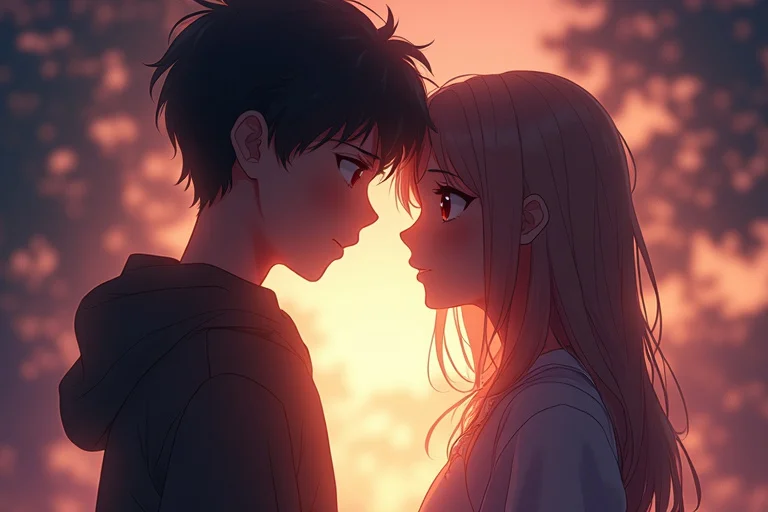第一章 色褪せた卒業写真
俺、相羽アキ(あいば あき)には、呪いのような祝福がある。
誰かの「青春の終わり」――その人が夢に破れ、情熱を燃やし尽くし、輝きの頂点で膝をつく、その瞬間に立ち会うと、俺はその人の「最も輝かしい記憶」をそっくり自分のものとして取り込んでしまうのだ。
引退を決めた老ヴァイオリニストの最後の演奏会。鳴り響く万雷の拍手と、弦を押さえる指先の痺れるような熱。
甲子園の夢破れた高校球児が、マウンドの土を握りしめた瞬間の、汗と涙のしょっぱい味。
コンテストに落選した画家の卵が、朝日の中で自らの最高傑作を燃やす時の、キャンバスが焦げる匂いと、諦念の静寂。
それらは俺の中に流れ込み、まるで自分が体験したかのように鮮やかに焼き付く。俺は他人の輝きを追体験することでしか、自分が生きているという実感を得られない。空っぽの器に、他人の記憶という名の酒を注ぎ込むように。
代償は、あまりに大きかった。他人の過去を一つ受け取るたびに、俺自身の「未来の記憶」が砂の城のように崩れていくのだ。来週、友人と交わした映画の約束。いつか行きたいと願った海辺の町の風景。そして、いつか愛する誰かと分かち合うはずだった、まだ見ぬ温もり。それらが、少しずつ、しかし確実に、俺の中から消え去っていく。
この世界では誰もが、過去の誰かの忘れられた夢や情熱の断片――「青春の残滓(ざんし)」を生まれながらに受け継いでいるという。それは人を突き動かす炎となるが、持ち主の未練が強すぎれば、受け継いだ者の未来を歪める呪いにもなる。俺の親友、カイトがそうだった。彼は、夭折した天才ギタリストの「未完の曲」という残滓に囚われ、自分の音楽を見失いかけていた。
そんなある日、俺は古道具屋の隅で、一枚の色褪せた卒業写真を見つけた。セピア色の集合写真。だが、妙だった。最後列の隅に、まるでそこにいるはずのない誰かの「影」が、陽炎のように滲んでいる。裏には、インクの掠れた文字で、日付と共にこう記されていた。
『未来への希望』
その写真を手にした瞬間、脳裏を鋭い閃光が貫いた。
知らないはずの景色。海風に揺れる白い灯台。夕暮れの教室で、俺を見て柔らかく微笑む、名前も知らない少女の横顔。激しい懐かしさと、胸を締め付けるような切なさが込み上げる。これは誰の記憶だ? 俺が今まで取り込んだ誰かのものか? いや、違う。これはもっと、俺自身の根源に触れるような、失われた記憶の残響だった。
この影の正体は何だ? この懐かしい景色の意味は?
俺は、自身の未来が完全に消え去る恐怖に抗いながら、答えを求めて他人の「青春の終わり」を探し、彷徨い続けることを決意した。写真の影が、俺を導く唯一の道標だった。
第二章 残滓のフーガ
「また、ぼーっとしてた。最近のお前、どこか遠くにいるみたいだぜ、アキ」
屋上で風に吹かれながら、カイトが錆びたフェンスに寄りかかって言った。その指先は、いつも通りギターのコードを押さえる形で虚空を彷徨っている。彼の瞳には、彼自身にも制御できない焦燥の炎が揺らめいていた。
「……そうか?」
俺は曖昧に笑って誤魔化す。本当は言えない。カイトと交わした「次のライブで新曲を披露する」という約束が、もう俺の記憶の中では輪郭を失いかけていることを。
俺は記憶を集め続けた。
引退するバレリーナのラストステージ。彼女が見た、スポットライトの眩しさと客席の闇。
その記憶を取り込んだ時、俺はカイトの誕生日に何を贈るつもりだったのかを、完全に忘れた。
写真の影は、少しだけ濃くなった。そして再び、あのビジョンが俺を襲う。灯台。夕暮れの教室。微笑む少女。彼女が何かを言おうと唇を開く。だが、その声は聞こえない。
「駄目だ、駄目だ……! 何も出てこない!」
隣でカイトが頭を掻きむしり、持っていたピックを地面に叩きつけた。
「俺の中には、あの人のメロディしかない。俺自身の音は、どこにもないんだ!」
彼の苦しみは、「未完の曲」という残滓の呪縛だった。あまりに強大で、美しすぎる過去の才能が、カイトという新しい器を食い破ろうとしている。このままでは、カイトの青春は歪められたまま、不完全に終わってしまう。
その夜、俺は自室で卒業写真を睨みつけていた。集めた記憶が増えるたび、影は人の形を取り戻し、写真全体も僅かに色を取り戻していく。まるで、失われたピースをはめるように。
ふと、俺は気づいてしまった。
俺が取り込んだ他人の記憶の中に、あの「灯台のある町」や「夕暮れの教室」は一度も現れていない。なのに、なぜ俺はこれほどまでにこの景色を知っている? なぜ、あの少女の微笑みが、俺の魂をこんなにも揺さぶる?
まさか。
この記憶は、他人のものではない。
俺が探し求めているのは、俺自身が「失った」未来の記憶の断片なのではないか。
この写真に写っている影は、未来を失い続ける果てに俺が辿り着くはずだった、「未来の自分」の姿なのではないか。
ぞっとするような仮説が、冷たい刃となって心臓を抉った。だとしたら、俺は自分の未来を取り戻すために、他人の過去を奪い続けていることになる。自分の未来が消える恐怖と、その根源に近づいているかもしれないという微かな希望が、俺の中で矛盾の渦を巻いていた。
第三章 君が灯した未来
その日は、冷たい雨が降っていた。
ライブハウスの控室。カイトは壁にギターを叩きつけようとしていた。その目は虚ろで、彼の内なる「残滓」が完全に彼を飲み込もうとしているのが分かった。これが、彼の「青春の終わり」の始まりだった。
「もう無理だ……! 俺には何も生み出せない! あの人の亡霊が、俺を笑ってるんだ!」
カイトの絶叫が、狭い部屋に木霊する。隣では、共通の友人であるヒナタが泣きそうな顔で彼を止めようとしていた。俺は、その光景をただ見ていることしかできなかった。俺の能力が、この瞬間を待っていた。カイトの挫折、その輝かしい苦悩の記憶を、今まさに取り込もうと疼いていた。
そうすれば、写真の影はもっと鮮明になるだろう。失われた記憶の謎に、また一歩近づけるかもしれない。
だが。
俺の脳裏に、カイトと笑い合った日々が断片的に蘇る。下手くそなギターを教え合った放課後。いつか二人でステージに立つと誓った夜。その記憶すら、もう霞がかかったように曖昧だ。こいつの未来を奪って、俺は自分の過去を探すのか? それはあまりに身勝手で、醜悪ではないか。
「やめろよ、カイト」
俺の声は、自分でも驚くほど静かだった。
「……お前に何が分かる! 未来のないお前に!」
カイトの言葉が、ナイフのように突き刺さる。そうだ、俺には未来がない。だから、分かる。未来を失うことの、本当の恐ろしさが。
「分かるさ。だから……俺にくれよ」
俺はカイトの肩を掴んだ。彼の瞳の奥で、黒い炎のように揺らめく「残滓」を真っ直ぐに見据える。
「お前を苦しめるその呪いも、お前が諦めようとしてる未来も、全部俺にくれ! 俺がお前の代わりに、その記憶の終わりを見届けてやる!」
これは賭けだった。一人の人間の、青春そのものを取り込む。それが何を意味するのか、俺にも分からない。だが、これしか道はない。
ヒナタの悲鳴が聞こえた。俺はカイトの額に手を当てる。瞬間、凄まじい奔流が俺の中に流れ込んできた。それは単なる記憶ではなかった。夭折したギタリストの無念。完成させることのできなかった一曲への執着。そして、それに押し潰されそうになっているカイトの絶望、苦悩、そしてそれでも捨てきれない音楽への愛。
「ぐっ……あああああああっ!」
俺自身の未来の記憶が、猛烈な勢いで消し飛んでいく。ヒナタの顔が、声が、思い出が、掻き消えていく。カイトとの誓いも、何もかも。視界が白く染まる。意識が遠のく寸前、俺は見た。
流れ込んできた膨大な記憶の奔流の、その最も深い場所で、静かに輝く一つの光景を。
海辺の町。白い灯台。夕暮れの教室。
そして、あの少女が、泣きそうな顔で俺を見て、はっきりとこう言ったのだ。
『忘れないで。私たちの「未来への希望」を』
全てが、繋がった。
色褪せた卒業写真が、懐から滑り落ちる。それは、まるで生まれたてのような鮮やかな色彩を取り戻していた。
写真の中央。かつて影だった場所には、俺とよく似た、しかし確かな希望に満ちた瞳で笑う少年が写っていた。その隣には、カイトやヒナタによく似た友人たち。そして――あの少女が、幸せそうに少年の腕に寄り添っていた。
ああ、そうか。
俺が探していたのは、「未来の自分」なんかじゃなかった。
これは、俺自身がかつて生きた、「失われた過去」の姿だったんだ。
第四章 希望という名の残光
俺こそが、全ての始まりだった。
遥か遠い昔、俺は「青春を全うできなかった」最初の人間だった。不治の病で、仲間たちとの未来を、愛する人との約束を、目前で断ち切られた。死の間際、俺は強く願ったのだ。俺の輝きが、俺たちの夢が、ここで終わってたまるか。この想い、この希望よ、未来へ届け。誰かの中で、生き続けてくれ、と。
その途方もない願いが、世界に「青春の残滓」という法則を生み出した。俺の魂は砕け散り、輝きの断片として未来へ託された。だが、その願いはあまりに強すぎた。それは時に、受け継いだ者の未来を縛る呪いとなった。
そして巡り巡って、俺の魂の欠片の一つが、相羽アキという空っぽの器に宿った。俺自身の失われた記憶に引かれ、無意識に他人の記憶、つまりかつての俺がばらまいた「残滓」を集め続ける宿命を背負って。俺が取り込んでいたのは、他人の記憶であると同時に、俺自身の魂の欠片だったのだ。
「……思い、出した」
俺は、完全に色彩を取り戻した写真を見つめる。そこに写る、愛しい人々の顔。俺が失った、しかし確かに存在した「輝かしい青春」の残像。裏には、俺自身の筆跡で『未来への希望』と書かれていた。
カイトは、俺の中で暴れていた「残滓」が消え去り、呆然と立ち尽くしている。俺の身体は、足元から光の粒子となって崩れ始めていた。存在の限界だった。
「アキ……? お前、どうしたんだよ……」
カイトの声が震えている。俺は、最後の力を振り絞って微笑んだ。
「お前には、お前の音楽がある。もう誰かの亡霊に惑わされるな。お前の未来を、生きろ」
俺は、この身に集めた全ての「残滓」――かつての俺が遺した、強すぎる願いの呪いを解放する。それは、友人たちを縛る楔からの解放であり、俺自身の長すぎた旅の終わりだった。
「ヒナタにも、伝えてくれ。……ありがとう、って」
もう、彼女の顔は思い出せない。けれど、胸の奥に残る温もりだけは、本物だった。
身体が完全に光となり、世界から消え去る。誰の記憶にも、記録にも残らず、相羽アキという存在は、はじめからいなかったことになる。だが、それでいい。俺の魂は、呪いではなく、真の祝福として、もう一度世界に還るのだから。
新しい世代の子供たちの中に宿る、「未来への限りない可能性」という、新たな「青春の残滓」として。
数年後。
カイトは、シーンを代表するギタリストになっていた。彼の作る曲は、どこか切なく、それでいて聴く者の胸に力強い希望を灯す、不思議な魅力を持っていた。
ヒナタは、海外で子供たちのための学校を作るという夢を叶えていた。時折、なぜだか分からないけれど、胸の奥が温かくなる瞬間があると、彼女は友人に語っていた。
二人とも、相羽アキという少年がいたことを、もう覚えていない。彼と過ごした日々の記憶は、綺麗に抜け落ちていた。けれど、彼らの心には、失われたはずの思い出の代わりに、理由の分からない「未来への確かな希望」が、暖かく灯っていた。
ある晴れた日の午後。カイトは新曲の構想を練るために、海辺の町を訪れていた。ふと空を見上げると、白い灯台が夕暮れの光を浴びて、静かに佇んでいる。
どこかで見たことがあるような光景だった。
一度も来たことがないはずなのに、どうしようもなく懐かしい。
まるで、ずっと昔に忘れてしまった、大切な誰かとの約束の場所のような気がした。
「……いい曲ができそうだ」
カイトは小さく呟くと、潮風に吹かれながら、新しいメロディを口ずさみ始めた。その旋律は、空に溶けていく残光のように、優しく世界を包み込んでいた。