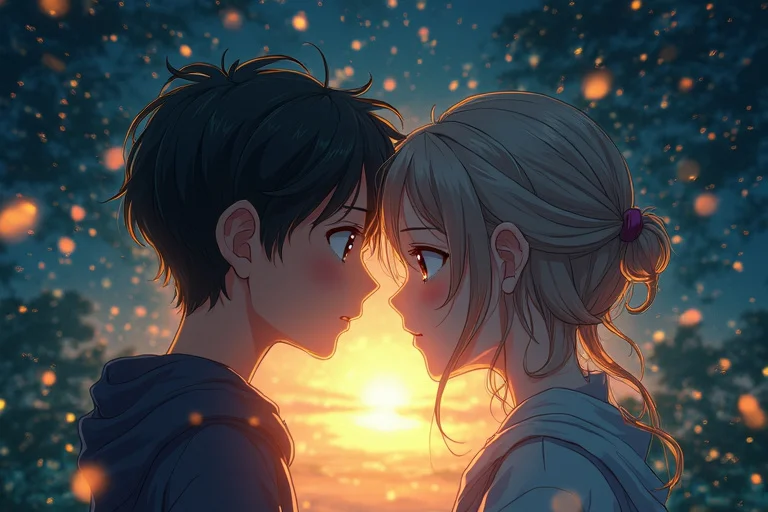第一章 クリスタルの不協和音
僕、水島湊の世界は、音で飽和している。だが、君たちが知る音とは少し違う。僕にとって、人の声はすべて、大きさも音色も異なる無数の風鈴が鳴り響く音として聞こえるのだ。
教室は、その最たる地獄だった。教師の退屈な説明は、錆びついた鉄の風鈴が単調に揺れる音。クラスメイトたちのひそひそ話は、ガラスの破片がぶつかり合うような甲高い音。喧騒は、不協和音の嵐となって僕の鼓膜を絶え間なく打ちつける。だから僕は、いつもノイズキャンセリングヘッドフォンで耳を塞ぎ、自分だけの静寂な繭に閉じこもっていた。他人に興味はない。彼らの声が奏でる耳障りな音から、ただ逃れたかった。
高校二年の初夏。その日も、僕は窓際の席でヘッドフォンをつけ、流れてくるノイズミュージックの洪水に身を委ねていた。世界との間に分厚い壁を築き、その内側で安堵する。それが僕の日常だった。
担任が、気の抜けた風鈴の音で何かを告げた。新しいクラスメイト。興味など湧くはずもなかった。どうせまた一つ、不快な音源が増えるだけだ。僕は目を閉じたまま、やり過ごそうとした。
「夏川陽菜(なつかわひな)です。よろしくお願いします」
その瞬間、僕の世界は一変した。
ノイズミュージックの壁を突き破り、鼓膜を震わせたのは、風鈴の音ではなかった。それは、澄み切ったクリスタルを指で弾いたような、一つの完成された旋律。清らかで、どこか懐かしい、短いピアノのアルペジオのようなメロディーだった。
僕は思わず顔を上げ、ヘッドフォンを首にずらした。教壇に立つ少女と、目が合った。色素の薄い髪が、窓から差し込む光を吸い込んで柔らかく輝いている。彼女は小さく微笑むと、もう一度、何かを言った。その声もまた、僕が生まれて初めて聞く、美しい音楽となって鼓膜に届いた。
心臓が、これまで感じたことのないリズムで高鳴る。教室を満たしていたはずの耳障りな風鈴の音はすべて消え去り、ただ彼女の奏でるメロディーだけが、僕の世界を満たしていた。生まれて初めて、僕は誰かの「声」をもっと聞いてみたいと、心の底から願ったのだ。
第二章 消えゆく音のスケッチ
夏川陽菜は、僕の静寂な繭をいとも簡単に破ってみせた。彼女は、僕がヘッドフォンで世界を拒絶していることなど意にも介さず、屈託のないメロディーで話しかけてきた。
「水島くん、いつも何を聴いてるの?」
昼休み、弁当を広げた彼女が、前の席からくるりと振り返って尋ねる。彼女の声は、春の小川のせせらぎにも似た、穏やかで優しい旋律を奏でていた。僕はどぎまぎしながらヘッドフォンを外し、どもるように答える。
「……ノイズ、ミュージック」
「へえ、ノイズ!面白そう。今度聞かせてよ」
彼女は、僕が他者との間に築いた壁を、壁として認識していないようだった。その天真爛漫さに、僕は戸惑いながらも、抗いがたい力で惹きつけられていった。彼女と話す時間は、僕にとって唯一、世界が美しい音で満たされる瞬間だった。
陽菜はいつも、首から古びたフィルムカメラをぶら下げていた。彼女はよく、誰も気に留めないような風景にレンズを向けては、シャッターを切った。錆びたブランコ、夕暮れの電線、水たまりに映る空。
「何を撮ってるの?」と一度尋ねたことがある。
彼女はファインダーから目を離さずに、こう答えた。その声は、少しだけ切ない短調のメロディーだった。
「消えゆく音を、撮ってるの」
「音を? 写真に?」
「うん。音は、鳴った瞬間に消えちゃうでしょ。だから、その音が鳴っていた景色の記憶を、形に残しておくの。私だけのやり方でね」
僕にはその言葉の真意が掴めなかった。けれど、彼女のその独特な感性が、僕にはとても魅力的に思えた。僕が拒絶してきた「音」を、彼女は慈しんでいる。その事実が、僕の心を揺さぶった。
僕たちは、放課後を共に過ごすことが増えた。図書室の古い木の匂い、夕暮れのグラウンドを駆ける足音、遠くで鳴る踏切の警報音。これまでただの雑音だったそれらの音も、陽菜の奏でるメロディーと共にあると、不思議と一つのハーモニーのように感じられた。
僕は変わり始めていた。ヘッドフォンを外している時間が、少しずつ増えていった。世界はまだ不協和音に満ちていたけれど、その中にたった一つ、完璧な旋律が存在することを知ってしまったから。僕はこの奇跡のような体質のことを、いつか彼女に打ち明けようと心に決めていた。君の声だけが、僕にとっての音楽なのだと。
第三章 レクイエムの告白
夏休みが目前に迫った、蒸し暑い日の放課後だった。僕たちは、丘の上にある閉鎖された古い天文台へ向かっていた。陽菜が、満天の星の下で「宇宙の音」を聞いてみたい、と言い出したからだ。
蝉時雨が、無数の小さな真鍮の風鈴が乱れ打つように降り注ぐ。汗が首筋を伝うのを感じながら、僕は意を決して口を開いた。
「夏川さん。僕、言わなきゃいけないことがあるんだ」
僕の声はきっと、ひどく強張った、歪なガラスの風鈴の音だっただろう。陽菜は歩みを止め、不思議そうな顔で僕を見つめた。彼女の眼差しは、静かな湖のような旋律をしていた。
「僕には、人の声が……全部、風鈴の音みたいに聞こえるんだ。みんな違う音色で、教室とかにいると、うるさくて頭がおかしくなりそうになる。だから、いつもヘッドフォンをしてた」
陽菜は黙って僕の言葉を聞いていた。僕は続ける。心臓が張り裂けそうだった。
「でも、君の声は違った。初めて聞いた時から……風鈴の音じゃなくて、綺麗なメロディーに聞こえたんだ。僕にとって、君の声だけが、音楽なんだ」
告白は、僕のすべてをさらけ出す行為だった。拒絶されるかもしれない。気味悪がられるかもしれない。だが、彼女の奏でるメロディーを前にして、嘘をつき続けることはできなかった。
沈黙が落ちる。蝉の声だけが、やけに大きく響いていた。
やがて、陽菜はゆっくりと口を開いた。彼女が紡いだメロディーは、僕が今まで聞いた中で、最も悲しく、最も美しいものだった。それはまるで、鎮魂歌(レクイエム)のようだった。
「そっか……。水島くんには、そう聞こえてたんだね」
彼女は、驚いていなかった。ただ、泣き出しそうな顔で、優しく微笑んでいた。
「嬉しいな。私の声、音楽だったんだ」
そして、彼女は僕の価値観を根底から破壊する事実を告げた。
「私ね、もうすぐ声が出なくなるの」
「……え?」
「進行性の病気で、声帯が少しずつ機能しなくなっていくんだって。話せば話すほど、声は擦り切れて、最後には、全く音が出なくなるの」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。彼女がいつも持ち歩いていたカメラ。消えゆく音を撮る、と言っていた言葉の意味が、稲妻のように脳を貫いた。
「だから、写真を撮ってたの。いつか私が失くしてしまう『声』っていう音の記憶を、景色と一緒に閉じ込めておきたくて。私が話した場所、笑った場所。その全部が、私の声の墓標になる」
僕が美しいと感じていた、あのクリスタルのように澄んだメロディー。それは、陽菜の残り少ない「声の命」が燃え尽きる瞬間に放つ、儚くも鮮烈な輝きそのものだったのだ。僕は、彼女の命が削れていく音を、ただ美しい音楽として享受していた。喜びと、耐えがたいほどの罪悪感が、僕の中で渦を巻いた。
夕焼けが、天文台の白いドームを燃えるようなオレンジ色に染めていた。僕は、何も言えなかった。世界から、すべての音が消え失せたように感じられた。
第四章 君が残した、音のないメロディー
あの日を境に、僕の世界は再び変わった。だが、以前のように音を拒絶する方向ではなかった。僕は、ヘッドフォンを捨てることを決めた。
陽菜の残り少ない声。その一音たりとも、聞き逃したくはなかった。彼女の命が奏でるレクイエムを、この耳と心に、永遠に刻みつけるために。教室の喧騒も、街の雑踏も、もはや苦痛ではなかった。それら全ての不協和音は、陽菜のメロディーが存在する世界を構成する、一つの背景音楽に過ぎなかった。
僕は、生まれて初めて音楽を作ろうと決めた。陽菜の声のメロディーを、五線譜の上に書き起こし始めたのだ。彼女が笑う時の軽やかな旋律を。僕の名前を呼ぶ時の、少しはにかんだような優しい旋律を。悲しい事実を告げたあの日の、胸が締め付けられるような旋律を。
それは、彼女の「声」を永遠にするための、僕なりの闘いだった。
陽菜の声は、日を追うごとに、かすれていった。澄んだクリスタルの音色は次第に曇りガラスのようになり、旋律は途切れがちになった。それでも彼女は、僕が書き上げた楽譜を見て、最後の力を振り絞るように、そのメロディーを口ずさんでくれた。それは、僕の人生で最も尊い演奏会だった。
季節は巡り、冬が訪れた。陽菜は、ついに完全に声を失った。
僕たちは、鉛色の空の下、静まり返った冬の海辺にいた。打ち寄せる波の音だけが、低く響いている。
陽菜は僕の隣に座り、小さなスケッチブックに何かを書くと、僕に見せた。
『私の声、まだ聞こえる?』
僕は、ポケットからポータブルプレイヤーを取り出し、イヤホンを片方ずつ分け合った。再生ボタンを押すと、スピーカーから音楽が流れ出す。僕が、彼女の声を元に作り上げた曲だった。ピアノとストリングスが、あの夏に聞いた、切なくも美しいレクイエムを奏でる。
僕は黙って頷き、目を閉じた。
もう、僕の耳に彼女のメロディーは聞こえない。けれど、僕の心の中では、今も陽菜の澄み切った声が、決して色褪せることなく響き続けていた。それはもはや、聴覚が捉える物理的な音ではない。僕の魂そのものに刻み込まれた、永遠の音楽となっていた。
陽菜が、そっと僕の肩に頭を預けてくる。その温かさが、言葉よりも雄弁に、彼女の想いを伝えていた。
かつて音のない世界を求めた僕は、今、音のない少女の隣で、世界で最も美しいメロディーを聴いている。君が僕に残してくれた、この音のないメロディーと共に、僕はこれからも生きていく。