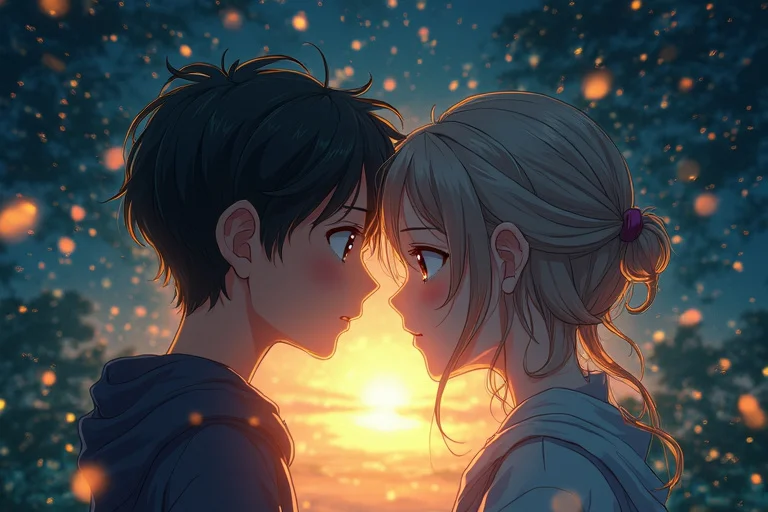第一章 濁った結晶と虹色の嘘
水瀬蒼が目を覚ますと、枕元にはいつものように、小さな石ころが一つ転がっていた。昨夜、眠りに落ちる寸前に、瞼の裏からぽろりと零れ落ちたものだ。それは『思い出の結晶』と呼ばれ、この世界では誰もが経験した出来事を、眠りと共に物理的な形として排出する。
蒼の結晶は、いつも決まってビー玉ほどの大きさで、色は鈍い乳白色だった。光を当てても、ぼんやりと反射するだけ。何の変哲もない、退屈な高校二年生である自分自身を体現しているようで、蒼は毎朝それを引き出しの奥にしまい込むのが習慣になっていた。
リビングに下りると、テレビのワイドショーが「最新結晶トレンド!」と題して、若者たちの間で流行している結晶交換会の様子を特集していた。画面には、ダイヤモンドのように煌めく結晶、夕焼けを閉じ込めたようなグラデーションの結晶、深海のような静かな青を湛えた結晶を手に、満面の笑みを浮かべる少年少女たちが映し出される。彼らの青春は、その結晶の輝きによって証明されているかのようだった。
「蒼の結晶は、最近どんな感じ?」
朝食のトーストをかじりながら、母が何気なく尋ねる。蒼は「別に、いつもと一緒だよ」と素っ気なく答えた。母の枕元には、時折、夫である父とのささやかな思い出が、真珠のような優しい光を放つ結晶となって生まれることを蒼は知っていた。それに比べて、自分の結晶はあまりにも無価値に思えた。
学校は、さながら結晶の見本市だった。教室のあちこちで、生徒たちが昨夜生まれたばかりの結晶を見せびらかし合っている。
「見てこれ! 昨日、彼と水族館に行った時の! イルカの形してるんだ!」
そんな歓声の中心にいるのは、たいてい幼馴染の陽奈だった。彼女の机の上には、太陽の光を浴びて虹色に輝く、複雑なカットが施された宝石のような結晶が置かれていた。明るい髪、整った顔立ち、誰にでも気さくな性格。陽奈のすべてが、その結晶のようにキラキラして見えた。
「蒼は? 何かいいの生まれた?」
陽奈が無邪気に笑いかけてくる。蒼はポケットに手を入れたまま、「ううん、別に。相変わらず石ころだよ」と曖昧に笑った。憧れと、どす黒い嫉妬が胸の中で渦を巻く。陽奈のようになりたい。あんな輝かしい青春の証が欲しい。そんな渇望が、蒼の心をじりじりと焦がしていた。
その日の午後、教室に一人の転校生が紹介された。黒髪が印象的な、どこか影のある少年。名を、桐谷海斗という。彼の登場に教室は少しざわついたが、蒼が何より驚いたのは、自己紹介を終えて席に着いた彼の机の上に、結晶を飾るための小さなトレイが置かれていないことだった。この世界では、それはあり得ないことだった。自分の思い出をひけらかす気が無い、という意思表示か、あるいは――。
蒼は、窓の外の灰色の空と、何も持たない彼の空っぽの机を、ただぼんと見比べていた。
第二章 模造の輝きと空っぽの彼
輝く結晶が欲しい。その思いは日に日に蒼の中で膨れ上がり、やがて危険な好奇心へと姿を変えた。インターネットの匿名掲示板で、『イミテーション・ジェム』という言葉を見つけたのは、そんな時だった。それは、特殊な樹脂と染料を使い、本物そっくりの思い出の結晶を人工的に作り出す、裏社会の技術だった。
『退屈な日常に、輝きを。誰にもバレない、完璧な思い出をあなたの手に』
サイトの謳い文句は、悪魔の囁きのように甘く響いた。数日悩んだ末、蒼は震える指で注文ボタンをクリックした。数日後、自宅に届いた小さな箱には、精巧な制作キットと、様々な色の染料が入っていた。罪悪感はあった。しかし、それ以上に、偽物でもいいから輝きを手に入れたいという欲求が勝っていた。
蒼は、陽奈が自慢していた虹色の結晶を思い出しながら、慎重に染料を混ぜ、樹脂に流し込んだ。硬化ライトを当てると、手のひらの上で、信じられないほど美しい、七色に輝く結晶が生まれた。それは、あまりにも完璧な『偽物』だった。
翌日、蒼はおずおずと偽の結晶を学校に持っていった。
「見て、これ…昨日、たまたま…」
陽奈に差し出すと、彼女は目を丸くした。
「すごい! 蒼、こんな綺麗な結晶、初めて見た! 何があったの!?」
「えっと…夕焼けが、すごく綺麗で…」
しどろもどろになりながら嘘をつくと、陽奈は「そっかぁ、よかったね!」と自分のことのように喜んでくれた。友人たちが「すごいじゃん、水瀬!」と集まってくる。初めて向けられる称賛の視線に、蒼の胸は高鳴った。しかし、その高揚感の奥底で、冷たい何かが心を蝕んでいくのを感じていた。偽りの輝きで得た賞賛は、どこまでも空虚だった。
それから、蒼は海斗のことが妙に気になり始めた。彼は誰とも深く関わろうとせず、休み時間になるといつも一人で屋上へ向かう。ある放課後、蒼はこっそりと彼の後をつけた。フェンス際で、海斗は地面に視線を落とし、何かを必死に探していた。その横顔は、蒼が今まで見たことがないほど切実だった。
「何か、探し物?」
思わず声をかけると、海斗は驚いたように振り返った。
「…別に」
彼は短く答えると、すぐに踵を返そうとする。
「桐谷くんは、結晶、生まれないの?」
蒼の問いに、彼の足がぴたりと止まった。彼はゆっくりと振り返り、蒼を真っ直ぐに見つめた。その瞳は、何も映していないガラス玉のように冷ややかに見えた。
「…生まれないんじゃない。生まないようにしてるんだ」
そう言って、彼は今度こそ屋上を去っていった。その言葉の意味が分からず、蒼はその場に立ち尽くすしかなかった。彼の空っぽの机と、「生まない」という言葉が、蒼の心に重くのしかかった。
第三章 砕けたプリズム
事件が起きたのは、梅雨入り間近の、湿った空気が街を包む金曜日の放課後だった。陽奈が交差点で車にはねられた、という報せがクラスのグループチャットを駆け巡った。蒼は血の気が引くのを感じながら、病院へと走った。
幸い命に別状はなかったが、頭を強く打って意識が戻らないという。蒼が病室に入ると、陽奈の母親が泣き崩れていた。ベッドの傍らのサイドテーブルには、事故の衝撃で陽奈のカバンから散らばったのだろう、たくさんの『思い出の結晶』が無造作に置かれていた。
その中に、蒼が見慣れた虹色の結晶があった。しかし、よく見ると、そのいくつかは角が欠け、そこから中の構造が剥き出しになっていた。それは、天然の鉱物のような複雑な構造ではなく、均一なプラスチックのような断面だった。
「これって…」
蒼は息を呑んだ。それは、自分が作った偽物と全く同じ質感だったのだ。テーブルの上の、息を呑むほど美しかった結晶のほとんどが、精巧に作られたイミテーションだった。
憧れていた陽奈の輝き。誰もが羨む彼女の青春の証。そのほとんどが、偽物だった。彼女もまた、自分と同じように、現実の自分と理想のギャップに悩み、偽りの輝きで武装していたのだ。いつも笑顔で、自信に満ち溢れているように見えた陽奈の、脆く必死な素顔が、砕けた結晶の破片と共に蒼の胸に突き刺さった。どうして気づかなかったんだろう。一番近くにいたのに。
呆然と病室を出た蒼の前に、海斗が立っていた。彼も報せを聞いて駆けつけたらしい。
「水瀬…」
「桐谷くん…陽奈の結晶、ほとんど偽物だった…」
蒼がかすれた声で言うと、海斗は静かに目を伏せた。
「…やっぱりな」
「どういうこと?」
「あいつ、時々、無理してるって顔するから」
そして、海斗はぽつりぽつりと自分の過去を語り始めた。彼が以前住んでいた町には、親友がいたこと。その親友は、誰よりも美しい結晶を生み出すことに執着し、完璧な思い出を作るために自分を追い詰め、やがて心を病んでしまったこと。そして、ある日、自ら命を絶ってしまったこと。
「あいつが最後に残した結晶は、今までで一番大きくて、綺麗だった。でも、それは空っぽの輝きだったんだ」
海斗の声は震えていた。
「俺は、思い出を作るのが怖くなった。何かを感じて、それが結晶になるのが。だから、心を閉ざした。何も感じなければ、結晶は生まれない。それが、俺なりの罰なんだ」
彼が屋上で探していたのは、その親友と最後に交わした、ささやかで、けれど本物の思い出の結晶だったという。失くしてしまった、たった一つの宝物。
陽奈の嘘。海斗の過去。二つの真実が、蒼の中で音を立てて崩れ落ちた。自分たちが追い求めていた輝きとは、一体何だったのだろう。結晶の美しさで人の価値が決まるかのようなこの世界で、自分たちは大切な何かを見失っていた。
第四章 夜明け色のカケラ
自分の病室に戻った蒼は、引き出しの奥から、今まで作った偽物の結晶と、自分が生み出してきた鈍い乳白色の結晶を全て取り出した。偽物は、相変わらずきらびやかに輝いている。しかし、今の蒼には、それがひどく空々しく、醜いものに思えた。蒼は、ためらうことなく偽物の結晶をゴミ箱に捨てた。
数日後、陽奈が意識を取り戻した。蒼は一番に彼女の病室を訪れた。
「ごめん…ずっと、嘘ついてて」
陽奈は、泣きながら謝った。周りの期待に応えなければというプレッシャーに、ずっと押しつぶされそうだったのだと。
「私も、ごめん。陽奈のこと、羨ましくて、嫉妬してた。陽奈の気持ちも知らないで…私も、偽物の結晶、作ってたんだ」
二人は、初めて本当の自分をさらけ出した。飾り気のない言葉で、泣いて、笑って、許し合った。それは、決して虹色に輝くようなドラマティックな瞬間ではなかった。けれど、蒼の心には、じんわりと温かいものが広がっていった。
その翌朝。蒼が目を覚ますと、枕元に小さな結晶が生まれていた。それは今までで一番小さく、形もいびつだった。しかし、色は違った。濁った白ではなく、夜が明ける直前の、淡い紫とオレンジが混じり合ったような、不思議な色をしていた。そっと手に取ると、内側から、確かな温もりが伝わってきた。陽奈との和解。それは誰かに見せるためのものではない、自分だけの、本物の思い出の証だった。
蒼は、その小さな結晶を握りしめて屋上へ向かった。海斗が、いつものようにフェンスの近くで地面を見ていた。
「桐谷くん」
蒼が声をかけると、彼はゆっくりと顔を上げた。
「これ、見て」
蒼が手のひらを開くと、夜明け色のカケラが、朝の光を浴びて優しく輝いた。
「綺麗だね」
海斗が、初めて穏やかに微笑んだ。
「うん。…一緒に探してもいい? 君の宝物」
「…でも、見つからないかもしれない」
「いいよ、別に。見つからなくても」
蒼は笑って言った。
「こうして、一緒に探してる今が、また新しい思い出になるんだから」
その言葉に、海斗は少しだけ目を見開いた。そして、諦めたように小さく息を吐き、隣に並んだ蒼と共に、再び地面に視線を落とし始めた。
結局、その日、海斗の結晶が見つかることはなかった。けれど、二人の間に流れる空気は、もう冷たくも空虚でもなかった。蒼は、自分の手のひらの中にある、不格好だけれど温かい光を放つ結晶をそっと見つめた。青春の輝きとは、誰かと比べて優劣をつけるものではない。傷ついたり、間違えたりしながらも、不器用に積み重ねていく、名もなき時間そのものなのかもしれない。
見上げた空は、いつもと同じ、何の変哲もない青空だった。しかし、蒼の目には、その青が昨日までとは少しだけ違って、どこまでも澄み渡って見えた。