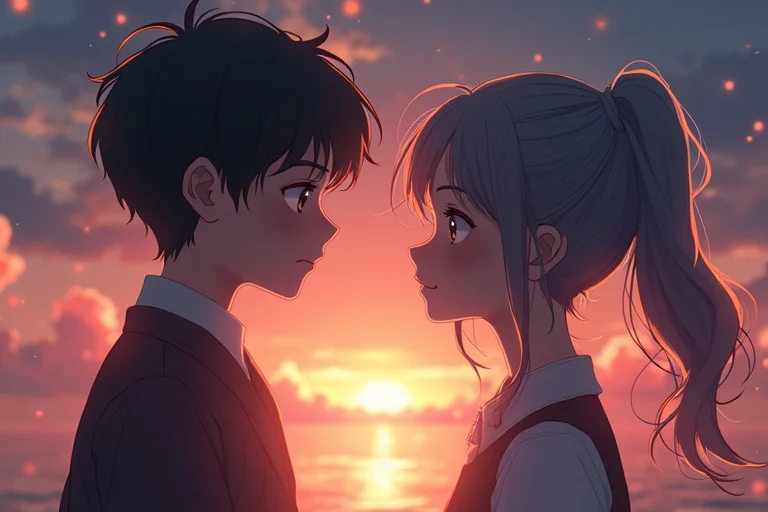第一章 青い残像
僕、水島湊には秘密がある。他人の強い感情が残した「残滓」を、色と香りとして感じ取ってしまうのだ。それは共感覚の一種らしいが、僕にとっては呪いに近かった。怒りは焦げ付くような赤錆色と金属の匂い。喜びは弾けるレモンイエローと砂糖菓子のような甘ったるい香り。人の感情が渦巻く教室は、様々な色と匂いが混ざり合う不協和音の世界で、僕はいつも耳を塞ぐように心を閉ざしていた。他人と深く関われば、その生々しい感情の濁流に飲み込まれてしまう。だから、僕は誰とも一定以上の距離を保ち、透明な壁の内側で息を潜めるように生きてきた。
そんな僕の日常に、小さな波紋が生まれたのは、高校二年の初夏のことだった。
放課後、誰も寄り付かない旧音楽室の前を通りかかった時、ふと足を止めた。鍵がかけられ、窓には埃が積もったその部屋の中から、今まで感じたことのない不思議な「残滓」が漏れ出ていたのだ。
それは、どこまでも澄み切ったウルトラマリンブルーの色をしていた。そして、雨が上がったばかりの森の土のような、懐かしくて切ない香りがした。それは誰かの悲しみでも怒りでもなく、かといって単純な喜びでもない。もっと複雑で、純粋な何か。まるで、大切に磨き上げた宝石を、そっと宝箱にしまったまま、二度と開けられなくなってしまった人の「果たされなかった夢」そのもののような感覚だった。
僕はその青い残滓に、どうしようもなく心を奪われた。これまで避けてきたはずの他人の感情の痕跡が、僕を内側から強く揺さぶる。この色の正体は何なのか。この香りは、誰がここに残していったのか。
その日から、僕の退屈だった灰色の日常は、旧音楽室から漏れ出す青い残像を追いかける、秘密の探求へと静かに色を変え始めた。
第二章 灰色の静寂
青い残滓の主に繋がる手がかりは、すぐに見つかった。同級生の早川栞。いつも物静かで、休み時間も一人で分厚い本を読んでいる図書委員の彼女が、頻繁に旧音楽室の近くの窓辺に佇んでいるのを見かけるようになったからだ。
彼女の周囲には、いつも淡いグレーの色が漂っていた。それは感情の欠如、あるいは完全な静寂を示す色。香りもほとんどしない。まるで、彼女の世界だけが音を消されたサイレント映画のようだった。僕は彼女に興味を抱き、自らも図書委員に立候補した。カウンターで隣り合って作業をするようになっても、彼女は必要最低限のことしか話さなかった。
「水島くんは、どうして図書委員に?」
ある日、彼女の方から珍しく話しかけてきた。返却された本にスタンプを押す、リズミカルな音だけが響く静かな図書室。
「……静かな場所が好きだから、かな。早川さんは?」
僕が問い返すと、彼女は少しだけ目を伏せ、本の背表紙を指でなぞった。
「私も、同じ」
その時の彼女からは、やはり灰色の残滓しか感じなかった。しかし、彼女がふと窓の外、旧音楽室のある方角に目を向けた一瞬、その灰色のオーラの縁が、微かにあのウルトラマリンブルーに揺らめいたのを、僕は見逃さなかった。
彼女の中に、あの青は確かに存在している。だが、分厚い灰色の壁に閉ざされている。僕はもどかしさを感じながらも、焦らずに彼女との距離を縮めていった。他愛ない会話を重ね、時々、彼女が小さく笑うようになった。その笑顔は、曇り空から一瞬だけ陽が差すように儚く、そして僕の心を温めた。
しかし、核心に触れることはできなかった。音楽の話題を振ると、彼女は決まって口を閉ざし、その瞳には再び深い静寂が戻ってくる。彼女が纏う灰色の壁は、僕が思っているよりもずっと高く、厚いようだった。僕は、ただ彼女の隣で、その静寂に寄り添うことしかできなかった。彼女の心の扉を叩く勇気も、資格も、僕にはまだなかったのだ。
第三章 不協和音の真実
転機は、図書室の閉架書庫の整理をしている時に訪れた。古い蔵書の中に、一冊の音楽雑誌が紛れ込んでいたのだ。一年ほど前のその雑誌を何気なくめくった僕の手が、あるページで凍り付いた。
『期待の新星、ピアニスト早川栞。コンクール目前に不慮の事故』
そこには、今よりも少し幼い、しかし紛れもない彼女が、グランドピアノの前で誇らしげに微笑んでいる写真が掲載されていた。記事には、彼女の類稀な才能と、将来を嘱望されていた矢先の悲劇が綴られていた。交通事故で、ピアニストにとって命とも言える左手の神経を損傷した、と。
全てのピースが、音を立ててはまった。旧音楽室の青い残滓。音楽の話を避ける彼女。感情を押し殺したような灰色の静寂。
僕は雑誌を手に、旧音楽室へ走った。用務員さんに頼み込んで鍵を開けてもらい、埃っぽい部屋に足を踏み入れる。部屋の中央には、白い布を被ったグランドピアノが静かに佇んでいた。そして、部屋全体が、あの澄んだ青い残滓で満たされていた。特に、ピアノの鍵盤の上には、インクを零したように色濃く、その想いが染み付いていた。
僕はピアノの椅子に置かれていた一冊の楽譜に気づいた。それは手書きで、まだ完成していないピアノ曲だった。その五線譜を指でなぞった瞬間、これまでで最も強く、鮮烈な青と、雨上がりの土の香りが僕の全身を駆け巡った。切なさ、情熱、そして深い、深い絶望。感情の奔流に、僕は立っていられなくなりそうだった。
その時、背後で息を呑む音がした。振り返ると、栞が入口に立ち尽くしていた。その顔は青ざめ、信じられないものを見るように僕と楽譜を交互に見つめている。
「どうして……それを……」
彼女の声は震えていた。
僕は言葉に詰まりながら、手にしていた雑誌を見せた。彼女の瞳が大きく見開かれ、次の瞬間、堰を切ったように感情が溢れ出した。彼女を包んでいた灰色の壁が粉々に砕け散り、凄まじい量のウルトラマリンブルーが奔流となって僕に襲いかかった。それは悲しみと、怒りと、音楽への捨てきれない愛情が混じり合った、あまりにも痛々しい魂の叫びだった。
「もう、弾けないの!」
彼女は泣きじゃくりながら、震える左手を見つめた。
「この指はもう、昔みたいに動いてくれない……! でも、頭の中ではずっと音が鳴ってる! 音楽が、私の中から消えてくれないの! 苦しいのよ!」
僕は、彼女の絶望の奔流にただ打ちのめされていた。厄介なだけだと思っていた僕の能力。だが、今、この瞬間、僕は誰よりも深く、彼女の言葉にならない痛みを理解していた。他人の感情から逃げ続けてきた僕が、初めて、その濁流の中心に飛び込んででも、目の前の人間を救いたいと、心の底から思った。それは僕自身の内側で起きた、静かだが決定的な革命だった。
第四章 ふたりのソナタ
僕は一歩踏み出し、泣き崩れる彼女の前に屈んだ。
「僕が、君の左手になる」
栞が顔を上げる。その瞳は涙で濡れ、戸惑いに揺れていた。
「僕にピアノは弾けない。でも、君が頭の中で鳴らしている音楽を感じることはできる。だから、教えてほしい。君が紡ぎたいメロディを、僕に。僕がそれを楽譜にする」
それは、あまりにも突拍子もない提案だったかもしれない。だが、僕の言葉から嘘や同情の色が一切感じられなかったのだろう。栞はしばらく僕をじっと見つめた後、小さく、しかし確かに頷いた。
その日から、僕たちの秘密の放課後が始まった。誰もいない旧音楽室で、栞はピアノの前に座り、途切れ途切れにメロディを口ずさむ。時には右手指一本で、おぼつかない音を奏でる。彼女の心象風景が、鮮やかな青い残滓となって僕に流れ込んでくる。僕はその色と香りを頼りに、五線譜の上に音符を書き留めていく。それは、他人の心の中にある音楽を採譜するという、奇妙で、そして信じられないほど親密な共同作業だった。
最初はぎこちなかったセッションも、次第に呼吸が合っていく。栞が思い描く複雑な和音を、僕が正確に捉え、楽譜に落とし込む。彼女の絶望の色だったウルトラマリンブルーは、僕たちの共同作業の中で、少しずつその色合いを変えていった。悲しみの中に希望の光が差し、情熱の赤が混じり合う。僕たちの時間は、まさに二人で一つの曲を奏でるソナタのようだった。
そして、文化祭の日。僕たちは、完成した『残響のソノリティ』と名付けた曲を、ピアノが得意なクラスメイトに託した。
体育館の舞台袖で、僕と栞は肩を並べて、その演奏を聴いていた。スピーカーから流れ出したのは、切なくも力強い、美しいメロディ。それは、栞が失ったものへの哀歌であり、同時に、未来への序曲でもあった。
演奏が終わった瞬間、満場の拍手が鳴り響く。僕は隣にいる栞を見た。彼女の体から溢れ出ていたのは、もはや絶望の青ではなかった。それは、夜が明け、水平線から太陽が昇る瞬間の空のような、希望に満ちた淡い水色だった。そして、今まで感じたことのない、柔らかく、温かい香りがした。彼女は泣きながら、最高に美しく笑っていた。
僕たちの関係がこれからどうなるのか、それはまだ分からない。でも、確かなことが一つだけある。僕はもう、自分の能力を呪いだとは思わない。これは、世界の声なき声を聞き、誰かの心に寄り添うための、かけがえのない贈り物なのだと。
旧音楽室には、僕と彼女が生み出した新しい感情の残滓が、優しい光のように、いつまでも静かに満ちていた。