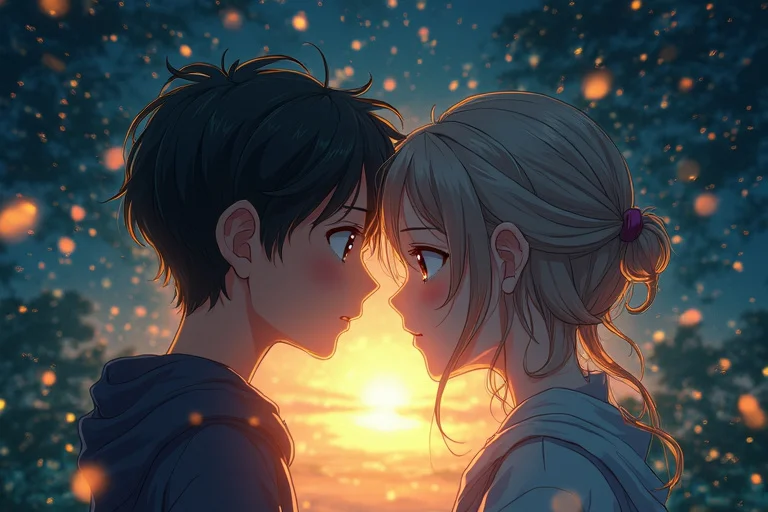第一章 残像の景色
僕の目には、他人の青春が『光の残像』として映る。
友人たちが教室の窓際で他愛ない冗談に笑い合うと、その周囲にシャンパンの泡のような金の粒子が弾け、体育祭のリレーでバトンを落とした先輩の背中からは、錆びた鉄の色をした光が静かに滲み出す。それは祝福であり、呪いでもあった。他人の心の揺らめきが色と形をもって流れ込んでくる世界で、僕はいつも一歩引いた場所にいる観測者だった。
「湊、また見てる」
隣の席の沙希が、ノートの端に猫の落書きをしながら僕を覗き込む。彼女の周りには、向日葵の蜜のような、暖かく快活な光が常に漂っている。僕がこの能力のことを打ち明けている、唯一の相手だ。
「見てるよ。沙希の周りは、今日も賑やかで眩しい」
「ふーん。湊の光は、どんな色してるのかな」
その問いに、僕はいつも答えられない。どれほど胸が高鳴っても、どれほど心が締め付けられても、僕自身の青春だけは、一度たりとも光の残像として視覚化されたことがないのだ。僕の世界は、僕という中心だけがぽっかりと抜け落ちた、奇妙な空洞を抱えていた。
その日の帰り道、古びた歩道橋の上で、僕はそれと初めて遭遇した。夕陽に背を向け、欄干に寄りかかるセーラー服の少女。しかし、その輪郭は陽炎のように揺らぎ、どこか現実感が希薄だった。ふと、彼女の足元から伸びる影の主が、腰の曲がった老婆であることに気づく。老婆が一歩進むと、少女も幻のように一歩進む。あれは、誰かの人生で最も輝いた青春の記憶が実体化した『分身』だ。人々が大人になり、手放したはずの過去の姿。
分身の少女は、何も言わず、ただ真っ直ぐに、街外れの森の方角へと歩いていく。その姿が視界から消えようとした瞬間、ポケットの中に入れていた小さなガラス玉が、微かに、本当に微かに温かくなった気がした。幼い頃から肌身離さず持っている、光を透過させるだけで何も映さない、僕の空虚さを象徴するような、ただのガラス玉だ。その内部に、一瞬だけ、塵のような光の点が瞬いて消えた。
第二章 彷徨う記憶
それ以来、僕は街を彷徨う分身たちを追うようになった。学ラン姿で仲間と肩を組む幻影、初めて手にしたギターを爪弾く若者の姿、恋文を握りしめ俯く少女。彼らは皆、本体である今の主の人生には一切干渉せず、まるで引力に引かれるように、同じ方角へと歩みを進めていた。
彼らが触れた電信柱や公園のベンチには、一瞬だけ過去の風景が滲み出す。セピア色の記憶の染みが、現代の景色に重なっては消えていく。僕はその儚い光景を、息を詰めて見つめた。それは、僕が決して見ることのできない、自分自身の過去の光を探す旅でもあった。
「そんなに気になるの? その……分身ってやつ」
放課後の図書室で、沙希が心配そうに僕の顔を覗き込む。窓から差し込む西日が、彼女の髪を琥珀色に染め、無数の光の残像をきらめかせていた。
「彼らがどこへ向かうのか、知りたいんだ」
「……湊にも、ちゃんとあるよ。私には見えるもん。湊だけの、素敵な光」
彼女の言葉は優しい。だが、その優しさが、僕の内側にある空洞をより一層際立たせるだけだった。僕の青春は、誰からも観測されない透明なフィルムのようなものだ。
分身に近づくたび、ポケットの中のガラス玉は、その存在を主張するかのように微かな熱と光を宿すようになった。それはまるで、遠い同胞の呼び声に応えるような、か細い共鳴だった。
第三章 ガラス玉の囁き
分身たちが目指す先は、街外れにある『光の樹海』と呼ばれる古い森らしかった。古くからの伝承が残り、人々が立ち入ることを禁じている場所。そこに行けば、何かが分かるかもしれない。僕が僕自身の光を見られない理由も、このガラス玉が時折囁くように光る意味も。
期待と同時に、得体の知れない恐怖が胸を占めていた。真実を知ることは、僕が抱えるこの空虚さが、決して埋まることのない決定的な欠落なのだと証明されることかもしれない。
僕はより深く分身たちの世界にのめり込んでいった。彼らの放つ光は、生身の人間のそれとは少し違う。それはすでに完結し、磨き上げられた宝石のような、完璧な輝きだった。喜びも、悲しみも、怒りさえも、全てが美しい結晶となってそこに存在していた。
ガラス玉を握りしめる。分身の群れが通り過ぎる時、玉の内部には銀河のような光の渦が生まれては消える。これはただのガラスじゃない。僕と、あの分身たちと、そして光の樹海を繋ぐ、何らかの鍵なのだと、確信に似た予感がしていた。僕の空っぽの中心で、このガラス玉だけが確かな質量を持って、僕の存在を証明しているようだった。
第四章 沙希の光
その日は、雨が降っていた。
屋根のあるバス停で、僕と沙希は二人きりだった。雨音が世界から他の音を消し去り、僕たちの沈黙がやけに大きく響く。
「湊」
沙希が僕を呼んだ。彼女の声は、雨音に負けないくらい、はっきりと僕の耳に届いた。
「私、湊のことが好き」
瞬間、世界が爆発した。
僕の視界は、これまで見たどんな青春の光よりも強烈で、純粋な輝きの奔流に飲み込まれた。沙希の告白という感情の結晶が、ダイヤモンドダストとなって僕に降り注ぐ。それはあまりに眩しく、あまりに暖かく、そしてあまりに痛かった。
沙希の青春は、僕に向けられていた。僕という存在が、彼女の光を生むきっかけになっていた。なのに。
なのに、僕の中から応える光は、ひとかけらも生まれない。
強すぎる光は、僕の内部にある空虚さの輪郭を、残酷なまでに浮き彫りにした。僕は器ですらない。ただの、光を透過させるだけの、空っぽの空間だ。
「……ごめん」
僕はそれだけを言うのが精一杯だった。沙希の顔を見ることができず、光の嵐から逃げ出すようにバス停を飛び出した。頬を伝うのが雨なのか、それとも別のものなのか、もう分からなかった。
失意の底で、僕は決意した。光の樹海へ行こう。そして、この全ての謎に答えを見つけよう。自分に光がない理由を知るために。たとえそれが、どれほど絶望的な真実であったとしても。
第五章 光の樹海
禁じられた森への入り口には、朽ちかけた注連縄が張られていた。それを跨いだ瞬間、空気が変わった。湿った土と苔の匂いに混じり、どこか甘く、懐かしい香りが鼻腔をくすぐる。
森の奥深くへ進むにつれて、光景は一変した。そこは、数えきれないほどの分身たちが集う、幻想的な場所だった。彼らは木々の間に佇み、あるいは岩に腰掛け、言葉を発することなく静かにそこに在る。一人一人の体から漏れ出る淡い光が、森全体を青白い燐光で満たしていた。まるで、無数の魂が眠りにつくための聖域のようだった。
ざわめきも、囁きもない。ただ、圧倒的な静寂と、凝縮された記憶の気配だけが満ちている。僕は息を呑み、その光景に見入った。ここが、全ての青春が行き着く場所。
森の最も開けた場所、ひときわ強い光を放つ巨大な古木の根元で、分身たちは何かを待つかのように、一つの中心点を取り囲んで円を作っていた。その円の中心は、なぜかぽっかりと空間が空いている。全ての分身たちの視線が、その何もない空間へと注がれていた。まるで、そこにやがて現れる主役を待ち望むように。
第六章 器の目覚め
僕がその円の中心へと、吸い寄せられるように一歩足を踏み出した、その時だった。
全ての分身たちが、一斉に僕の方を向いた。その無数の瞳に敵意はなかった。むしろ、長い旅路の果てにようやく巡り会えた目的地を見つけたような、安堵と慈しみに満ちた眼差しだった。
彼らはゆっくりと、僕に向かって歩み寄ってくる。
ポケットの中で、ガラス玉が心臓のように激しく脈打ち始めた。熱い。焼けるように熱い光が、僕の手のひらから全身へと駆け巡る。
一番近くにいたセーラー服の少女の分身が、そっと僕の腕に触れた。
その瞬間、彼女の身体はきらびやかな光の粒子となって砕け散り、奔流となって僕の身体へと吸い込まれていった。
「――っ!」
流れ込んできたのは、誰かの初恋の甘い痛み。友と笑い合った日の焦げるような高揚感。夢に破れた夜の、インクを零したような絶望。次から次へと、分身たちが僕に触れては光となり、溶けていく。様々な時代の、無数の人々の青春が、記憶が、感情が、僕という空っぽの器を満たしていく。
痛みと歓喜。孤独と共感。後悔と希望。相反する全てが僕の中で渦を巻き、一つに溶け合っていく。
ああ、そうか。
僕は、自分の光が見えなかったんじゃない。
僕自身が、まだ何も入っていない空っぽの『器』だったのだ。世界中に散らばった青春の輝きを集め、新たな青春を創造するための源。その中心に位置する、未完成な『核』だったのだ。
第七章 黎明の観測者
最後の分身が光となって僕に吸収された時、森の燐光は消え、世界は一度、完全な静寂と闇に包まれた。そして、僕の中心で、あのガラス玉が最後の殻を破るように眩い光を放った。それは僕の胸で輝く、新たな核となった。
僕は、初めて『自分自身の青春』を見た。
それは、沙希との思い出のような特定の形を持った光ではなかった。これから生まれるであろう全ての青春を育み、祝福する、地平線の彼方から昇る黎明の光。過去の誰かの記憶ではなく、未来へと繋がる、普遍的でどこまでも優しい輝きだった。
ふと気配を感じて振り返ると、息を切らした沙希がそこに立っていた。彼女は僕の姿を見て、目を見開く。
「湊……?」
彼女の瞳には、僕の周りに満ちる柔らかな光が映っていた。もう、誰か特定の残像ではない。世界そのものを祝福するような、暖かく、穏やかな光が。
僕は沙希に微笑みかけた。もう、僕は孤独な観測者ではない。空っぽの器でもない。
世界に散らばった無数の輝かしい過去を受け止め、それを未来へと繋ぐ源になったのだ。僕の青春は、今、この瞬間から始まる。そして、それは僕一人のものではなく、これから生まれる全ての物語へと続いていく。
僕たちの足元から、光の樹海の夜明けが、静かに始まろうとしていた。