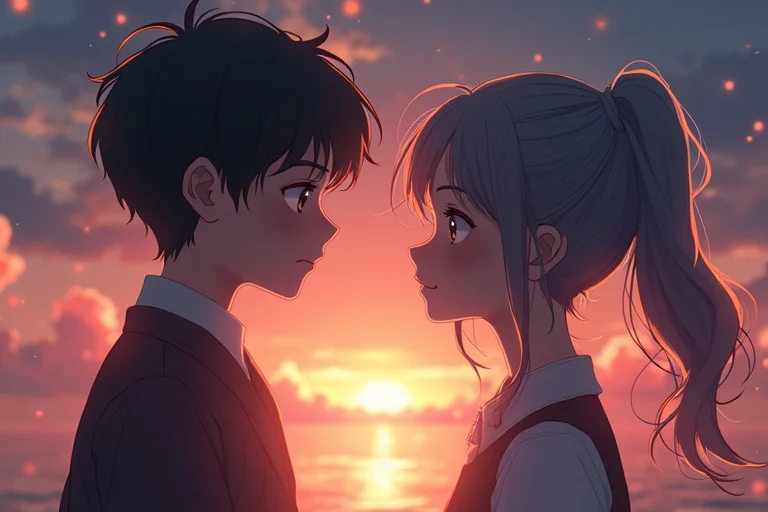第一章 歪んだチャイム
放課後の美術室は、油絵の具の匂いと、西日が差し込む埃のきらめきで満ちていた。僕は、水無月湊(みなづき みなと)。キャンバスに向かうこの瞬間だけが、僕にとって唯一、世界と調和できる時間だった。パレットナイフで混ぜ合わせた群青が、夕暮れの空の色と重なる。夢中だった。心の奥底で何かが昂り、指先が熱を帯びる。その時だ。
キーン、と甲高い音が鳴り響き、終わりのチャイムが空気を震わせた。だが、それは終わらなかった。メロディの最後の音が、まるで引き伸ばされた飴のように長く、長く尾を引く。窓の外に目をやると、羊雲がビデオの早送りのように猛烈な速さで空を横切っていくのが見えた。
「またか……」
胸がどきり、と嫌な音を立てる。僕の感情の昂ぶりが、また周囲の時間を歪ませてしまったのだ。僕の強い感情は「時間振動」として伝播し、半径数メートルの時空を微妙に伸縮させる。制御不能な、思春期の熱病のような厄介な体質だった。
「湊、大丈夫?」
背後からかけられた声に、僕はびくりと肩を揺らした。幼馴染の如月遥(きさらぎ はるか)が、心配そうにこちらを覗き込んでいる。彼女の澄んだ瞳に見つめられると、いつも罪悪感で胸が締め付けられた。
「ああ、なんでもない。ちょっと集中しすぎてただけ」
「そっか。でも最近、学校中で変なこと多いよね。授業が一瞬で終わったとか、掃除の時間が永遠に感じたとか」
遥の言葉に、僕はポケットの中の硬い感触を確かめる。祖父の形見である「刻針の懐中時計」。銀色の蓋を開くと、美しい文字盤の上で秒針は正しく時を刻んでいる。だが、その内部で、微かな歯車の震えが指先に伝わってきた。まるで、この世界全体の不協和音を拾っているかのように。
第二章 感情の季節
この世界には「感情の季節」という言葉がある。人が特定の感情に深く浸る期間を指す言葉で、特に僕らのような若者の「青春の季節」は、最も豊かで、最も不安定だとされている。楽しい時間は一瞬で過ぎ、苦しい時間は永遠に続く。誰もが経験するその主観的な時間の伸縮が、この世界では稀に、物理的な現象として観測されることがあった。僕の体質は、その極端な例なのだろう。
「湊はさ、卒業したらどうするの?やっぱり美大?」
帰り道、夕暮れの商店街を歩きながら、遥が屈託なく尋ねた。彼女はいつも未来を見ている。その眩しさに、僕は目を細めた。
「まだ、決めてない」
僕がそう答えた瞬間、胸に冷たい焦りが広がった。未来を考える資格なんて、僕にあるのだろうか。この能力がある限り、僕は誰かの時間を、世界の時間を、意図せず狂わせてしまうかもしれない。
その時、僕の足元を通り過ぎた猫が、一瞬、陽炎のようにぶれて見えた。道端の自動販売機で遥が買った缶コーヒーから立ち上る湯気が、ふっと一瞬で掻き消える。僕の感情が、また小さな歪みを生んだのだ。
ポケットの中で、懐中時計がカチリ、と微かな音を立てた。僕はそっと取り出して蓋を開ける。秒針が、一ミリほど、確かに逆へ動いたように見えた。
第三章 加速する焦燥
時間の歪みは、僕の周囲だけでなく、世界中で頻発し始めた。テレビのニュースキャスターが深刻な顔で語る。「専門家は、現代社会が抱えるストレスによる一種の集団的時間錯誤ではないかと指摘していますが……」。誰も、そんな解説を信じてはいなかった。
特に異常は、僕らが通う高校で顕著だった。目前に迫った文化祭の準備期間。体感では三日も経ったはずなのに、教室のカレンダーはまだ翌日を指している。廊下を駆け抜ける生徒たちの声には、焦りの色が滲んでいた。
「時間が足りない!」
「このままじゃ青春が終わっちゃう!」
その言葉が、僕の胸に突き刺さる。この現象は、僕の力が暴走した結果なのではないか。僕という存在が、皆の貴重な時間を奪っているのではないか。自己嫌悪が渦を巻き、息が苦しくなる。僕のせいで、皆の「青春の季節」が狂っていく。
僕は美術室に閉じこもる時間が増えた。絵を描くことでしか、この行き場のない感情を処理できなかったからだ。だが、描けば描くほど感情は昂り、窓の外の景色は目まぐるしく明滅を繰り返した。加速していく焦燥感が、更なる歪みを生む悪循環だった。
第四章 逆回りの針
自室で祖父の遺品を整理していた僕は、埃をかぶった木箱の中から、一冊の古い日記を見つけた。祖父は時計職人だった。パラパラとページをめくると、そこには「刻針の懐中時計」についての記述があった。
『この時計は、単に時を計るための道具ではない。持ち主一人の感情ではなく、一つの時代が抱える、大きな感情のうねりを映し出す鏡なのだ。人々の心が未来を渇望すれば針は速く進み、過去を懐かしめば、針は進むことを躊躇う』
日記には、祖父自身の青春時代にも、世界的な時間の歪みがあったことが綴られていた。戦争が終わり、誰もが未来への希望と過去への喪失感で揺れていた時代。
『誰もが終わりを惜しむ時、時間は進むことを躊躇うのかもしれないな』
その一文が、僕の頭を殴りつけた。まさか。この世界の歪みは、僕一人のせいではないのかもしれない。もっと大きな、途方もない何かが原因だとしたら……。
その瞬間だった。ポケットの懐中時計が、これまで感じたことのないほど激しく振動し始めた。まるで心臓のように脈打ち、熱を帯びる。慌てて取り出すと、信じられない光景が目に飛び込んできた。秒針が、分針が、時針が、揃ってゆっくりと逆回転を始めている。
窓の外に目をやる。グラウンドから聞こえていた野球部の掛け声が、古いレコードのように引き伸ばされ、低く響く。空に張り付いた夕焼けは、まるで燃え尽きることを忘れたかのように、その場に留まっていた。世界が、止まろうとしていた。
第五章 セピア色の願い
「湊、見て!街が……」
僕は遥と共に、街を見下ろす丘の上に立っていた。遥の声が震えている。僕らの眼下には、時間が停止した世界の光景が広がっていた。車のヘッドライトは光の筋となって固まり、家々の窓の明かりは瞬きを忘れている。それは恐ろしくも、どこか幻想的な光景だった。
祖父の日記の言葉が、頭の中で反響する。「誰もが終わりを惜しむ時……」。
僕は確信していた。この現象を引き起こしているのは、僕じゃない。
「遥、聞いてくれ」
僕は息を整え、遥に向き合った。
「この時間の歪みは、たぶん……この世界にいる大人たちの、無意識の願いなんだ」
「え……?」
「もう一度、青春を。あの輝いていた季節が終わってほしくない、という強い郷愁。僕らの親の世代、祖父たちの世代……彼らが無意識のうちに抱いている、セピア色の願いが、僕らの時間を巻き戻そうとしているんだ」
若者たちの「時間が足りない」という焦りが、その願いを増幅させる触媒になっていたのだ。終わりを恐れる若者と、終わりを惜しむ大人。二つの巨大な感情が共鳴し、世界の時間を停止させようとしている。
僕のポケットで、懐中時計の逆回転が、さらに速度を増していた。このままでは、僕らの時間は過去へと飲み込まれてしまう。
第六章 明日への秒針
「俺たちが、終わらせなくちゃいけないのかもしれない」
僕の言葉に、遥は黙って頷いた。彼女は何も聞かず、ただ僕を信じてくれていた。
僕は自分の能力を制御しようとするのをやめた。歪みを抑え込むのではなく、受け入れる。そして、新しい感情の波を起こすのだ。
青春の終わりを。その切なさと、寂しさを。だけど、それは絶望じゃない。新しい季節への扉なんだ。
僕は遥の手を、強く握った。彼女の指先が少し冷たい。
「遥と過ごしたこの時間は、確かにあっという間だった。もっと一緒にいたいと思う。でも、終わりが来るから、今日この瞬間が、こんなにも愛おしいんだと思う」
それは、僕の心の底からの、偽りのない感情だった。
「ありがとう、遥。僕の青春は、君がいたから輝いていた」
僕の心に、静かで、しかし力強い波紋が広がった。それは焦りや不安から生まれる歪な振動ではない。受容と感謝から生まれた、調和の波だった。
その感情が世界に伝播していく。
すると、ポケットの中で狂ったように振動していた懐中時計が、すっと静かになった。逆回りしていた針が動きを止め、やがて、カチリ、と小さな音を立てて、ゆっくりと正しい方向へと進み始めた。
空に留まっていた夕日が、穏やかに地平線へと沈んでいく。止まっていた街の時間が再び流れ出し、車のヘッドライトが動き、家々の明かりが温かく瞬き始めた。世界が、息を吹き返したのだ。
僕と遥は、丘の上で夜空を見上げていた。星々が、新しい一日が始まることを告げている。青春はいつか終わる。でも、その記憶は決して消えない。僕らはその光を胸に抱いて、明日へと歩いていくのだ。
ポケットの中の懐中時計は、もう不規則に震えることはなかった。ただ静かに、僕とこの世界の、新しい時間を刻み続けている。この世界の時間は、誰かの切ない想いでできている。僕は、その真実を美しいと思えるようになっていた。