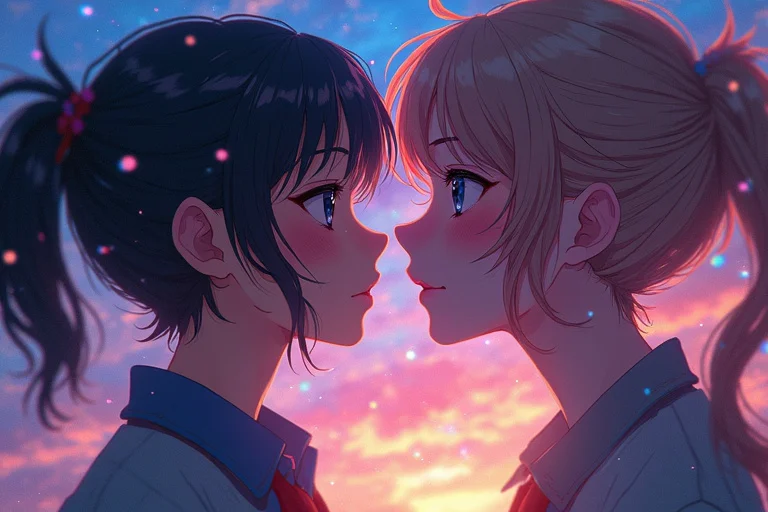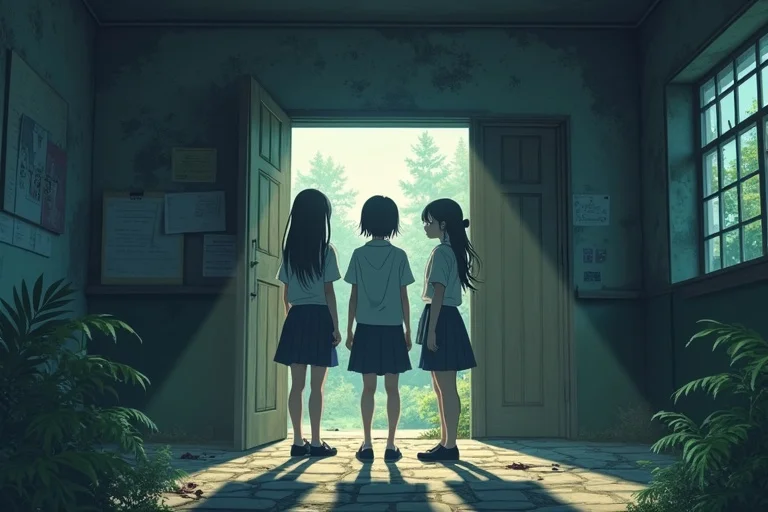第一章 窓辺の不在証明
放課後の美術室は、油絵の具のツンとした匂いと、西陽が落とす長い影で満たされていた。俺、蒼井湊(あおいみなと)にとって、この場所は世界のすべてだった。イーゼルに立てかけたF10号のキャンバスには、誰もいない夕暮れの教室が描かれている。しかし、俺の目には、そこにはっきりと「彼」が見えていた。
窓枠に腰掛け、悪戯っぽく笑う少年。日に透ける柔らかな髪、俺とお揃いの制服。幼馴染のハルだ。現実の教室には、俺の他に誰もいない。だが、俺が筆を走らせるこのキャンバスの中だけが、ハルと再会できる唯一の場所だった。
「湊、また難しい顔してる。そんなんじゃ、良い絵なんて描けないぜ」
声が聞こえる。もちろん、幻聴だ。でも、その声はあまりに鮮明で、鼓膜を優しく震わせる。俺は小さく息をつき、パレットナイフでセルリアンブルーを練った。ハルの瞳の色。彼が愛した、夏の終わりの空の色だ。
「うるさいな。お前のせいだろ。勝手にいなくなったりするから」
口の中でだけ呟く。ハルは、小学校を卒業する直前、理由も告げずに遠くへ引っ越してしまった。手紙も電話も、繋がる術は何一つ残さずに。それ以来、俺の世界から色は少しずつ抜け落ち、代わりに、絵を描くことでしか埋められない空白が生まれた。そして、いつからか、俺が描く風景画の中には、必ずハルが現れるようになったのだ。
「蒼井くん」
背後からの静かな声に、心臓が跳ねた。振り向くと、新任の美術教師、月島先生が立っていた。細身の体に、黒縁の眼鏡。その奥の瞳は、まるで絵画を鑑定するように、俺のキャンバスと俺自身を交互に見つめている。
「……先生」
「熱心だね。良い絵だ。光の捉え方が、とても繊細だ」
月島先生はそう言うと、一歩近づき、キャンバスを覗き込んだ。そして、俺が最も恐れていた質問を、静かな、しかし有無を言わさぬ響きで口にした。
「この窓辺にいる少年は、誰かね? モデルがいるのか?」
空気が凍りついた。先生の指が示す先には、俺だけに見えるはずのハルの姿がある。まさか、先生にも見えているのか? いや、そんなはずはない。先生は、俺が描いた、実在しないはずの少年の輪郭を正確になぞっている。俺の呼吸が浅くなる。パレットを握る手に、じっとりと汗が滲んだ。この絵の中にだけ存在する親友の秘密。俺の青春そのものである聖域が、今、静かに暴かれようとしていた。
第二章 記憶のパレット
月島先生の問いに、俺は結局「昔の友達です」と曖昧に答えることしかできなかった。先生はそれ以上何も聞かず、ただ「そうか」とだけ呟き、俺の肩を軽く叩いて美術室を去っていった。しかし、あの一瞬の出来事は、俺の心に小さな棘のように突き刺さったままだった。
あの日以来、俺はより一層、絵の世界に没入するようになった。現実の人間関係が希薄な俺にとって、絵の中のハルは唯一無二の理解者だった。彼と会話を交わし、思い出の場所を描くことで、俺は孤独を癒していた。
「なあ、湊。覚えてるか? あの灯台だよ」
キャンバスに描いた、海辺に立つ寂れた灯台。俺とハルが、二人だけの秘密基地にしていた場所だ。絵の中で、ハルは防波堤に座り、遠い水平線を見つめている。
「忘れるわけないだろ。あそこで見つけたガラスの浮き玉、まだ持ってるぞ」
俺は机の引き出しから、古びた緑色の浮き玉を取り出した。表面には無数の傷がついている。これも、ハルとの大切な思い出のかけらだ。絵の中のハルが振り向き、眩しそうに目を細める。
「懐かしいな。あの頃は、未来なんて無限に広がってるって信じてたよな」
その言葉が、胸にずしりと響いた。ハルを失った俺の未来は、色褪せたモノクロームの世界だ。だからこそ、俺は過去を描き続ける。鮮やかな色彩に満ちた、ハルがいた日々を。
そんな俺の姿を、クラスメイトの水野さんが時折、遠巻きに眺めていることに気づいていた。彼女は何度か話しかけようとしてくれたが、俺はいつもタイミングを逸し、あるいは意図的に避けてしまっていた。現実の誰かと関係を築くことが、ハルとの繋がりを薄めてしまうような気がして怖かったのだ。
月島先生は、そんな俺の絵を黙って見守っていた。批評も、賛辞も口にしない。ただ、時々、深い思索に沈むような目で、俺のキャンバスを見つめるだけだった。その視線は、まるで俺の心の奥底まで見透かしているようで、俺は落ち着かない気持ちになった。
「蒼井くん」ある日の放課後、先生は唐突に言った。「今度の写生会、どこを描くか決めたかね?」
「……はい。海に行こうと思ってます」
「あの灯台か」
先生の言葉に、俺は息を呑んだ。なぜそれを。俺は一度も、あの灯台の絵を先生に見せたことはない。
「君の絵には、いつも潮の香りがする。そして、決まって同じ空の色が使われている。セルリアンブルー。まるで、誰かの面影を探しているような色だ」
先生の言葉は、的確に俺の核心を射抜いていた。俺は反論できず、ただ唇を噛み締めた。
「一度、本気で向き合ってみるといい。君が本当に描きたいものと、そして、君自身と」
先生の静かな声が、シンと静まり返った美術室に響き渡った。それは、優しい助言のようでもあり、残酷な宣告のようにも聞こえた。
第三章 崩れ落ちた風景
夏の写生会の日、俺は言葉通り、あの海辺の灯台に来ていた。潮風が頬を撫で、カモメの鳴き声が遠くに聞こえる。スケッチブックを開き、鉛筆を走らせる。最高のハルの絵を描くんだ。俺の記憶にある、最も輝いていた瞬間の彼を、この場所に蘇らせる。
時間も忘れ、夢中で筆を動かした。何度も塗り重ねたセルリアンブルーの空。白くそびえ立つ灯台。そして、その下に立つハルの後ろ姿。我ながら、最高の出来栄えだった。描き終えた俺の前に、いつの間にか月島先生が立っていた。
「完成したかね」
「……はい」
先生はしばらく黙って絵を眺めていたが、やがて、ゆっくりと口を開いた。その声は、夏の終わりの空気のように、どこか物悲しい響きを帯びていた。
「蒼井くん、一つ、聞いてもいいだろうか。君が描いている『ハル』という子は、本当に実在したのかね?」
頭を殴られたような衝撃だった。何を、言っているんだ、この人は。
「実在したに決まってるじゃないですか! 俺の一番の親友です!」
俺は声を荒らげた。しかし、先生は少しも動じない。ただ、悲しげな瞳で俺を見つめている。
「私も、そうであってくれればと願ったよ。だから、少しだけ調べさせてもらった。君が卒業した小学校の卒業アルバム、近隣の住民への聞き込み……だが、君の言う『ハル』という名の少年が、君の周りにいたという記録も、記憶も、どこにも存在しなかったんだ」
嘘だ。そんなはずがない。だって、思い出はこんなに鮮明なのに。灯台で見つけた浮き玉。二人で笑い転げた帰り道。夕陽を浴びて、また明日なって手を振ったハルの笑顔。それも全部、嘘だっていうのか?
「……この、浮き玉だって……」
震える手で、カバンから緑色のガラス玉を取り出す。先生は静かにそれを受け取ると、傷だらけの表面を指でなぞった。
「これは、君が小学校の自由研究で、一人で海を探索していた時に見つけたと、君のお母さんから聞いたよ。宝物なんだと、嬉しそうに話していたそうだ。たった一人で、見つけた宝物だと」
先生の言葉が、固く閉ざしていた記憶の扉をこじ開けていく。そうだ。あの日、灯台にいたのは、俺一人だった。浮き玉を見つけて、誰かに見せたくて、でも見せる相手がいなくて、寂しくて……。その時だ。「すごいじゃないか、湊!」って、言ってくれたのは。俺が、聞きたかった言葉を。
記憶の断片が、パズルのように組み変わっていく。ハルと話した会話。それは、俺の自問自答だった。ハルが見せた笑顔。それは、俺がそうあってほしいと願った表情だった。ハルは、引っ越したんじゃない。最初から、いなかったんだ。
孤独に耐えきれなかった幼い俺が、自分を守るために創り出した、理想の友人。もう一人の自分。
その真実にたどり着いた瞬間、目の前の風景がぐにゃりと歪んだ。俺が今まで描いてきた、色鮮やかな思い出の世界が、音を立てて崩れ落ちていく。キャンバスの中のハルの後ろ姿が、陽炎のように揺らめいて、セルリアンブルーの空に溶けて消えていった。残されたのは、ただの白い灯台と、広すぎる空と、どうしようもないほどの、空虚感だけだった。
第四章 君のいないセルリアンブルー
それから数日、俺は絵を描けなくなった。真っ白なキャンバスを前に、筆を持つことすらできない。ハルという幻影を失った俺の世界は、再び色を失い、音も消え、完全な沈黙に支配された。美術室にも足が向かず、ただ部屋に引きこもる日々が続いた。
そんなある日、月島先生が俺の家を訪ねてきた。部屋に招き入れると、先生は壁に立てかけてある、描きかけのキャンバスに目をやった。
「まだ、描けないか」
俺は無言で頷いた。
「そうだろうな。君の世界の半分が、消えてしまったようなものだからな」
先生は俺の隣に座ると、静かに続けた。
「幻だったのかもしれない。だが、君がハルくんを想い、彼と心の中で過ごした時間は、君の中で確かに本物だったはずだ。彼を創り出した君の孤独も、彼に救われた君の喜びも、その感情まで、すべてが嘘だったと本当に思うのかね?」
その言葉は、乾ききった俺の心に、一滴の水のように染み渡っていった。そうだ。ハルはいなかったかもしれない。でも、彼を想っていた俺の気持ちは、確かに存在した。ハルに励まされ、前に進もうとした瞬間は、紛れもなく本物だった。ハルは、俺が前に進むために、俺自身が生み出した杖だったんだ。
俺は、ゆっくりと顔を上げた。窓の外には、夏の終わりの空が広がっている。ハルの瞳と同じ、セルリアンブルーの空が。
翌日、俺は久しぶりに美術室へ向かった。そして、新しいキャンバスをイーゼルに立て、筆を握った。迷いはもうなかった。
俺は、ハルを描かなかった。誰もいない、放課後の教室を描いた。あの日、先生に見られたのと同じ構図。しかし、その絵は以前とはまったく違っていた。窓から差し込む西陽は、絶望的な孤独の色ではなく、明日への希望を照らす暖かい光として描いた。がらんとした教室は、空虚さの象徴ではなく、これから何かが始まる予感に満ちた空間として。
絵が完成に近づいた時、俺はパレットに、ほんの少しだけセルリアンブルーを絞り出した。そして、窓の外に広がる空の、一番高い場所に、その色をそっと置いた。それは、幻影との決別の証であり、同時に、彼が俺の中に残してくれたものへの、感謝の印だった。
絵を描き終えた俺の背後に、人の気配がした。振り向くと、水野さんが心配そうな顔で立っていた。
「蒼井くん、最近、元気なかったから……」
以前の俺なら、きっと目を逸らしていただろう。だが、俺は違った。俺は、完成したばかりの絵を指さし、少し照れながら、でもはっきりと、彼女に言った。
「この絵、見てみない?」
水野さんの顔が、ぱっと花が咲くように輝いた。俺の世界に、新しい色が生まれた瞬間だった。空に溶けたセルリアンブルーの残像は、もう寂しくはない。それはこれからもずっと、俺の心の一番高い場所で、俺自身の青春を見守ってくれるだろう。