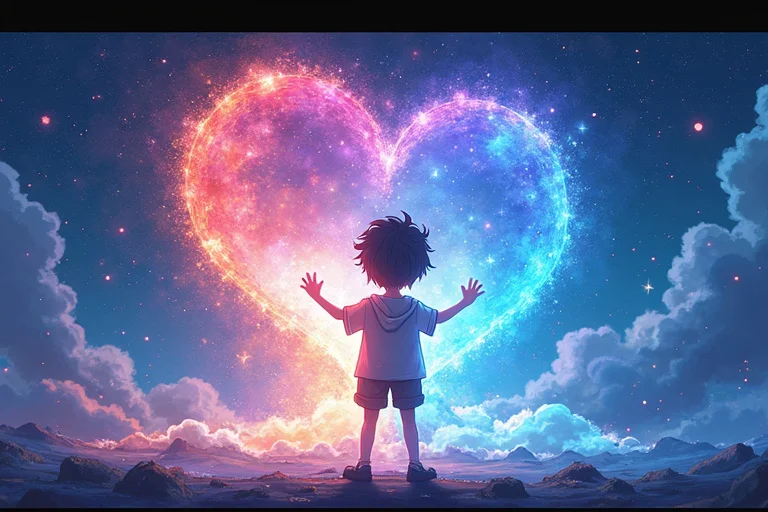第一章 忘却のバースデー
僕たちの住む海辺の町には、一つの奇妙な法律がある。「追憶保存法」。それは、すべての住民が十八歳を迎える日に、自らの「青春」の中から最も輝かしい記憶を一つだけ選び出し、町の地下アーカイブに永久保存することを義務付ける法律だ。最新の記憶工学技術によって抽出された記憶は、ホログラムとして完璧な形で保存される。町の誇りであり、文化遺産なのだ。だが、それには大きな代償が伴う。保存された記憶は、提供者の脳から完全に消去されるのだ。永遠を手に入れる代わりに、僕たちは最も大切な何かを失う。
十八歳の誕生日を明日に控えた僕は、放課後の写真部部室で、現像液のツンとした匂いに包まれながら、途方に暮れていた。窓の外では、夕陽が空と海を茜色に染め上げている。どの記憶を選べばいいのか、皆目見当がつかなかった。フィルムに残した無数の瞬間が、頭の中で明滅する。夏の合宿で見た満天の星空。文化祭のステージで、緊張しながらギターを弾いた瞬間。仲間たちと食べた、何の変哲もないカップラーメンの味。どれもが等しく愛おしく、失うことなど考えられなかった。
「まだ決まらないの、湊?」
背後から、陽の光を凝縮したような声がした。幼馴染の月島陽菜だ。彼女もまた、一週間後に十八歳になる。僕がカメラを向けると、彼女はいつも、悪戯っぽく笑いながら最高の表情を見せてくれた。僕のアルバムは、彼女の笑顔で埋め尽くされている。
「陽菜は決めたのかよ」
「とっくにね!」
彼女は胸を張って、得意げに笑う。その笑顔が眩しくて、僕は思わず目を細めた。プリントされたばかりの、海辺で笑う彼女の写真を指でなぞる。この瞬間を保存すれば、僕は彼女とこの海に行ったことを永遠に忘れてしまう。それは、僕という人間の土台が、根こそぎ奪われるような恐怖だった。
「何を保存するか、教えてはくれないんだろ」
「うん、それは当日のお楽しみ。湊も、早く決めなよ。最高の青春、たった一つ」
陽菜はそう言うと、軽やかな足取りで部室を出て行った。残された僕は、窓の外に広がる、あまりにも美しい夕景をただ見つめることしかできなかった。沈みゆく太陽は、まるで僕たちの過ぎ去りゆく時間そのもののようだった。失うことを前提とした輝きなんて、あまりにも残酷じゃないか。シャッターを切る指が、微かに震えていた。
第二章 ファインダー越しの永遠
それからの数日間、僕はまるで強迫観念に駆られたように、陽菜の姿を撮り続けた。通学路の桜並木で、他愛ない話に笑う横顔。図書室の窓から差し込む光の中で、本を読む真剣な眼差し。部活帰りの堤防で、潮風に髪をなびかせながら遠くを見つめる背中。カシャリ、カシャリと、乾いたシャッター音が響くたび、僕はその瞬間を永遠に繋ぎ止めようと必死になっていた。
「また撮ってる。湊は本当に写真が好きだね」
「好きだからな」
「私のこと、そんなに好きなの?」
冗談めかした陽菜の言葉に、僕は答えられなかった。ファインダー越しに見る彼女は、いつも少しだけ違う世界にいるように見えた。僕だけが知っている、完璧な被写体。だが、レンズを通して彼女を見つめるほど、僕は自分の記憶のほとんどが、彼女という存在に侵食されている事実に気づかされる。
二人で自転車を飛ばした夏の坂道。初めて喧嘩して、気まずい沈黙が流れた帰り道。僕がコンクールで賞を取った時、自分のことのように喜んでくれた時の、涙で濡れた瞳。僕の青春は、陽菜の記憶そのものだった。どれか一つを選ぶということは、他の全ての陽菜を僕の中から消し去ることだった。
「なあ、陽菜」
ある日の放課後、僕たちはいつもの堤防に座っていた。波の音が、規則正しくコンクリートを叩いている。
「もし……もし俺が、陽菜との記憶を保存したら、どうする?」
僕の問いに、陽菜は少しだけ驚いたように目を見開いた。そして、すぐにいつもの笑顔に戻って、僕の肩を軽く叩いた。
「ばっかじゃないの? 私との記憶なんて選んじゃダメだよ」
「なんでだよ」
「だって、そしたら湊の青春、ほとんど無くなっちゃうじゃん。もったいないよ」
「……」
「湊はさ、私がいない記憶を選べばいいんだよ。写真部の仲間との記憶とか、家族との記憶とか。そっちの方が、ずっと湊のためになる」
彼女はこともなげに言った。まるで、僕の記憶から自分が消えることなんて、何でもないことのように。その言葉が、鋭い棘のように僕の胸に突き刺さった。陽菜のいない僕の青春に、どれほどの価値があるというのだろう。お前は、僕にとっての青春そのものなのに。その言葉は喉まで出かかったが、結局、弱い波の音にかき消されてしまった。
第三章 はじめまして、さようなら
誕生日当日、僕は重い足取りで市のアーカイブセンターに向かった。白亜のモダンな建物は、まるで神殿のようにも、墓標のようにも見えた。受付で手続きを済ませ、カウンセリングルームに通される。そこで、僕は担当の職員から、信じられない事実を告げられた。
「月島陽菜さんですね。彼女は先週、すでに手続きを終えられていますよ」
職員の言葉に、心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。陽菜は、もう記憶を保存した? 僕に何も言わずに?
「彼女が……何を保存したか、聞いても?」
「個人情報ですので、本来はお教えできません。ですが、今回は特殊なケースですので……ご本人からも、蒼井さんには伝えてほしいと許可を得ています」
職員はタブレット端末を操作し、僕に画面を見せた。そこに表示されていた保存記憶のタイトルを見て、僕は息を呑んだ。
保存対象:個人格『蒼井湊』に関する全ての記憶
「……これは、どういう意味ですか?」
声が震えた。職員は、静かに、しかし淡々と説明を続けた。
「追憶保存法には、例外的な適用法があります。特定の出来事ではなく、特定の『個人』に関する記憶の全てを保存対象とすることも可能です。ただし、これは提供者に最も大きな負荷……つまり、最も広範囲な記憶の喪失を強いるため、滅多に選択されることはありません」
陽菜が、僕に関する全ての記憶を、保存した。
僕と出会った日のこと、一緒に笑ったこと、喧嘩したこと、僕が撮った写真のこと。その全てを、彼女は自ら手放したというのか。
「なんで……」
「月島さんは、こうおっしゃっていました。『彼が、私との記憶を失って苦しむくらいなら、私が全てを忘れたい。私の青春は、彼そのものだったから、一つなんて選べなかった。だから、全部、綺麗なまま残したいんです』と」
陽菜が言っていた「私がいない記憶を選べばいい」という言葉の意味が、最悪の形で僕の脳髄を貫いた。彼女は、僕を守るために、自ら僕を忘れる道を選んだのだ。
僕はアーカイブセンターを飛び出し、全力で陽菜の家へと走った。息が切れ、肺が張り裂けそうだった。どうか、嘘であってくれ。いつもの悪戯だよと、笑ってくれ。
玄関のドアを開けてくれたのは、陽菜だった。僕の顔を見るなり、彼女は困ったように、そしてどこか申し訳なさそうに、小さく首を傾げた。その瞳には、僕の知る光はどこにも宿っていなかった。それは、見知らぬ他人に向ける、警戒心と戸惑いの色だった。
「あの……どちら様でしょうか?」
その声は、僕が焦がれた陽菜の声のはずなのに、全く違う響きを持っていた。僕というフィルターを失った、ただの音の羅列。
世界から、色が消えた。音が消えた。僕の青春が、目の前でゆっくりと死んでいく。彼女は、僕という存在を失った世界で、ただ静かに微笑んでいた。
第四章 残光のポートレート
絶望の淵で、僕は陽菜の部屋で見つけた一冊のアルバムをめくっていた。それは僕が彼女にプレゼントしたもので、僕が撮った彼女の写真が、時系列順に丁寧に貼られていた。最後のページに、一枚の便箋が挟まっていた。見慣れた、少しだけ丸い彼女の文字が並んでいた。
『湊へ。
これを読んでいるということは、私はもう、あなたのことを覚えていないんだね。ごめんなさい。
私の最高の青春は、全部あなたでした。ファインダー越しのあなた。笑うあなた。怒るあなた。だから、たった一つなんて、どうしても選べなかった。
忘れてしまうのは、本当はすごく怖い。でも、あなたが私との大切な記憶を失って、胸にぽっかり穴を開けて生きていく姿を想像する方が、もっと怖かった。
だから、私が忘れるね。あなたは、私のいない記憶を選んで、あなたの未来を生きてください。私の青春は、アーカイブの中で、湊と一緒に永遠に輝き続けるから。
今まで、本当にありがとう。私の、最初で最後のヒーロー。
さようなら。』
涙が、便箋のインクを滲ませた。なんて馬鹿なやつなんだ。自己犠牲にも程がある。それは、あまりにも残酷で、そしてあまりにも深い、愛情の形だった。彼女は僕の未来を守るために、自らの過去の全てを差し出したのだ。
僕は再びアーカイブセンターに戻った。もう、迷いはなかった。カウンセラーに、保存したい記憶を告げる。
「僕が保存したいのは、たった今、この瞬間の記憶です」
「……今、ですか?」
「はい。幼馴染の手紙を読んで、彼女の本当の想いを知った、この瞬間の全て。彼女が僕に託した未来を、今度は僕が背負っていくと決意した、この痛みと、感謝と、覚悟の全てを、僕は保存したい」
それは、過去を失うことで未来を掴むための、僕なりの儀式だった。陽菜が守ろうとした僕の過去を、僕もまた手放すことで、彼女の選択に応えたかったのだ。
数年後。僕は、大学で写真を学びながら、時折コンクールに作品を出していた。先日、「失われた光」というテーマで組んだ写真が、小さな賞を受賞した。僕の作品には、なぜかいつも、陽の光の中に佇む、名前も知らない少女の面影が滲んでいた。
僕は何を失ったのか、もう正確には思い出せない。ただ、胸の奥に、温かくて、同時にひどく切ない、空洞のようなものがずっと居座っている。
ある晴れた午後、僕は雑踏の中で、偶然彼女とすれ違った。友人と楽しそうに笑い合う姿は、僕の知らない、けれどどこか懐かしい陽菜だった。僕たちの視線が、ほんの一瞬だけ交差する。もちろん、彼女が僕に気づくはずもない。僕もまた、彼女を知らない。
それでも、胸の奥の空洞が、きゅっと音を立てて疼いた。僕は衝動的にカメラを構え、無意識にシャッターを切った。
ファインダーの向こうで、彼女がふと、不思議そうにこちらを振り返った、気がした。
青春は消えても、その残光だけは、魂の感光板に焼き付いて、決して消えることはないのかもしれない。僕は現像されることのないその一枚を胸にしまい、再び歩き始めた。空は、あの日のように、どこまでも青かった。