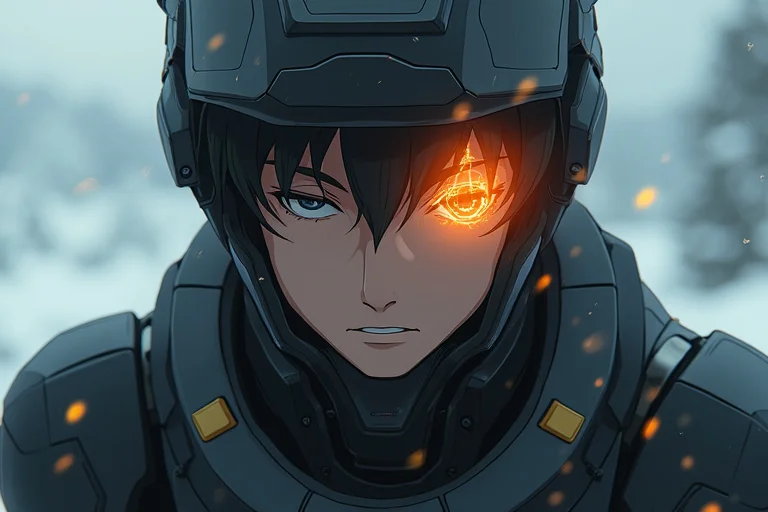第一章 緑の福音
砲弾の名は「アルバスの種子」。人々はそれを、畏敬と希望を込めて「緑化弾」と呼んだ。長きにわたる大戦で、大地は汚染され、砂漠化が進んだ。そんな灰色の世界に、一瞬で生命の森を芽吹かせる奇跡の兵器。その射手を務めることが、僕、カイ・アシュトンの誇りだった。
「座標修正、デルタ・セブン。着弾予測、誤差なし。発射準備」
管制室の無機質な声が、ヘッドセットを通して鼓膜を揺らす。僕は照準モニターに映る、敵国オルテシアの乾ききった大地を睨み、深呼吸した。茶色くひび割れた大地。そこにはかつて、街があったと聞く。だが今は、文明の残骸すら風化し、ただ虚無が広がっているだけだ。僕たちの任務は、この死の大地に緑の息吹を取り戻すこと。これは破壊ではない。創造だ。戦争を終わらせるための、聖なる一撃なのだ。
「発射」
指先に全神経を集中させ、発射ボタンを押し込む。轟音とともに車体が震え、砲塔から放たれた弾丸が空を引き裂いていく。モニターの映像が、着弾予測地点にズームアップする。数秒の沈黙。そして、閃光。爆発音はない。代わりに、画面の中の大地が、まるで生き物のように脈動を始めた。亀裂から無数の蔦が溢れ出し、瞬く間に天を覆う大樹へと成長していく。わずか数分で、荒野は鬱蒼とした森へと姿を変えた。管制室から歓声が上がる。また一つ、世界に緑を取り戻した。
故郷の妹、リナに送る手紙に、僕はいつもこの光景を綴った。「今日もお兄ちゃんは、大きな森を作ったよ。いつか戦争が終わったら、リナをこの緑の森に連れて行ってあげる。鳥たちが歌い、綺麗な花が咲く、優しい森だよ」と。
その夜だった。任務報告のデータを受信している最中、僕は奇妙なノイズに気づいた。ザー、という砂嵐のような音に混じって、何か微かな音が聞こえる。それはまるで、遠くで泣く赤ん坊の声のようにも、あるいは苦痛に呻く誰かの声のようにも聞こえた。
「隊長、この通信記録、何か異音が混じっていませんか?」
上官である隊長は、モニターを一瞥して眉をひそめたが、すぐに首を振った。
「イオン嵐の影響だろう。よくあることだ。気にするな」
そう言われれば、それまでだった。だが、その夜、僕は初めて眠れぬ夜を過ごした。耳の奥で、あの甲高い音が、いつまでも木霊していたからだ。それは僕が創造したはずの、生命の森から響いてくる、最初の不協和音だった。
第二章 沈黙の森
僕の部隊は英雄だった。「緑の使徒」と呼ばれ、行く先々で歓迎された。僕が撃ち込んだ緑化弾の数は、やがて百を超えた。オルテシアの国土は、地図の上で急速に緑色に塗り替えられていく。戦況は我々に有利に傾き、終戦の噂も聞こえ始めた。妹からの手紙には、僕を誇りに思うと、何度も書かれていた。
だが、僕の心は晴れなかった。あの夜から、幻聴は僕を執拗に追いかけ続けた。緑化弾を撃ち込むたび、着弾の瞬間に響く閃光と生命の奔流の中に、僕は無数の悲鳴を聞くようになった。それは僕だけの秘密だった。誰に話しても、戦場でのストレスだと片付けられるだけだろう。
疑念は、別の形でも膨らんでいった。偵察衛星が送ってくる、僕たちが創り出した森の映像は、どこか異様だった。あまりにも、静かすぎるのだ。あれほど巨大な森ならば、無数の動物が住み着き、生命の営みで満ち溢れているはずだ。しかし、映像には鳥の姿一つなく、赤外線センサーにも動物の体温反応はほとんど映らない。ただ、植物だけが異常な生命力で密集し、光さえも拒むように葉を茂らせている。それは僕がリナに語った「優しい森」とは似ても似つかない、「沈黙の森」だった。
ある日、僕は整備士に頼み込み、緑化弾の構造データをこっそりと見せてもらった。複雑な化学式と設計図が並ぶ中、僕の目を引いたのは、弾頭に搭載された有機触媒の項だった。「対象領域の炭素系有機物に作用し、急速な細胞分裂と再構築を促進する」。専門的で難解な言葉だったが、その一文が、僕の心臓に冷たい楔を打ち込んだ。炭素系有機物。それは、土や枯れ木だけを指す言葉ではない。それは、生きているもの全てを包括する言葉だ。
その夜、僕はリナへの手紙を書けなかった。ペンを握る手が震え、インクの染みが便箋の上に広がるだけだった。「お兄ちゃんは、何を作っているんだろう?」という、答えの出ない問いが、頭の中をぐるぐると回り続けていた。
第三章 嘆きの種子
転機は、思いがけない形で訪れた。オルテシアから、一人の高名な植物学者が亡命してきたのだ。エリアス・ヴァーレンと名乗る老人は、やつれていたが、その瞳には狂気にも似た強い光が宿っていた。彼は、緑化弾の開発に初期段階で関わっていたという。軍の上層部は、彼の持つ情報を重要視し、僕を聴取の席に着かせた。最高の射手である僕の経験が、彼の証言の信憑性を裏付けると考えたのだろう。
重々しい空気の中、エリアス老人は震える声で語り始めた。
「『アルバスの種子』…あなた方はそう呼んでいるそうですね。我々はそれを、『嘆きの種子』と呼んでいました」
彼は咳き込みながら、一枚の写真をテーブルに滑らせた。それは、緑化弾の着弾前と着弾後の、同一地点の土壌を電子顕微鏡で撮影したものだった。
「左が着弾前。土壌には無数の微生物、有機物の粒子が見える。ごく普通の、生命を育む土です。そして右が、着弾後の森の土。見てください。微生物が、一匹もいない。完全に無菌状態です」
息を呑む僕に、彼は続けた。
「緑化弾は、無から有を生み出す魔法ではありません。あれは、変換装置なのです。着弾領域に存在する、あらゆる炭素系有機物…土の中の微生物、草の根、昆虫、動物…そして、そこに残された人々を、強制的に植物細胞へと変換し、その生命エネルギーを暴走させて、一夜にして森を形成する、悪魔の兵器なのです」
その言葉は、雷鳴となって僕の頭蓋を打ち砕いた。
血の気が引き、指先が氷のように冷たくなる。幻聴。沈黙の森。構造データにあった一文。全てのピースが、最悪の形で組み合わさっていく。
「人々…?」かろうじて絞り出した僕の声は、自分のものではないように掠れていた。
「ええ」老人は静かに、しかしはっきりと頷いた。「オルテシアの民は、あなた方の侵攻から逃げ遅れ、地下のシェルターや廃墟に隠れていました。あなた方が緑化弾を撃ち込んだ、あの『死の大地』には…まだ、大勢の人間がいたのです」
あの赤ん坊の泣き声のような音は、幻聴ではなかった。あれは、植物に作り替えられていく人々の、最後の叫びだったのだ。僕が創り出したと思っていた美しい森は、無数の人々の命を養分にして咲き誇る、巨大な墓標だった。
僕は英雄ではなかった。僕は、歴史上最も残忍な方法で、何十万という命を奪った大量虐殺者だった。リナに語った優しい森の物語は、血と絶望で塗り固められた、醜悪な嘘だったのだ。僕は椅子から崩れ落ち、嗚咽を漏らすことしかできなかった。
第四章 風が運ぶもの
僕の世界は色を失った。食事の味も、仲間たちの声も、何も感じなくなった。ただ、耳の奥で鳴り響く悲鳴だけが、日に日に鮮明になっていく。僕は任務を拒否した。当然、上官たちは僕を尋問し、精神鑑定にかけ、最終的には反逆罪の容疑で独房に監禁した。
数週間後、戦況が最終局面を迎えたというニュースが聞こえてきた。オルテシア首都への、総攻撃。その仕上げとして、僕が所属していた部隊が、首都圏全域に数百発の緑化弾を同時に撃ち込む作戦が計画されているという。それを聞いた瞬間、僕の中で何かが切れた。憎しみではない。絶望でもない。それは、償いへの渇望だった。
僕は脱走した。かつての仲間たちの助けを借り、夜陰に紛れて、自分がかつて操縦していた長距離自走砲のコックピットに滑り込む。目的地は一つ。この狂った兵器を生み出した、自国の兵器開発研究所だ。憎しみの連鎖は、その根源を断ち切らなければ終わらない。
照準モニターに、研究所の巨大なドームが映し出される。指先に、発射ボタンの冷たい感触が伝わる。これを押せば、すべてが終わる。だが、その瞬間、僕の脳裏にリナの笑顔が浮かんだ。僕がここで引き金を引けば、僕はただの破壊者になる。僕が殺してきたオルテシアの人々と同じように、何の罪もない研究所の職員たちを、緑の墓標に変えるだけだ。憎しみに憎しみで応えて、何が生まれる?
僕は、そっと指をボタンから離した。そして、砲塔を空に向け、搭載されていた最後の緑化弾を、成層圏の遥か彼方へと撃ち放った。誰にも届かない、誰の命も奪わない場所へ。それが、僕にできる唯一の答えだった。
夜明けの光が差し込む頃、僕は自走砲から降り、駆けつけた兵士たちの前で静かに両手を上げた。
戦争は、その数日後に終わった。
数年後、僕は戦犯として、終身刑を宣告された。独房の小さな窓からは、遠くに僕が作り出した「嘆きの森」が見える。人々は森を恐れ、誰も近づこうとはしない。
ある春の午後だった。窓の外を眺めていると、あの沈黙の森から、一羽の小さな鳥が飛び立つのを見た。それは、僕が知るどの鳥とも違う、新しい姿をしていた。そして、風が運んできたのだろうか。窓の格子に、見たこともないほど小さな、白い綿毛のような種子がひとつ、引っかかっていた。
森は、まだ死んではいなかった。無数の命を奪った嘆きの土壌の中で、気の遠くなるような時間をかけて、何か新しい生命を育み始めているのかもしれない。僕が犯した罪は、永遠に消えない。だが、あの小さな種子に、僕は祈りを捧げた。いつか、この緑の墓標が、本当の意味で生命を謳歌する「優しい森」になる日が来るように。そして、その風が運ぶ祈りが、遠い空の下にいるリナのもとへ届くようにと。
僕は静かに涙を流した。その涙は、絶望の色ではなく、遥かな未来への、微かな希望の色をしていた。