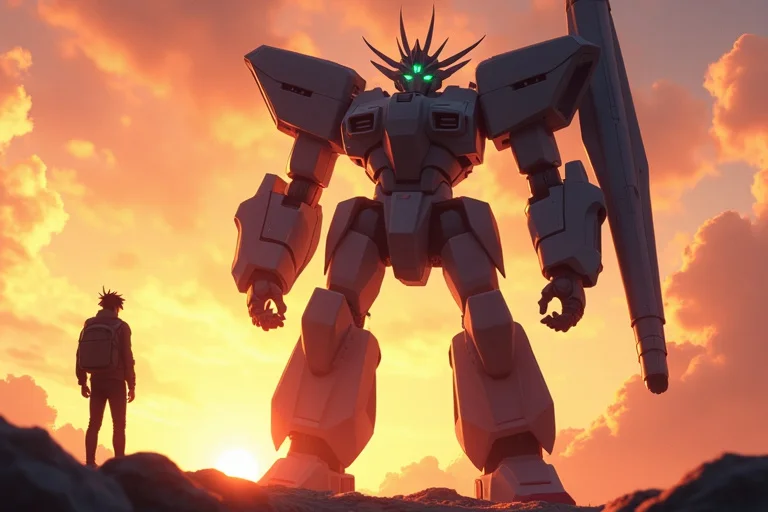第一章 錆びたインクの匂い
埃と、乾いた血と、そして名もなき人々の人生が終着する場所の、独特の甘いような黴びたような匂い。それが、僕、水島健司の仕事場だった。帝国軍後方支援部隊、遺品管理課。ここは、戦場で散った敵国兵士たちの所持品が最後に流れ着く、巨大な淀みのような場所だ。
僕の仕事は、それらを仕分けし、記録し、焼却炉へと送ること。錆びた懐中時計、割れたガラスの向こうで永遠に微笑む家族の写真、インクが滲んで読めなくなった手紙。毎日毎日、何百という「死」の残骸に触れていると、感覚は次第に麻痺していく。それはもう、誰かの人生の証ではなく、単なる「処理すべき物品リスト」の一つに過ぎなかった。敵兵Aの所持品。敵兵Bの所持品。感情を挟む余地など、どこにもない。そう、思っていた。
その日も、僕は無感動に木箱を開けた。中から現れたのは、いつもと同じような品々だ。泥に汚れた軍服、弾痕の空いた水筒、そして一冊の本。手に取った瞬間、僕はわずかな違和感を覚えた。敵国の装丁ではない。ざらりとした手触りの表紙には、僕が生まれ育った国の言葉で、タイトルが書かれていた。
『星を渡る機関車』
息が、止まった。それは、僕が子供の頃、擦り切れるまで読んだ絵本だった。戦争が始まってすぐ、敵国の文化を排斥する動きの中で絶版となり、今では幻の一冊とされている。なぜ、敵兵がこれを? ページをめくる指が微かに震える。インクと紙の古い匂いが、忘れていた子供時代の記憶を呼び覚ます。機関車が夜空を駆け抜け、星の海を渡る物語。最終ページにたどり着いた時、僕の心臓は鷲掴みにされたように軋んだ。
そこには、拙い、けれど力強い子供の文字で、こう書かれていた。
「また会おうね、ケンジ」
それは、僕の名前だった。そしてその筆跡は、十数年前に故郷で別れた、たった一人の親友のそれに、あまりにも似すぎていた。
第二章 スケッチブックの故郷
その日から、僕の世界は静かに歪み始めた。あの絵本は、僕の机の引き出しの奥深くに隠してある。焼却炉に送ることなど、到底できなかった。敵兵の記録台帳をめくり、絵本の持ち主の名前を探し出す。「レオ・シュナイダー」。それが、彼の名前だった。階級は伍長。二十三歳没。僕と、同じ歳だった。
レオ・シュナイダー。その名前を、僕は何度も舌の上で転がしてみた。異国の響きを持つその名前と、子供の頃の親友「ハルキ」の面影が、頭の中で奇妙な協奏曲を奏でる。ありえない。ただの偶然だ。そう自分に言い聞かせても、心のざわめきは一向に収まらなかった。
僕は、レオ・シュナイダーの遺品を収めた木箱を、こっそりと保管庫の隅に隠した。そして、誰もいない夜を見計らっては、その中身を検分するようになった。それは、規則違反を通り越して、もはや狂気の入り口に立つような行為だった。
木箱の中には、絵本の他に、一冊の小さなスケッチブックがあった。鉛筆で描かれたその絵は、驚くほど精緻で、そして優しかった。描かれているのは、戦場の風景ではない。名もなき草花、空を流れる雲、そして、いくつかの風景画。
一枚の絵に、僕は釘付けになった。緩やかな丘の上に、一本だけ立つ大きな樫の木。その下には、夏の日差しを浴びて、数えきれないほどのひまわりが咲き誇っている。それは、僕の故郷の、あの丘の風景そのものだった。子供の頃、ハルキと二人で秘密基地を作った、思い出の場所。
もう一枚めくると、今度はレンガ造りの小さな教会の絵が出てきた。これも見覚えがある。僕らが住んでいた町の、丘の上にあった教会だ。僕とハルキは、よくその鐘の音を聞きながら、川で魚を釣ったものだった。
なぜだ。なぜ、敵国の兵士が、僕の故郷の風景を知っている?
それまで単なる「敵」という記号でしかなかったレオ・シュナイダーという存在が、僕の中で急速に血の通った一人の人間として像を結び始めた。彼は、僕と同じ空を見て、同じ風を感じていたのかもしれない。このスケッチブックに故郷の絵を描いた時、彼は何を思っていたのだろう。
僕は、もはや遺品を「処理」できなくなっていた。血の滲んだ手帳の一文字一文字に、持ち主の最後の息遣いを感じるようになった。割れた写真立ての向こうにいる家族の悲しみを想像するようになった。「死」は数字ではなく、一つ一つが取り返しのつかない物語の終わりなのだと、遅まきながら理解し始めていた。僕の中で、何かが決定的に変わりつつあった。
第三章 親友の名はレオ
疑念は、やがて確信に近い渇望へと変わった。僕は、レオ・シュナイダーのすべてを知らなければならない。そうしなければ、前に進めない。その衝動に突き動かされ、僕はついに最後の一線を越えた。深夜、上官のオフィスに忍び込み、重要個人情報が保管されているキャビネットの鍵を盗み出したのだ。
心臓が喉から飛び出しそうだった。月明かりだけが差し込む記録保管庫で、僕は「サ」行の棚から「シュナイダー、レオ」のファイルを探し当てた。震える手でファイルを開く。そこに記されていた個人情報に目を通した瞬間、僕は息を呑んだ。
出生地:ヴァインブルク市。
それは、僕の故郷の隣町だった。国境線の変更によって、十数年前に敵国領に編入された街だ。
そして、ファイルの最後に添付されていた一枚の書類が、僕の思考を完全に停止させた。それは、身分証明書用の、古いモノクロ写真だった。レンズを見つめる真剣な眼差し。少し不器用そうな微笑み。そこに写っていたのは、紛れもなく、僕の記憶の中にいる親友、桜井春樹(さくらい はるき)の、少し大人びた顔だった。
桜井春樹。それが、ハルキの本名だ。
頭の中で、雷鳴が轟いた。記憶の断片が、激しい勢いで繋がり始める。ハルキは、父親の仕事の都合で、まだ国境が曖昧だったあの頃に、隣町のヴァインブルクへ引っ越していった。「遠い国に行くんじゃない。すぐ隣だよ。またすぐに会えるさ」。そう言って笑っていたハルキの顔。彼が去った後、二つの国の関係は急速に悪化し、やがて戦争が始まった。僕たちは、二度と会うことはなかった。
ハルキは、敵国で育ち、レオ・シュナイダーという新しい名前を与えられ、その国の国民として徴兵されたのだ。そして、皮肉にも、かつての故郷であるこの国に銃口を向け、戦い、そして死んだ。
僕が処理しようとしていた「敵兵A」は、僕のたった一人の親友だった。
あの絵本。「また会おうね、ケンジ」。それは、引っ越しの日に僕がハルキに渡した絵本に、彼が書き加えた約束の言葉だった。ハルキは、僕との約束を、思い出を、ずっと胸に抱いて生きていた。そして、戦場で命を落とすその瞬間まで、この絵本を肌身離さず持っていたのだ。
「敵」とは何だ。「味方」とは何だ。僕とハルキを隔てていたのは、一体何だったというのだ。国境という、人間が勝手に引いた一本の線か。憎しみを煽る指導者たちの言葉か。足元から世界が崩れ落ちていく。僕がこれまで信じていた、あるいは信じようと努めていたすべてのものが、意味を失って砕け散った。涙は出なかった。ただ、胸にぽっかりと空いた穴を、冷たい風が吹き抜けていくだけだった。
第四章 ひまわり畑の約束
やがて、長い戦争は終わった。熱狂も、憎しみも、嘘のように遠い過去の出来事として語られるようになった。僕は、遺品管理課の仕事を辞め、灰色の風景が広がる故郷の町へと戻った。
町の姿は変わり果てていたが、丘だけは昔のままだった。僕は、ハルキのスケッチブックを頼りに、あのひまわり畑を目指して丘を登った。息を切らしながらたどり着いたその場所には、かつてと何も変わらない光景が広がっていた。夏の終わりの強い日差しを浴びて、数えきれないほどのひまわりが、まるで黄金色の海のように、風に揺れている。
僕は、ひまわり畑の真ん中に立ち、リュックサックからあの絵本を取り出した。レオ・シュナイダーこと、桜井春樹の最後の所持品。『星を渡る機関車』。
僕は、ひまわりの根元に小さな穴を掘り、その絵本をそっと置いた。そして、柔らかい土をかけた。それは僕なりの弔いであり、果たされることのなかった約束を、ようやく終わらせるための儀式だった。
「会いに来たよ、ハルキ」
声に出すと、堪えていた涙が初めて頬を伝った。僕たちは敵だったのだろうか。君が引き金を引こうとした相手は、僕だったのかもしれない。僕が砲弾の音に怯えていたその時、君は空の向こうにいたのかもしれない。答えは、どこにもない。
戦争は、勝者と敗者を生む。しかし、そこには常に、ハルキのような名もなき人々の、語られることのない無数の物語が埋もれている。国という大きな物語のために、僕たち一人一人の小さな物語が、いとも簡単に踏み潰されていく。
僕は、その事実からもう目を逸らさない。ハルキの物語を、僕が語り継いでいこう。彼がどんなに優しい絵を描き、どんなに古い約束を大切にしていたか。そして、彼が「敵」としてではなく、「ハルキ」として死んでいったことを。それが、この理不尽な世界で僕にできる、たった一つの、そして最も意味のある戦いなのだと信じた。
風が、ひまわりの間を吹き抜けていく。ざわわざわわ、と、まるで遠い日の親友の囁きのような音がした。空の青と、ひまわりの黄色が、残酷なほどに美しく、僕の目に焼き付いて離れなかった。