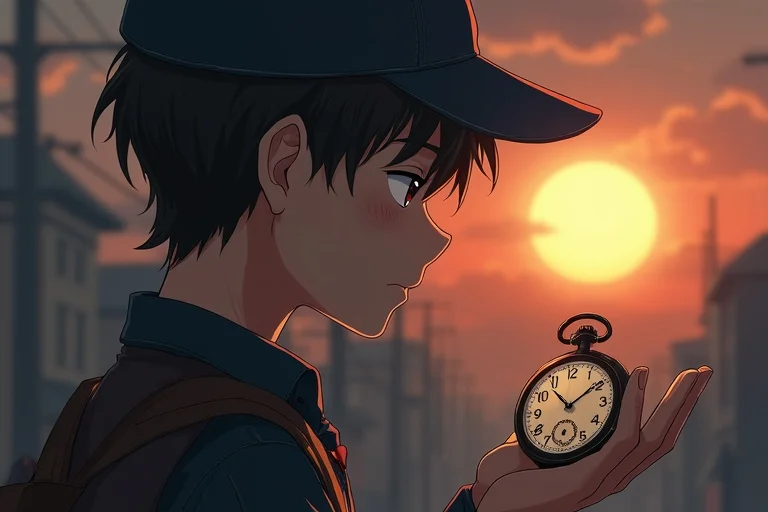第一章 忘却の塵と甘い香り
灰色の空から、銀色の粒子が静かに舞い降りていた。人々が「忘却の塵(レテ・ダスト)」と呼ぶそれは、音もなく塹壕を、瓦礫の山を、そして名もなき兵士たちの骸を覆い尽くしていく。俺、リヒトはこの塵が嫌いだった。仲間たちは、この塵が戦場の恐怖を和らげてくれると嘯く。昨日死んだ戦友の顔も、故郷に残した恋人の温もりも、等しく薄れさせてくれるから、と。だが、俺にはできなかった。
俺には、奇妙な体質があった。忘却の塵によって失われた記憶は、俺の鼻腔を微かな「香り」として掠めるのだ。仲間が昼食のメニューを忘れるたびに焦げたパンの香りが立ち上り、小隊長が作戦内容を失念するたびにインクと羊皮紙の匂いが漂った。それは誰にも理解されない、孤独な感覚だった。形を失い、意味を剥奪された記憶の残滓は、ただの香りの断片として俺の周囲を彷徨う。内容までは分からない。ただ、その香りが持つ感情の色彩――懐かしさ、喜び、悲しみだけが、胸を締め付けた。
その日も、俺は泥濘に膝をつき、敵陣を睨んでいた。湿った土の匂い、硝煙の焦げ臭さ、そして仲間たちから漂う無数の「忘却の香り」が混じり合い、頭が割れそうだった。その時だ。風向きが変わり、敵の塹壕から、これまで嗅いだことのない香りが運ばれてきた。
それは、陽だまりのように温かく、焼き立ての林檎パイのように甘美な香りだった。午後の柔らかな日差し、レースのカーテン、母の優しいハミング。断片的なイメージが脳裏を閃き、涙がこぼれそうになる。間違いない。これは俺の香りだ。俺がずっと昔に失くしてしまった、幼い日の幸福な記憶の香り。
なぜだ。なぜ、殺し合うべき敵から、俺自身の失われたはずの記憶の香りがする? 銃を握る手に力がこもる。灰色の戦場で、その甘い香りだけが、あまりにも鮮やかな謎として立ち上っていた。
第二章 香りの囚人
数時間後、俺たちは敵の塹壕を制圧した。突撃の号令と共に、思考を放棄して引き金を引いた。耳鳴りが止んだ後、俺は香りの源を探して、泥と血に塗れた塹壕を歩いた。そして、見つけた。
塹壕の隅で、一人の敵兵が気を失っていた。小柄な女性兵士だった。彼女の軍服から、あの甘い林檎パイの香りが、幻のように立ち上っている。俺は、他の兵士が彼女にとどめを刺す前に、咄嗟に叫んだ。「捕虜にする! 情報を引き出せるかもしれん!」
医療テントに運ばれた彼女は、エマと名乗った。栗色の髪は泥で汚れ、頬には痛々しい擦り傷があったが、その瞳は驚くほど澄んでいた。彼女もまた、忘却の塵の影響を強く受けていた。自分の所属部隊はおろか、どうしてここにいるのかさえ、曖昧にしか覚えていない。
「何か……とても温かいものを、失くした気がするんです」
診察の合間に、彼女はぽつりと言った。その言葉と共に、彼女からふわりと甘い香りが漂い、俺の胸を締め付けた。それは俺の記憶だ。俺の母親が作ってくれた、世界で一番美味しい林檎パイの記憶。俺はその事実を告げることもできず、ただ黙って頷くことしかできなかった。
俺はエマの監視役を命じられた。二人きりになると、彼女から漂う香りはより一層濃くなった。それは林檎パイの香りだけではなかった。初めて自転車に乗れた日の、誇らしい土の匂い。夏祭りの夜に見た、花火の火薬の香り。父に肩車をされて見上げた、満天の星の香り。次から次へと溢れ出す俺の「幸福な記憶」の香りに、俺は眩暈を覚えた。
彼女は、俺の幸福な過去を閉じ込めた、生きた香水瓶のようだった。彼女と話していると、失ったはずの温かい感情が蘇る。だが同時に、なぜ彼女が俺の記憶を持っているのかという疑念と、自分の最も大切な部分を他人に所有されているという屈辱感が、心を蝕んでいった。彼女は何も知らない。彼女もまた、この不条理な戦争の被害者なのだ。俺は彼女を憎むこともできず、かといって、この奇妙な関係を受け入れることもできずに苦しんでいた。
第三章 記憶市場の真実
疑念は、一つの確信に変わりつつあった。エマという個人の問題ではない。この戦争そのものに、俺の知らない巨大な欺瞞が隠されている。俺は危険を冒し、夜陰に紛れて司令部の記録保管室に忍び込んだ。狙いは、忘却の塵に関する最高機密文書だ。
厳重に施錠されたキャビネットを開けると、そこから濃厚な香りが溢れ出した。それは一つの香りではない。何千、何万という人々の記憶が凝縮された、むせ返るような芳香だった。歓喜、愛情、安らぎ――全てが極上の「幸福」の香りだった。それは兵士たちが戦場で嗅ぐような、掠れた残滓ではなかった。完璧な形で保存され、熟成された、最高級のヴィンテージワインのような記憶の香り。
俺は文書を貪るように読んだ。そして、全身の血が凍りつくのを感じた。
忘却の塵は、記憶を消すだけの兵器ではなかった。それは、人間の脳から特定の記憶、特に感情を強く伴う「幸福な記憶」を抽出し、粒子化するためのナノマシンだったのだ。そして、抽出された記憶は「追憶香(メモリー・フレグランス)」と名付けられ、両国の富裕層やエリート層の間で高値で取引されているという。
この戦争の目的は、領土でも、資源でも、イデオロギーでもなかった。兵士たちから収穫される「幸福な記憶」という商品が目的だったのだ。俺たちは、記憶を狩られるための家畜だった。戦場で死ねばそれまで。生き残っても、幸福な記憶を根こそぎ奪われ、抜け殻となって社会に放り出される。エマが俺の記憶を持っていたのは、偶然ではなかった。おそらく、抽出された俺の記憶が商品として流通し、何らかの形で彼女の脳に「移植」されたのだ。彼女は、誰かの気まぐれで、俺の過去を着せられた人形に過ぎなかった。
司令部の奥、上官の部屋の扉の隙間から、上質なラム酒と古い革の匂いに混じって、甘い林檎パイの香りが漏れ出ていることに気づいた時、俺の中の何かが音を立てて崩れ落ちた。彼らは、俺たちが命懸けで戦っている間に、俺たちの最も美しい記憶を嗜んでいたのだ。
怒りよりも先に、途方もない虚無が俺を襲った。国への忠誠も、戦友との絆も、敵への憎しみも、全てが茶番だった。この灰色の世界で俺がよすがにしてきたもの全てが、砂の城のように崩れていった。
第四章 未来の萌芽
俺はエマのいるテントに戻った。彼女は静かに眠っていたが、その寝顔から漂う甘い香りは、もはや俺を慰めはしなかった。それは、奪われたものの証であり、俺たちの尊厳が踏みにじられた痕跡だった。
「行くぞ」
俺はエマを揺り起こした。彼女は戸惑いの表情を浮かべたが、俺の鬼気迫る目に何かを察したのか、黙って頷いた。俺たちは夜の闇に紛れて、基地を抜け出した。もはや俺たちに、国も、軍も、敵も味方もなかった。あるのは、記憶を商品として弄ぶ、巨大なシステムという共通の敵だけだ。
二人で夜の荒野を、当てもなく歩き続けた。忘却の塵は、ここには届かないようだった。澄んだ夜空には、俺が父の肩車から見上げた時と同じ、無数の星が輝いていた。
「リヒトさん」
隣を歩くエマが、不意に口を開いた。
「私、あなたの隣にいると、不思議と心が安らぐんです。なぜでしょうね」
彼女から、ふわりと林檎パイの香りがした。だが、俺はもうその香りに心を揺さぶられることはなかった。それは偽りの過去だ。移植された、借り物の安らぎだ。
「これから、本物を見つければいい」
俺は言った。エマはきょとんとした顔をしたが、やがて小さく微笑んだ。
その時だった。俺の鼻腔を、新しい香りがくすぐった。それは今まで嗅いだことのない、生まれたての香りだった。朝露に濡れた若草の匂いと、夜明け前の冷たい空気の匂い、そして、すぐ隣にいるエマの温かい肌の匂いが混じり合った、ささやかで、けれど確かな希望の香り。
それは、まだ誰にも奪われていない、名もなき未来の記憶の萌芽だった。
失われた過去を取り戻すことはできないだろう。この狂った世界を変えることも、今はまだ不可能かもしれない。だが、俺たちはもう、ただ奪われるだけの存在ではない。俺はエマの隣で、ゆっくりと息を吸い込んだ。これから二人で創り上げていく、新しい記憶の香りを、この胸に深く刻み込むために。その香りがいつか、絶望に満ちたこの世界で、誰かの心を照らす小さな灯火になることを信じて。