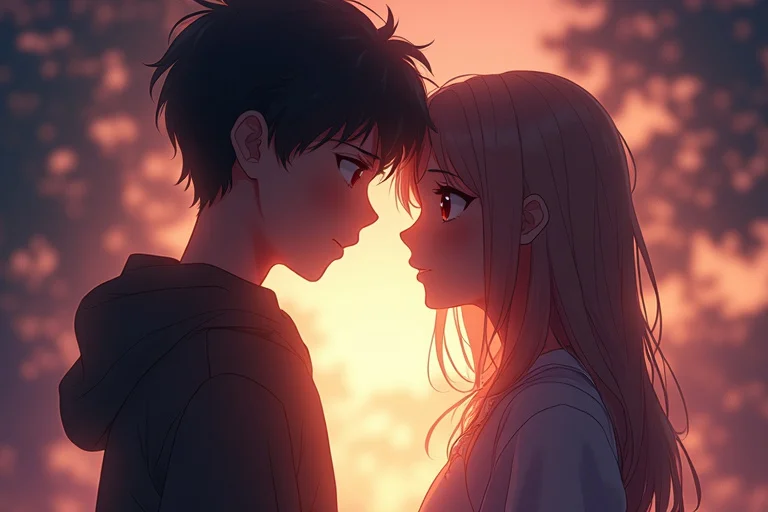第一章 色褪せるカレンダーと防波堤の影
壁に掛かったカレンダーの、八月という数字がやけに色褪せて見えた。俺、向井陽太の18歳の誕生日まで、あと三十四日。この海辺の町で生まれ育った者にとって、それは単なる年齢の節目ではない。「選別の日」へのカウントダウンだ。
この町には、古くからの風習がある。18歳になった者は、「記憶の儀式」を経て、それまでの青春時代の記憶を、たった一つだけを残してすべて失うのだ。どの思い出を選び、自分の核として残すか。それが、その後の人生の道標になるのだと大人たちは言う。彼らは皆、遠い目をして、まるで他人の物語のように自分の青春を語る。その穏やかさが、俺には不気味にさえ思えた。
「で、陽太は決めたのか? 残すメモリ」
放課後のファストフード店。ポテトをつまみながら、友人の健吾が軽薄な口調で訊ねる。俺は飲みかけのシェイクの氷をストローでかき混ぜながら、曖昧に肩をすくめた。
「まだ。つーか、そんな大層な思い出、ねえよ」
嘘だ。本当は、焦っていた。甲子園を目指したわけでも、ステージで喝采を浴びたわけでもない。俺の十七年間は、凪いだ海のように平凡で、取り立てて「これだ」と胸を張れるような、輝かしい瞬間が見つからなかった。皆が未来の自分へ託す宝物を探しているのに、俺の宝箱は空っぽのままだった。
店を出ると、じりじりと肌を焼く西日がアスファルトに長い影を落としていた。健吾と別れ、一人で海沿いの道を歩く。潮の香りが、夏の終わりの気怠さを運んでくる。防波堤に、見慣れた人影を見つけた。
水瀬雫。俺の、幼なじみ。
彼女はスケッチブックを膝に広げ、水平線の向こうをじっと見つめていた。夕陽が彼女の黒髪を赤金色に染めている。声をかけようとして、やめた。彼女の纏う空気が、いつもと違って見えたからだ。それは悲しみとも諦めともつかない、張り詰めた静寂だった。
雫も、俺の一ヶ月後に18歳になる。彼女は、どんな思い出を選ぶのだろう。絵を描くことが好きな彼女は、初めてコンクールで入賞した日の記憶だろうか。それとも、もっと別の、俺の知らない何かだろうか。
俺たちの間には、共有してきたはずの膨大な時間がある。だが、そのほとんどが砂のように指の間からこぼれ落ち、消えていく。残るのは、たった一粒の光る砂金だけ。だとしたら、俺たちが今こうして同じ景色を見ていることにも、果たして意味はあるのだろうか。
虚しさが、波音に混じって胸に満ちてくる。カレンダーの数字が一つ減るたびに、俺の青春が、その価値を問われている気がした。
第二章 刹那を重ねるファインダー
空っぽの宝箱を抱えたままではいられない。焦燥感に駆られた俺は、柄にもなく「最高の思い出作り」に奔走し始めた。夏休み最後のイベントである町内会の夏祭り。その実行委員に立候補し、雫を半ば強引に誘った。
「私が、手伝うことなんて…」
「いいから。お前、絵とか得意だろ。ポスター描いてくれよ」
雫は少し戸惑いながらも、こくりと頷いた。
それから数週間、俺たちの日常はにわかに色づき始めた。放課後の公民館。ペンキの匂いと、仲間たちの笑い声。巨大な看板に背景の夜空を描く雫の横顔を、俺は盗み見ていた。真剣な眼差し、時折口元に付着する青い絵の具。その一つ一つが、今まで見過ごしてきた彼女の新しい魅力だった。
祭りの当日。汗だくで焼きそばを売り、最後の片付けが終わる頃には、空に月が昇っていた。
「花火、始まるぞ」
俺は雫の手を引いて、神社の裏にある小高い丘へと走った。息を切らして辿り着くと、眼下に広がる町の夜景の向こう、ヒュルル、と甲高い音が響く。
次の瞬間、夜空に大輪の菊が咲いた。赤、緑、金色の光の粒子が、闇に吸い込まれるように消えていく。
「綺麗…」
雫がぽつりと呟いた。その声は、花火の音にかき消されそうなほどか細い。俺は、いつか父に借りたままだった古いフィルムカメラを構えた。ファインダー越しに見た雫の横顔は、打ち上がる光に照らされて、泣いているようにも、笑っているようにも見えた。
カシャ、と乾いたシャッター音が響く。
この瞬間だ。俺が残したい記憶は、これかもしれない。初めてそう思った。特別な偉業じゃなくていい。この、どうしようもなく胸が締め付けられるような、雫と二人で見た花火の記憶。それさえあれば、俺は未来を生きていける。
だが、俺の思いが募るほどに、雫は時折、ふっと遠くへ行ってしまうような表情を見せた。彼女のスケッチブックには、町の風景や俺たちの似顔絵に混じって、見たこともない、冷たい幾何学模様のような図形が描かれていることがあった。
「これ、何?」
一度だけ尋ねたことがある。雫は慌ててスケッチブックを閉じ、力なく笑った。
「なんでもないの。ただの、落書き」
その笑顔が、俺たちの間に見えない壁を作っているように感じた。俺は最高の思い出を見つけたと浮かれているのに、彼女はまるで、思い出を作ることを恐れているかのようだった。その理由を、俺はまだ知らなかった。
第三章 スケッチブックの真実
九月に入り、儀式の日が刻一刻と迫っていた。俺は現像した夏祭りの写真を雫に渡そうと、彼女の家を訪ねた。呼び鈴を鳴らしても応答がなく、玄関のドアが少しだけ開いていることに気づく。風だろうか。そっと中へ声をかけると、奥の部屋から雫の母親の嗚咽が聞こえてきた。
「あの子は、どうして…あんな役目を背負わなければならないの…」
胸がざわついた。聞き耳を立てる罪悪感よりも、好奇心と不安が勝る。俺は息を殺し、壁際に身を寄せた。
「…仕方ないだろう。それが水瀬の家に生まれた者の宿命だ。この町の平穏は、あの子が『管理人』としての役目を果たすことで保たれてきた。我々がそうであったように」
静かで、厳格な父親の声。管理人? 宿命? 理解できない言葉の断片が、頭の中で渦を巻く。
その夜、俺は雫を呼び出した。防波堤の上。月明かりが、追い詰められたような彼女の顔を白く照らしていた。
「お前の家で、話を聞いた。管理人って、どういうことだ?」
雫は観念したように、深く息を吸った。そして、震える声で語り始めた真実は、俺の足元を根こそぎ崩壊させるような、残酷なものだった。
「この町の『記憶の儀式』は、ただの風習じゃないの」
彼女の家系、水瀬家は、この町の創設者と共に、町のシステムを管理する「管理人」の一族だった。そして、俺たちが失う青春の記憶は、ただ消えるわけではなかった。
「消された記憶は…この町の生命線を維持するための、エネルギーに変換されるの」
町の穏やかな気候、低い犯罪率、豊かな自然。その全てが、何世代にもわたって捧げられてきた若者たちの「青春」を燃料にして成り立っているというのだ。俺たちが「最高の思い出」と呼んでいたものは、町に捧げるための、最も純度と熱量の高い供物でしかなかった。
「スケッチブックに描いてた模様は…」
「記憶がエネルギーに変換される時のパターン図。効率の良い変換式を、私は小さい頃から学ばされてきた…」
頭を殴られたような衝撃だった。じゃあ、大人たちのあの穏やかさは、記憶を奪われた者の抜け殻の姿だというのか。俺たちの青春は、搾取されるためのただの期間だったのか。
「じゃあ、お前が残す記憶は…」
俺は恐る恐る尋ねた。雫は、俺から目を逸らし、きつく唇を噛んだ。
「私は…陽太くんに出会う前の記憶を選ぶ。たった一人で絵を描いていた、小学校の頃の記憶を」
「な、んで…」
「だって、そうしないと、陽太くんとの思い出が…夏祭りも、花火も、全部、町のエネルギーになってしまうから! そんなの、耐えられない…! それに、陽太くんとの記憶を失くしてしまえば、儀式の後であなたに会っても、私はあなたを傷つけずに済む…」
雫の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
俺は、言葉を失った。俺が宝物だと思っていた時間は、彼女にとっては守るべきものであり、同時に、手放さなければならない呪いでもあったのだ。彼女は俺との思い出を守るために、俺との思い出を消し去ろうとしていた。
楽しかったはずの日々が、一瞬にして悲劇の色に染まる。ファインダー越しに見た彼女の笑顔が、胸の奥で音を立てて砕け散った。
第四章 残響のプロローグ
絶望が、冷たい霧のように全身を包んだ。何もかもが欺瞞だった。だが、雫の涙を見ているうちに、怒りや虚しさを通り越して、別の感情が湧き上がってきた。
儀式の真実がどうであれ、俺たちが過ごした時間は、偽物じゃなかった。胸が高鳴った瞬間も、彼女の笑顔に救われた気持ちも、全てが本物だった。システムがどうだろうと、俺たちの心の動きまで支配することはできない。
「ふざけるなよ」
俺は呟き、雫の肩を掴んだ。
「俺たちの思い出を、そんな悲しいものにさせてたまるか」
雫が驚いて顔を上げる。
「俺は決めた。俺が残す記憶は、『無し』だ。一つも残さない。全部、町にくれてやる」
「だめ! そんなことしたら、陽太くんの中に何も…」
「いいんだよ。全部捧げたって、記憶が消えたって、俺の心が、魂が、お前を覚えているはずだから。いや、覚えているんじゃない。また、見つけるんだ。ゼロになった俺が、ゼロになったお前を、もう一度見つけ出すんだ」
記憶は、過去の記録でしかない。だが、人を惹きつけ、愛おしいと思う感情は、未来へ向かう力だ。
「だから、雫もそうしろ。俺との思い出を、怖がらないで、悲しまないで、全部手放せ。それは供物じゃない。俺たちが、この残酷な町で、もう一度出会うための『約束』なんだ」
俺の言葉に、雫の瞳が揺れた。彼女はしばらく黙っていたが、やがて、こぼれ落ちる涙と共に、小さく、しかしはっきりと頷いた。
儀式の日。俺と雫は、それぞれの場所で、目を閉じた。夏の日の全てを、輝かしい青春の記憶の全てを、惜しみなく手放した。それは、喪失ではなかった。未来への、最も純粋な祈りだった。
数年後。
俺は、見知らぬ海辺の町を歩いていた。なぜこの大学を選び、なぜこの町に惹かれたのか、自分でもよく分からない。ただ、この潮風が、なぜかひどく懐かしいのだ。
駅前の広場。噴水の縁に座ってスケッチブックを広げている女性が、ふと顔を上げた。俺も、なぜか彼女から目が離せなかった。
互いに名前も、過去も知らない。記憶は、何一つない。
けれど、目が合った瞬間、心の奥底で、忘れていた何かが微かに震えた。それはまるで、長い間鳴りを潜めていた弦が、初めて指で弾かれた時のような、か細く、しかし確かな響きだった。
俺たちは、どちらからともなく、小さく微笑み合った。
それは、忘れられた青春の残響か、それとも、これから始まる新しい物語の、静かなプロローグだったのかもしれない。