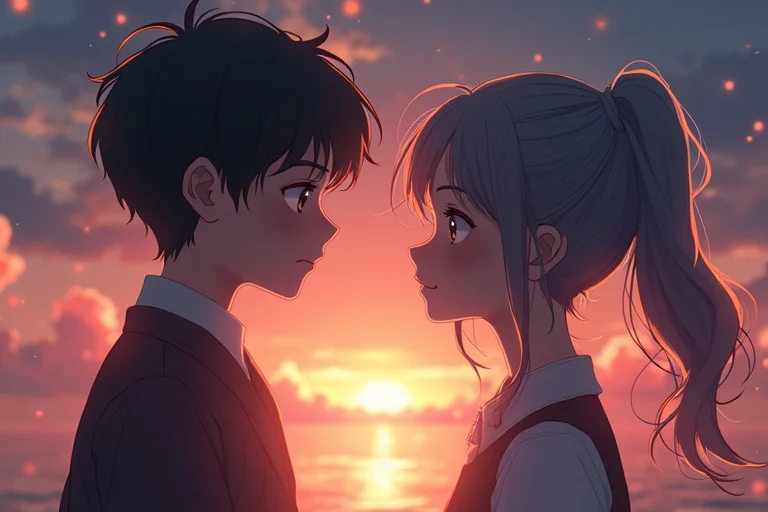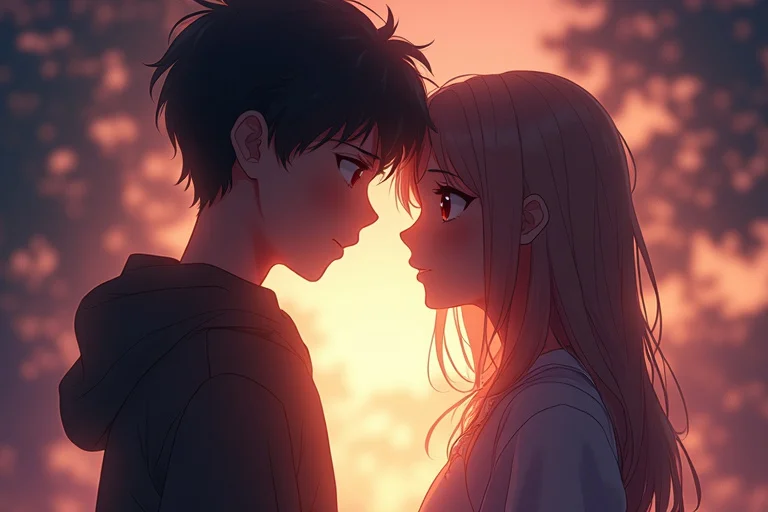第一章 錆びついたブランコの味
僕の青春は、いつも過去の味から始まった。
思春期と呼ばれる時期に差し掛かった頃から、僕、湊の身体には奇妙な変質が起きていた。過去の記憶が、未来の出来事を知らせる予兆として、五感にフラッシュバックするのだ。例えば、明日の天気が雨なら、決まって舌の上に小学校の校庭にあった錆びついたブランコの味が広がる。あの、ひんやりとしていて、どこか血の匂いが混じった金属の味。その予兆は正確で、僕の日常を静かに、そして確実に規定していた。
誰にも言えない秘密だった。友人に話せば気味悪がられるだろうし、親に打ち明けても心配させるだけだ。だから僕は、人との間に薄い膜を一枚張るようにして生きてきた。未来の断片を一人で味わい、一人でやり過ごす。教室の窓から見える空は、いつも少しだけ色褪せて見えた。
その日、僕は放課後の図書室で、忘れられていた一冊の古い詩集を手に取った。ページをめくると、はらりと一枚の栞が床に落ちる。それは何の変哲もない、ただの無地の厚紙だった。けれど、指先で拾い上げた瞬間、ふわりと、記憶にない甘い花の香りが鼻腔をくすぐった。それは過去の記憶ではない、初めての感覚。僕はなぜかその栞に強く惹かれ、制服の胸ポケットにそっとしまい込んだ。
その夜、ベッドの中で目を閉じると、舌の上にあの懐かしい錆の味が広がった。
「……明日も、雨か」
僕は小さく呟き、来るべき灰色の空を思い浮かべながら、眠りに落ちていった。
第二章 硝子越しの未来
翌日の雨は、予兆通りに世界を濡らしていた。バスの窓ガラスを叩く雨粒をぼんやりと眺めていると、不意に、脳裏に鮮烈な光景が映し出された。
――ざあざあと降りしきる雨の中、見知らぬ路地裏で、セーラー服の少女が一人、膝を抱えて泣いている。長い黒髪が頬に張り付き、その肩は小さく震えていた。
それは、僕の記憶ではなかった。僕が体験したことのない、全くの他人の光景。混乱する僕の思考を置き去りにして、そのビジョンは数秒で掻き消えた。あれは一体、何だったんだ?
バスを降り、学校へ向かう途中、ふと路地の奥に小さな光を見つけた。まるで雨粒が陽光を反射して輝いているような、淡い虹色の光。吸い寄せられるように近づくと、そこにはビー玉ほどの大きさの、透き通った結晶が落ちていた。それは「夢の欠片」。この世界では、人々が「初めての喪失」を経験した時、その心が砕けて現実世界に実体化すると言われている。失われた夢や、あり得たかもしれない未来の可能性が、そこに封じ込められているのだという。
僕は恐る恐るその欠片に指先で触れた。その瞬間、先ほど見た少女の、胸が張り裂けそうなほどの悲しみが、冷たい奔流となって僕の心に流れ込んできた。息が詰まる。これが、喪失の痛み。
ポケットの中で、昨日拾った栞が微かに熱を持っていることに気づいた。僕は震える手で栞を取り出し、夢の欠片にかざしてみる。すると、真っ白だったはずの栞の表面に、まるでインクが滲むように、繊細な蔦のような模様が淡く浮かび上がった。
第三章 交錯する残響
その日を境に、僕の世界は一変した。街中に散らばる「夢の欠片」が、僕にだけはっきりと見えるようになったのだ。そして、それに触れるたびに、僕は持ち主である誰かの「喪失の未来」を体験するようになった。野球選手になる夢を怪我で絶たれた少年の未来。大切なペットを失い、雨の日に窓の外を見つめ続ける老人の未来。そのどれもが、どうしようもない哀しみに満ちていた。
そんな中、僕はクラスメイトの陽菜(ひな)の周りに、ひときわ強く輝く「夢の欠片」が漂っていることに気づいた。彼女はいつも明るく、クラスの中心にいるような存在だったが、時折、遠くを見つめるその瞳に、ふと深い影がよぎることがあった。
ある日の放課後、僕は音楽室から漏れ聞こえるピアノの音色に足を止めた。ショパンの『別れの曲』。その旋律は、あまりにも切なく、胸を締め付けた。そっと扉の隙間から中を覗くと、陽菜が鍵盤の上に指を置いていた。だが、弾いてはいない。ただじっと、鍵盤を見つめているだけだった。彼女の足元には、あの強い光を放つ「夢の欠片」が落ちている。
僕は衝動的に、その欠片に手を伸ばした。
途端に、激しい未来視が僕を襲う。
――横断歩道。けたたましいブレーキ音。宙を舞うカバン。そして、動かなくなった陽菜の手。その指先は二度とピアノを弾けないほどに傷つき、病院のベッドで声を殺して泣く彼女の姿が、僕の網膜に焼き付いた。
これは、これから起こる未来。陽菜がピアニストになるという夢を、完全に「喪失」する瞬間の記憶。僕は全身から血の気が引くのを感じた。このままでは、陽菜が。
第四章 可能性に印を
翌日、僕の舌には、焦げ付いたトーストの味がこびりついていた。それは僕の過去の記憶の中で、最も強烈な「失敗」と「後悔」を象徴する味だった。陽菜に起こる悲劇の、最終通告のように思えた。
僕は一日中、陽菜から目を離さなかった。彼女の行動を追い、あの未来視で見た横断歩道に彼女が近づかないよう、それとなく声をかけ、引き留めた。だが、運命の糸は、まるで僕を嘲笑うかのように、彼女をその場所へと導いていく。
下校時刻。陽菜が友人たちと別れ、例の横断歩道に差し掛かった。信号が青に変わる。彼女が足を踏み出した、その瞬間。一台のトラックが、信号を無視して猛スピードで角を曲がってきた。
「危ない!」
僕は全てを忘れて駆け出し、陽菜の腕を強く掴んで歩道側へ引き寄せた。トラックが、僕たちの数センチ先を轟音と共に走り抜けていく。
その刹那、僕の意識は弾け飛んだ。
陽菜の未来視だけではない。街中の、いや、世界中の無数の「夢の欠片」から、ありとあらゆる人々の「喪失の未来」が、巨大な津波となって僕の中に流れ込んできたのだ。絶望、後悔、悲嘆、諦め。膨大な負の感情が僕を飲み込もうとする。意識が闇に沈みかける中、僕は胸ポケットの栞を、最後の希望のように強く握りしめた。
――まだ、終わらせない!
僕は心の中で叫んだ。この悲劇的な未来に、陽菜が笑顔でピアノを弾く、たった一つの「可能性」に、印をつけるんだ!
栞が、胸元で太陽のようにまばゆい光を放った。無地だった表面に刻まれた模様が、一瞬にして複雑で美しい紋様へと変化する。僕の脳裏で、泣き崩れる陽菜の未来が、コンサートホールの喝采の中で微笑む彼女の未来へと、鮮やかに書き換わった。
しかし、その光景を最後まで見届けることなく、僕の身体は力を失い、その場に崩れ落ちた。
第五章 世界が忘れた喪失
目を覚ますと、そこは学校の保健室だった。窓の外は、もう茜色に染まっている。
「……湊くん」
心配そうな顔で僕を覗き込んでいたのは、陽菜だった。彼女の指には、包帯一つ巻かれていない。
「ありがとう。湊くんが、助けてくれたんだね」
僕はゆっくりと身体を起こし、倒れる直前に見た光景を、途切れ途切れに陽菜へ話した。無数の人々の喪失の未来。それが個人のものではなく、まるで巨大な一枚の絵を構成する、無数の小さなピースのように感じられたこと。
陽菜は静かに僕の話を聞いていたが、やがてぽつりと言った。
「それ、わかる気がする。私ね、事故で指を怪我するのが怖くて、コンクールに出るのを諦めようとしてたの。夢を失うのが怖くて、自分から夢を捨てようとしてた。……みんな、そうなのかも」
彼女の言葉に、僕ははっとした。そうだ。この世界に生きる人々は、いつからか未来に希望を抱くことをやめていた。失敗を恐れ、喪失を恐れ、挑戦する前に諦めてしまう。空はいつも色褪せて見え、世界は緩やかな諦念に満ちていた。
僕たちが見ていた無数の「喪失の未来」は、個人のものではない。この世界全体が、かつて経験した一つの「大きな喪失」の残響なのだ。それは「未来は無限の可能性に満ちている」という、誰もが当たり前に持っていたはずの輝かしい感覚そのものの喪失。
僕の特異な能力も、街に溢れる「夢の欠片」も、すべてはその失われた世界の「青春」を取り戻すための予兆だったのだ。
第六章 新しい空の青
「終わらせるんじゃなくて、始めるんだ」
僕は、光の羅針盤のように複雑な模様が刻まれた「可能性の栞」を手に、陽菜に言った。彼女は強く頷き返した。
僕たちは学校の屋上へ向かった。夕暮れの光が、世界中に散らばる無数の「夢の欠片」をきらきらと輝かせている。僕は栞を空高くかざした。
「行け!」
僕の意志に応えて、栞は金色の光を放った。その光は僕の身体を媒介にして、世界中の「夢の欠片」と共鳴し始める。街角から、遠い国から、忘れられた場所から、光の粒となった無数の喪失の記憶、叶わなかった未来、可能性の残響が、僕の元へと集まってくる。
それは凄まじい情報の奔流だった。けれど、もう怖くはなかった。一つ一つの喪失には、それと同じだけの強い「願い」が込められていることを知っていたから。僕の身体の中で、それらが溶け合い、混ざり合い、一つの巨大な「青春の可能性」へと昇華していくのを感じた。
僕の身体から、未来を予兆する力は完全に消え去っていった。代わりに、温かくて力強い何かが、心の奥深くに満ちていく。
やがて光が収まった時、世界は生まれ変わっていた。街行く人々の表情が、どこか晴れやかになっている。空を見上げ、忘れていた夢を思い出したかのように、小さく微笑んでいる。淀んでいた空気が澄み渡り、世界の輪郭が鮮やかになったようだった。
僕の隣で、陽菜が息を呑む。
「ねえ、湊くん。これから、どんな曲を弾こうか?」
その声は、未来への喜びに満ちていた。
僕はもう、錆びついたブランコの味を感じることはないだろう。けれど、失ったものよりも遥かに大きなものを得た。それは、統合された無数の未来の「可能性」を内包した、全く新しい青春そのものだった。
陽菜の手を取り、空を見上げる。そこには、今まで見たことのないほどに鮮やかで、どこまでも続く、無限の可能性を秘めた青が広がっていた。