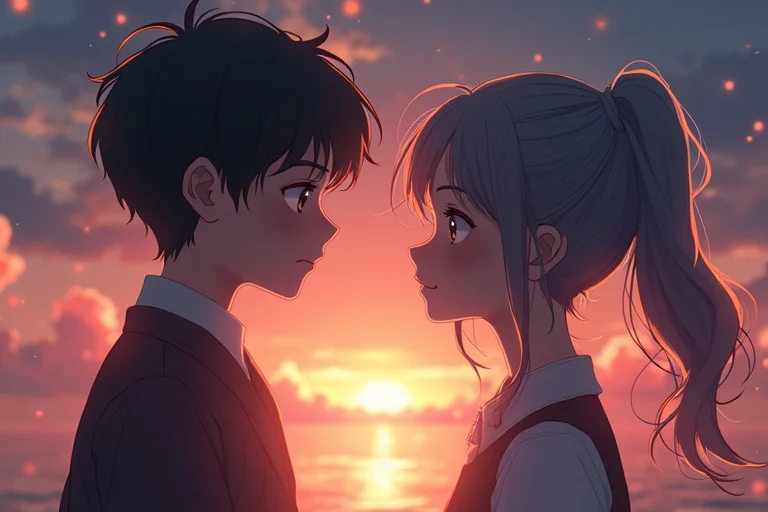第一章 色褪せたファインダー
僕の目は、カメラのレンズを通してしか世界を正しく捉えられない。
校舎の屋上、金網の向こうに広がる街は、初夏の淡い光に溶けて、まるで古い映画のワンシーンのようだった。僕は愛用のミラーレスカメラを構え、絞り(アペルтура)を調整する。カチ、カチ、と小気味よいダイヤルの音が、僕と世界との唯一の接点だった。
「水野くんって、いつも何か撮ってるよね」
不意に背後からかけられた声に、僕はファインダーから目を離した。クラスメイトの月島陽菜が、弁当箱を片手に屈託なく笑っていた。風に揺れる彼女の髪が、キラキラと光を乱反射させる。僕はその一瞬を切り取りたい衝動に駆られたが、慌ててカメラを下ろした。
「……記録、だから」
「記録?」
「うん。撮っておかないと、忘れちゃうから」
僕の言葉に、彼女は「あー、わかる!私もすぐ忘れちゃうもん」と大げさに頷いた。違うんだ、月島さん。君の『忘れちゃう』と、僕のそれは、深海と水たまりくらい違う。でも、それを説明する言葉を僕は持たなかった。僕にとって記憶とは、SDカードに保存されるJPEGデータであり、暗室で像を結ぶ銀塩の粒子だ。それ以外の記憶は、数日もすれば陽炎のように揺らぎ、跡形もなく消え去ってしまう。原因不明の、特殊な記憶障害。それが僕の世界のすべてだった。
だから僕は撮り続ける。通学路の曲がり角に咲く紫陽花。教室の窓から見える雲の形。購買で買ったクリームパンの甘い匂い。それらすべてを写真に収めなければ、僕の昨日は空白になってしまう。人との繋がりも同じだ。友達との他愛ない会話も、一緒に笑った瞬間も、撮らなければ存在しなかったことになる。それはまるで、永遠に満たされることのない渇きだった。
数日後の放課後、廊下で陽菜に呼び止められた。
「水野くん!大変!先週の土曜に駅前で話したカフェ、覚えてる?今度の日曜で閉店なんだって!最後に行かない?」
陽菜の目は期待に輝いていた。僕は彼女の言葉を反芻する。先週の土曜日。駅前。カフェ。僕の頭の中のデータベースを検索するが、該当するデータはどこにもなかった。その日のフォルダは、街猫の写真と古本屋のショーウィンドウだけで埋まっている。彼女と会った記憶はない。つまり、僕はその瞬間を撮らなかったのだ。
「……ごめん。覚えてない」
僕がそう告げた瞬間、陽菜の顔から光が消えた。笑顔が固まり、瞳が戸惑いに揺れる。
「え……?うそ。だって、30分くらい立ち話したじゃない。私が読んでた小説の話で、すごく盛り上がったのに……」
「……悪いけど、本当に思い出せないんだ」
嘘じゃない。僕にとってはそれが真実だった。しかし、彼女にとっては、共有したはずの時間が一方的に消去されたのと同じことだ。彼女は何かを言いかけて、唇を噛み、そして悲しそうに俯いた。「そっか……ごめん、変なこと言っちゃった」。そう言って走り去っていく彼女の背中を、僕はカメラを握りしめたまま、ただ見送ることしかできなかった。シャッターを切る資格など、僕にはない気がした。
第二章 二人だけの秘密
あの日以来、陽菜は僕を避けるようになった。教室で目が合っても気まずそうに逸らされ、廊下ですれ違っても、彼女は友人との会話に夢中なふりをした。失われた時間は、僕たちの間に透明で分厚い壁を作ってしまった。僕は、陽菜との間に生まれた小さな繋がりを、自分のせいで断ち切ってしまったことが苦しかった。彼女のあの悲しそうな顔が、撮ってもいないのに、なぜか脳裏に焼き付いて離れなかった。
このままではいけない。そう思った僕は、放課後、写真部の部室で一人作業をしていた彼女を訪ねた。暗室の赤いセーフライトだけが灯る静かな空間。現像液のツンとした匂いが鼻をつく。
「月島さん」
僕の声に、彼女の肩が小さく跳ねた。
「……何か用?」
「この前のこと、謝りたくて。それと……話したいことがあるんだ」
僕は、自分の秘密を打ち明ける覚悟を決めていた。僕の記憶障害のこと。写真に撮らなければ、すべてを忘れてしまうこと。君との会話を覚えていなかったのは、決して軽んじていたからではないこと。言葉を選びながら、僕は静かに語り始めた。
話終えると、長い沈黙が落ちた。陽菜は、現像バットに浮かぶ印画紙を、じっと見つめていた。やがて、彼女は顔を上げ、僕の目をまっすぐに見た。その瞳は、戸惑いではなく、深い理解の色を湛えていた。
「じゃあ、水野くんの世界は、全部写真でできてるの?」
「……まあ、そんな感じかな」
「大変、だったね。ずっと、一人で」
彼女のその一言に、心臓を鷲掴みにされたような衝撃が走った。これまで誰にも同情されたいとは思わなかった。これは僕が背負うべき現実だと、諦めていたからだ。しかし、彼女の言葉は、僕がずっと無意識に隠してきた孤独の鎧を、いともたやすく剥がしてしまった。
僕は彼女を自分の部屋に招いた。壁一面を埋め尽くす、コルクボードに貼られた無数の写真。日付と短いメモが添えられた、僕の生きてきた証。陽菜は一枚一枚を、まるで大切な宝物を見るかのように、ゆっくりと目で追っていた。
「すごい……。全部、水野くんの記憶なんだね」
彼女はふと、一枚の写真の前で足を止めた。それは、僕が何気なく撮った、教室の窓辺に置かれた小さなサボテンの写真だった。
「このサボテン、覚えてる。私がクラスの緑化委員で持ってきたやつだ。水やり、サボってたのに、誰かさんが毎日お水あげてくれてたんだよね。もしかして……」
僕にはサボテンを撮った記憶しかない。誰が持ってきたのかも、水をあげた記憶も、データとしては存在しない。だが、陽菜の言葉を聞いた瞬間、写真の中のサボテンが、急に温かい意味を持って輝き始めた気がした。
「ねえ、水野くん」と、陽菜が振り返った。「一つ、提案があるんだけど」
彼女は悪戯っぽく微笑んだ。
「今度の日曜日、カメラなしで出かけてみない?私が、蒼くんの記憶になってあげる。私が全部覚えてて、いつでも話してあげる。だからさ、一度だけでいいから、レンズを通さない世界を、私と一緒に見てみない?」
蒼くん、と彼女は初めて僕を名前で呼んだ。その響きは、僕の心に柔らかな波紋を広げた。カメラのない一日。それは、僕にとって記憶が空白になることを意味する。恐ろしい提案のはずなのに、不思議と胸が高鳴っていた。
第三章 シャッターを切らない午後
日曜日の空は、まるで絵の具を溶かしたように青かった。僕は、いつも首から提げているはずのカメラを家に置いてきた。ストラップの重さがない首筋が、なんだか心もとない。待ち合わせ場所に現れた陽菜は、僕の姿を見ると、満足そうに笑った。
「身軽でしょ?」
「うん。でも、少し不安だ」
「大丈夫。私がいるから」
僕たちは、陽菜が立てた計画通りに街を歩いた。大きな水槽を悠々と泳ぐジンベイザメ。潮の香りがする薄暗い空間で、陽菜は子供のようにはしゃいだ。僕は、ファインダー越しではない彼女の笑顔を、ただ目に焼き付けようと必死だった。シャッターチャンスを逃す焦りも、構図を考える癖も、今は忘れたかった。
公園のベンチでアイスを食べた。溶けたアイスが陽菜の指を伝うのを、僕たちは顔を見合わせて笑った。夕暮れの丘の上で、街がオレンジ色に染まっていくのを黙って眺めた。陽菜が小さく歌う鼻歌が、優しい風に乗って耳に届く。すべてが、今まで僕が見てきた世界とはまるで違って見えた。鮮やかで、温かくて、少しだけ切ない。忘れてしまうかもしれない恐怖よりも、今この瞬間を彼女と共有している喜びが、確かに勝っていた。生まれて初めて、「忘れてもいい」と思えるほど、幸福な時間だった。
帰り道、駅のホームで電車を待っている時だった。陽菜がバッグから、色褪せた一枚の写真を取り出した。
「蒼くん、これ」
渡された写真には、日焼けした二人の子供が写っていた。向日葵畑の前で、大きな麦わら帽子をかぶった男の子と、ワンピース姿の女の子が、歯の抜けた笑顔でピースサインをしている。男の子の顔は、紛れもなく幼い頃の僕だった。そして、隣で笑う女の子は――。
「私たち、小学生の時からずっと一緒だったんだよ」
陽菜は、静かに言った。
「蒼くんは、小五の時の夏、交通事故に遭ったの。頭を強く打って……それから、少しずつ昔のことを忘れちゃうようになった。私のことも、全部」
頭を殴られたような衝撃だった。僕が必死に記録してきた日々の、その始まりよりもずっと前に、僕たちの物語は始まっていたというのか。
「高校で再会した時、蒼くんは私のこと、全然覚えてなかった。だから、初めましてのフリをしたの。もう一度、友達になりたくて」
陽菜の声は、少し震えていた。
「この前、駅前で会ったこと覚えてないって言われた時、すごく悲しかった。……でもね、それは、それが初めてじゃなかったからなんだ」
僕が失った記憶。僕が空白だと思っていた過去。そこには、いつも陽菜がいた。僕が忘れてしまった時間の中で、彼女はずっと一人で僕たちの思い出を守ってくれていたのだ。僕が追い求めてきた「記録」は、なんて不完全で、身勝手なものだったのだろう。一番大切なピースが抜け落ちたままの、ガラクタの集まりじゃないか。足元から世界が崩れていくような感覚に、僕はただ立ち尽くすことしかできなかった。
第四章 君という名の光
自分の部屋に戻り、壁一面の写真を前に呆然と座り込んだ。僕が築き上げてきた記憶の城は、脆くも崩れ去った。一枚一枚の写真は、もはや真実の一部を切り取った断片でしかなかった。陽菜という光を失った、色褪せた記録の集積。親に問いただすと、陽菜の話はすべて事実だった。事故のこと、記憶障害のこと、そして、僕が陽菜を忘れてしまったことも。
翌日、僕はカメラを手に、陽菜を探した。彼女は、あの夕焼けの丘に一人で座っていた。僕の足音に気づくと、驚いたように振り返る。
「ごめん」
僕が最初に発した言葉は、それだけだった。
「僕が忘れていた時間、君はずっと一人で……」
「ううん」と陽菜は首を振った。「蒼くんが悪いわけじゃない。それに、私、忘れてなかったから。蒼くんと過ごした時間、全部ここに覚えてるから」
そう言って、彼女は自分の胸をトンと叩いた。その仕草が、あまりにも切なくて、愛おしかった。
僕はカメラを構えた。でも、レンズを向けたのは彼女の顔ではなかった。僕は、僕たちの間に置かれた陽菜の白くて小さな手を、ファインダーに収めた。そして、そっと自分の手を、その隣に置いた。
「これからは、写真のために生きるのはやめる」
僕は、ファインダーを覗いたまま言った。
「君と一緒にいる、この瞬間のために撮る。たとえ明日、今日のことを忘れてしまっても、この写真を見れば、僕がどれだけ幸せだったか、きっとすぐに思い出せるから。この温かい気持ちを、未来の自分に繋ぐために」
カシャッ。
乾いたシャッター音が、丘の上に響き渡った。写真に写っていたのは、二つの不器用な手と、その背景に広がるどこまでも優しい夕焼けの空。それは、僕が初めて「記憶」ではなく「感情」を記録した一枚だった。
それから数年が経った。僕の部屋の壁には、新しい写真が少しずつ増えていった。二人で笑い合う写真。喧嘩してそっぽを向いている写真。何気ない日常を切り取った、たくさんの写真。僕は時々、過去の記憶の詳細を思い出せなくなることがある。でも、そんな時は決まって、隣にいる陽菜が「あの時はね」と、楽しそうに物語を語ってくれる。
僕の記憶は、今も不確かで脆い。写真がなければ、多くの出来事は風化してしまうだろう。
だけど、それでいいんだ。ファインダーの向こう側には、いつも君という名の光がいてくれる。写真が呼び覚ます温かい感情と、君が語ってくれる物語が、僕の世界を彩ってくれる。僕の不完全な記憶は、君といることで、ようやく一つの完璧な物語になるのだから。