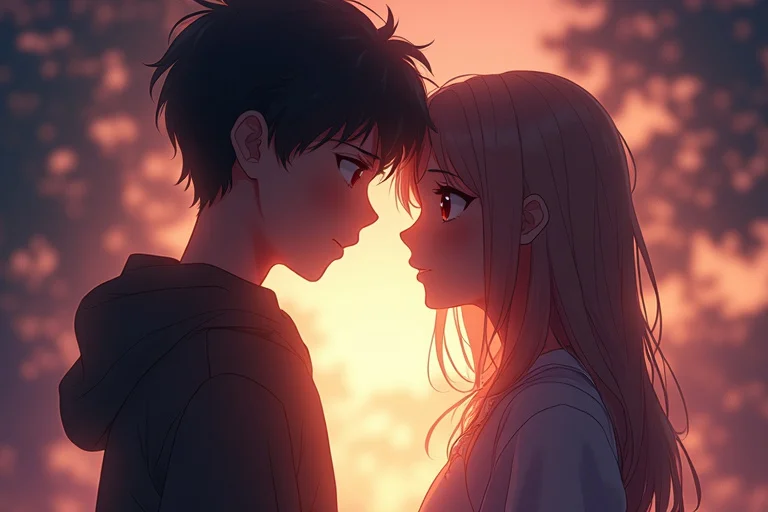第一章 幻影の羅針盤
僕、瀬戸悠の目には、他人の未来が見える。いや、正確には「未来の選択肢が織りなす可能性の光の軌跡」が見える、といった方が正しいだろう。ある友人がクラスメイトに告白するかどうか迷えば、彼の頭上には二つの光の筋が揺らめく。一つは成功の輝かしい未来へ、もう一つは残念ながら友情の停滞へと続く。それはまるで、世界を覆う巨大な羅針盤のようで、人々はその光に導かれるか、あるいは逆らって新たな軌跡を創り出す。僕自身は、その光が示す選択の多さにうんざりしていた。あまりにも多くの可能性が、あまりにも多くの未来が、僕らを振り回すように見えたからだ。僕自身の未来だけは、常に薄い霧に包まれていて、はっきりと見定めることができない。それが、僕をどこか無気力にさせていた。どうせ見えないなら、考えたって仕方ない。そう諦めていた。
新学期のざわめきが満ちる教室の扉が開かれ、担任が新しい転校生を紹介した。
「天宮瑞葉さんだ。みんな仲良くするように」
一歩前に出た少女は、背筋をピンと伸ばし、しかし視線は床に落としたままだった。肩にかかる黒髪は、微かな光さえ吸い込んでしまうかのように艶やかで、白い肌との対比が印象的だ。教室の視線が一斉に彼女に集まる。その瞬間、僕は息を呑んだ。
彼女の周囲には、一切の光の軌跡が見えないのだ。
今まで誰一人として、こんなことはなかった。人間が発する感情や思考が未来の選択肢となり、それが光として具現化する。それが僕の世界の常識だった。しかし、天宮瑞葉からは、まるで存在そのものが未来を拒絶しているかのように、何も見えなかった。彼女は、光の羅針盤が指し示す世界から、完全に隔絶された場所にいるようだった。
僕は釘付けになった。なぜだ? なぜ彼女には光が見えない? 彼女の未来は真っ白なのか? それとも、あまりにも強烈な光すぎて僕には認識できないのか?
瑞葉はほとんど声にならないような小さな声で「天宮瑞葉です。よろしくお願いします」と挨拶を済ませると、担任が指定した窓際の席へと向かった。そこは、僕の隣の席だった。
透明な空気が、彼女の周りだけを切り取ったように流れる。僕の視線を感じたのか、瑞葉はちらりと僕の方を見た。その瞳は、深淵の闇を湛えているかのように、何も映していなかった。僕は咄嗟に視線を逸らしたが、心臓の鼓動は早鐘を打っていた。僕の無気力な日常に、突然、巨大な石が投げ込まれたような感覚だった。
第二章 透明な少女の影
瑞葉は、クラスの中で浮いた存在だった。決して悪意を持って無視されているわけではない。ただ、彼女自身が周囲との間に透明な壁を築いているようだった。質問されても簡潔に答え、それ以上言葉を続けることはない。休憩時間には、誰とも目を合わせず、ただ静かに窓の外を見つめていた。その姿を見ていると、僕の胸の奥に、何か微かな痛みが走った。
僕は瑞葉の隣に座りながらも、彼女から放たれる「光の不在」にずっと囚われていた。彼女が筆記具を取る時、ページをめくる時、その一つ一つの動作に、何の可能性の光も見えない。それはまるで、既に全ての未来が確定しているか、あるいは全く未来が存在しないかのようだった。
ある日、昼休みに屋上へ向かう途中、僕は瑞葉が一人で図書室の隅に座っているのを見かけた。開かれているのは、古い星図の本。僕は吸い寄せられるように彼女に近づいた。
「天宮さん、星が好きなんですか?」
瑞葉は顔を上げ、驚いたような表情を見せた。次の瞬間、彼女の瞳に一瞬だけ、微かな光が宿ったように見えたが、すぐに消えた。
「…昔から」と、か細い声が返ってきた。
「僕も、星を見るのは好きです。ただ、星空を見上げると、自分の存在がちっぽけに感じられて、どうでもよくなっちゃうこともありますけど」
僕は少し自嘲気味に笑った。瑞葉は何も言わず、ただ僕の言葉に耳を傾けている。その沈黙が、居心地悪くはなかった。
「天宮さんは、どうですか? 星を見ていると、何を思いますか?」
瑞葉は再び星図に目を落とし、細い指で一つの星座をなぞった。
「…星は、いつか消えてしまうのに、それでも輝き続ける。遠い過去の光を、今、見ている。…それだけ」
彼女の言葉は、まるで彼女自身を映し出しているかのようだった。過去の光に囚われ、未来が見えない。いや、見ないようにしているのだろうか。
瑞葉との短い会話は、僕の心を少しずつ揺り動かしていった。これまで自分の未来が見えないことに絶望し、何も選ぼうとせず、ただ流されるまま生きてきた僕だったが、瑞葉の「光の不在」は、僕のその諦めを許さないような気がした。彼女の空白は、僕に「何か」を求めるように突き刺さった。彼女の未来の光が見えない理由を知りたい。その渇望が、僕の中に新たな熱を生み出していた。それは、僕自身の未来の霧を晴らす、かすかな光になるかもしれない、と。
第三章 消された未来の残像
瑞葉との距離は、少しずつ縮まっていった。言葉数は少ないものの、僕が話しかければ、彼女は耳を傾けてくれた。僕は彼女に、僕の能力のこと、そして彼女から光が見えないことがどれほど僕を戸惑わせているかを、正直に話した。瑞葉は驚いた様子もなく、ただ静かに聞いていた。
「僕の目には、人々の可能性が光として見えるんです。選ばれるかもしれない未来が、幾重もの光の筋として。でも、天宮さんにはそれが全く見えない。まるで、あなたの未来がどこにもないみたいに…」
瑞葉は、ゆっくりと顔を上げた。その瞳は、何かを諦めたような、それでいて深い悲しみを湛えていた。
「それは…私が、そうしてしまったから」
僕の心臓が、大きく跳ねた。
「どういうことですか?」
瑞葉は唇を噛みしめ、視線を逸らした。その表情は、今にも崩れ落ちそうなほど弱々しかった。
その日の放課後、瑞葉は急に体調を崩した。顔色は真っ青で、汗が滲んでいる。養護教諭の先生に連れられ、保健室へと向かう彼女の背中を、僕はただ茫然と見送るしかなかった。その夜、彼女から連絡があった。病院に運ばれ、しばらく入院することになったという。
僕は居ても立ってもいられず、病院へ向かった。病室のドアを開けると、瑞葉は点滴につながれ、眠っていた。その枕元に、数冊の本が積んである。そのうちの一冊が、僕が以前見た星図の本だった。その中に挟まっていた一枚の小さな写真が、僕の目を引いた。
それは、中学時代の僕が、満面の笑みで陸上競技のユニフォームを着て、表彰台に立っている写真だった。その隣には、瑞葉が、やはりユニフォーム姿で、しかしどこか不安げな表情で微笑んでいる。僕の記憶にはない光景だ。僕は陸上部ではなかった。中学時代、僕は受験勉強に専念していたはずだ。どうして?
その写真の裏には、震えるような文字でこう書かれていた。
「ごめんなさい、悠。あなたの輝かしい未来を…私が」
その時、かすかに目を開けた瑞葉が、僕の視線に気づいた。彼女の瞳には、再び深い悲しみが宿っていた。
「瀬戸くん…見てしまったの?」
彼女の震える声が、僕の頭の中で反響した。
「この写真…どういうことなんですか? 僕、陸上なんて…」
瑞葉はゆっくりと体を起こし、力なく微笑んだ。
「ごめんなさい、悠。私は…未来を消すことができるの。あなたの…輝かしい未来を、消してしまった」
僕は目の前が真っ白になった。未来を、消す? そんな馬鹿な。
「僕は…高校受験の年に、陸上部の全国大会で優勝するはずだった。そして、スポーツ推薦で名門高校に進学し、将来は世界を舞台に活躍する…はずだったの」
瑞葉の言葉は、僕の胸に鋭いナイフのように突き刺さった。そんな未来、僕には全く見えなかった。僕の未来は、いつも霧に包まれていた。
「でも、その輝かしい未来の先に、あなたの人生を決定づける…あまりにも大きな悲劇が待っているのが見えたの。私は…私はそれをどうしても避けたくて、耐えられなくて…」
彼女の目に大粒の涙が溢れた。
「だから、その悲劇に繋がる『輝かしい未来』を、私が消してしまったの。過去の選択を書き換えるように、ね。その代償として、私の未来は…」
瑞葉は言葉を詰まらせ、自分の手を見つめた。僕の目には、彼女から一切の光が見えない。その理由が、今、恐ろしいほど明確に理解できた。彼女は、他者の未来を消す代わりに、自分自身の未来の光を全て失ってしまっていたのだ。僕の、失われたはずの「輝かしい未来」の残像が、僕の脳裏に焼き付いた。僕の無気力は、誰かに与えられたものだったのか。僕の「霧」は、誰かの善意によってかけられたものだったのか。
僕の価値観は、根底から揺らぎ、崩れ落ちた。
第四章 選択を越える光
病室には、重い沈黙が降り注いでいた。僕の心の中では、激しい嵐が吹き荒れている。怒り、絶望、そして裏切り。自分の人生の最も輝かしい可能性が、誰かの手によって奪われていたという事実。僕は瑞葉を強く睨みつけた。
「どうしてそんなことをしたんですか! 僕の人生なのに、どうして勝手に…!」
僕の震える声に、瑞葉は顔を伏せ、嗚咽を漏らした。
「ごめんなさい…ごめんなさい…! でも、私には見えてしまったの。あなたがその道を選んだ先に、どれほど辛く、取り返しのつかない出来事が待っているか。大切な人を失い、自分自身も傷つき、それでもがくあなたの姿が…」
彼女は顔を上げ、涙で濡れた瞳で僕を見つめた。その瞳の奥には、僕がこれまで見たこともないほどの苦痛が宿っていた。
「私には…あなたをその悲劇から守ることしか、できないと思ったの。それが、私の能力が持つ唯一の意味だと…だから、その悲劇に繋がる全ての選択肢の光を、私は消し去った。あなたは、陸上を諦めて、普通に受験勉強に励んだ。それは、私にとって…苦渋の選択だった。あなたから光を奪うことだって、分かっていたから」
瑞葉の言葉は、僕の怒りを少しだけ冷やした。僕の未来を奪った彼女の行為は許しがたい。しかし、その行為の裏にあった、彼女の深く、純粋な「善意」と「苦悩」もまた、僕の胸に痛いほど響いた。彼女は僕を守るために、自分自身の未来の光を犠牲にしていたのだ。
「…その代償に、あなたは自分の未来を失ったって言うんですか?」
瑞葉は小さく頷いた。
「もう、私の目には何も見えない。どの選択をしても、同じ。だから、私は自分の未来に何の光も持たない。ただ、あなたの…消し去った未来への後悔だけを抱えて、ここにいる」
僕の心の中で、怒りと悲しみが複雑に絡み合った。僕の人生は、彼女の勝手な判断によって変えられた。それは事実だ。しかし、彼女の目に映った悲劇の未来と、それを回避しようとした彼女の必死な想いを考えると、僕は彼女を責め続けることができなかった。
僕が見ていた光の羅針盤は、あくまで「可能性」を示すものだった。瑞葉は、その可能性の「最悪のシナリオ」を回避するために、自らの未来を犠牲にした。それは、僕の知っていた「未来は自分で選び取るもの」という信念を、根本から揺るがす出来事だった。
しかし、同時に僕は理解した。瑞葉がそうしたのは、他でもない「僕のため」だったのだと。彼女は、僕の知らなかった、僕自身の可能性と、その先の悲劇の両方を見て、深い絶望の中で決断を下したのだ。彼女の孤独、彼女が背負っていた重荷が、僕の胸に強く迫ってきた。
僕の無力感は、未来が見えないことではなく、自分の未来を他者に操作されたことによって、さらに深まるはずだった。だが、なぜだろう。瑞葉の告白を聞いた瞬間から、僕の中の「霧」が、少しだけ薄れたような気がした。
第五章 交差する未知の道
病室の窓からは、夕焼けに染まる空が見えていた。茜色から藍色へとグラデーションをなす空は、まるで僕と瑞葉の心のようだった。僕は、失われた未来を嘆くのではなく、今ここにある瑞葉との繋がりに意識を集中させた。
「僕の未来を消したこと、本当に後悔していますか?」
瑞葉は目を伏せ、小さく頷いた。
「後悔している。だって、あなたから輝かしい可能性を奪ってしまったから。でも…あの時の私には、それが最善だと思えた。あなたを傷つけたくなかった」
彼女の言葉は、まるで千切れるほど細い糸のように、僕の心臓に絡みついてきた。
「なら、これからは、僕の未来も、あなたの未来も、自分で選びましょう」
僕は瑞葉の手を握った。彼女の手は、驚くほど冷たかった。
「たとえ、光が見えなくても、選び続ける。それが、僕たちが今できることじゃないですか? 自分の人生を、自分の足で進むこと。それが、僕があなたと出会って、ようやく見つけた答えです」
瑞葉の瞳に、再び涙が溢れた。今度は、悲しみだけではない、何か温かい光が宿っているように見えた。彼女の唇が、ゆっくりと微笑みを形作った。それは、僕が初めて見た、偽りのない彼女の笑顔だった。
「うん…そう、だね」
僕の目には、瑞葉の周囲に、いまだ未来の光の軌跡は見えない。しかし、僕と瑞葉が手を取り合った瞬間、僕の視界が大きく変わった。これまで見てきた個々の選択肢を示す光ではなく、僕たちの足元から、淡く、しかし確かな光が螺旋を描きながら天へと昇っていくのが見えたのだ。それは、特定の目的地を示す光ではない。いくつもの可能性が絡み合い、二人が共に歩むこと自体が創り出す、無限の未来を象徴する光の螺旋だった。
それは、瑞葉が未来を操作する能力を持つ必要も、僕が他者の光に導かれる必要もない、僕たち自身の道だった。未来は、決して確定されたものではなく、今この瞬間、自分たちの手で創り上げていくものなのだ。失われた可能性を悔やむのではなく、残された空白を、二人で埋めていく。
瑞葉の冷たい手が、少しだけ温かくなった気がした。僕たちの青春は、見えない未来に怯えるものではもうない。光の軌跡なき道を、手を取り合って進む、未知の旅なのだ。あの螺旋の光は、僕たちが選び続ける限り、消えることはないだろう。