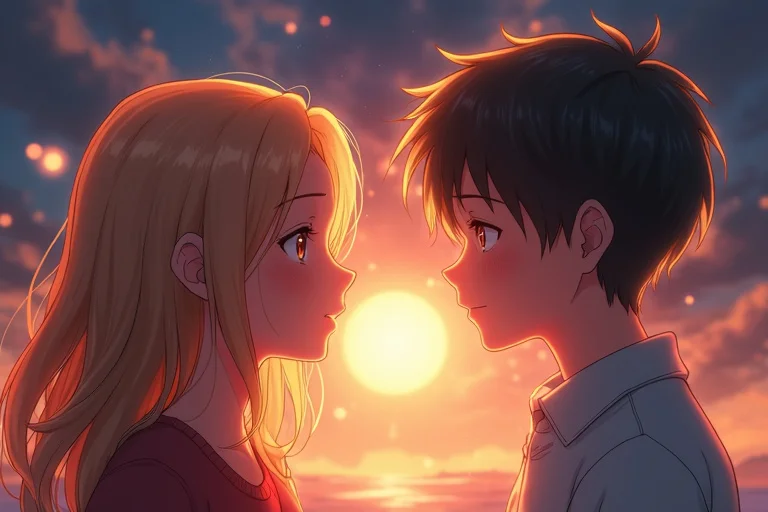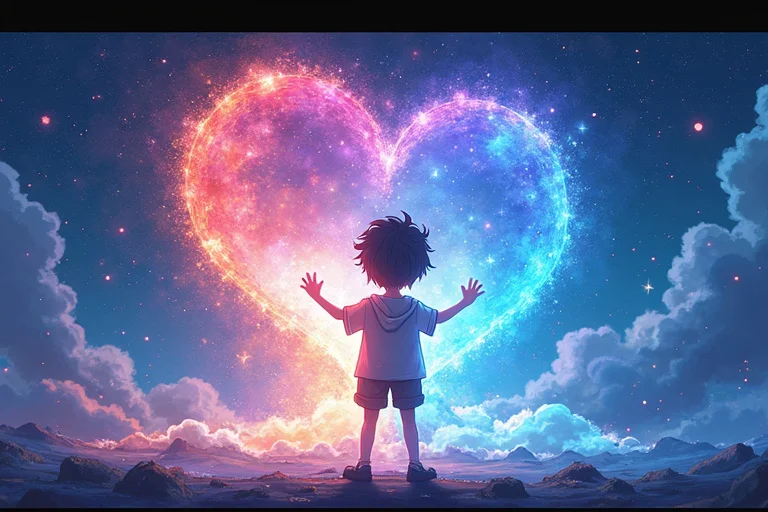第一章 閉ざされた宝箱
僕たちの世界では、思い出は形になる。強い感情を伴う記憶は、胸の奥で静かに結晶化し、「記憶晶(きおくしょう)」と呼ばれる宝石のようなオブジェクトになるのだ。それは指先で取り出すことができ、他人に譲渡することも可能だった。誕生日に親から愛情の記憶晶を贈られたり、恋人同士が初めてのデートの記憶晶を交換したり。記憶晶のやり取りは、この世界で最も純粋なコミュニケーションの形とされていた。
だが、僕、水野湊(みずの みなと)は、その慣習が好きではなかった。自分の内側で生まれた、脆くて不確かなものを、誰かの目に晒すのが恐ろしかったのだ。僕の胸の中には、誰にも見せたことのない記憶晶が、まるで宝箱の底に沈んだガラクタのように、いくつも溜まっていた。
「ねぇ、湊」
放課後の教室。夕陽が差し込み、机の木目を黄金色に染め上げていた。窓際に立つ幼馴染の佐伯陽菜(さえき ひな)が、僕の机に影を落とす。彼女の明るい声が、やけに真剣な響きを帯びていた。
「私たちの、あの夏の記憶晶、くれない?」
心臓が、嫌な音を立てて跳ねた。あの夏。それは、僕たちがまだ小学六年生だった頃の、夏祭りの夜のことだ。二人でこっそり裏山に登り、街の灯りと打ち上げ花火を独り占めした、秘密の思い出。僕の胸の中で、それは淡いラムネ色に輝く、最も美しい記憶晶となっている。
「……なんで、急に」
「いいから。お願い」
陽菜は、僕が今まで見たこともないような、切羽詰まった顔をしていた。その瞳の奥には、僕の知らない深い影が揺れている。彼女はいつも太陽みたいに笑っているのに、今日の彼女はまるで、もうすぐ沈んでしまいそうな夕陽そのものだった。
記憶晶を渡すことは、その思い出の所有権を完全に譲渡することを意味する。渡した側には、その記憶の輪郭がおぼろげにしか残らなくなる。陽菜に渡してしまえば、あの夜の空気も、ラムネの味も、隣で笑う彼女の横顔も、すべてが霞んでしまうのだ。
「……嫌だ」
絞り出した声は、自分でも驚くほど冷たく響いた。陽菜の肩が小さく震える。彼女は何も言わず、傷ついた表情で踵を返し、教室から出て行ってしまった。残されたのは、窓から吹き込む生ぬるい風と、自分の心を守ることしかできない、どうしようもない僕だけだった。
第二章 硝子越しの喧騒
陽菜との関係は、あの日を境にぎこちないものになった。廊下ですれ違っても、彼女は目を伏せ、僕は声をかけるタイミングを失う。クラスメイトたちが楽しげに記憶晶を交換している光景が、やけに目に付いた。透明なピンク色の記憶晶を恥ずかしそうに渡す女子。力強い琥珀色の記憶晶を受け取って、友の肩を叩く男子。彼らが交換しているのは、単なる記憶ではない。信頼や、好意や、共感といった、目に見えない絆そのものだ。
僕には、それが眩しすぎた。自分の胸の中にある記憶晶は、誰にも理解されない、自分だけのもの。それを渡すことは、自分の一部を削り取られるような行為に思えた。陽菜に渡さなかったのも、思い出が惜しかったからだけではない。僕にとって最も大切なあの思い出を、彼女が僕と同じように大切に思っているという確信が持てなかったのかもしれない。もし、彼女が他の誰かとの思い出と同じように、それを扱ったら? そう思うと、胸の奥が冷たく凍るようだった。
図書室で、古い文献を読んでいた。そこには、記憶晶に関するこんな一節があった。『記憶晶とは、魂の足跡である。それを他者と分かち合うことは、自らの魂の地図を広げ、新たな道を見出す旅に他ならない』。
魂の地図、か。僕の地図は、たった一人で歩くための、行き止まりだらけの路地裏みたいだ。陽菜と歩いた、あの夏祭りへ続く道も、僕が頑なに閉ざしてしまった。
どうして陽菜は、あんなにも必死だったのだろう。理由を尋ねる勇気も出ないまま、時間だけが過ぎていく。陽菜のいない日常は、色が抜けた写真のように味気なかった。彼女の笑い声がない教室は静かすぎたし、一緒に帰る道のりは長すぎた。僕は、記憶晶という硝子を隔てて、世界から切り離されてしまったような孤独を感じていた。陽菜を失うかもしれないという恐怖が、じわじわと僕の心を蝕んでいった。
第三章 ラムネ色の偽物
このままではいけない。陽菜を、失いたくない。何日も悩み抜いた末、僕はついに決心した。僕の意地やこだわりよりも、陽菜との未来の方がずっと大切だ。
僕は自室のベッドに横たわり、深く息を吸い込んだ。意識を胸の中心に集中させる。やがて、ひんやりとした感触が指先に伝わった。ゆっくりと引き出すと、手のひらの上に、淡いラムネ色の記憶晶が現れた。夜の闇を溶かし込んだような、繊細な青。中には、小さな気泡のような光がいくつも浮かんでいて、まるで星空のようだ。これが、僕の宝物。僕と陽菜だけの、夏の夜の記憶。
これを、陽菜に渡そう。そして、ちゃんと謝ろう。
翌日の放課後、僕は陽菜を探した。彼女は屋上に続く階段の踊り場で、一人、窓の外を眺めていた。その背中は、泣いているかのように小さく見えた。
「陽菜」
声をかけると、彼女の肩がびくりと跳ねた。振り返った陽菜の目は少し赤かった。僕はポケットから記憶晶を取り出し、彼女の前に差し出した。
「これ……渡すよ。ごめん、遅くなって」
陽菜は僕の手の中にあるラムネ色の結晶を見て、息を呑んだ。その瞳が大きく見開かれ、みるみるうちに涙で潤んでいく。彼女が何かを言おうと口を開き、僕に駆け寄ろうとした、その時だった。
カラン、と硬質な音が床に響いた。陽菜が持っていたトートバッグの口から、何かがこぼれ落ちたのだ。それは、僕が手にしているものと寸分違わぬ、ラムネ色に輝く記憶晶だった。一つじゃない。二つ、三つ……。大きさも色合いも微妙に違うけれど、どれもが夏祭りの夜を思わせる、ラムネ色の記憶晶だった。
「……これ、なに?」
僕の声は震えていた。陽菜は真っ青な顔で、床に散らばった偽物の星くずを、ただ見つめている。なぜだ。なぜ陽菜が、僕と同じ思い出の記憶晶を、こんなにたくさん持っているんだ? 僕が渡そうとしているこの本物は、世界に一つしかないはずなのに。
頭が真っ白になった。僕が大切に守ってきた思い出は、こんな道端に転がっている石ころみたいに、ありふれたものだったというのか。僕の特別は、僕だけが信じていた幻想だったのか。絶望と混乱が、濁流のように僕の心を飲み込んでいった。
第四章 きみが忘れた夏
「……ごめんなさい」
絞り出すような陽菜の声で、僕は我に返った。彼女は床に散らばった記憶晶を拾い集めようともせず、ただ俯いていた。
「湊の記憶晶が、どうしても欲しかった。でも、湊はくれないし……だから、似たような思い出を探したの。フリーマーケットで、誰かが売っていた『友達と見た花火の記憶』とか、『夏祭りで食べたかき氷の記憶』とか……」
言葉の意味が、すぐには理解できなかった。なぜ、そんなことを。
「私ね、少しずつ、いろんなことを忘れちゃう病気なんだって」
陽菜は、まるで他人事のように、淡々と告げた。
「最初は、昨日の夕飯とか、そういう些細なことからだった。でも最近、もっと大事なことも、靄がかかったみたいに思い出せなくなる時があるの。お医者さんは、進行性の記憶障害だって。いつか……湊のことも、忘れちゃうかもしれない」
その言葉は、僕の心臓を鷲掴みにするのに十分だった。陽菜が、僕を忘れる? あの太陽みたいな笑顔も、僕を呼ぶ声も、全部なくなってしまうのか?
「怖かった。湊との思い出が、私の中から消えてしまうのが、何よりも怖かった。形に残したかった。たとえ偽物でも、このラムネ色を見ていれば、湊と過ごしたあの夜を、ずっと覚えていられる気がして……。でも、やっぱりダメなの。本物じゃなきゃ、意味がない。湊がくれたものじゃなきゃ……」
陽菜はボロボロと大粒の涙をこぼした。僕が意地を張って、自分の殻に閉じこもっている間に、彼女はたった一人で、記憶が消えていく恐怖と戦っていたのだ。僕が守ろうとしていたのは、思い出なんかじゃなかった。傷つくことを恐れる、矮小な自分自身だけだった。
床に転がる偽物の記憶晶が、陽菜の絶望の欠片に見えた。そして、僕の手の中にある本物の記憶晶が、途端に重くなった。これはもう、僕一人のものじゃない。これは、陽菜が失いかけている世界の一部であり、僕たちが共に生きた証そのものなのだ。
僕はゆっくりと陽菜の前に膝をつき、彼女の涙を指で拭った。そして、手のひらにあったラムネ色の記憶晶を、そっと彼女の手に握らせた。
「これは、貸すだけだ」
「……え?」
「これは陽菜に預ける。だから、失くさないで持ってて。いつか、陽菜の病気が治ったら、一緒にこの記憶晶を見て、あの夜の話をしよう。そしたら、ちゃんと俺に返してくれ。……その代わり、また新しい思い出を作って、今度は二人で交換するんだ。約束だ」
陽菜は、僕の手の中の記憶晶と僕の顔を、何度も交互に見た。そして、嗚咽を漏らしながら、力強く頷いた。彼女の冷たい指先が、僕の温かい記憶晶を、まるで命そのものであるかのように、ぎゅっと握りしめた。
胸の奥が、空っぽになったはずだった。でも、そこには喪失感ではなく、不思議な温かさが広がっていた。思い出は、自分の中にしまい込むことで輝きを保つんじゃない。誰かと分かち合い、未来への約束を交わすことで、初めて永遠になるのだ。
空っぽになった胸で、僕は陽菜と繋がっている未来を、確かに感じていた。さよなら、僕だけのラムネ色。そして、こんにちは、僕たちの未来。僕たちの物語は、まだ始まったばかりなのだから。