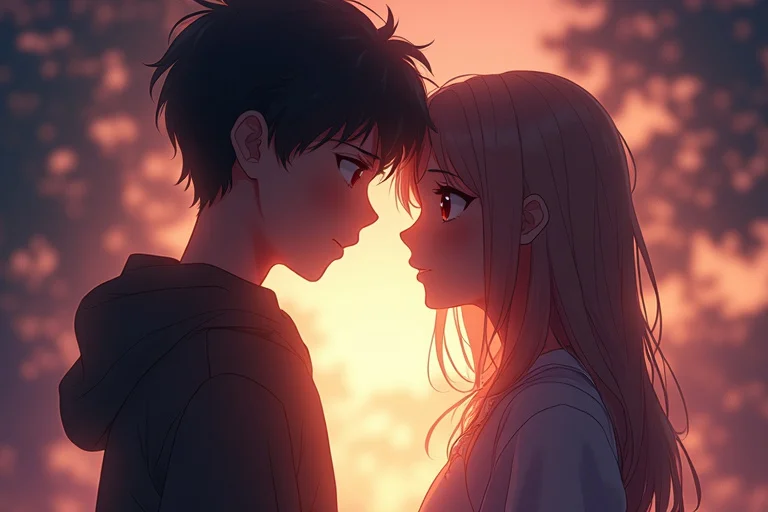第一章 色褪せた予兆
僕、高槻カイの背中には、瑠璃色の『感情の羽根』がある。思春期を迎えた誰もがそうであるように、この羽根は僕の心の天気を映し出す鏡だ。だが僕には、もう一つの、誰にも言えない秘密があった。親しい人間との『決定的な別れの瞬間』を、予知してしまう能力。人々はそれを知らないが、僕だけが『終焉のフラッシュバック』と呼んでいた。
その日、僕の唯一無二の親友、相葉アキトと学校の屋上でくだらない話をしていた時だった。彼の背で夕焼けのように燃える橙色の羽根が、彼の快活な笑い声に合わせて楽しげに揺れている。その眩しさに目を細めた瞬間、世界から音が消えた。
―――色彩のない、スローモーションの幻視。
海を見下ろす古い灯台の頂上。潮風がアキトの髪を静かに揺らす。彼は何かを僕に告げ、悲しげに微笑んでいた。次の瞬間、彼の背にあったはずの鮮やかな羽根が、まるで陽炎のように揺らめき、音もなく透明な塵となって夜の闇に吸い込まれていく。完全な消滅。それは、心が嘘に蝕まれ、完全に壊れてしまった証。
幻視が終わり、現実の喧騒が耳に戻ってきた。僕の手のひらには、ずしりと重い、錆びついた掌サイズの羅針盤が握られていた。幻視を見る度に現れる、『真実の羅針盤』。針は頼りなげに震えるばかりで、何も指し示してはいなかった。
「どうした、カイ? 顔色悪いぞ」
アキトが屈託なく僕の顔を覗き込む。彼の羽根は、まだ夕焼けの色を宿して力強く輝いていた。
僕は無理に笑みを作った。この未来は変えられない。抗えば抗うほど、別れはより残酷な形で訪れることを、僕は過去の経験で知っていた。それでも、この男との別れだけは、どうしても受け入れることなどできなかった。
第二章 揺れる羅針盤と黒い影
あの日以来、僕はアキトの影になった。運命に抗う愚かさを知りながら、彼の羽根が塵と化す未来から目を逸らせなかった。アキトは変わらず明るく振る舞っていたが、時折、彼の羽根が一瞬だけ色褪せ、くすんだ灰色が混じるのを僕は見逃さなかった。その度に、僕の胸は氷の爪で掻きむしられるように痛んだ。
「最近のカイ、なんかストーカーみたいだよな」
アキトはそう言って笑うが、その目の奥には僕の知らない影が揺れていた。彼の嘘は何だ? 何が、あの太陽のような彼を蝕んでいる?
ある放課後、アキトが一人で向かった古い音楽教室の扉の前で、僕は息を殺していた。中から聞こえてくるのは、途切れ途切れのピアノの旋律。悲しく、美しい音色だった。その時、背後に人の気配を感じた。振り返ると、そこにいたのは漆黒のスーツに身を包んだ男だった。彼の背中には、夜の闇そのものを固めたような、異常なほど黒く、それでいて星々のように強く輝く羽根があった。
「それ以上、運命の歯車に手をかけるな、少年」
男の声は低く、感情が削ぎ落とされている。
「彼の嘘は、君が暴いてはならない聖域だ」
「あんたは誰だ」
「我々は『調律師』。この世界の嘘と真実の調和を保つ者だ」
男はそれだけ言うと、影に溶けるように姿を消した。インクを零したような、奇妙な匂いだけがその場に残っていた。
第三章 偽りの旋律
僕は調律師の警告を無視した。アキトを救えるのは僕しかいない。そう信じたかった。
翌日、僕はアキトを問い詰めた。
「昨日の音楽教室、あれは何だ? お前、何か隠してるだろ」
アキトの顔から、一瞬で笑顔が消えた。彼の羽根が、さっと色を失いかける。
「……何でもないよ。昔、少しだけピアノを習ってただけだ」
その言葉が紡がれた瞬間、ポケットの中の羅針盤が熱を持った。取り出すと、その錆びた表面に、まるで霜が降りたかのように複雑な羽根の文様が白く浮かび上がっていた。そして、今まで曖昧に揺れていただけの針が、カチリ、と音を立てて北を指し示した。
嘘だ。アキトは今、明確な嘘をついた。
それからというもの、僕が真実に近づこうとする度に、あの黒い羽根の大人たちが現れ、僕の行く手を阻んだ。彼らは物理的な力を使うことも厭わず、僕をアキトから引き離そうとした。彼らの目的は何なのか。なぜアキトの嘘を守ろうとするのか。謎は深まるばかりだった。
第四章 崩れ落ちる夕焼け
焦燥感に駆られた僕は、ついにアキトが夜行バスのチケットを予約したことを突き止めた。もう時間がない。僕は彼が向かうであろう場所へと走った。予知で見た、あの古い灯台だ。
螺旋階段を駆け上がると、アキトがそこにいた。海風に吹かれながら、静かに街の灯りを見下ろしている。
「行くのか、アキト。何も言わずに」
僕の声は震えていた。
アキトはゆっくりと振り返った。その顔は、僕の知らない、深く傷ついた大人の表情をしていた。
「……ごめんな、カイ」
「嘘なんだろ! お前の羽根が消えるなんて! どんな嘘をついてるんだ、言えよ!」
僕は彼の肩を掴んで叫んだ。僕自身の瑠璃色の羽根が、激情に打ち震える。
アキトは悲しそうに微笑んだ。「俺は……大きな嘘をついてきたんだ」。彼は静かに語り始めた。かつて、将来を嘱望された天才ピアニストだったこと。しかし、コンクール直前の事故で右手の指に、二度と元には戻らない怪我を負ったこと。音楽家の夢を絶たれ、絶望の中で彼は『明るく快活な相葉アキト』という嘘の仮面を被ったのだと。
「もう疲れたんだ。この街で、音楽の亡霊に怯えながら生きるのは……」
彼の告白と共に、夕焼け色だった羽根が急速に色を失っていく。橙色が薄れ、灰色が広がり、やがて脆いガラスのように透明になっていく。
ああ、これが、『終焉のフラッシュバック』の正体だったのか。僕は、彼の心の崩壊をただ見ていることしかできないのか。絶望が、冷たい水のように僕の心を満たしていく。
第五章 真実の音色
アキトの羽根が、最後の輝きを失い、塵となって消えようとしたその時だった。
「でも、これが俺の全部じゃない」
アキトが、静かだが力強い声で言った。
その言葉に応えるように、灯台の入り口から複数の影が現れた。あの『調律師』たちだ。リーダー格の、長い黒髪を持つ女性が僕たちの前に進み出る。彼女の黒い羽根は、銀河のように荘厳な輝きを放っていた。
「彼の嘘は、絶望だけではありません。希望もまた、嘘の仮面を被っていたのです」
女性の言葉に、僕は顔を上げた。
「カイ」とアキトが僕の名を呼んだ。「お前の能力のこと、知ってたんだ。いつか、俺との別れを見ることになるんじゃないかって、ずっと思ってた」
彼は全てを知っていた。そして、僕を試していたのだ。
「俺が本当に隠していた嘘は、絶望じゃない。……俺は、まだ音楽を諦めていない。もう一度、あの舞台に立ちたい。その消せない情熱こそが、俺の最大の『嘘』だったんだ」
街を離れるのは、逃げるためではなかった。指の治療法を見つけ、新たな音楽を学ぶため。その覚悟を、彼は誰にも告げず、たった一人で抱えていたのだ。僕が運命に抗い、彼の真実を見つけ出すことを、彼は信じて待っていた。
「君の友人は、自らの嘘と決別し、新たな真実へと旅立とうとしているのです。我々調律師は、その『卒業』を見届けるために来ました」
女性がそう告げた瞬間、僕の手の中の羅針盤が灼熱の光を放った。針は狂ったように回転し、灯台の最上部、天蓋の真下を強く指し示した。そこには、風に飛ばされぬよう石で押さえられた、一枚の楽譜が置かれていた。
第六章 透明な夜明け
全ての真実が、夜明けの光のように世界を照らし出した。
その瞬間、アキトの背で崩れかけていた羽根に、信じられない変化が起きた。それは消滅ではなかった。彼の人生の全ての感情――夕焼けの橙、絶望の灰色、そして諦めきれなかった希望の金色が奔流となって混ざり合い、虹色の、これまで誰も見たことのない壮絶な輝きを放ち始めたのだ。
「ありがとう、カイ。お前のおかげで、俺は本当に自由になれる」
アキトの羽根は、最高潮の輝きに達した瞬間、一枚、また一枚と光の粒子に変わり、夜明け前の空へと舞い上がっていく。それは崩壊ではなく、解放だった。過去の嘘から解き放たれ、未来へと向かう、自由への飛翔だった。
彼は僕に、最高の笑顔を見せた。
「また会おう、親友」
そう言い残し、彼は光の中へと歩き出す。もう彼の背に羽根はない。だが、その足取りは誰よりも力強かった。
僕は、空に溶けていく無数の光の羽根を、ただ黙って見上げていた。やがて、僕自身の背中に、静かな変化が訪れるのを感じた。僕の瑠璃色の羽根が、ゆっくりと色を失っていく。しかしそれは、アキトが見せた崩壊の色とは違う。それは、何色でもない、未来のあらゆる可能性の色をその内に秘めたかのような、澄み切った『透明』な輝きだった。
『終焉のフラッシュバック』は、終わりを告げる呪いではなかったのだ。それは、誰かの大切な人生の『始まり』の瞬間を分かち合うための、未来からの贈り物だったのかもしれない。
僕は、まだ温かい羅針盤を強く握りしめた。針はもうどこも指さず、ただ静かに夜明けを映している。空には、アキトが放った最後の光が、一番星のように瞬いていた。