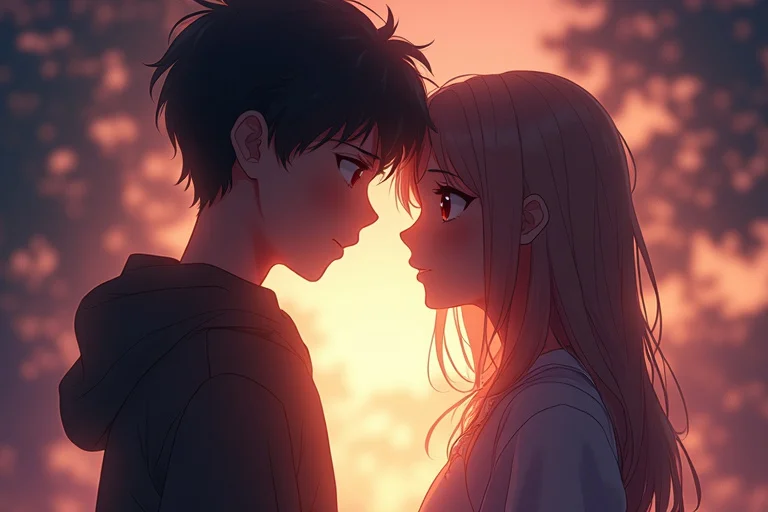第一章 ファインダー越しの侵入者
僕の世界は、いつも角の丸い長方形だった。カメラのファインダーを覗くと、現実の喧騒は心地よい静寂に変わり、色彩と光と影だけが支配する秩序だった空間になる。僕は写真部の水野蓮。風景を撮るのが好きで、人を撮るのが、少し苦手だった。レンズを向けると、相手の視線が、感情が、生々しく僕のテリトリーに流れ込んでくる気がして息が詰まるのだ。だから僕はいつも、遠くの山並みや、夕暮れの電線に止まる鳥のシルエットにシャッターを切っていた。
そんな僕の静かな世界に、彼女は土足で、いや、満開の笑顔で踏み込んできた。
高校二年の五月。梅雨入り前の、気まぐれな風が教室のカーテンを揺らす昼下がり。担任が紹介した転校生、橘陽菜は、太陽のかけらを凝縮したような少女だった。蜂蜜色の髪が光を弾き、大きな瞳は好奇心にきらめいている。自己紹介で「趣味は人を笑わせることです!」と言い切った彼女に、クラスの空気は一瞬で掌握された。僕とは住む世界が違う。そう結論付けて、僕はそっと視線を窓の外に向けた。
その日の放課後、誰もいない写真部の部室で、僕は現像液のツンとした匂いに包まれながら、撮りためた風景写真を整理していた。その時だった。
「みーつけた!」
背後からの声に心臓が跳ねた。振り返ると、戸口に橘陽菜が立っていた。なぜ僕の名前を? なぜここに? 思考が停止する僕に、彼女は構わずずかずかと入ってきて、壁に貼られた僕の写真を興味深そうに眺め始めた。
「すごいね、水野くん。写真、すごく綺麗。なんだか、時間が止まってるみたい」
「……ありがとう」
かろうじてそれだけを絞り出す。彼女の存在は、この薄暗い部室にはあまりに眩しすぎた。
「ねえ、お願いがあるんだけど」
彼女はくるりと振り返り、僕の目をまっすぐに見た。その瞳の力強さに、僕はたじろいだ。
「私の、専属カメラマンになってくれない?」
「……は?」
「だから、私の写真を撮ってほしいの。卒業までに、最高の笑顔の写真を、ちょうど百枚」
百枚? 最高の笑顔? 意味が分からなかった。僕が人を撮るのが苦手だと、彼女は知らないはずだが、それにしても突飛すぎる依頼だった。
「なんで……僕に?」
「水野くんの写真、静かだけど、すごく優しい色をしてるから。君になら、本当の私を撮ってもらえる気がするんだ」
彼女は悪戯っぽく笑った。その笑顔は、僕が今までレンズ越しに見てきたどんな風景よりも鮮やかで、そして、どこか計り知れない深さを持っていた。僕は、その笑顔から目が離せなくなった。角の丸い長方形だった僕の世界の縁が、少しだけ、ひび割れた気がした。
第二章 百分の一の笑顔
橘陽菜の「専属カメラマン」になってからの僕の日常は、一変した。彼女は本当に、僕をどこへでも連れ回した。放課後の教室、夕日が差し込む屋上、雨上がりの紫陽花が咲く通学路、夏の匂いがする河川敷。彼女はどんな場所でも被写体になった。
「ほら、蓮! 早くしないと光が逃げちゃう!」
いつの間にか彼女は僕を名前で呼ぶようになっていた。僕は彼女を「橘さん」と呼び続けていたが、ファインダー越しに彼女を捉えるたび、その距離は少しずつ縮まっているのを感じていた。
最初の頃、僕はやはり緊張していた。レンズを向けると、陽菜は完璧なモデルのように笑う。でも、それは彼女が言う「最高の笑顔」ではない気がした。どこか作り物めいていて、シャッターを押す指がためらわれた。
「だーめ! それじゃただの証明写真だよ」
ある日、陽菜はそう言って僕のカメラを覗き込んだ。
「もっと、私の心の中まで入ってきてよ」
彼女はそう言って、僕の頬に不意にキスをした。シャボン玉が弾けるような、柔らかい感触。僕の頭は真っ白になり、持っていたカメラを落としそうになった。顔を真っ赤にして固まる僕を見て、彼女は腹を抱えて笑った。
「あはは! 今の顔、撮っておきたかったな!」
その時の彼女の笑顔。それは、屈託がなく、心の底から湧き出たような、本物の輝きを放っていた。僕は夢中でシャッターを切った。カシャッ、と乾いた音が響く。それが、僕が初めて捉えた彼女の「最高の笑顔」だった。
それから、僕たちは少しずつ変わっていった。僕は陽菜の不意打ちに驚きながらも、彼女の自然な表情を捉えるコツを掴んでいった。アイスを食べている時、猫とじゃれている時、僕のくだらない冗談に笑い転げている時。陽菜は、僕の前でどんどん無防備になっていった。
写真の数は、三十枚、五十枚、七十枚と増えていった。部室の壁は、陽菜の様々な笑顔で埋め尽くされていく。それを見るたび、僕の胸は温かいもので満たされた。モノクロームだった僕の世界は、陽菜という太陽によって、いつしか極彩色のパノラマに変わっていた。
けれど、時折、陽菜は見せるのだ。ふとした瞬間に、すべての光が消えたような、遠いどこかを見つめる寂しげな横顔を。僕がそれに気づいてレンズを向けると、彼女はハッとして、いつもの笑顔に戻る。
「どうしたの?」と聞いても、「なんでもないよ」と笑うだけ。その笑顔の裏に隠された影が、僕はずっと気になっていた。季節は巡り、木々が赤や黄色に染まる秋。陽菜の笑顔の写真は、九十九枚になっていた。
第三章 空白のシャッター
最後の百枚目は、特別な一枚にしよう。僕たちはそう話していた。陽菜の誕生日に、彼女が一番好きだと言っていた海が見える丘で撮る約束をした。その日を、僕は指折り数えて待っていた。
しかし、約束の一週間前、陽菜は突然、学校に来なくなった。
一日、二日と過ぎても彼女の席は空いたままだった。クラスメイトは「風邪でもこじらせたのかな」と噂していたが、僕の胸には鉛のような不安が広がっていた。メールを送っても返信はなく、電話も繋がらない。
約束の日が来てしまった。僕はいてもたってもいられず、彼女の住所を頼りに家を訪ねた。チャイムを鳴らしても、応答はない。ドアノブに手をかけると、鍵がかかっていなかった。嫌な予感が全身を駆け巡る。
「ごめんください……橘さん?」
家の中は、がらんとしていた。家具が運び出され、生活の匂いが消え失せている。まるで、最初から誰も住んでいなかったかのように。リビングの壁に、ぽつんと一枚だけ写真が残されていた。それは、僕が撮った陽菜の笑顔の写真だった。
呆然と立ち尽くす僕の背後から、声がした。陽菜の親友の、佐藤さんだった。彼女は泣きはらした目で、僕に一通の手紙を差し出した。陽菜から、僕への手紙だった。
震える手で封を開ける。そこには、陽菜の少し癖のある、綺麗な文字が並んでいた。
『蓮へ。ごめんね、黙ってて。私は今、たぶん遠い国の空の下にいます。実は私、生まれつき心臓が悪くて、手術を受けなきゃいけなくなったんだ。ずっと隠してて、本当にごめん』
文字が滲んで、読めなくなる。
『蓮に写真をお願いしたのは、わがままな理由から。もし、手術がうまくいかなくて、私が帰ってこられなくなっても、みんなに私のことを、笑顔の私を覚えていてほしかったから。そして何より、蓮に、私の生きた証を残してほしかったから。君のファインダー越しに見る世界は、いつもキラキラして見えたよ。ありがとう』
手紙が手から滑り落ちた。佐藤さんが、途切れ途切れに教えてくれた。手術の成功率は、決して高くないこと。陽菜は、僕に心配をかけたくなくて、ギリギリまで黙っていたこと。彼女の笑顔は、死の恐怖とすぐ隣り合わせの場所で、懸命に咲かせていた花だったのだ。
僕は、何も知らずに、ただ無邪気に彼女の笑顔を撮り続けていた。彼女が時折見せた寂しげな表情の意味を、今、痛いほどに理解した。部室の壁を埋め尽くす九十九枚の笑顔が、急に重い意味を持って僕に迫ってくる。僕は、彼女の本当の苦しみに、何一つ気づいてやれなかった。
カメラを持つ手が、鉛のように重い。もう、シャッターを押せる気がしなかった。僕のファインダーは、再び色を失い、ただの空白が広がっているだけだった。
第四章 君のいない世界で
陽菜がいなくなってから、世界は再び色褪せて見えた。僕はカメラを手に取ることなく、ただ無気力に日々を過ごした。部室の壁に貼られた九十九枚の笑顔は、見るのが辛くて、布をかけて隠してしまった。シャッターを切る音は、僕の日常から消えた。
そんなある日、ふと陽菜の言葉を思い出した。
『君のファインダー越しに見る世界は、いつもキラキラして見えたよ』
僕は、おそるおそる壁の布を外した。そこに並ぶ九十九の陽菜は、やはり眩しいほどに笑っていた。一枚一枚、丁寧に見ていく。アイスを頬張る顔。猫に顔を舐められてくしゃくしゃになった顔。僕をからかって悪戯っぽく笑う顔。
そこに写っているのは、決して悲壮なだけの少女ではなかった。死の影に怯えながらも、それ以上に「今、この瞬間」を全力で楽しむ、生命力そのものだった。彼女は、残された時間を嘆くのではなく、輝かせることを選んだのだ。彼女は僕に、悲しみではなく、生きる喜びを撮ってほしかったんだ。
涙が、止まらなかった。でも、それは絶望の涙ではなかった。
僕はカメラを手に取った。久しぶりに触れたその感触は、ひんやりと、しかし確かに僕の手に馴染んだ。僕は部室を飛び出し、陽菜と約束した、海が見える丘へと向かった。
夕暮れ時。丘の上から見下ろす街は、家々の窓にオレンジ色の灯りをともし始めていた。海は金色の光をたたえ、空には一番星が瞬いている。陽菜が愛した、この世界の風景。
僕はファインダーを覗いた。そこには、陽菜はいない。でも、彼女が僕に教えてくれた、世界の美しさが満ちていた。人を撮ることで、僕は初めて、風景の本当の温かさを知ったのだ。
僕は、息を吸い込み、そっとシャッターを切った。
カシャッ。
空白だったファインダーに、再び世界が写った。これが、百枚目の写真だ。君はいないけれど、君が愛したこの世界が、僕の目の前で笑っている。
数年後、僕は大学生になり、小さなギャラリーで初めての個展を開いた。タイトルは『百分の一の青』。壁には陽菜の九十九枚の笑顔と、そして中央に、あの丘から撮った夕景の写真を大きく引き伸ばして飾った。多くの人が、その写真の前で足を止め、何かを感じるように見入ってくれた。
個展の最終日。一人の見知らぬ女性が、僕に小さな封筒を渡した。差出人の名前はない。ただ、見慣れた外国の消印が押されているだけだった。
封筒を開けると、中には一枚の写真が入っていた。
見知らぬ国の、青い空と海を背景に、少し大人びた陽菜が、はにかむように、でも紛れもなく「最高の笑顔」で笑っていた。その写真の裏には、たった一言、こう書かれていた。
『これが、百一枚目ね』
僕はその写真を見つめ、静かに笑った。僕のファインダーは、これからも世界を捉え続けるだろう。喜びも、悲しみも、そして、君がくれた数えきれないほどの光も、すべてを写し撮っていく。僕たちの青春は、まだ、終わらない。