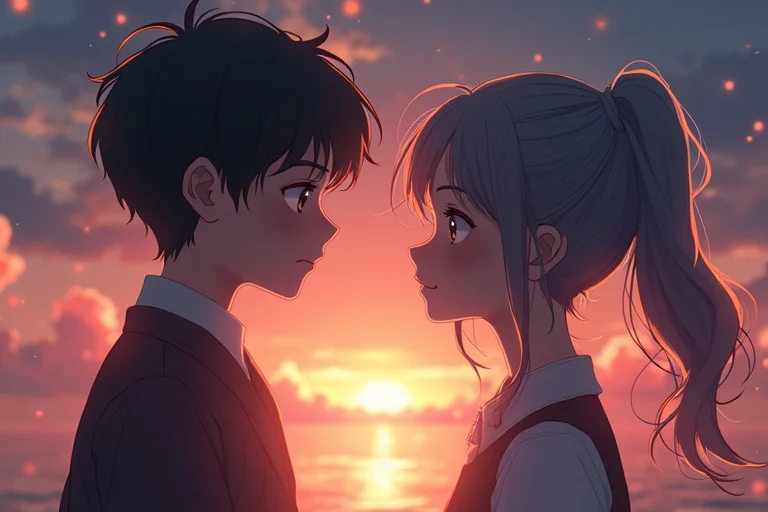第一章 歪んだ世界と真っ直ぐな君
僕、水島蓮の世界では、言葉はねじ曲がる。
物理的に、だ。人が嘘をついたり、本心とは違うことを口にしたりすると、その言葉が発せられた瞬間、まるで熱せられた飴細工のようにぐにゃりと歪む。母さんの「大丈夫よ」はいつも少しだけ溶けているし、クラスメイトの当たり障りのない会話は、粘土のようにこねくり回されて原型を留めていない。
この奇妙な共感覚がいつから始まったのか、はっきりとは覚えていない。物心ついた頃にはもう、僕の世界は「真実」と「歪み」で構成されていた。だから僕は、人と深く関わることを避けてきた。歪んだ言葉のシャワーを浴び続けるのは、精神がすり減る。それはまるで、絶え間なく流れる不協和音の中にいるようなものだった。まっすぐな言葉だけが、僕にとっての静寂だった。
高校二年の初夏、その静寂は、一人の転校生によって僕の世界に鳴り響いた。
「月島陽菜です。よろしくお願いします!」
教壇に立った彼女が放った言葉は、僕がこれまで見たこともないほど、一点の曇りもない直線だった。まるでレーザー光線のように、寸分の狂いもなく僕の鼓膜に届く。そのあまりの清冽さに、僕は思わず息を呑んだ。
陽菜は、こともあろうに空いていた僕の隣の席を指さして言った。
「先生、私、あそこがいいです!」
その言葉もまた、完璧な直線だった。クラス中が少しざわめいたが、彼女は気にしない。荷物を置くと、僕に向かって太陽みたいな笑顔で言った。
「よろしくね、ええと……」
「……水島」
「水島くん! 私は陽菜。気軽に呼んでね」
彼女の言葉はすべてがストレートだった。そこには微塵の歪みも、躊躇いも、裏もなかった。僕は混乱していた。こんな人間が存在するのか? 嘘をつけないのか、それとも、嘘をつく必要がないほど満たされた人生を送ってきたのか。
放課後、僕は所属している美術室へ向かった。一人でキャンバスに向かう時間が、僕にとって唯一の安息だったからだ。しかし、その安息の場所にも、彼女は現れた。
「わ、美術部だったんだ! 私も入ってもいいかな?」
驚いて振り向くと、陽菜が入り口に立っていた。もちろん、その言葉も驚くほど真っ直ぐだ。彼女は僕の描いていた途中の、誰もいない駅のホームの絵を覗き込む。
「すごい……なんだか、すごく静かで、でも、誰かを待ってるみたいな絵だね」
的確な感想に、心臓が跳ねた。僕の絵の本質を、彼女は一瞬で見抜いた。
「君は、何を描くんだ?」
僕が尋ねると、陽菜は少しはにかんで、「空。私、空を描くのが好きなの」と答えた。
その日から、僕のモノクロームだった日常は、陽菜という鮮やかな色彩によって少しずつ色づき始めた。歪んだ言葉が飛び交う教室も、彼女が隣にいるだけで、ノイズが少し遠のく気がした。
第二章 色彩をくれた時間
陽菜と過ごす時間は、僕の世界からノイズを消し去ってくれた。美術室で並んでイーゼルを立て、黙々とキャンバスに向かう。時折交わす言葉は、いつも決まって真っ直ぐだった。絵の具の匂い、窓から差し込む西日、筆がカンバスを擦る乾いた音。そのすべてが、僕にとってかけがえのないものになっていった。
彼女は本当に空ばかり描いていた。抜けるような青空、燃えるような夕焼け、星が瞬く夜空。どの空も、まるで生きているかのように表情豊かだった。
「どうして、そんなに空が好きなんだ?」
ある日、僕は尋ねた。彼女は筆を止め、窓の外に広がる空を見上げながら、穏やかに言った。
「空は、どこにいても繋がってるから。遠くにいる人とも、同じ空を見上げてるって思えるでしょ」
その言葉は、少しだけ切なさを帯びていたが、やはり歪んではいなかった。
夏休みが終わり、文化祭の季節がやってきた。僕たちのクラスは、お化け屋敷をやることになった。僕はその看板制作を押し付けられ、辟易していたが、陽菜が「私も手伝う!」と名乗りを上げてくれた。
放課後の教室で、二人きりでベニヤ板に向かう。陽菜はデザインのアイデアを次々と出し、僕はそれを形にしていく。彼女の屈託のない笑顔と、真っ直ぐな言葉に囲まれていると、僕の心の中の警戒線が、少しずつ解けていくのを感じた。
「蓮くんって、本当はすごく優しいよね」
ペンキで汚れた顔で、陽菜が不意に言った。
「そんなことない」
僕はぶっきらぼうに返したが、その言葉は自分でも分かるほど、少し歪んでいた。本当は、嬉しかったのだ。
「ほら、歪んでる」
「え?」
「ううん、なんでもない。蓮くんの絵、好きだよ。静かだけど、温かいから」
陽菜は僕の能力のことなど知る由もない。けれど、彼女の言葉はいつも僕の核心を突いてくる。僕は、この時間が永遠に続けばいいと、本気で願っていた。いつか、この能力のことを彼女に打ち明けられる日が来るかもしれない。彼女なら、きっと信じてくれる。僕の歪んだ世界を、まるごと受け止めてくれるかもしれない。そんな淡い期待を抱くほどに、僕は陽菜に惹かれていた。
第三章 最も美しい嘘
文化祭当日。校内は浮き足立った熱気に包まれていた。僕らが作った看板も好評で、お化け屋敷には長蛇の列ができていた。喧騒の中、陽菜が僕を探して駆け寄ってきた。その笑顔は、いつもと同じ太陽のようだった。
「蓮くん、見つけた!」
彼女は少し息を切らしながら、僕の制服の袖を掴んだ。
「今日の放課後、屋上で待ってて。大事な話があるの」
その瞬間、世界が音を立てて崩れた。
彼女の言葉が、歪んだ。
いや、ただの歪みじゃない。僕が今まで見たどんな嘘よりも、醜く、激しく、ぐにゃぐにゃにねじ曲がっていた。それはまるで、意思を持った生き物のようにのたうち回り、僕の視界を黒く塗りつぶした。
頭を鈍器で殴られたような衝撃。血の気が引き、指先が冷たくなっていく。
嘘だ。陽菜の言葉が、嘘だった。
僕が唯一信じていた、あの真っ直ぐな言葉が。
僕の世界の静寂が、けたたましいノイズに変わった。裏切られた、という思いが全身を駆け巡る。やっぱり、この世界に真っ直ぐな人間なんていなかったんだ。
放課後、僕は死刑台に向かう罪人のような足取りで屋上へと続く階段を上った。扉を開けると、夕暮れの赤い光を背に、陽菜が立っていた。何を言われるんだろう。「今まで楽しかったけど、実は罰ゲームでした」とか? それとも「好きな人ができたの」とか? どんな言葉も、もう僕には歪んで聞こえるだけだ。
「来てくれたんだね」
陽菜の声は、震えているように聞こえた。
「……大事な話って、何だよ」
僕は精一杯、冷たい声を装った。
陽菜は俯き、小さな声で言った。
「ごめんね、蓮くん。私……来週、また転校するんだ」
その言葉は、やはり激しく歪んでいた。ああ、そうか。「また転校する」というのが嘘なのか。僕をからかうための、手の込んだ嘘。
「そうか。じゃあな」
僕は背を向けた。もう、一秒もここにいたくなかった。
「待って!」
陽菜が叫んだ。振り返った僕の目に映ったのは、泣き出しそうな彼女の顔だった。
「本当は……本当はね、ずっとここにいたいの。転校なんてしたくない。蓮くんと……もっと一緒に、いたい」
その言葉は、これまでで最も激しく、美しく、そして悲しく歪んだ。ねじれ、溶け、崩れ落ちながら、僕の心に突き刺さる。
僕は混乱の極みにいた。なぜだ? なぜ、そんなにも心がこもっているように聞こえる言葉が、こんなにも歪むんだ?
「それも、嘘なのかよ!」
僕は叫んでいた。「一緒にいたい」なんて、そんな都合のいい言葉が、一番の嘘じゃないか!
陽菜は、堰を切ったように泣き出した。しゃくりあげながら、彼女は信じられないことを告白した。
「私、病気なの。小さい頃から、ずっと。治療のために、日本中の、ううん、世界中の病院を転々としてるの。転校っていうのは、そのため……。もう、あんまり時間がないんだって」
頭の中で、何かが砕け、そして再構築されていく感覚。
時間がない……?
陽菜は涙を拭いながら、続けた。
「だから、『一緒にいたい』って思う気持ちは本当だよ。でも、それが絶対に叶わないって、私自身が一番よく分かってるから……。だから……ごめん……」
その瞬間、僕はすべてを理解した。
雷に打たれたように、世界の真実が僕の中に流れ込んできた。
歪みは、「嘘」ではなかった。
それは、「本心」と、口に出した「言葉」との間にある、埋めようのない断絶。叶わないと知りながらも、それでも願わずにはいられない、悲痛な祈りの形だったのだ。
母さんの「大丈夫よ」は、心配で張り裂けそうな本心との乖離だった。友人の「気にするな」は、本当は自分も傷ついているのに、僕を気遣う優しさの歪みだった。
そして、陽菜の「一緒にいたい」という言葉は。それが叶わないという残酷な現実を知っているからこそ、誰よりも強く、誰よりも美しく、歪んだのだ。
僕がノイズだと思っていたものは、人々の心の痛みそのものだった。世界は嘘で満ちていたんじゃない。どうしようもない現実を前にした、切実な願いと優しさで満ちていたんだ。
第四章 言葉が生まれる場所
僕は、泣きじゃくる陽菜の肩を、震える手でそっと抱きしめた。
「……そうか」
声が、掠れた。
「そっか……」
歪んだ言葉の本当の意味を知った今、彼女の言葉の一つ一つが、たまらなく愛おしく、そして切なく胸に響いた。僕の世界を覆っていたノイズは、今や美しい旋律となって聞こえていた。
陽菜が転校するまでの、残された一週間。僕たちは、濃密な青春を駆け抜けた。もう、言葉の歪みを恐れることはなかった。むしろ、僕はその歪みの中にこそ、人の本当の心を探そうとした。陽菜が「楽しいね」と笑う時、その言葉が少しだけ歪むのを見て、彼女が心のどこかで迫りくる別れを感じていることを知り、僕はより強く彼女の手を握った。
別れの日。駅のホームで、彼女はいつもと同じ太陽のような笑顔で言った。
「じゃあね、蓮くん。元気でね」
その言葉は、驚くほど真っ直ぐだった。僕を心配させまいとする、彼女の最後の強さ。そこに歪みはなかった。でも、僕にはもう分かっていた。その真っ直ぐな言葉の裏にある、彼女の本当の心を。
「……ああ。陽菜も」
僕がそう言うと、彼女は少しだけ驚いたように目を見開き、そして、ふっと微笑んだ。
陽菜が去った後、僕は一人、美術室に戻った。彼女が描き残していった、一枚の空の絵。それは、夜明け前の、紫とオレンジが混じり合った、希望のような空だった。
ふと、キャンバスの裏に何か書かれているのに気づいた。
『またね』
たった三文字。そのインクで書かれた文字が、僕の目には、ほんの少しだけ、優しく、愛おしく歪んで見えた。それはきっと、叶うはずのない、けれど心からの願い。
僕は、自分のイーゼルに向かった。新しいキャンバスを立て、パレットに絵の具を出す。
以前の僕なら、きっとまた誰もいない風景を描いただろう。だが、今の僕が描きたいものは違った。
僕は、人を描こうと思った。笑ったり、泣いたり、怒ったりする、普通の人々を。その言葉が歪む瞬間の、その表情を。言葉の裏にある、声にならない心の形を。僕にしか見えない、この世界の本当の美しさを、描いてみようと思った。
世界は何も変わらない。相変わらず、言葉は歪み、ノイズは鳴り響いている。
でも、僕の世界の見え方は、もう二度と元には戻らない。
この歪みに満ちた世界は、なんて豊かで、切なくて、そして美しいんだろう。
僕は筆を手に取り、最初の一筆を、キャンバスに落とした。それは、陽菜がくれた、新しい世界の始まりの色だった。