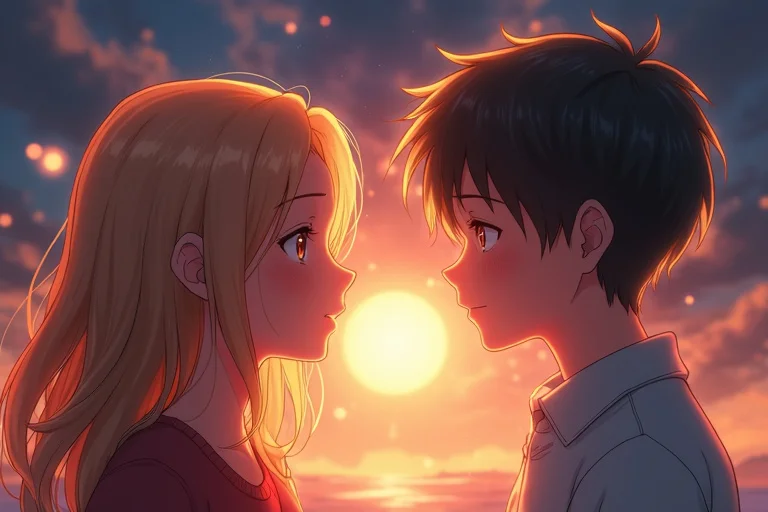第一章 秒針が狂う世界で
教室の時計が、妙に早く時を刻んでいるように見えた。いや、正確には「見えた」ではない。実際に、周囲の時間だけが加速していたのだ。窓の外を行き交う生徒たちの姿は早送りされたフィルムのように流れ、教師の声は不自然なほど高音で、意味をなさない。俺、朝倉悠真は、自らの意思とは関係なく、時々この奇妙な現象に巻き込まれる。それは、俺の感情が極端に高ぶった時に起こるのだ。喜び、怒り、焦り、そして何よりも——恐怖。
今日の原因は、隣の席の女子が放った一言だった。「朝倉君、次の化学の実験、班が一緒なんだけど、大丈夫?」彼女の少し上擦った声が、俺の心臓を不規則に打ち鳴らした。普段、俺は目立たないように、誰とも深く関わらないように生きてきた。それが、この厄介な「能力」を隠す唯一の方法だったからだ。クラスメイトたちからすれば、俺はただの無口で、少し変わった奴。だが、実際は、自分の内に秘めた感情が、世界そのものを歪めてしまうことに怯え続けていた。
「だ、大丈夫……だよ」
俺が口を開いた瞬間、教室の空気は一変した。時計の秒針が再び正常な速度に戻り、教師の声もいつものトーンに落ち着く。安堵の息を漏らす俺の隣で、彼女は「そっか、よかった」と微笑んだ。その笑顔に、俺の心臓はまた別の意味で脈打った。
その日の放課後、俺は図書室の隅で、自分の感情をコントロールするための本を読んでいた。呼吸法、瞑想、マインドフルネス。あらゆる方法を試したが、効果は一時的だ。感情というものは、そう簡単に制御できるものではない。特に青春と呼ばれるこの時期は、あらゆる感情が嵐のように吹き荒れる。
「ねえ、そこで何読んでるの?」
突然、頭上から降ってきた声に、俺は思わず肩を跳ね上がらせた。顔を上げると、そこに立っていたのは、星野光だった。クラスでも一際明るく、いつも笑顔を絶やさない彼女は、俺とは正反対の存在だ。太陽のように輝く彼女の存在は、俺の灰色の日常に不釣り合いなほど鮮やかで、まぶしかった。
「いや、別に……」
思わず目をそらしたが、光は気にする様子もなく、俺の隣の椅子に腰掛けた。「もしかして、感情コントロールの本? なんか、朝倉君っぽいね」そう言って、彼女はクスッと笑った。その笑顔に、俺の胸はまたキュッと締め付けられる。感情が揺れるたびに、時間が歪んでしまうかもしれないという恐怖が、俺の口を重くした。
光は、俺が何を読んでいるのか、なぜそんな本を読んでいるのか、深く詮索するようなことはしなかった。ただ、隣で静かに本を読み始めたり、時折、図書室の窓から差し込む夕日を眺めながら、ぽつりと感想を漏らしたりした。「夕日って、なんでこんなに儚いんだろうね。あっという間に沈んじゃうのに、ずっと見ていたくなる」
彼女の言葉が、なぜか俺の心に深く響いた。儚い。その言葉が、俺の能力を象徴しているようにも思えた。俺が感情を揺らせば、時間は加速し、今この瞬間も、あっという間に過去へと流れていってしまう。その事実に、俺は常に恐怖を覚えていた。
「……ねえ、朝倉君はさ、もし時間を止められたら、どうする?」
光が、ふとそんな問いを投げかけた。俺は、まさかそんなことを聞かれるとは思わず、言葉に詰まった。もし時間を止められたら? 俺は、時間を止めるどころか、加速させてしまう厄介な能力を持っている。でも、もし、もし本当に時間を止められるとしたら。
「……君といる時間を、止めるかもしれない」
俺の口から出た言葉に、光は目を丸くした。そして、ふわりと微笑んだ。
「そっか。私は、逆に時間を進めちゃうかもな。もっと色々なことを知りたいし、見たいし」
その言葉に、俺はなぜか胸の奥がチクリと痛むのを感じた。俺が時間を止めても、光はきっと、その先の未来へ進んでしまうのだろう。
その夜、俺は光の言葉を反芻しながら、夜空の星を眺めていた。あの星々も、途方もない時間をかけて、今ここに光を届けている。俺と光の時間も、いつかそうなるのだろうか。俺の能力は、本当に呪いなのだろうか。
第二章 君の隣で、時は加速する
光と過ごす時間は、それまでの俺の日常とは比べ物にならないほど鮮やかだった。図書室の片隅、屋上のベンチ、放課後の帰り道。他愛ない会話を重ねるたびに、俺の心は温かい光に包まれるような、それでいて、いつ暴発するかわからない爆弾を抱えているような、複雑な感情で満たされていった。
俺の感情の波は、光の前では特に激しくなる傾向があった。彼女が笑うと、心臓が大きく跳ね上がり、周囲の時間が一瞬、早送りされる。彼女が俺を心配そうに見つめる時、その優しさに胸が締め付けられ、世界がゆっくりと、まるで水中を漂うように減速する。光は、俺の感情によって引き起こされる微妙な時間の歪みに、薄々気づき始めているようだった。
ある日、俺たちは公園のブランコに揺られていた。隣に座った光の髪が、風に揺れてサラサラと俺の頬をくすぐる。
「ねえ、朝倉君ってさ、たまに時間止まってるみたいだよね」光が、冗談めかして言った。
俺は思わず心臓が止まるかと思った。「え……?」
「ほら、前にも図書室で、朝倉君が本読んでる時、なんか周りの時間がゆっくりになってる気がしたんだ。私だけかな?」
光は空を見上げて、微笑んだ。その言葉に、俺の全身が凍り付く。
「それは、気のせいだよ」
俺は必死に平静を装ったが、声は震えていた。俺の焦りが、また周囲の時間を加速させる。ブランコから見える景色が、一瞬で遠ざかり、戻ってくる。
光は、俺の反応を見て、何も言わなかった。ただ、優しく俺の手を握った。その手の温かさに、俺の加速していた時間が、ゆっくりと正常に戻っていくのを感じた。
「朝倉君、もしかして、何か隠してることある?」
光の真っ直ぐな瞳が、俺の胸の奥底を見透かしているようだった。俺は、正直に話すべきか迷った。もし話せば、彼女は俺から離れていってしまうだろうか。この異質な能力を持つ俺を、怖がるだろうか。
だが、光の瞳は、恐怖ではなく、深い心配の色を湛えていた。
「俺は……時々、周りの時間を変えてしまう能力があるんだ。感情が高ぶると、時間が加速したり、減速したりする。だから、俺は、誰とも深く関わらない方がいいって……」
俺が苦しい告白をすると、光は驚きに目を見開いたが、すぐに微笑んだ。「なんだ、そんなことだったの?」
「そんなことって……」
「だって、朝倉君の感情がそうさせてるんでしょ? それって、朝倉君がすごく感受性豊かってことじゃない。素敵なことだよ」
光は、俺の能力を、呪いでも、異物でもなく、「素敵なこと」だと言った。その言葉に、俺の目から熱いものが溢れそうになる。初めて、この能力を肯定してくれた人がいた。
俺は、光が俺の能力を受け入れてくれたことに感動し、心の底から安堵した。しかし、それと同時に、俺の心は新たな恐怖に襲われ始めた。光と過ごす時間が、あまりにも心地よすぎて、この「今」が加速して、あっという間に過ぎ去ってしまうのではないかという恐怖だ。
「ねえ、朝倉君、文化祭の劇、一緒にやらない? 私たち、同じ班だし」
光が満面の笑みで誘ってきた。俺は、その誘いに心ときめかせたが、同時に、胸に刺さるような不安を感じていた。文化祭。人前で感情を強く動かされるイベント。それは、俺の能力を暴走させるには十分すぎる要因だ。
しかし、光の隣で、この普通じゃない青春を、俺は確かに生きていた。それが、俺の心を、狂った秒針のように揺らし続ける。
第三章 消された時間の真実
文化祭の準備は、俺にとって試練の日々だった。光と二人で台本を読んだり、小道具を作ったりする時間は、至福でありながらも、常に綱渡りのような緊張感を伴っていた。光が熱心に劇のアイデアを語るたび、俺の心は高揚し、周囲の時間がわずかに加速する。彼女の笑顔を見るたび、喜びが溢れて、時間の流れが速まるのを感じる。俺は、光との「今」を大切にしたいと願うほど、それが早く過ぎ去ってしまうという矛盾に苦しんだ。
文化祭当日。俺たちのクラスは、シンデレラの現代版アレンジ劇を上演することになっていた。俺は脇役だが、光は主役のシンデレラ役。幕が上がり、大勢の観客の視線が集まる中、光は輝くばかりの笑顔で舞台に立っていた。
俺は舞台袖で、彼女の演技を息を飲んで見つめていた。光が王子様とダンスを踊るシーン。スポットライトを浴びた彼女の姿は、あまりにも美しく、俺は完全に魅了された。その瞬間、俺の胸に、かつてないほどの強い感情が押し寄せた。それは、喜びであり、憧れであり、そして同時に、この輝く時間が、永遠に続いてほしいという切なる願いだった。
だが、その願いは、最悪の形で裏切られた。
俺の感情が極限まで高まったその瞬間、舞台上の光の動きが、ほんの一瞬、不自然に止まった。いや、止まったように見えた。観客は気づいていないようだったが、俺にははっきりと見えた。光の表情が、一瞬だけ、凍り付いたように虚ろになったのだ。
直後、光は何事もなかったかのように演技を再開したが、俺の心臓は激しく警鐘を鳴らしていた。
終演後、俺は光を捕まえて、舞台裏の静かな場所へ連れ出した。「今の、どういうことなんだ?」
光は、俺の問いに、困ったように眉を下げた。「朝倉君、私ね……時々、記憶が飛ぶことがあるの。ほんの数秒とか、数分。まるで、その間の時間が、私の中から消え去ってしまったみたいに」
俺の全身に、戦慄が走った。
「それは……いつからだ?」
「たぶん、昔から。特に、朝倉君と仲良くなってから、頻繁に起こるようになった気がする」
光の言葉に、俺は息を呑んだ。まさか、俺の能力が、光にこんな影響を与えていたなんて。俺が光を大切に思うほど、彼女との時間が加速し、やがてその一部が、彼女の記憶から「消え去っていた」のだ。
「私、時々、朝倉君と話したはずのことが、思い出せないことがあるの。なんでだろうって思ってたんだけど……もしかして、朝倉君の能力と関係ある?」
光の瞳が、不安げに揺れる。俺は、言葉を失った。俺が、俺が望むほどに、光との時間は失われていく。まるで、俺の愛が、光の時間を蝕む毒であるかのように。
それは、俺がこれまで抱いてきた恐怖を、遥かに凌駕する絶望だった。俺は、自分の能力を呪った。この力は、俺にとっての呪いであるだけでなく、俺が最も大切にしたいと願う相手を傷つけるものだったのだ。
俺の価値観は根底から揺らいだ。俺は、光との時間を、永遠に続くものにしたいと願っていた。しかし、その願いが強ければ強いほど、光の時間は「加速」し、そしてその一部が「消滅」してしまう。俺は、光から、最も大切なものを奪っていたのだ。
「ごめん、光……俺のせいで……」
俺の謝罪の言葉は、震えて途切れた。光は、そんな俺の頬にそっと手を添えた。「朝倉君のせいじゃないよ。私ね、確かに思い出せない時間はたくさんある。でもね、朝倉君と一緒にいる時間は、私にとって、どれもすごく大切なの。たとえ記憶に残らなくても、私の心には、確かに残ってる気がするんだ」
光の言葉は、俺の絶望に、一条の光を灯した。失われた時間は戻らない。だが、そこで感じた感情、育まれた心は、確かに残っている。そして、俺は、この能力と共に、どうやって光と向き合っていけばいいのか、その答えを必死に探し始めた。
第四章 時の螺旋のその先へ
光の言葉は、俺の心を深く揺さぶり、新たな決意を芽生えさせた。失われた時間は戻らない。だが、その事実を受け止め、それでもなお、光との未来を築きたいと強く願った。俺は、自分の能力を呪い続けるのではなく、制御し、そして光と共に、新たな「時間」を創造することを選んだ。
それから、俺は必死に自分の感情と向き合った。激しい喜びや悲しみ、焦りといった感情の波が押し寄せた時、それが時間の歪みとして現れる前に、自らを落ち着かせる練習を重ねた。マインドフルネス、瞑想、深呼吸。これまで効果が薄いと感じていた手法も、光を守りたいという強い思いがあれば、違って見えた。
光は、そんな俺に寄り添い続けた。俺が感情を制御できず、周囲の時間が乱れるたびに、彼女は俺の手を握り、優しく語りかけた。「大丈夫。朝倉君ならできるよ」「ゆっくりでいいんだよ」彼女の存在そのものが、俺の時間の暴走を鎮める、奇跡のようなアンカーだった。
ある時、俺は光に尋ねた。「俺のせいで、たくさんの時間が失われた。それでも、俺と一緒にいてくれるのか?」
光は、少し考える素振りを見せた後、まっすぐに俺の目を見て言った。「朝倉君と出会う前の私の記憶は、正直、ぼんやりしてる部分も多い。でも、朝倉君と出会ってからの時間は、たとえ忘れてしまっても、私の心が覚えてる。だって、朝倉君が私にたくさんの初めてを教えてくれたから。初めて、こんなに誰かのことを考えたし、初めて、未来をこんなに楽しみに思えた。だから、私は、朝倉君との時間を、全部、大切にしたい。どんな時間でも、朝倉君となら」
その言葉は、俺の心の奥底に深く染み渡った。俺がどれだけ能力に怯え、未来を悲観しても、光は俺の隣に立って、前を向いてくれていたのだ。
俺は、もう自分の能力を隠すことをやめた。そして、光と共に、この「秒針が狂う世界」を歩むことを決めた。
卒業が近づいたある日、俺たちは再び、あのブランコのある公園にいた。夕日が空を茜色に染め上げ、時間の儚さを際立たせる。
「ねえ、朝倉君」光が、ぽつりと言った。「もし、私がまた何かを忘れてしまっても、朝倉君が教えてくれる?」
俺は、静かに頷いた。「何度でも。君が忘れても、俺が覚えている。そして、また一緒に、新しい時間を刻んでいこう」
俺の言葉に、光は心から安心したように微笑んだ。その笑顔は、かつて俺が抱いた恐怖を洗い流すほどに、優しく、温かい。
俺たちの青春は、一般的なものとは大きく異なる。時間は常に、俺たちの感情に呼応して歪み、時には、大切な記憶さえも奪い去るかもしれない。しかし、その「不完全な時間」の中に、俺たちは確かな絆と、未来への希望を見出した。
俺は、もう人との繋がりを恐れない。自分の感情を押し殺すこともしない。なぜなら、俺には光がいる。そして、彼女との出会いが、俺に、この歪んだ世界の中で、最も大切な「時」を教えてくれたからだ。失われた時間は、もう戻らない。だが、俺たちは、今この瞬間を、そしてこれから先の未来を、誰よりも深く、鮮やかに、そして互いを慈しみながら、共に刻んでいく。
秒針は、これからも不規則に動き続けるだろう。それでも、俺は、光の隣で、この狂った秒針の檻の中で、愛と希望に満ちた自分たちの物語を紡いでいく。失われた過去の向こうに、確かに輝く未来があることを信じて。