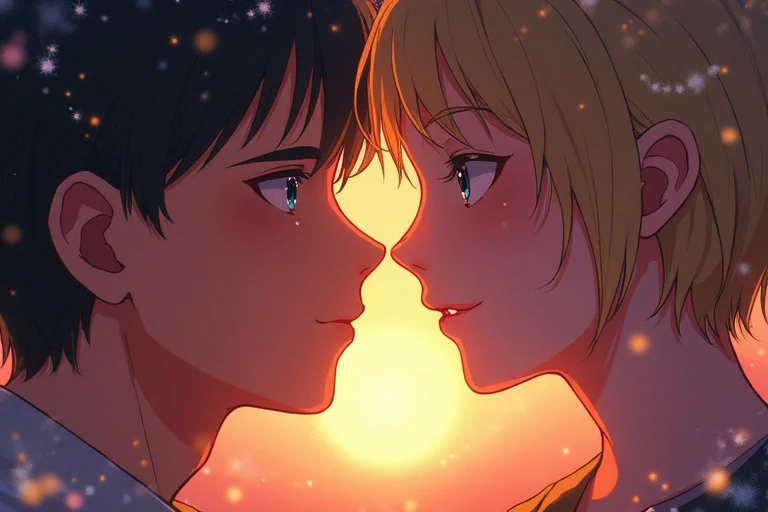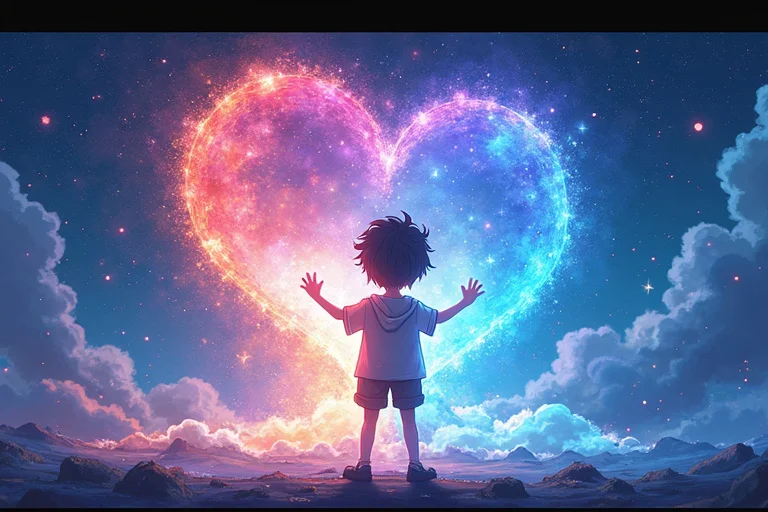第一章 色褪せたファインダー
薬品のツンとした匂いが、僕の思考を鈍らせる。高校の写真部の暗室。赤いセーフライトだけが灯るこの空間は、世界の他のすべてから切り離された聖域であり、同時に僕の心を映す檻でもあった。壁には、僕が撮りためたモノクロの写真が無数に貼られている。文化祭で笑い合うクラスメイト、夕暮れのグラウンドを走る陸上部、窓辺で本を読む少女。そこに写る光景は、紛れもなく「青春」と呼ばれるものなのだろう。しかし、そのどれを見ても、僕の心は微動だにしなかった。
僕、水島湊は、一ヶ月後に十八歳の誕生日を迎える。この世界では、それは「追憶の儀」と呼ばれる通過儀礼の日を意味していた。十五歳から十八歳までの三年間、その膨大な記憶の中から、たった一日、たった一つの「最も輝かしい記憶」だけを選んで残し、他のすべては感情の伴わない、霞がかった記録へと変わる。大人になるための、美しくも残酷な儀式。誰もがその日を前に、自分の青春のハイライトを必死に探す。
だが、僕には選ぶべき記憶がなかった。壁の写真に目をやる。その中の一枚、友人たちに囲まれてピースサインをする僕。表情は笑っている。けれど、その感情のディテールが思い出せない。まるで、他人の人生を眺めているようだ。ファインダーを覗いている時だけが、僕が世界と繋がれる唯一の時間だった。レンズを通して切り取られた世界は美しく、感情豊かに見える。だが、シャッターを切った瞬間、それはただの記録となり、僕の中から熱を失っていく。
「最高の瞬間なんて、僕にはないのかもしれない」
赤い闇の中で呟いた声は、現像液に落ちる水滴の音にかき消された。焦りと諦めが入り混じった冷たい感情が、胸の奥に澱のように溜まっていく。そんな時だった。
「わ、暗っ! ここ、誰かいるのー?」
暗室の分厚い扉が勢いよく開かれ、外の眩しい光とともに、太陽の匂いをまとったような声が飛び込んできた。目を細めると、そこに立っていたのは、同じクラスの夏川陽菜だった。彼女は、僕とは正反対の人間。常に輪の中心で笑い、その一挙手一投足が、まるで映画のワンシーンのように輝いて見える。
「水島くん? やっぱり。何してるの、こんなところで」
「……写真の整理」
「へえ、すごい数! これ全部、水島くんが撮ったんだ。ねえ、儀式で残す記憶、決まった?」
彼女は悪気なく、僕が最も触れられたくない核心に踏み込んできた。僕は答えずに、手元の写真を一枚、現像液に浸す。じわりと像が浮かび上がってくる。
「私はね、まだ決まらないんだ。だって、選べないよ。昨日も楽しかったし、今日も楽しいし、きっと明日も楽しいもん。全部が最高すぎて困っちゃう!」
そう言って彼女は、屈託なく笑った。その笑顔はあまりに眩しく、僕は目を逸らした。僕が必死に探しても見つけられないものを、彼女は「ありすぎて困る」と言う。苛立ちと、ほんの少しの羨望。その複雑な感情が、僕の無彩色の世界に、ほんの僅かなノイズを走らせた。この出会いが、僕のファインダーが捉える世界の色を、根底から変えてしまうことになるとは、まだ知る由もなかった。
第二章 君という名のプリズム
陽菜は、まるで嵐のように僕の日常に踏み込んできた。「最高の記憶がないなら、今から作ればいいじゃん!」という単純明快な理屈で、彼女は僕を様々な場所へ連れ出した。
最初は、寂れた神社の夏祭り。リンゴ飴を頬張る彼女の横顔を、僕は無意識にカメラで追っていた。次に訪れたのは、打ち寄せる波がきらめく真夏の海。波打ち際ではしゃぐ彼女に水をかけられ、思わず声を上げて笑った自分に驚いた。今までなら、ただ湿った砂の感触と潮の匂いを記録するだけだったはずなのに。
「ほら、水島くんも笑えるんじゃん」
悪戯っぽく笑う陽菜の顔が、レンズ越しにやけに鮮やかに見えた。シャッターを切る。カシャリ、という乾いた音が、僕の心臓の鼓動と重なった気がした。彼女は、僕のファインダーにとって特異な被写体だった。彼女をレンズ越しに見つめていると、世界が奇妙なほど色鮮やかに、そして情感豊かに見えてくるのだ。彼女というプリズムを通すことで、僕の世界に初めて光が差し込んだようだった。
文化祭の準備期間は、その集大成だった。僕たちのクラスは、手作りのプラネタリウムを作ることになった。陽菜は実行委員として、クラスを引っ張っていた。段ボールに穴を開け、教室の壁を黒い布で覆い、中心に置かれた古びたプロジェクターを調整する。誰もが汗とペンキにまみれながら、一つの目標に向かっていく。その熱気の中で、僕は初めて「参加者」になっている自分に気づいた。
ある日の放課後、二人きりで作業をしていた時のことだ。陽菜は、天井の黒い布に星を描きながら、ふと呟いた。
「ねえ、水島くん。もし、記憶が全部残せるなら、どうする?」
「……考えたこともない」
「そっか。私はね、たぶん、困ると思う。嬉しいことだけじゃなくて、悲しいこととか、恥ずかしいこととか、全部覚えとかないといけないんでしょ? それって、結構しんどいかもなって」
彼女は笑っていたが、その横顔には一瞬、僕が今まで見たことのない影が差した。まるで、何か重いものを背負っているかのような、諦観にも似た表情。僕はその瞬間を撮り逃すまいと、咄嗟にカメラを構えた。だが、シャッターを押す直前、彼女がこちらを振り向いた。
「でも、忘れちゃうのも、寂しいよね」
その瞳は、夏の終わりの海のように、どこまでも澄んでいて、少しだけ寂しそうだった。僕はシャッターを押せなかった。この感情を、一枚の写真に閉じ込めて記録として消費してしまうことが、ひどく冒涜的な行為に思えたからだ。
この頃からだった。僕が撮る写真に、少しずつ体温が宿り始めたのは。陽菜と過ごした時間が、僕の中で霞ではない、確かな質感を持った記憶として積層されていくのを感じていた。儀式で残すなら、この文化祭の準備期間の、何気ない一日かもしれない。そう思い始めた矢先、僕の価値観は、音を立てて崩れ落ちることになる。
第三章 残酷なセレクト
文化祭も終わり、儀式まであと数日と迫った、秋風が吹き始めた日の放課後だった。夕陽が差し込む教室で、僕は陽菜と二人きりだった。僕は、陽菜と一緒にプラネタリウムを見上げた、あの文化祭最終日の記憶を残そうと、心に決めていた。そのことを彼女に伝えようと口を開きかけた時、陽菜が先に言った。
「私ね、水島くんに、言わなきゃいけないことがあるんだ」
彼女の声は、いつもの弾むような響きを失い、静かに沈んでいた。窓の外では、茜色の空に一番星が瞬き始めている。
「私、本当は十九歳なんだ。去年、一年間休学してたの」
言葉の意味が、すぐには理解できなかった。十九歳。それはつまり、彼女が既に「追憶の儀」を経験していることを意味する。僕の頭は真っ白になった。
「去年…儀式を終えたんだ。私が残した記憶はね、高二の夏、水島くんと初めて会った日の記憶だった」
「え……?」
「図書室で、難しい顔して写真集を見てる水島くんを見かけたの。なんだか、すごく真剣で、世界で一人だけみたいに見えて。声をかけられなかったけど、なぜかあの日のことが忘れられなくて。だから、その一日を残したんだ」
陽菜は、淡々と語った。まるで、遠い国の物語を話すように。
「でもね、間違ってた。一つの記憶だけを大事に残すと、どうなるか知ってる? 他の、霞んでしまったたくさんの記憶たちが、その一つの輝きを責めるんだよ。『どうして私じゃなかったの』って。楽しかったはずの一日が、失ったものの大きさを突きつけるだけの、重くて苦しいだけの記憶に変わっちゃった。友達と笑い合ったことも、部活で泣いたことも、全部、感情のない白黒の記録になった。残した記憶だけが、孤独に色を持ってる。それって、すごく、すごく残酷なことなんだよ」
彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。夕陽がそれを宝石のようにきらめかせ、彼女の頬を伝っていく。
「だから、私は決めたの。もう一度、この一年をやり直して…今度の儀式では、『何も残さない』っていう選択をするために。記憶に縛られて苦しむくらいなら、全部手放して、ゼロから新しい自分になりたいって。この一年、水島くんと過ごせて本当に楽しかった。最高の思い出ができた。だからこそ、今度は、この最高の思い出ごと、綺麗に手放すの」
衝撃だった。世界が、足元から崩れていくような感覚。「最高の記憶」を残すことは、誰もが憧れる幸福な通過儀礼だと信じて疑わなかった。だが、陽菜はそれを「残酷だ」と言った。残すことは、失うことの証明でしかないと。僕がようやく見つけたと信じた「最高の瞬間」は、彼女にとっては手放すべき過去でしかなかったのだ。
僕が今まで撮ってきた写真は、一体何だったのだろう。瞬間を切り取り、永遠に残す行為。それは、陽菜が言う「残酷なセレクト」そのものではないか。僕はずっと、ファインダー越しに、残酷なことを繰り返してきたのかもしれない。
夕闇が教室を完全に支配する頃、僕は言葉を失くしたまま、ただそこに立ち尽くしていた。陽菜の告白は、僕が拠り所にしてきた価値観のすべてを、粉々に打ち砕いた。
第四章 霞の中の焦点
「追憶の儀」の当日。僕は自室で、陽菜と過ごした日々の写真を広げていた。夏祭り、海、文化祭。どの写真の中の彼女も、太陽のように笑っている。しかし、僕にはもう、その笑顔を無邪気に見ることはできなかった。この輝きの裏にある、彼女の痛みと孤独を知ってしまったから。
どの記憶も、愛おしかった。どれか一つを選ぶなんて、不可能に思えた。陽菜の言葉が、何度も頭の中で反響する。「残した記憶だけが、孤独に色を持ってる」。もしそうなら、僕が選ぶべき記憶とは、一体何なのだろう。
時間だけが刻一刻と過ぎていく。儀式を執り行う施設の白い部屋で、僕は目を閉じた。脳裏に、数多の記憶が走馬灯のように駆け巡る。そして、最後に僕の心に浮かび上がったのは、意外な光景だった。
それは、夕暮れの教室。陽菜が、涙を流しながら「何も残さない」と僕に告白した、あの一日だった。
最高に輝かしい瞬間ではない。むしろ、痛みと哀しみに満ちた、切ない記憶だ。けれど、あの瞬間にこそ、僕の青春のすべてが凝縮されている気がした。陽菜の本当の想い、世界の残酷さ、そして、そんな世界でもがきながら懸命に生きようとする人間の美しさ。僕が初めて、ファインダー越しではなく、自分の心で世界と向き合った瞬間。
僕は、その一日を選んだ。
儀式が終わり、目を開ける。世界は昨日と何も変わらないように見えた。けれど、何かが決定的に違っていた。陽菜と過ごした日々の記憶は、その輪郭を失い、霞がかかったように曖昧になっていた。夏祭りの賑わいも、海のしょっぱさも、文化祭の熱気も、もう鮮明には思い出せない。ただ、胸の奥に、確かな温もりだけが残っていた。
そして、陽菜が泣きながら笑った、あの夕暮れの教室の光景だけが、焼き付いたフィルムのように、僕の中に鮮烈に残っている。
僕は、カメラを手に街へ出た。陽菜が、約束通り「何も残さない」選択をしたのか、僕には知る術がない。彼女が今、どんな「今」を生きているのかも。
でも、それでいいと思った。僕が残したこの痛みを伴う記憶は、僕が彼女の苦しみを忘れないという誓いだ。そして、失われた無数の記憶たちへの、僕なりの弔いだ。青春とは、一つの輝かしいハイライトではない。成功も失敗も、喜びも悲しみも、そのすべてが混ざり合った、美しいグラデーションなのだ。
僕はカメラを構え、ファインダーを覗く。霞んだ記憶の向こうに広がる、新しい世界。これから僕は、何を撮るのだろう。答えはまだない。だが、シャッターを切る指先に、迷いはなかった。失われたものの代わりに、これからの未来を刻みつけていくために。僕の青春は、一枚のセピア色の記憶を道標に、今、静かに始まったのだから。