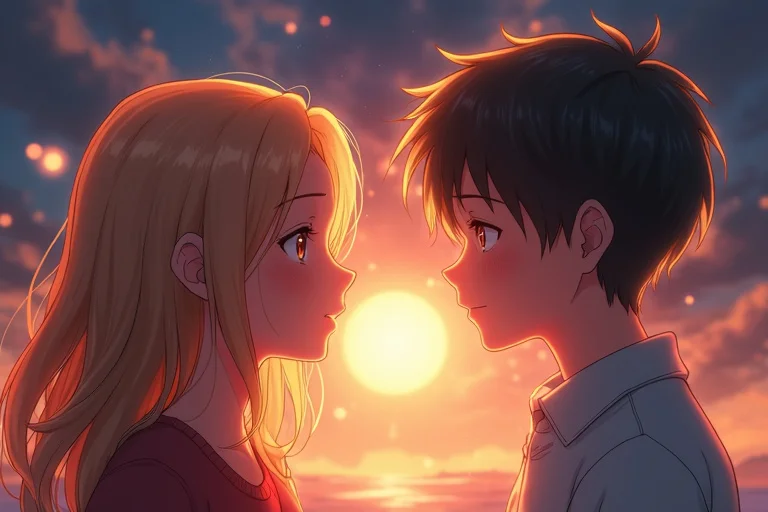第一章 白色のサイレンス
僕、水島湊(みなしま みなと)の世界は、音が色を纏って降り注ぐ。それは生まれつきの体質で、共感覚というらしい。クラスメイトの軽薄な笑い声は、安っぽいターコイズブルーの飛沫となって弾ける。教師の退屈な説教は、澱んだ灰色の霧となって教室に滞留する。誰かが嘘をつけば、その声はたちまち粘ついた焦茶色に変色し、僕は息が詰まりそうになる。世界は、僕にとってあまりにも騒々しく、不誠実な色彩で溢れかえっていた。
だから、僕にとって月島陽菜(つきしま ひな)は、唯一の避難場所だった。
幼馴染の彼女の声だけは、どんな時でも、純粋な「白色」だった。それはまるで、降り積もったばかりの雪原のように静かで、汚れない光。彼女が「おはよう、湊」と微笑むだけで、僕の周りを渦巻く雑多な色が浄化されていくような気さえした。彼女の隣だけが、僕が心から安らげる無音の世界だった。
その日も、そうであるはずだった。
放課後の美術室。西日が差し込み、床に長い影を落としている。陽菜が、全国高校美術コンクールで大賞を受賞したというニュースが、学校中を駆け巡っていた。僕は自分のことのように嬉しくて、イーゼルの前に立つ彼女の元へ駆け寄った。
「陽菜、おめでとう! すごいじゃないか!」
僕の声はきっと、興奮で鮮やかな金色に輝いていたはずだ。
陽菜は振り向くと、いつもと変わらない穏やかな笑みを浮かべた。油絵の具の匂いが、彼女の輪郭をふちどっている。
「ありがとう、湊。なんだか、まだ実感が湧かないや」
その声は、いつもの、僕を安心させる純粋な白色だった。僕は心の底から安堵し、彼女の快挙を祝福した。だが、その刹那だった。
「本当に、嬉しいよ」
そう言った陽菜の声。その純白の光の中心に、ほんの一瞬、インクを垂らしたような「漆黒」の点が、ゆらりと揺らめいたのだ。それは僕がこれまで十六年間、一度も見たことのない色。光をすべて飲み込むような、底なしの闇の色だった。
それは瞬きする間に消え去り、彼女の声はまた完璧な白色に戻っていた。僕の見間違いだったのかもしれない。西日が目に悪戯をしただけかもしれない。
しかし、僕の心臓は、警鐘のように激しく鳴り響いていた。僕の安息所だった陽菜の「白色」に、初めて生まれた異物。その漆黒の染みは、僕らの世界の完璧な調和に穿たれた、小さな、しかし致命的な亀裂のように思えた。
第二章 揺らぐプリズム
あの日以来、僕の世界は静かに歪み始めた。陽菜は普段通りだった。いつもと同じように笑い、同じように僕の名前を呼んだ。彼女の声は、変わらず清らかな白色を保っている。しかし、僕にはもう、その白を無邪気に信じることができなかった。一度見てしまった漆黒の残像が、瞼の裏に焼き付いて離れないのだ。
僕は、呪わしいとさえ思っていた自分の能力を、初めて渇望した。もっとはっきりと、陽菜の声の色を見たい。彼女の心の内側を、真実を、この目で確かめたい。
僕は陽菜を観察するようになった。彼女は受賞の取材や、周囲からの祝福に追われ、忙しそうにしていた。その笑顔に翳りはないように見える。だが、ふとした瞬間、彼女が窓の外へ向ける視線には、僕の知らない色が滲んでいるような気がした。それはまるで、遠い星を見つめるような、途方もない孤独の色だった。
ある日の帰り道、僕は思い切って尋ねてみた。
「なあ、陽菜。最近、何か悩みでもあるのか?」
僕の声は、不安でくすんだ藤色に震えていたに違いない。
陽菜は一瞬、驚いたように目を見開いたが、すぐに首を横に振った。
「ううん、何でもないよ。どうして?」
完璧な白色の声。だが、僕はその白の向こう側を透かして見ようと、必死に目を凝らしていた。何も見えない。ただ、深く、静かな白があるだけだ。
僕らの間に、見えない壁が生まれたのを感じた。それは陽菜が築いたのか、それとも僕の疑念が生み出したのか、分からなかった。
手がかりを探して、僕は陽菜の親しい友人に話を聞いてみた。彼女は最近、学校の裏手にある丘の上の、今は使われていない古い天文台によく一人で行っているらしい。星が好きだったなんて、初耳だった。僕の知らない陽菜が、そこにはいるのかもしれない。
週末、僕は丘の上へと向かった。錆びついた鉄の扉を開けると、埃っぽい空気と、微かなカビの匂いが鼻をつく。螺旋階段を上り、ドーム状の観測室へ出た。中はがらんとしていて、中央に鎮座する巨大な望遠鏡だけが、かつての栄光を物語っている。
そして、そこに陽菜はいた。
彼女は大きなキャンバスに向かい、一心不乱に筆を動かしていた。描かれているのは、満天の星空。しかし、その星々は、燃えるような赤や、凍えるような青、悲しみを湛えた紫など、現実にはありえない、激しい感情の色で描かれていた。まるで、誰かの心の叫びを、そのまま夜空にぶちまけたような絵だった。
僕の足音に気づき、陽菜がゆっくりと振り返る。その顔には、驚きと、そして諦めが入り混じったような、複雑な色が浮かんでいた。
第三章 無色の告白
「どうして、ここに?」
陽菜の声は、静かな白色だった。しかし、その白はもはや僕を安心させてはくれなかった。それはまるで、あまりに強すぎる光で真実を覆い隠す、眩惑の白のように感じられた。
「お前のことが、分からなくなったんだ」僕は正直に告げた。「コンクールの日、お前の声に黒い色が見えた。あれは、何だったんだ? この絵は、何なんだ?」
陽菜は僕から視線を外し、描きかけの星空に目を戻した。ドームの隙間から差し込む夕光が、彼女の横顔をオレンジ色に染めている。長い沈黙の後、彼女はか細い、けれどはっきりとした声で言った。
「湊は、自分のその眼が、嫌い?」
「当たり前だろ」僕は即答した。「人の嘘や偽りばかりが見えて、うんざりする。お前の声だけが、俺の救いだったのに」
「……ごめんね」
陽菜の謝罪は、僕が予想していたものとは全く違っていた。彼女はゆっくりと僕に向き直る。その瞳は、何か重いものを覚悟したように、まっすぐに僕を射抜いていた。
「湊が、自分の能力で苦しんでるのは、小さい頃から知ってた。人の声の色が見えるって、打ち明けてくれた時から」
彼女は続ける。
「だから、決めたの。湊といる時だけは、湊が安らげるようにって。私の声から、『色』を消そうって」
頭を殴られたような衝撃だった。色を、消す?
「どういう、ことだ……?」
「私にも、少しだけ、変わった力があるの。それは……他人の感覚を、少しだけ遮断する力」
陽菜の告白は、僕の常識を根底から覆した。彼女の「白色」は、純粋さの象徴などではなかった。それは、色が「ない」状態。彼女が、僕の共感覚から僕自身を守るために、彼女自身の力で作り出した、人工的な静寂だったのだ。
「でも、最近、この力が弱くなってきた。コンクールの時もそう。大賞のプレッシャーとか、将来への不安とか、強い感情が溢れそうになって……抑えきれなかった。あの黒い色は、私の絶望の色。湊に見せたくなかった色」
彼女の白い声が、微かに震え始めた。僕は言葉を失くして立ち尽くす。僕が安らぎだと思っていたものは、陽菜の優しさと、孤独な戦いの証だった。彼女はずっと一人で、僕のためにその力をコントロールし続けてきたのだ。僕が彼女の白に安堵している間、彼女はたった一人で、自分の心に溢れる色彩を押し殺していた。
「この絵は?」
僕は、感情が爆発したような星空の絵を指さした。
「ここにいる時だけは、本当の自分の色を出せるから。抑え込んでた気持ちを、全部ここにぶつけないと、私、壊れちゃいそうだった」
陽菜の頬を、一筋の涙が伝った。その瞬間、僕は見た。彼女の「ごめんね」という声に、今まで見たこともない、淡く、儚い水色の光が灯るのを。それは後悔と、安堵と、そしてほんの少しの恐怖が入り混じった、あまりにも人間的で、美しい色だった。
第四章 きみが灯す色
僕が求めていた真実は、あまりにも切なく、そして温かかった。僕はずっと、陽菜に守られていただけだったのだ。彼女の犠牲の上に成り立つ安らぎに、甘えていただけだった。自分の無力さと、彼女の愛情の深さに、胸が張り裂けそうになった。
僕は一歩、彼女に近づいた。そして、震える声で言った。
「もう、いいんだ。陽菜」
僕の声は、きっと涙で濡れた、深い藍色をしていたと思う。
「もう、隠さなくていい。俺は、陽菜の本当の色が見たい。嬉しい色も、悲しい色も、怒った色も……どんな色だって、全部。俺が受け止めるから。これからは、俺がお前の避難場所になる」
僕の言葉に、陽菜は堰を切ったように泣き出した。嗚咽と共に漏れる彼女の声は、まるでプリズムを通り抜けた光のように、様々な色に変化した。感謝の金色、安堵の若草色、悲しみの青、そして僕への愛情を示す、柔らかな桜色。それは僕が今まで見てきたどんな色彩よりも鮮やかで、生命力に満ち溢れていた。
僕の世界は、色で溢れている。それはこれからも変わらないだろう。嘘や偽りの濁った色に、うんざりすることもあるはずだ。
でも、もう僕は自分の能力を呪わない。この眼は、世界を呪うためではなく、たった一人の大切な人の心を、その本当の色彩を、理解するためにあるのだと知ったから。
天文台の窓から、一番星が瞬き始めた。僕らは言葉もなく、陽菜が描いた感情の星空と、本物の星空を、並んで見上げていた。隣で静かに息をする陽菜の声からは、穏やかで温かい、乳白色の光が灯っていた。それはもう、全てを遮断する無機質な白ではない。あらゆる感情の色を、優しく包み込む、生命の光の色だった。
世界は相変わらず騒々しい色彩に満ちている。けれど、僕の隣には、真実の色を灯してくれる君がいる。それだけで、この世界は、もう怖くはなかった。