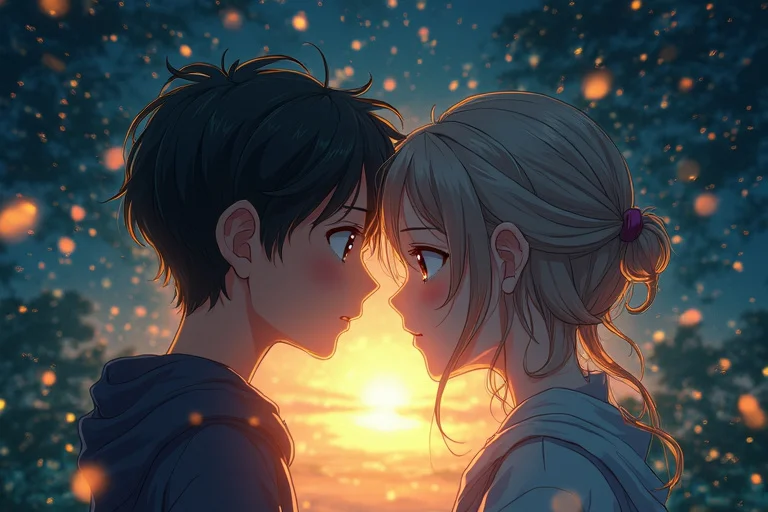第一章 硝子の心臓
僕、水野蒼(みずの あお)の身体には、奇妙な機能が備わっている。感情が高ぶると、その情動が小さな結晶となって、汗のように肌から滲み出てくるのだ。医者にも説明できない、僕だけの秘密。
怒りは、濁った血のような赤黒い礫(つぶて)に。喜びは、陽光を閉じ込めたような金色の砂粒に。そして、悲しみは、澄んだ空を映したような青い雫になる。僕はそれらを採集し、机の引き出しに仕舞った古い標本箱に種類ごとに並べていた。それはまるで、自分自身の心を解剖し、陳列しているかのようだった。客観的に眺めることで、揺れ動く感情の奔流から、かろうじて自分を保っていられる気がした。
コレクションの中で、僕が最も大切にしている宝物がある。小指の先ほどの大きさの、深く、吸い込まれそうな瑠璃色の結晶。それは僕がまだ幼かった頃、亡くなった姉と過ごした最後の夏祭りの夜に生まれたものだ。綿飴の甘い匂い、夜空を焦がす花火の音、繋いだ手の温もり。僕の人生における、最も純粋で、凝縮された幸福の記憶。そう信じていた。この瑠璃色の結晶を眺めている時だけ、僕は孤独ではないと感じられた。
高校二年の春、僕の静かな世界に、小さな波紋が広がった。転校してきた月島燈(つきしま あかり)という女子生徒が、僕の隣の席になったのだ。彼女は太陽みたいな子だった。誰にでも屈託なく笑いかけ、その周りにはいつも明るい空気が流れていた。僕のような日陰の存在とは、住む世界が違う。そう思っていた。
ある日の放課後、僕は教室で、不意に訪れた寂寥感から生まれた小さな水色の結晶を、誰にも見られないよう、そっとハンカチに包もうとしていた。それは昼休みの喧騒の中で感じた疎外感の欠片だった。
「わぁ、綺麗」
背後から、息のかかるような距離で声がした。心臓が跳ねる。振り返ると、そこに月島さんがいた。彼女の視線は、僕の指先にある、米粒ほどの水色の結晶に真っ直ぐに注がれていた。
「それ、ソーダ味の飴?すごく澄んだ色だね」
普通の人間には、それはただの硝子片か、プラスチックのゴミにしか見えないはずだった。感情の彩りなど、見えるわけがない。なのに彼女は、僕の結晶が持つ「色」を、あまりにも自然に言い当てた。
僕は咄嗟に手を握りしめ、結晶を隠した。
「なんでもない。見間違いだ」
早口でそう言って鞄を掴むと、逃げるように教室を後にした。背中に突き刺さる彼女の視線は、好奇心だろうか、それとも――。
この日から、僕の心臓は、まるで硝子細工のように、些細なことでひび割れそうになるのだった。月島燈という存在が、僕が固く閉ざしてきた世界の扉を、静かにノックし始めていた。
第二章 共鳴しない旋律
月島さんと関わるようになってから、僕の標本箱は忙しなくなった。彼女と目が合うだけで生まれる、蜂蜜色の小さな結晶。彼女の笑顔を思い出すたびに零れる、淡い薔薇色の欠片。僕はそれを「興味」や「好意」のカテゴリーに分類しながらも、日に日に増えていく暖色系の結晶たちに、どうしようもない戸惑いを覚えていた。
彼女は、僕が意図的に張っていた見えない壁を、いともたやすく通り抜けてきた。昼休みには「水野くん、一緒に食べよ」と弁当を持って隣に座り、移動教室では「ねぇ、次の授業って何だっけ?」とごく自然に話しかけてくる。その度に、僕の心臓は軋みを上げ、肌からは様々な色の感情が滲み出そうになるのを、必死で抑え込んだ。この体質を知られたら、きっと気味悪がられる。化け物だと思われる。その恐怖が、僕を臆病にさせた。
文化祭の準備が始まると、僕たちはさらに多くの時間を共に過ごすことになった。僕たちのクラスは、お化け屋敷をやることになった。僕は昔から絵を描くのが得意だったため、背景画や小道具のデザインを担当することになった。月島さんは、持ち前の明るさでクラスの実行委員をまとめあげていた。
ある夕暮れ、誰もいなくなった美術準備室で、僕は壁一面に貼る巨大な背景画を描いていた。描いていたのは、古びた洋館の、月明かりが差し込む窓辺の風景。集中していると、不意に珈琲の香りがした。
「お疲れ様。差し入れ」
月島さんが、紙コップを二つ持って立っていた。彼女は僕の隣に腰を下ろし、描きかけの絵をじっと見つめた。
「すごいね、水野くん。この絵、なんだか…悲しいくらい綺麗」
彼女の言葉に、僕は筆を止めた。僕の絵から、彼女は僕が込めた静かな寂寥感を正確に読み取っていた。僕たちはしばらく黙って、並んで珈琲を飲んだ。沈黙が苦にならない、不思議な時間だった。
「月島さんは、どうしてそんなに明るいの?」
自分でも驚くほど、素直な疑問が口をついて出た。
彼女は少しだけ遠い目をして、それからふわりと笑った。
「そう見える?…でもね、明るくしていないと、潰れちゃいそうになる時もあるよ」
その笑顔の裏に、深い影が潜んでいるのを感じた。その瞬間、僕は理解した。彼女もまた、何かを必死で隠し、何かに耐えているのだと。僕と同じように。
この人に、僕の本当の心を見せたい。僕が一番大切にしている、あの瑠璃色の輝きを共有したい。僕の「最高の幸福」を見せれば、彼女の心にある影も、少しは晴れるかもしれない。そんな衝動が、恐怖心を上回って、僕の中で大きく膨らんでいった。
文化祭の最終日、夜の校舎に提灯の明かりが灯る頃、僕は月島さんを呼び出す決心をした。
第三章 偽りの瑠璃色
文化祭の喧騒が嘘のように静まり返った屋上は、僕と月島さんの二人だけの舞台だった。ひんやりとした夜風が、火照った頬を撫でていく。遠くで聞こえる後夜祭のバンド演奏が、僕たちの間の沈黙を埋めていた。
「話って、何?」
月島さんが、期待と不安が入り混じったような声で尋ねた。
僕はポケットから、小さな布の包みを取り出した。心臓が早鐘を打つ。指先の震えを抑えながら、ゆっくりとそれを開いた。現れたのは、夜の闇の中でもなお、内側から光を放つかのように輝く、あの瑠璃色の結晶だった。
「これ…僕の宝物なんだ」
僕は、用意していた言葉を紡いだ。
「僕が一番幸せだった時の記憶。亡くなった姉さんと行った、最後の夏祭り。この結晶を見るたびに、僕は一人じゃないって思えるんだ。月島さんにも、僕の幸せを、少しだけおすそ分けしたくて」
月島さんは、僕の手のひらに乗った結晶を、息を詰めて見つめていた。その表情が、みるみるうちに青ざめていくのを、僕は見逃さなかった。彼女は何かを堪えるように唇をきつく結び、それからゆっくりと自分のスカートのポケットに手を入れた。
彼女が取り出したものを見て、僕は息を呑んだ。
彼女の手のひらにあったのは、僕のものと寸分違わぬ、深く、静かな輝きを放つ瑠璃色の結晶だった。
「違う…」
彼女の声は、夜風に掻き消えそうなほどか細く、震えていた。
「水野くん、それは…喜びの結晶じゃない」
何を言っているんだ?理解が追いつかない。僕の頭は真っ白になった。
「感情の結晶はね、本当は…喜びや愛情みたいな温かい感情は、金色や橙色になるの。太陽みたいな、暖かい色に」
彼女は泣きそうな顔で続けた。
「そして…悲しみや絶望は、青や紫になる。深く、冷たい色に。この瑠璃色は…私たちが今まで経験した、どんなものよりも深い…耐え難いほどの『喪失』と『悲しみ』の色だよ」
彼女の言葉が、ハンマーのように僕の頭を殴りつけた。
喪失?悲しみ?そんなはずはない。だって、あの夏祭りの夜は、あんなにも楽しくて、輝いていたじゃないか。
その瞬間、僕の脳裏に、鍵をかけて固く閉ざしていた記憶の扉が、凄まじい音を立ててこじ開けられた。
――そうだ。あの夏祭りの夜。花火の音に紛れて、甲高いブレーキ音と、人の悲鳴が響いた。僕の手を引いていた姉の身体が、ふわりと宙に浮いた。人混みに押されて転んだ僕の目の前で、姉の赤い浴衣が、アスファルトの上でさらに濃い赤色に染まっていく。助けを呼ぶ声も出せず、ただ、その光景を見ていることしかできなかった僕の心から、何かがごそりと抜け落ちていった。
あの瑠璃色の結晶は、幸福の記憶などではなかった。それは、姉を失った瞬間の、声にならない絶望と、時間を止めてしまった深い哀しみの塊だったのだ。僕は、耐えきれないほどの悲しみを「最高の幸福」だと思い込むことで、自分自身を守っていた。偽りの記憶で、本当の痛みに蓋をしていたのだ。
「ああ…あああああ…」
喉の奥から、獣のような声が漏れた。足元から世界が崩れ落ちていく。僕が拠り所にしてきた全てのものが、ガラガラと音を立てて砕け散った。僕の宝物は、僕の青春は、全てが偽りだった。
第四章 透明な夜明け
僕が立っていられなくなり、その場に崩れ落ちると、月島さんがそっと隣に膝をついた。彼女は何も言わず、ただ静かに、自分の瑠璃色の結晶を僕の結晶の隣に置いた。二つの深い青は、まるで共鳴するように、悲しく、そして美しく輝いていた。
「私も、同じ。二年前に、たった一人の家族だった母を亡くしたの。その時の結晶」
彼女の声は、涙で濡れていた。
「だから、わかるよ。痛いほどに。この色が、どれだけ重たいか」
彼女の告白は、僕の凍てついた心に、小さな灯火をともした。僕は一人じゃなかった。この耐え難いほどの悲しみを、同じように抱えて生きている人が、すぐそばにいたのだ。
堰を切ったように、僕の目から涙が溢れ出した。姉の名前を呼び、声を上げて泣いた。これまでずっと押し殺してきた、ありのままの感情だった。悲しくて、悔しくて、寂しくて、どうしようもなかった。偽りの幸福にすがりついていた、弱い自分自身が情けなかった。
涙は、頬を伝って、コンクリートの床にいくつもの染みを作った。そして、その涙の雫が、ぽつり、ぽつりと、小さな結晶になっていくのが分かった。それは、瑠璃色ではなかった。赤でも、金色でもない。
光にかざすと、向こう側が透けて見えるほどに、どこまでも無色透明な結晶だった。
それは、偽りも飾りもない、純粋な「解放」の涙だったのかもしれない。僕が初めて、自分の本当の悲しみと向き合い、それを受け入れた証だった。
泣き疲れて、声も出なくなった僕の肩を、月島さんはそっと抱き寄せた。彼女の温もりが、じんわりと心に沁みていく。
やがて東の空が白み始め、夜の闇が薄れていく頃、僕は顔を上げた。手の中には、二つの結晶が残っている。一つは、偽りの幸福であり、真実の悲しみである瑠璃色の結晶。もう一つは、今生まれたばかりの、透明な結晶。
僕は瑠璃色の結晶を捨てなかった。これもまた、紛れもない僕自身の一部なのだ。この深い悲しみがあったからこそ、僕は今、ここにいる。
「月島さん」
僕は、まだ少し掠れた声で彼女を呼んだ。
「君の他の結晶も、見せてくれる?」
僕の問いに、彼女は一瞬驚いたように目を見開き、それから、夜明けの空のように、柔らかく微笑んだ。
「うん。私の全部、見てほしい」
僕たちの青春は、輝かしい光だけではできていなかった。それは、深い悲しみの色を知り、互いの痛みにそっと触れ合うことで、初めて輪郭を持つものだったのかもしれない。僕たちはこれから、たくさんの色の結晶を、共に集めていくのだろう。喜びも、悲しみも、その全てを抱きしめながら。
僕の手のひらに残った透明な結晶は、朝陽を浴びて、小さな虹色の光を放っていた。