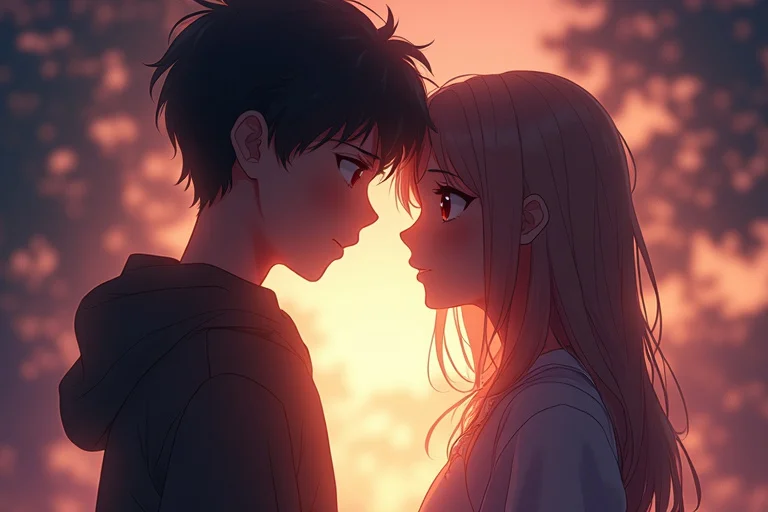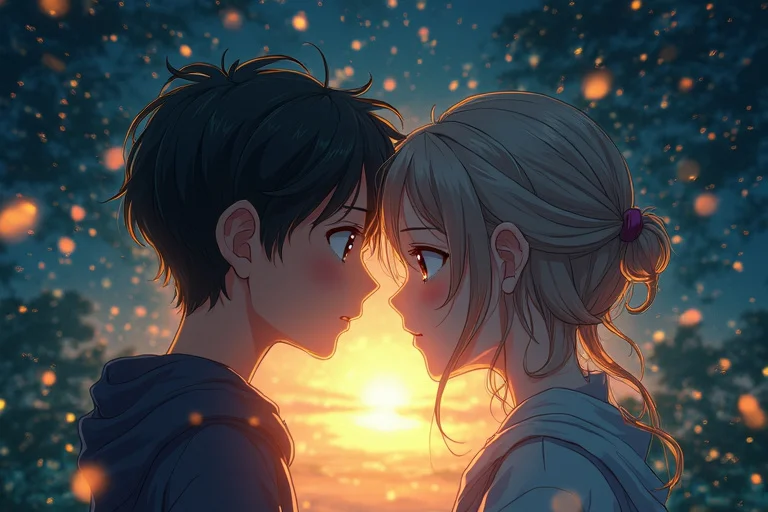第一章 無色の少女
僕、水島湊(みなしま みなと)の世界は、常に他人の感情の色で飽和していた。人の頭の周りに、オーラのように揺らめく光の靄。それは、その人が強く抱える記憶の色だった。楽しかった思い出は温かな蜜柑色に、胸を焦がす恋心は淡い桜色に、そして、どうしようもない後悔は、澱んだ鉛色に光る。
この能力は、物心ついた頃からの呪いだった。誰もが笑顔の裏に隠した嫉妬の深緑や、優しい言葉の奥に潜む悲しみの藍色が見えてしまう。だから僕は、人と深く関わることを諦めた。ヘッドフォンで耳を塞ぐように、僕は心を閉ざし、色に溢れた世界との間に透明な壁を築いて生きてきた。教室の隅、窓際の席が僕の定位置。そこから見える、カラフルで騒がしい同級生たちの群れは、まるで遠い国の出来事のようだった。
そんな灰色の日常に、ある日、一筋の光が差し込んだ。いや、正確に言えば「光のない空間」が生まれたのだ。
転校生、月島咲(つきしま さき)。彼女が教室に入ってきた瞬間、僕は息を呑んだ。美しさや、快活な自己紹介にではなかった。彼女の周りには、色が、一切なかったのだ。まるで彼女という存在が、僕の視界にだけ存在するノイズキャンセリング機能を発動させたかのように、そこだけが完全にクリアだった。他の生徒たちの頭上で渦巻く様々な色が、彼女の数メートル手前で吸い込まれるように消える。
それは僕にとって、生まれて初めて体験する「静寂」だった。色の洪水から解放された、安らぎの空間。僕は無意識のうちに、その無色透明な彼女の存在に強く惹きつけられていた。
「隣、いいかな?」
昼休み、僕が一人で弁当を広げていると、咲が屈託のない笑顔で話しかけてきた。断る理由も、断る気もなかった。彼女が隣に座ると、僕の周りを囲んでいた息苦しい色の靄が、すうっと晴れていくのを感じた。
「水島くん、いつも音楽聴いてるよね。何聴くの?」
「……別に、なんでも」
素っ気ない返事しかできなかったが、咲は気にした様子もなく話を続けた。彼女の言葉は、まるで澄んだ湧き水のように、僕の乾いた心に染み込んでいく。彼女と一緒にいる間は、他人の心の裏側を覗き見てしまう苦痛から解放される。この平穏が、ただただ心地よかった。
なぜ彼女だけが無色なのか。記憶がないのだろうか?それとも、僕の能力が彼女にだけは通用しないのだろうか?謎は深まるばかりだったが、今は理由などどうでもよかった。この安らぎが一日でも長く続くことだけを、僕は願っていた。
第二章 偽りの平穏と藍色の影
咲と過ごす時間が増えるにつれて、僕の世界は変わり始めた。文化祭の実行委員に半ば強引に推薦された時も、昔の僕なら断っていただろう。だが、隣で「一緒にやろうよ!」と微笑む咲の無垢な顔を見ると、頷く以外の選択肢はなかった。
買い出しのために二人で歩く放課後の雑踏も、彼女と一緒なら苦痛ではなかった。行き交う人々の頭上には、相変わらず不安の灰色や欲望の赤紫色が渦巻いている。けれど、僕の隣には咲がいた。彼女という絶対的な無色の領域が、僕を守る盾となってくれている。
「湊くんって、本当は優しいよね」
段ボール箱を抱えながら、咲がふと言った。僕の名前を初めて呼んだ彼女の声に、心臓が跳ねる。
「そう見えないだけで」
「ううん、わかるよ。なんとなく」
彼女は時々、こうして僕の心の芯を射抜くようなことを言う。そして、何かを思い出すかのように、ふと遠い目をする癖があった。その度に僕は、彼女が何か大切な記憶を失っているのではないかという疑念を強くした。無色なのは、やはり彼女の中に強い記憶が存在しないからなのだろうか。
そんな穏やかな日々に、時折、不穏な影が差した。幼なじみの木戸蓮(きど れん)だ。快活なバスケ部のエースで、彼の周りはいつも練習の充実感を示す鮮やかなオレンジ色や、仲間との友情を物語る黄色に輝いている。彼は僕と咲の関係を、いつも少し離れた場所から微笑ましそうに見守っていた。
だが、ある雨の日だった。部活が休みになった蓮が、教室で窓の外を眺めていた。その背中から、僕は今まで見たこともないほど深く、冷たい藍色が立ち上っているのを見た。それはただの悲しみではなかった。後悔と、罪悪感と、どうしようもない喪失感が複雑に絡み合った、底なしの海の底のような色だった。
「蓮……?」
僕が声をかけると、蓮はびくりと肩を震わせ、慌てて振り返った。その瞬間、藍色は嘘のように掻き消え、いつもの快活なオレンジ色が彼の周りに戻ってきた。
「よお、湊。どうしたんだ、そんな真剣な顔して」
「いや……なんでもない」
彼は何事もなかったかのように笑う。だが、僕には分かった。蓮は、何かとてつもなく重い秘密を抱えている。そしてその秘密の藍色は、僕が咲と親しくなればなるほど、その濃さを増していくようだった。
偽りの平穏。僕が手に入れた安らぎは、まるで薄氷の上にあるかのように、危うく、脆いものに思えてならなかった。
第三章 色褪せた真実
文化祭当日。校内は熱気に包まれ、生徒たちの記憶の色がそこかしこで火花のように弾けていた。僕は咲と一緒にクラスのカフェの呼び込みをしていた。彼女の隣は、やはり世界で唯一の安全地帯だった。
その時だった。ステージで演奏していた軽音楽部のギターの弦が、甲高い音を立てて切れた。その衝撃音に、周りの生徒たちが一斉に驚きの声を上げる。僕も、咲も、その音に耳をふさいだ。
しかし、咲の様子がおかしかった。彼女は真っ青な顔で頭を抱え、ぜえぜえと苦しそうに息をしている。
「咲! どうしたんだ!」
「……音が、頭に……なにか、思い出しそう……」
その瞬間、信じられない光景が僕の目に飛び込んできた。今まで完全な無色だった咲の身体から、夥しい量の「色」が奔流のように溢れ出したのだ。悲しみの藍、苦痛の赤、後悔の鉛色、そして、僕が決して見たことのない、眩いほどの純白の光――。色の洪水は僕を直撃し、脳内に無数のイメージが流れ込んできた。
幼い頃の記憶。公園の砂場。泣いている僕。隣で笑う、今より少し幼い蓮。そして、僕の手を握る、小さな女の子。
――違う。彼女は、月島咲じゃない。僕には、知らないはずの女の子だ。
混乱する僕の前に、蓮が血相を変えて駆け寄ってきた。
「咲! しっかりしろ!」
蓮が咲の肩を掴んだ瞬間、彼の周りにあの深い、深い藍色が渦を巻いた。そして、その藍色の記憶もまた、僕の脳内に流れ込んでくる。
雨の日の交差点。けたたましいブレーキ音。飛び出してきた猫を庇って、トラックの前に倒れる幼い僕。そして、僕を庇うように覆いかぶさった、あの女の子――。
「思い……出した……」
咲が、か細い声で呟いた。彼女は涙を流しながら、僕を見つめていた。
「湊くん……ごめんね」
全てのピースが、絶望的な形で繋がった。
咲は、記憶を失っていたわけではなかった。僕と同じ――いや、僕以上の能力者だったのだ。彼女が無色だったのは、自分の記憶の色を完全に「消去」する力を持っていたから。僕に安らぎを与えるためだけに。
そして、蓮の藍色の記憶が、最後の真実を告げていた。
数年前のあの日、事故に遭ったのは僕だった。瀕死の僕を前にして、幼い咲は、自らの生命エネルギーそのものである「記憶の色」のほとんどを僕に注ぎ込み、命を救った。その代償として、彼女は自らの記憶の大半と、色を鮮やかに放つ力を失った。蓮は、その全てを見ていた唯一の証人だった。彼の藍色は、僕に真実を告げられなかった罪悪感と、咲を止められなかった後悔の色だったのだ。
僕が持っていたこの能力は、僕自身のものじゃなかった。
それは、咲が命懸けで僕に与えてくれた、彼女の記憶のかけらだった。
僕が感じていた孤独も、苦悩も、全ては彼女の壮絶な自己犠牲の上に成り立っていた。足元が崩れ落ちるような感覚。僕が「呪い」と呼んでいたものは、彼女からの「祈り」だったのだ。
第四章 きみがくれた色の世界で
真実の奔流は、僕の価値観を根底から破壊した。僕が築いてきた壁は、彼女の優しさでできていた。僕が逃げていた世界は、彼女が守ってくれた世界だった。
しばらく呆然としていた僕だったが、ふと、咲から受け継いだこの「力」で、僕にしかできないことがあると気づいた。僕は、涙でぐしゃぐしゃの顔を上げた咲と、罪悪感に苛まれる蓮の前に、ゆっくりと歩み寄った。
「咲」
僕は彼女の名前を呼んだ。そして、初めて、自分の意志でこの能力を使った。
「見てほしいものがあるんだ」
僕は、僕自身の記憶に意識を集中させた。
――初めて咲と会った日の、驚きと安らぎの記憶。それは、透明な水晶のような色をしていた。
――彼女と初めて言葉を交わした時の、ぎこちないけれど温かい記憶。淡い陽だまりのような色。
――文化祭の準備で笑い合った、たくさんの日々。弾けるような、鮮やかな蜜柑色の記憶。
僕が咲と出会ってから生まれた、たくさんの、たくさんの色。それら全てを、僕は彼女に見せた。僕の頭の周りに、僕だけの記憶の色が、万華鏡のようにきらめいた。
「きみがくれたこの力で、僕は救われた。きみと出会ってからの僕の世界は、こんなにも彩り豊かだったんだよ」
僕の言葉と色を受け取って、咲の瞳から再び涙が溢れた。だが、今度の涙は絶望の色ではなかった。彼女の周りに、今まで決して見えなかった、ごく淡い、しかし確かな光が灯り始めた。それは、新しい記憶が芽生えた瞬間の、生まれたての虹のような色だった。
「……ありがとう、湊くん」
隣で、蓮が静かに泣いていた。彼の周りを覆っていた深い藍色は、少しだけその色合いを和らげ、雨上がりの空のような澄んだ青に変わり始めていた。過去は消えない。罪悪感が完全になくなることもないだろう。それでも、彼は一歩前に進む覚悟を決めたのだ。
あの日から、僕の世界は何も変わらない。世界は相変わらず様々な記憶の色で溢れている。けれど、僕自身の世界は、完全に変わった。もう、他人の色を見ることを恐れはしない。この力は呪いではなく、僕と咲とを繋ぐ、かけがえのない絆の証なのだから。
夕日に染まる帰り道。僕と、少しだけ表情が柔らかくなった咲と、どこか吹っ切れたような顔をした蓮と。三人で並んで歩く。僕らの周りには、悲しみの藍色も、喜びの蜜柑色も、そして未来への希望を宿した新しい虹色も、全てが混じり合って、静かに、そして美しく輝いていた。
僕は、きみがくれたこの色の世界で、ようやく本当の意味で、息を始めた。