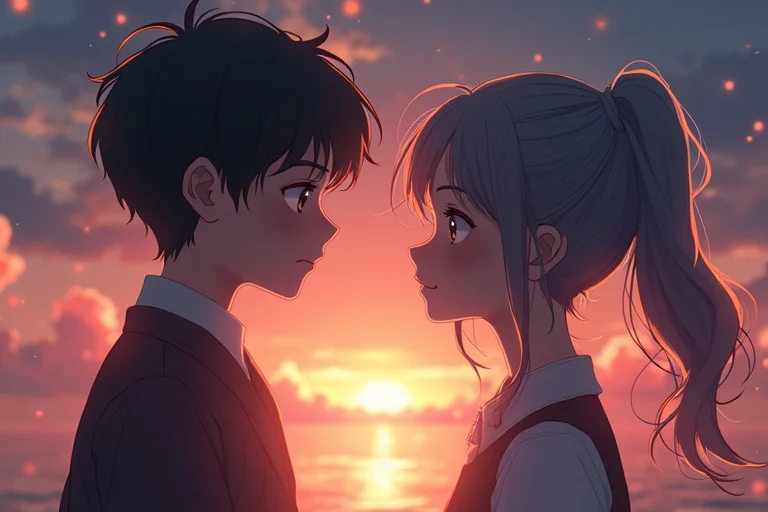第一章 終わらない空白の朝
それは、ある朝の光景から始まった。僕は目覚まし時計の電子音で飛び起き、反射的に手を伸ばして止めた。カーテンの隙間から差し込む朝日に目を細め、一瞬、どこか懐かしいような、しかし同時に全く見覚えのない部屋の景色が目に飛び込んできた。
「……あれ?」
脳裏に浮かぶのは、霧がかったように曖昧な映像ばかり。昨日の夕食は何だっただろう? 誰と話した? 今日は何曜日で、何をすべき日だった? 全てが白く塗りつぶされたキャンバスのようだった。
僕は慌ててベッドサイドに置かれたノートに手を伸ばした。そこには、乱雑な文字でこう書かれている。
『20XX年9月1日(金)
僕の名前は朝霧 悠。高校二年生。
今日、また記憶がリセットされた。これが「忘却の朝」だ。
大切なことを忘れないよう、毎日ここに記録すること。
親友は「蓮」。彼は絵を描くことが好き。
気になる人は「七海」。彼女は天文部にいる。
今日の予定:学校。倫理の小テスト。放課後、蓮に話しかける。』
ノートのページをめくると、同じような記述が、日付だけを変えてびっしりと書き込まれていた。毎日、毎朝、僕は自分が誰であるか、昨日何があったかをこのノートで「再認識」していたのだ。最初にこの現象が起きたのは、夏休み明けのちょうど二週間前だったと、ノートは教えてくれた。
「また、だ……」
溜息が漏れる。この現象が始まってから、僕の日常は奇妙な空白に満ちたものになった。朝、目覚めるたびに自分がリセットされ、ノートだけが唯一の羅針盤だ。しかし、ノートに書き残されていない出来事、例えば誰かの笑顔や、風の匂い、心臓が跳ねるような瞬間は、まるで夢の残滓のように、朧げな感覚として脳のどこかに残るだけだった。
学校へ向かう道、通学路の銀杏並木が、まだ青々とした葉を揺らしている。その鮮やかな緑さえ、僕にはどこか非現実的に見えた。昨日も同じ道を歩いたはずなのに、記憶がない。この道のどこかに、僕が忘れてしまった大切な何かが隠されているような気がして、僕は無意識のうちに周囲に目を凝らした。
教室に入ると、僕の席の隣には、いつもキャンバスを抱えている親友の蓮がいた。彼は僕の顔を見るなり、少し困ったような、それでも優しい笑顔を向けてくれた。
「おはよう、悠。また、忘れたのか?」
蓮の言葉は、僕が毎朝記憶を失っていることを知っている者のそれだった。
「うん、まただよ。昨日、何かあった?」
僕の問いに、蓮は少しだけ俯き、キャンバスのスケッチを指差した。
「昨日、お前が『この色使い、最高だ』って褒めてくれたんだ。新しい絵のアイデアが浮かんで、ずっと描いてた」
蓮が指差すスケッチには、どこか寂しげな色使いで描かれた、崩壊しかけた古城と、そこから空へと伸びる螺旋階段が描かれていた。僕はそれをじっと見つめ、胸の奥に微かな痛みを感じた。褒めた記憶はないのに、その絵にはなぜか見覚えがあるような気がした。それが「忘却の朝」の、僕にとっての唯一の現実的な手がかりだった。
第二章 記憶の断片、心の地図
その日も、ノートの指示に従い、僕は蓮に話しかけ、倫理の小テストを受け、そして放課後、天文部へと向かった。天文部の部室には、いつも一人、望遠鏡を覗き込んでいる七海の姿があった。
七海は、黒曜石のような瞳で星を見つめる、不思議な魅力を持った少女だ。彼女の周りには、いつも静かで凛とした空気が漂っていた。ノートには「気になる人」と書かれているけれど、その理由までは書かれていない。僕の心臓が、彼女を見るたびに微かに高鳴るのを感じる。これもまた、忘却に抗う感情の残滓なのだろうか。
「七海さん、今日は何か見える?」
僕の問いに、七海はゆっくりと顔を上げた。その視線は、僕の目をまっすぐに見つめ、一瞬にして、僕の心の奥底を覗き込むような錯覚に陥った。
「ええ。今日は、昨日より少しだけ、あの星が明るく見えるわ」
彼女が指差すのは、部室の窓から見える夕焼けの空に、かすかに輝き始めた一番星だ。僕にはただの星にしか見えないが、彼女の言葉には確かな説得力があった。
「昨日も、その星を見てたのか?」
「ええ。あなたも、私と一緒に」
七海の言葉に、僕は驚いた。ノートには、七海と昨日会ったという記述はない。しかし、彼女は僕がいたと言う。僕の記憶から抜け落ちている空白の時間に、僕と七海は共に星を見ていたのだろうか。
「昨日……僕は、何を話してた?」
七海は微笑み、望遠鏡から目を離し、部室の隅に立てかけられた、古びた地図を指差した。それは、この街の過去の姿を描いたような、手書きの地図だった。
「あなたはいつも、忘却の朝に囚われながらも、何かを探しているようだったわ。この地図の、どこかに」
地図には、いくつかの古い建造物が赤いペンで印されていた。その中の一つ、「旧天文台」の文字が、僕の目を引いた。そこには、蓮が描いた古城と螺旋階段の絵が、どこか重なるような印象があった。
「この旧天文台、何があるんだ?」
「昔、この街で星祭りが開かれていた頃、そこは街の人々にとって、夢を語り合う場所だったと聞いているわ」
七海の言葉に、僕は蓮の描いた絵と、僕が抱えている胸の痛み、そして「忘却の朝」の全てが、一本の線で繋がっていくような予感に襲われた。蓮の絵、七海の言葉、そして僕が失った記憶。これらが示す「夢」とは一体何なのか。
僕は、蓮が描いた絵と、七海が指差した地図の印を、ノートに必死に書き留めた。明日、この記憶がリセットされても、この手がかりだけは失いたくない。僕はノートを心の地図に変え、失われた記憶の断片を繋ぎ合わせようと決意した。
第三章 消された旋律の真相
旧天文台へと向かったのは、僕と蓮、そして七海の三人だった。ノートに記録した情報をもとに、僕は蓮を誘い、七海もまた、何かを察したように同行してくれた。旧天文台は、街外れの小高い丘の上にひっそりと佇んでいた。蔦に覆われた石造りの建物は、まさに蓮の描いた絵の古城そのものだった。
「ここか……蓮の描いた絵は、ここだったんだな」
僕の言葉に、蓮は無言で頷いた。その表情は、どこか複雑な感情を宿しているように見えた。内部は朽ち果てていたが、中央にはかつて巨大な望遠鏡が据えられていたであろう台座が残されていた。そして、壁には、色褪せた写真や、手書きの楽譜が貼り付けられていた。その中の一枚の楽譜に、僕は目を奪われた。
「これ、僕の曲だ……」
楽譜には、確かに僕が昔作った覚えのあるメロディが記されていた。タイトルは『星々の旋律』。しかし、僕が知る『星々の旋律』とは、どこか調和が取れていない、未完成な響きがした。
「悠、それ、俺が昔、お前と一緒に作った曲だよ」
蓮の言葉に、僕は驚きを隠せない。蓮と僕で、一緒に曲を? そんな記憶は全くない。しかし、そのメロディは確かに僕の指が覚えているような気がした。
「僕が、忘れてしまっただけなのか?」
七海が、そっと僕の肩に手を置いた。
「悠くん、あなたは『忘れたい』と強く願ったのでしょう。この場所にまつわる、ある出来事を」
七海の言葉が、僕の心の奥底に眠っていた蓋を、ゆっくりと開けていく。
「忘れたい……?」
その瞬間、頭の中に、鮮やかな映像がフラッシュバックした。それは、夏の日の旧天文台だった。僕と蓮が、肩を並べて楽譜とスケッチブックを広げている。二人の顔は、未来への期待に満ちて輝いていた。
「いつか、僕らの音楽と絵で、この旧天文台を最高の表現の場にしよう!」
「ああ、最高の星祭りだ!」
僕と蓮は、固く誓い合った。僕の音楽と、蓮の絵で、この場所をもう一度輝かせようと。
しかし、その後に続く映像は、希望とは裏腹の、激しい衝突だった。
僕は、友人から誘われた音楽コンクールへの出場を決めた。それは僕にとって、大きなチャンスだった。だが、蓮との約束を顧みず、彼はコンクールの練習に没頭し、旧天文台での共同制作を疎かにした。
「お前の音楽は、俺の絵と共にあるものだと思っていたのに……!」
蓮の悲痛な叫びが、僕の頭の中に響き渡る。蓮は、僕の裏切りに深く傷つき、絵筆を置いた。そして、旧天文台での星祭りの夢は、僕の手によって打ち砕かれたのだ。
僕は、自分の愚かさと傲慢さに、身震いした。この出来事を、僕は無意識のうちに「忘れたい」と強く願っていた。そして、その願いが「忘却の朝」という形で、僕を罰していたのだ。
「だから、僕の記憶は、毎日リセットされてたのか……」
膝から崩れ落ちそうになる僕を、蓮がそっと支えた。
「悠……。お前が苦しむ姿を見るのは、もう嫌だ。だから俺は、お前の記憶が失われるたびに、お前が過去に囚われないように、必死で話しかけ続けたんだ」
「蓮……」
まさか、蓮が僕の記憶喪失の秘密を知っていて、僕のために寄り添ってくれていたとは。そして、七海が僕をこの場所へと導いたのは、僕が真実と向き合うことを望んでいたからだ。僕が失った記憶の空白は、僕自身の罪悪感と、それを乗り越えさせようとする友人たちの温かい支えで埋められていた。僕の価値観は、根底から揺さぶられた。忘却は罰ではなく、乗り越えるべき試練だったのだ。
第四章 再生への不協和音
真実を知った僕の心は、激しい後悔と、同時に蓮と七海への感謝で満たされた。僕が忘れてしまった日々、彼らは僕の隣で、僕が過去と向き合うための道筋を示し続けてくれていたのだ。
「ごめん、蓮……僕、なんてひどいことを……」
声が震え、言葉にならない。蓮は静かに僕の背中を撫でた。
「いいんだ、悠。俺も、お前に嫉妬した。お前の才能に、俺はどこか怯えていたのかもしれない。だから、あの時、素直にお前の夢を応援できなかった」
蓮の告白に、僕はまたもや胸を締め付けられる。彼は僕を許し、自分自身の弱ささえも曝け出してくれた。
「でも、これで終わりじゃない。俺たちはまだ、終わっていないんだ」
七海が、壁に貼られた僕の未完成な楽譜『星々の旋律』を指差した。
「忘却の朝は、あなたにとって過去を清算し、新しい未来を描くための、もう一度与えられた時間だったのかもしれないわ」
僕らは旧天文台の窓から、夕焼けに染まる空を見上げた。あの時、僕らが夢を語り合った場所で、僕らは新たな未来を模索していた。
僕の記憶は、あの日の出来事を境にリセットされていた。しかし、忘却の朝の中で、僕は七海と星を見上げ、蓮の絵に感動し、そして何よりも、友人たちの優しさに触れてきた。それは、記憶がなくても確かに存在した、僕の青春の断片だ。
「僕、もう一度、蓮と一緒に、ここで星祭りをやりたい」
僕の言葉に、蓮はゆっくりと顔を上げた。その目には、諦めていたはずの情熱が、再び燃え上がっているように見えた。
「悠の音楽で、俺の絵を彩ってくれるのか?」
「ああ。今度は、絶対に諦めない。蓮の絵と、僕の音楽で、最高の星祭りを!」
旧天文台に響き渡る僕の声は、少し掠れていたけれど、確かな決意に満ちていた。過去の過ちを忘れ去ろうとするのではなく、それを受け止め、乗り越えること。それが、本当の「再生」なのだと、僕は悟った。僕らの間にあった不協和音は、まだ完全に消えたわけではない。しかし、僕らはもう一度、共に旋律を奏でようとしている。
第五章 忘れぬこと、そして始まる歌
旧天文台での真実を知ってから、僕の「忘却の朝」は不思議な変化を見せ始めた。毎朝、依然として記憶はリセットされるものの、以前よりも感情の残滓が鮮明になった。蓮と七海との会話、旧天文台での発見、僕が感じた喜びや後悔の念が、夢のようにおぼろげながらも、心に深く刻まれるようになっていた。それはまるで、心の中に新しい記憶のフィルムがゆっくりと焼き付けられていくようだった。
僕はもう、忘れることを恐れない。むしろ、忘却の朝の中で得た新しい感情の断片を、大切に抱きしめるようになった。朝、目覚めるたびにノートを開き、蓮が描いた絵のこと、七海と見た星のこと、そして僕が過去と向き合い、未来へと進む決意を、改めて心に刻む。
僕と蓮は、再び旧天文台に通い始めた。蓮は、朽ちた壁に新たな絵を描き、僕は彼の絵からインスピレーションを得て、新しいメロディを紡ぐ。僕らが最初に誓い合った『星々の旋律』は、あの日の未完成な楽譜とは全く違う、希望に満ちた曲へと生まれ変わろうとしていた。七海もまた、僕らの活動を静かに見守りながら、旧天文台で見た星々の物語を僕らに語ってくれた。
ある日の夕暮れ、旧天文台の屋根の上で、僕と蓮は完成したばかりの曲と絵を前に座っていた。夕焼け空には一番星が輝き、涼しい風が僕らの頬を撫でる。
「悠、俺たちの星祭り、きっと最高になるな」
蓮の言葉に、僕は深く頷いた。僕らは過去を忘れ去るのではなく、過去の過ちも、痛みも、全てを抱きしめて、未来へと進むのだ。
記憶は、単に過去の記録ではない。それは、僕らが誰であるかを形作り、僕らが何を信じ、何を愛するかを示す、心の羅針盤だ。忘却の朝は、僕にそのことを教えてくれた。失った記憶の空白は、僕に真の友情と、自己と向き合う勇気を与え、新しい青春の扉を開いてくれたのだ。
僕はもう、記憶がリセットされることに怯えない。たとえ明日、今日のことを忘れてしまっても、僕の心には、確かに蓮との友情があり、七海との絆があり、そして旧天文台で始まった新しい夢がある。
僕らの物語は、まだ始まったばかりだ。僕らは、この空白のフィルムに、何度でも新しい物語を焼き付けていくだろう。そして、その全てが、僕らの忘れえぬ青春の歌となるのだ。