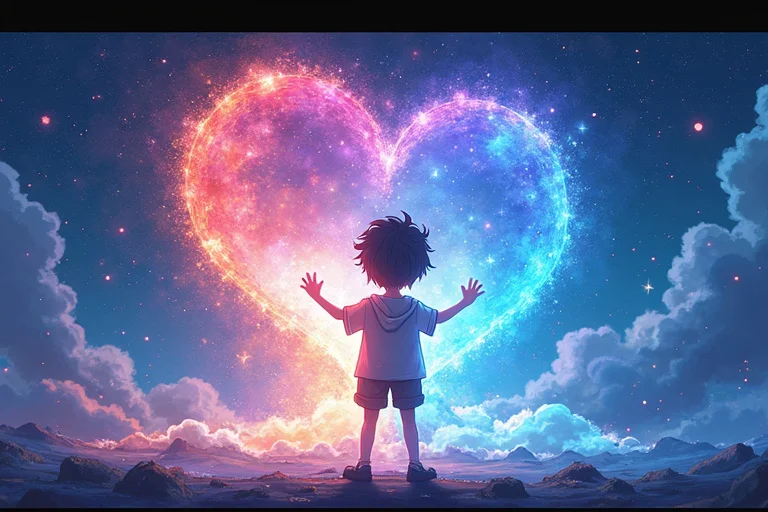第一章 記憶保管委員会と沈黙の儀式
僕、相沢海斗が所属しているのは、正式名称すらない、非公式の部活動だ。僕たちはそれを、ただ「記憶保管委員会」と呼んでいる。活動場所は、海風が絶えず窓を揺らす旧校舎の三階、使われなくなった生物準備室。棚にはホルマリン漬けの標本の代わりに、大小様々なガラス瓶が星屑のように並んでいる。
活動内容は、至極シンプルだ。忘れたい記憶を持つ生徒から依頼を受け、その記憶を瓶に封じ込める。それだけ。
「準備、できたよ」
部長の千歳(ちとせ)先輩が、白衣の袖をまくりながら振り返った。夕陽が差し込む埃っぽい室内で、彼女の影だけがくっきりと輪郭を結んでいる。今日の依頼人は、二年生の女子バスケ部のエースだった。夏の大会で、彼女は最後のフリースローを外し、チームは敗退した。その記憶を消してほしい、と彼女は泣きながら訴えた。
千歳先輩は、依頼人のこめかみにそっと指を添える。目を閉じて、深く息を吸うと、彼女の指先から依頼人へと、淡い、ほとんど目に見えないほどの光の糸が伸びていくように見えた。僕には、その光景が微かにだが「視える」。それが、僕がこの奇妙な委員会に引きずり込まれた理由だった。
やがて先輩は、ゆっくりと指を離し、そばに置かれた空のコルク瓶に、まるで捕まえた蝶でも閉じ込めるかのように、その見えない何かをそっと移した。瓶の中で、バスケットボールの色をしたオレンジ色の光の粒子が、一瞬激しく渦を巻き、やがて静かに底へと沈んでいった。
「これで、もう大丈夫。あなたは、大事な試合で少しだけ緊張した。それだけよ」
先輩の言葉は、まるで優しい催眠術のようだ。依頼人の顔からは苦悩の色が消え、どこか腑抜けたような、それでいて安堵した表情が浮かんでいる。彼女は何度も頭を下げて、部室を後にして行った。
残されたのは、僕と先輩、そして棚に新しく加わった一つの「記憶」だけ。僕は棚に並ぶ無数の瓶を眺めた。告白して振られた記憶、親友と喧嘩別れした記憶、コンクールで大失敗した記憶。青春の痛みという痛みが、ここでは美しい光の標本となって眠っている。
だが、僕にはずっと拭えない疑問があった。
その日の活動が終わり、僕が校門を出ようとした時だった。遠回りになる海沿いの道を、千歳先輩が歩いているのが見えた。その手には、昼間とは違う、いくつもの小さな瓶が入った布袋が握られている。好奇心に抗えず、僕は距離を保ちながら、彼女の後を追った。
彼女が向かったのは、観光客も来ない、寂れた防波堤だった。夕闇が海と空の境界を溶かし始めた頃、先輩は立ち止まり、袋から一つの瓶を取り出した。そして、何のためらいもなく、それを遠くの海へと投げ込んだ。
ぽちゃんと小さな音がして、瓶はあっという間に黒い波間に消える。また一つ、そしてまた一つと、彼女は黙々と瓶を海に投げ捨てていく。それはまるで、何かを弔うための、厳かで沈黙に満ちた儀式のようだった。
なぜだ? 忘れたいと願う他人の記憶を、あんなにも大切そうに瓶詰めにしたのに。なぜ、それを海に捨てるんだ? あの瓶の中に込められていたのは、誰かの痛みであり、紛れもない人生の一部のはずだ。僕の胸に、冷たくて重い疑念が音を立てて沈んでいった。
第二章 集まる痛み、揺らぐ境界
翌日から、僕は千歳先輩の行動一つ一つを、無意識に目で追うようになっていた。彼女はいつも通り、誰にでも明るく微笑みかけ、冗談を言っては周りを和ませる。だが、その完璧な笑顔の裏に、昨夜の防波堤で見せた、底知れないほどの静けさを湛えた横顔がちらついて離れなかった。
「記憶保管委員会」には、相変わらず様々な記憶が持ち込まれた。それはまるで、この海辺の町の高校生たちが抱える痛みの縮図のようだった。ピアノの発表会で指が動かなくなった記憶は、鍵盤のような白と黒の光が乱雑に明滅していた。初めて飼った子犬が死んでしまった記憶は、温かい毛布のような琥珀色の光が、悲しげに揺らめいていた。
僕は、依頼人たちが記憶を手放した後の表情を見るのが、少し怖くなっていた。彼らは確かに楽になっている。だが、その顔からは、苦悩と共に、何か大切なものまで一緒に削ぎ落とされてしまったような、奇妙な空虚さが感じられた。まるで、パズルのピースが一つ欠けてしまったみたいに。
「海斗くんは、どう思う?」
ある日の放課後、二人きりの部室で、先輩が不意に問いかけてきた。
「この活動のこと。僕たちがやっていることは、本当に正しいのかなって」
核心を突くような僕の問いに、先輩は瓶を磨く手を止め、窓の外に広がる灰色の空を見つめた。
「正しいかどうかなんて、誰にもわからないわ。でもね、人は前に進むために、何かを置いていかなきゃいけない時があるのよ。重すぎる荷物を背負ったままじゃ、一歩も歩けなくなるから」
その声は、どこか自分自身に言い聞かせているようにも聞こえた。
僕は自分の微弱な能力を使い、棚に並ぶ瓶の一つに意識を集中させてみた。それは、少し前に依頼された「親友を裏切ってしまった」という記憶だった。瓶の中を覗き込むと、僕の脳裏に断片的な映像が流れ込んでくる。
――雨の日の帰り道。些細な誤解から、親友に酷い言葉を投げつけてしまう少女。傷ついた親友の瞳。後悔。自己嫌悪。――
確かに、それは痛みそのものだった。だが、映像の隅々に、それだけではないものが映り込んでいることに気づく。二人で笑い合った教室の風景。交換したキーホルダー。一緒に食べたアイスの味。忘れたいと願った記憶は、決して単体で存在するわけじゃない。それは、かけがえのない時間と、固く結びついていた。
これを、本当に忘れてしまっていいのだろうか。
痛みごと、あの温かい時間まで消し去ってしまって、本当にいいのだろうか。
僕の中で、この委員会の存在意義そのものが、大きく揺らぎ始めていた。そして同時に、千歳先輩が海に捨てていた瓶の中身が、どうしても気になって仕方がなかった。あれは本当に、僕たちが保管した他人の記憶なのだろうか。それとも――。僕の知らない、何か別のものが、あの瓶には詰められているのではないか。僕と彼女の間には、見えない境界線が引かれている気がした。
第三章 嵐の夜の告白
その夜、季節外れの嵐が町を襲った。叩きつけるような雨と、全てをなぎ倒さんばかりの強風。僕は、いてもたってもいられず、傘を片手に家を飛び出した。予感がしたのだ。こんな嵐の夜だからこそ、彼女はきっと海へ行くと。
案の定、防波堤の先端に、風雨に打たれる小さな人影があった。千歳先輩だった。彼女はいつものように、布袋から瓶を取り出している。しかし、その手は激しく震えていた。
「先輩!」
僕が叫ぶと、彼女はびくりと肩を震わせ、ゆっくりと振り返った。雨に濡れた彼女の顔は、驚くほど白く、その瞳には僕が今まで見たこともないような、深い絶望の色が浮かんでいた。
「どうして、ここに……」
「やめてください! それ以上、何を捨てようとしてるんですか!」
僕は彼女の腕を掴んだ。その手から滑り落ちた瓶が、コンクリートの上で甲高い音を立てて割れる。しかし、そこから溢れ出したのは、僕が知っているような色とりどりの光の粒子ではなかった。それは、どす黒く、重苦しい、まるで泥のような光だった。そして、その光が僕の肌に触れた瞬間、凄まじい量の「記憶」が濁流となって流れ込んできた。
――交通事故の凄惨な光景。両親の激しい口論。友人の裏切り。自分の失敗。見知らぬ人々の悪意。悲しみ、怒り、憎しみ、後悔、恐怖――
それは、一人の人間が到底抱えきれるはずのない、膨大で、あまりにも鮮明な負の記憶の奔流だった。僕は思わずその場に膝をついた。
「……これは、先輩の記憶、なんですか?」
息も絶え絶えに尋ねる僕に、彼女は観念したように、静かに頷いた。
「私には、一度見聞きしたことを、絶対に忘れられないの」
彼女は、いわゆる「完全記憶能力」の持ち主だった。だが、それは祝福などではなく、呪いだった。初めて読んだ絵本の文章から、道端に落ちていた石ころの形、昨日すれ違った人の不機嫌な舌打ちまで、全てが寸分の狂いもなく、彼女の頭の中に蓄積されていく。楽しい記憶も、幸せな記憶も。そして、耐え難いほどの辛い記憶も、色褪せることなく永遠に残り続ける。
「心が、壊れそうになるの。忘れたいのに、忘れられない。だから……だから、この方法を考え出した」
「記憶保管委員会」は、他人のためではなかった。他人の「忘れたい」という強い意志を触媒にしなければ、彼女は自分の中から記憶を切り離し、瓶に封じることができなかったのだ。僕たちが集めていた他人の記憶は、彼女が自分自身の記憶を捨てるための、いわば「生贄」だった。
「みんなの記憶は、ちゃんと部室の奥に保管してあるわ。私が海に流していたのは、いつも、私の記憶だけ」
嵐の中、彼女は初めて僕の前で子供のように泣きじゃくった。その嗚咽は、風の音に混じり、僕の心を激しく揺さぶった。彼女が背負っていた孤独と苦しみの重さに、僕はただ立ち尽くすことしかできなかった。僕が抱いていた疑念も、彼女への淡い憧れも、何もかもがこの嵐に洗い流され、根底から覆されてしまった。
第四章 君が忘れた温もり
嵐が去った翌朝、空は嘘のように晴れ渡っていた。僕と千歳先輩は、誰もいない部室で向かい合っていた。昨夜の告白の後、僕たちは言葉少なめに、ただ濡れた体を寄せ合って朝を待った。
先輩の目は赤く腫れていたが、その表情には、長年つけていた仮面が剥がれ落ちたような、不思議な透明感があった。
「ごめんなさい。ずっと、君を騙してた」
「……いいえ」僕は首を横に振った。「僕こそ、何も知らずに先輩を疑ってました。すみません」
沈黙が落ちる。棚に並んだ瓶たちが、朝の光を浴びて静かにきらめいていた。あれは、誰かの痛みであると同時に、千歳先輩の苦しみの証でもあったのだ。
僕は、ずっと自分のこの中途半端な能力が嫌いだった。望んでもいないのに他人の感情の断片が流れ込んできて、心をかき乱される。だから、いつも目を逸らし、深く関わることを避けてきた。だが、今は違った。この力で、僕にしかできないことがあるはずだ。
「先輩」と僕は口を開いた。「忘れたい記憶だけじゃないはずです。先輩の中には、忘れたくない記憶も、たくさんあるでしょう?」
彼女は虚を突かれたように目を見開いた。忘れることばかりに囚われ、彼女は自らの中に眠る宝物の存在すら、忘れかけていたのかもしれない。
「僕に、探させてください。先輩が忘れてしまったかもしれない、温かい記憶を」
僕はそっと目を閉じ、意識を目の前の千歳先輩に集中させた。彼女の膨大で混沌とした記憶の海へ、小さな舟を漕ぎ出すように、意識を沈めていく。昨夜見たような、どす黒い濁流が渦巻いている。だが、僕は必死にその流れに抗い、もっと深く、もっと奥へと潜っていった。
すると、暗い海の底で、小さな光が瞬いているのを見つけた。
僕はそれを、そっと掬い上げる。
――幼い千歳先輩が、今はもういない祖母と手を繋いで、夕暮れの浜辺を歩いている。祖母が歌う、少し調子の外れた子守唄。潮風の匂い。砂の感触。世界は優しさと安心感に満ちていた。――
僕が目を開けると、千歳先輩の瞳から、一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。
「……おばあちゃん……の歌……」
それは、あまりに多くの記憶の層の下に埋もれて、彼女自身も忘れてしまっていた、温かい記憶の欠片だった。
「忘れることだけが、救いじゃないと思います」僕は言った。「辛い記憶も、楽しい記憶も、全部抱えたまま、それでも前を向くことだってできるはずです。僕が、手伝いますから」
僕たちは、その日、活動方針を少しだけ変えることにした。「記憶保管委員会」は、「忘れる」ためだけの場所ではなくなった。時には「思い出す」ために。そして、一人では抱えきれないものを、二人で「分かち合う」ために。
夕暮れ時、僕たちは二人で、あの防波堤に立っていた。手には、空っぽのガラス瓶が一つ。
「何を捨てるんですか?」と僕が尋ねると、彼女は悪戯っぽく微笑んだ。
「ううん、何も捨てない。これは、昨日までの私たちを手放すための瓶。そして、明日を迎えるための瓶よ」
千歳先輩は、その空の瓶を、未来へ向かって放るように、海へと投げた。夕陽を反射してきらめいた瓶は、美しい放物線を描いて波間に消えていく。それはもう、悲しい儀式ではなかった。
僕たちは、青春という、痛みと輝きが入り混じった複雑な季節を、まだしばらく生きていくのだろう。忘れたいことも、忘れられないことも、きっとたくさんある。でも、隣に君がいるなら、きっと大丈夫だ。僕たちは顔を見合わせ、どちらからともなく、小さく笑い合った。遠くから聞こえる潮騒が、僕たちの新しい始まりを、優しく祝福してくれているようだった。