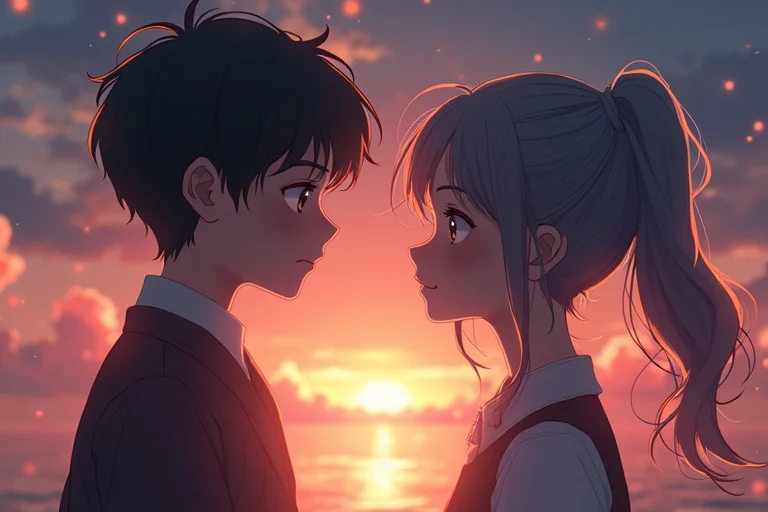第一章 影は光を焼く
右目を細める癖がついたのは、蓮(レン)と出会ってからだ。
午後の教室。
窓際の席に座る彼を直視すると、視神経が焼き切られそうな痛みが走る。
西日が差し込んでいるせいじゃない。
彼という存在そのものが、網膜を焦がすほどの光量を放っているからだ。
「カケル、顔色が悪いぞ」
蓮が振り返る。
その動作だけで、教室中の埃が金粉のように舞い上がり、彼を祝福するようにきらめいた。
クラスメイトの視線が、磁石に吸い寄せられる砂鉄のように彼へ集まる。
僕は反射的に顔を伏せ、手元のスマートフォンをいじった。
画面には、先日の修学旅行の集合写真。
中央で太陽のように笑う蓮。
その数人隣、背景の石垣に溶け込むように、輪郭の曖昧な僕が写っている。
拡大しても、ピントが合っていないみたいに表情が読み取れない。
僕には、他人の『輝き』が見える。
才能、未来、魂の純度。
蓮のそれは、僕の人生で見たどんな光よりも強く、そして暴力的だった。
「なあ、ちょっと付き合えよ」
蓮が僕の机に影を落とす。
その影の中にいる時だけ、僕は息ができる気がした。
放課後の理科準備室裏。
錆びついた焼却炉の前に、蓮は立っていた。
彼の指先には、親指大のガラス片が摘ままれている。
多面体にカットされた、古ぼけたプリズムだった。
「拾ったんだ。これ、なんか変なんだよ」
「変って?」
「握るとさ、頭の中が透けていく感じがするんだ。余計なものが削ぎ落とされて、願いが……一つだけ、叶う気がする」
蓮の声が震えていた。
いつもの自信に満ちた彼じゃない。
追い詰められたような、祈るような響き。
彼の全身から発せられる黄金の光が、不規則に明滅を始めた。
直視できない。
心臓の鼓動が早まる。
もしも。
僕の心の奥底で、どす黒い澱(おり)が蠢いた。
もしも、この眩しすぎる光が消えてくれたら。
そうすれば、僕という薄い存在にも、色が戻るんじゃないか。
「蓮、それ危ない気がする。捨てろよ」
口ではそう言った。
けれど、僕は手を伸ばさなかった。
止めるふりをして、事の成り行きを期待してしまった。
蓮がプリズムを強く握りしめる。
ガラスのエッジが皮膚に食い込み、血が滲む。
「俺は……」
彼が何かを呟こうとした瞬間。
プリズムが、周囲の光を一気に飲み込んだ。
キィン、と耳鳴りが世界を裂く。
色彩が反転し、黄金の輝きが渦を巻いてガラス片の中へ吸い込まれていく。
まるで排水溝に流れる水のように。
「あ……」
蓮の膝が折れた。
糸の切れた人形のように、コンクリートに崩れ落ちる。
彼の周囲に満ちていたあの圧倒的な圧力が、消失していた。
「蓮!」
駆け寄り、肩を揺する。
反応がない。
いや、目は開いている。
けれど、その瞳孔は開ききり、どこにも焦点を結んでいない。
「おい、しっかりしろ! 俺だ、カケルだ!」
僕の声が、静まり返った校庭に虚しく響く。
数秒、あるいは数分にも感じられる沈黙の後、蓮の唇が微かに動いた。
「……近寄るな」
掠れた声。
彼は怯えたように身を縮め、僕の手を振り払った。
その目には、見知らぬ不審者を見る警戒の色と、根源的な恐怖が宿っていた。
「蓮?」
「誰だか知らないけど……触らないでくれ」
心臓を、氷の手で鷲掴みにされた。
「ふざけんなよ。俺たち、ずっと一緒だっただろ。サッカー部の入部テストも、昨日のテスト勉強も……」
言葉を重ねるごとに、蓮の表情が強張っていく。
僕の知っている蓮は、もうそこにはいなかった。
共有した時間のすべて、交わした言葉の温度、その一切合切が、更地のように消え失せている。
足元で、プリズムが転がった。
先ほどまでの透明度は失われ、白濁し、死んだ魚の眼球のように濁っていた。
僕の願いが叶ってしまったのか。
あいつの光を消してくれという、最低の願いが。
-----
第二章 硝子の叫び
診断名は『全生活史健忘』。
ストレスや心因性のショックが原因とされる、自己の歴史すべてを失う症状。
蓮の病室に通い続けて三日。
彼は僕を見るたび、礼儀正しく、しかし分厚い壁越しに「はじめまして」と繰り返す。
そのたびに、僕は自分自身が希釈されていく感覚に襲われた。
自宅の机の上。
持ち帰ったプリズムが、重たい石のように鎮座している。
表面はざらつき、光を一切通さない。
「お前のせいだ」
濁ったガラスに向かって呟く。
違う。僕のせいだ。
あの一瞬、蓮を止めなかった僕の罪だ。
悔恨と自己嫌悪で、胃液が逆流しそうになる。
衝動的にプリズムを掴み、壁に投げつけようと振りかぶった。
その時だ。
ビリッ。
指先から、電流のような衝撃が走った。
痛覚ではない。
もっと直接的な、脳髄を揺さぶるような『感情』の奔流。
視界が歪む。
僕の部屋の風景が弾け飛び、知らない映像がノイズ交じりにフラッシュバックする。
――高い場所。屋上のフェンス。
――眼下に広がる街の灯り。
(怖い……)
蓮の声ではない。
けれど、それは紛れもなく蓮の感情だった。
プリズムを通して、彼が封じ込めた記憶の断片が、僕の中に流れ込んでくる。
――誰からも期待される完璧な自分。
――失敗が許されない重圧。
――本当の自分なんて、誰も見ていない。
息が詰まる。
彼から見えていた世界は、こんなにも色がなかったのか。
黄金に輝くオーラの内側で、彼は窒息しかけていた。
映像が切り替わる。
教室の片隅。
窓の外を見ている、一人の男子生徒の背中。
……僕だ。
蓮の視点から見た僕は、背景に溶け込んでなんていなかった。
むしろ逆だ。
周囲の喧騒から切り離され、静謐(せいひつ)で、何にも染まらない透明な存在として映っていた。
(カケルみたいになりたかった)
蓮の切実な思考が、僕の胸を抉(えぐ)る。
(あいつは自由だ。何色にでもなれる。俺の光が強すぎて、あいつを影にしているなら……俺のこの記憶(ひかり)全部と引き換えにしてもいい)
(あいつに、自分の凄さを気づかせてやりたい)
熱いものが頬を伝う。
プリズムを持つ手が震え、止まらない。
馬鹿だ。
大馬鹿野郎だ、お前は。
僕は蓮を妬み、彼がいなくなることを願った。
なのに蓮は、自分のすべてを犠牲にして、僕という存在を肯定しようとしていた。
「違うんだよ、蓮……」
濁ったプリズムを、額に押し当てる。
冷たかったガラスが、僕の体温と涙を吸って、微かに熱を帯び始めた。
僕が見ていた『輝き』は、彼が必死に燃やしていた命の輝きだった。
そして彼が見ていた僕は、透明人間なんかじゃなかった。
僕はずっと、何者かになりたかった。
色を持ちたかった。
けれど、透明であることにも意味があるなら?
どんなに強い光も、そのままでは直視できない。
けれど、透明な媒介を通せば、それは優しい虹になる。
僕は涙を拭った。
部屋を出る。
夜の病院へ走る。
謝罪なんていらない。
僕がやるべきことは、彼が捨てた光を、もう一度彼に届けることだ。
-----
第三章 光の在処
消灯時間を過ぎた病室は、深海のように静まり返っていた。
蓮はベッドの上で、膝を抱えて窓の外を見ていた。
月明かりに照らされたその横顔は、陶器のように脆く、そして色彩を欠いていた。
「蓮」
息を切らせて入り込むと、彼はビクリと肩を震わせた。
警戒心。
けれど、僕はもう足を止めない。
「帰って……ください。頭が痛いんだ」
「帰らない。お前に返すものがある」
僕はポケットからプリズムを取り出した。
月光にかざす。
まだ濁りは消えていない。
けれど、僕の手のひらの熱が伝わっているのか、中心部に小さな灯火のような揺らぎが見えた。
「これは、お前の記憶だ。お前が重すぎて捨てた、でも絶対に失くしちゃいけない光だ」
「記憶……? 何を言ってるの?」
蓮が困惑の表情を浮かべる。
僕はベッドサイドに歩み寄り、彼の手を取った。
冷たい。
血が通っていないかのように。
「怖かったんだろ。みんなの期待も、将来も。だから全部消してしまいたかった」
蓮の瞳が揺れる。
図星を突かれた子供のような顔。
「でも、お前は僕を見ていた」
僕はプリズムを、彼と僕の目の間に掲げた。
「僕が透明だって言ったな。何にも染まらないって」
言葉にするたび、胸の奥が熱くなる。
これまで飲み込んできた言葉、劣等感、そして蓮への憧れ。
それら全てを燃料にして、僕は叫び出しそうになる感情を制御する。
「見てろ。透明な僕が、お前の光をどう変えるか」
僕は祈った。
神様にじゃない。
目の前の、空っぽになってしまった親友に。
僕の目に見える『輝き』の能力。
それは、光を受け止め、屈折させ、解釈するための力だ。
彼が放っていた暴力的なまでの光を、僕というフィルターを通して、彼自身が愛せる形に変える。
(思い出せ、蓮!)
僕の網膜に焼き付いている、いつかの放課後。
泥だらけのユニフォーム。
テスト明けのサイダー。
くだらない冗談で笑い合った、あの日々の色彩。
僕の記憶を、プリズムへと注ぎ込む。
カッ!
プリズムの内部で、閃光が爆ぜた。
濁った白が弾け飛び、鋭利な光の矢が四方八方へと放たれる。
それは、ただの黄金色ではなかった。
青、赤、緑、紫。
無数の色が複雑に絡み合い、病室の無機質な壁を鮮やかに塗り替えていく。
「う……あ……」
蓮が目を見開く。
彼の瞳の中に、七色の光を背負った僕が映り込んでいた。
その瞬間、僕は悟った。
僕は透明人間なんかじゃない。
光を受けて輝く、プリズムそのものだったんだ。
蓮の瞳から、大粒の涙が溢れ出した。
恐怖の色が消え、懐かしさと、安堵の色が満ちていく。
「……眩しいな」
蓮が呟いた。
その声には、確かな体温が宿っていた。
「ああ。お前の光だ」
「違うよ」
蓮が、震える手でプリズムごと僕の手を包み込んだ。
「これは、カケルの色だ」
光が収束していく。
病室に、静寂が戻る。
けれど、もう冷たい空気はない。
蓮が深く息を吐き、僕を見た。
その顔に、以前のような完璧な仮面はない。
少し弱気で、年相応の少年の顔。
「……なんか、すげえ長い夢を見てた気がする」
「悪夢か?」
「いや。変な奴が、俺の前で必死に光っててさ。暑苦しいくらいの」
蓮が微かに笑った。
僕も、つられて頬が緩む。
記憶が完全に戻ったのかは分からない。
失われたピースはあるかもしれない。
けれど、彼を縛り付けていた黄金の鎖は、もう見えなかった。
窓の外、東の空が白み始めている。
「腹減ったな」
「購買のパンなら奢るよ」
「高いやつ頼むわ」
ありふれた会話。
僕たちは並んで窓の外を見た。
ガラスに映る二人の姿は、どちらも薄くなく、確かな輪郭を持って、朝焼けの色に染まっていた。