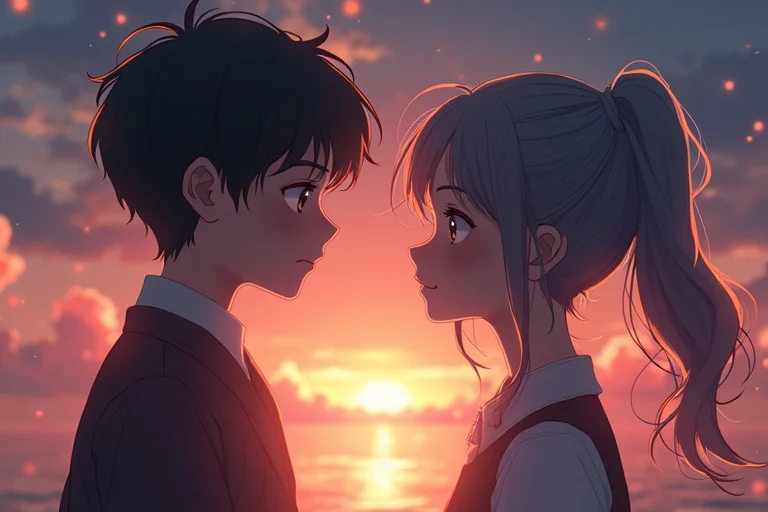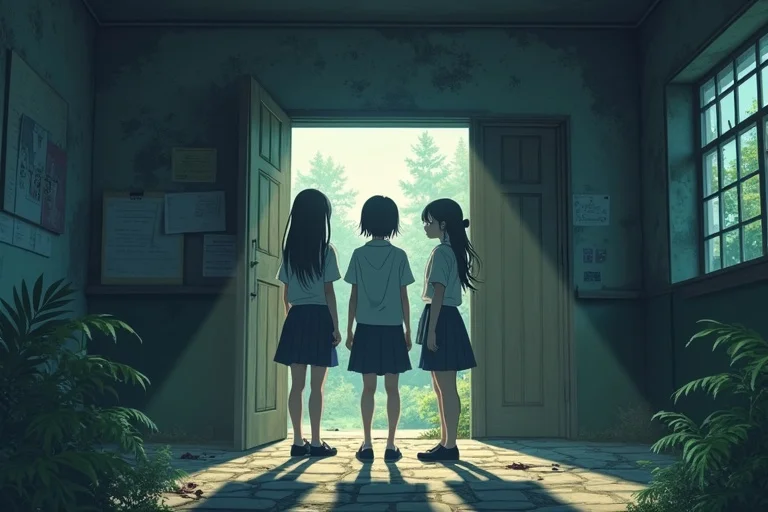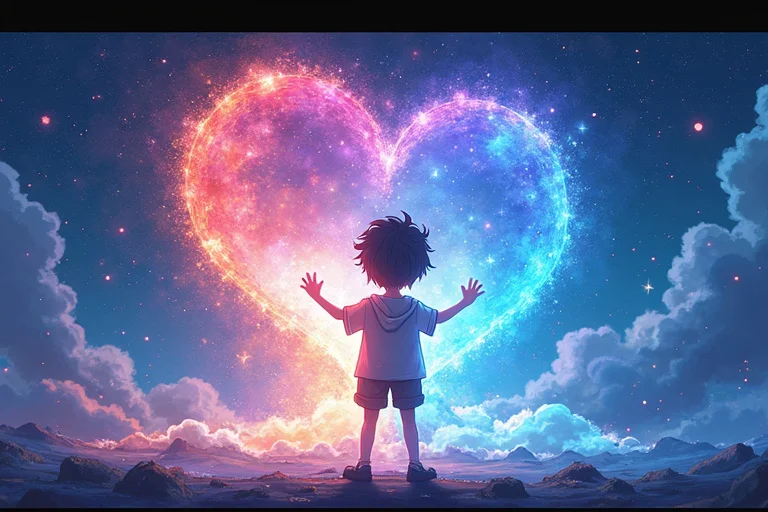第一章 教室に満ちる悪臭
ガラスの試験管を、蛍光灯の冷たい光にかざす。
中身は、空っぽだ。
薄汚れた教室の埃が、透明な円筒の中で頼りなく舞っている。
俺、香月薫は、指紋のついたガラス表面を親指で強く擦り、制服の内ポケットへ滑り込ませた。
胸元でカチリと硬い音がする。その微かな重みだけが、俺の輪郭を保っている気がした。
息を吸うのが、億劫だ。
鼻腔の粘膜にへばりつくのは、チョークの粉塵と、カビた雑巾の湿り気。
そして――何百もの濡れた犬を狭い部屋に閉じ込めたような、生温かい獣臭。
「香月、またシケた面してんのかよ」
隣の席の男子生徒が、遠慮なく俺の肩を叩く。
彼が腕を動かすたび、焦げ付いた砂糖のような甘ったるい悪臭がふわりと舞った。
『今朝、寝坊して彼女のLINEを既読無視した』
そんな些末な罪悪感。
彼自身も気づいていないような小さな「後悔」が、俺には明確な「匂い」として知覚できる。
この教室は、十代特有の未熟な後悔で煮詰まっている。
試験の失敗、友人への嫉妬、言えなかった言葉。
それらが複雑に混ざり合い、発酵し、俺の肺をじわじわと汚染していく。
俺は息を止め、ハンカチを鼻に押し当てた。
俺は傍観者だ。
この悪臭に満ちた水槽の中で、ただ静かにエラ呼吸をしてやり過ごす。それしかできない。
その時。
教室の空気が、ピシリと凍りついた。
「転校生だ。入れ」
担任の事務的な声と共に、引き戸が開く。
瞬間。
俺の三半規管が警報を鳴らした。
「……ッ」
胃袋を裏返して絞り上げられたような不快感。
俺は反射的に口元を覆い、机に突っ伏した。
なんだ、これは。
腐り落ちた百合の花束を、ホルマリンのプールに沈めて数年放置したような。
あるいは、綺麗にラッピングされた生肉が、内側から蛆に食い荒らされているような。
甘く、冷たく、そして鼻が曲がるほどに強烈な「死臭」。
「佐倉律です。よろしくお願いします」
涼やかな声が、静まり返った教室に響く。
顔を上げる。脂汗が目尻を伝う。
黒板の前に立っていたのは、あまりにも整いすぎた少年だった。
色素の薄い髪、陶器のように滑らかな肌、長い睫毛に縁取られた瞳。
そこにいるだけで周囲の光を吸い寄せるような、圧倒的な造形美。
教室中の空気が変わる音がした。
女子生徒たちが頬を紅潮させ、男子生徒たちが息を呑む。
羨望、憧れ、好奇心。
ねっとりとした熱視線が、一斉に彼へと注がれる。
だが、俺の目には違って見えた。
彼が歩を進めるたび、足元からドス黒い紫煙が立ち上っている。
それは床を這い、机の脚に絡みつき、教室の空気をどろりと濁らせていく。
今まで嗅いだどんな「後悔」よりも重く、深く、絶望的だ。
まだ十七歳の人間が、これほど濃密な腐敗臭を纏えるはずがない。
まるで、魂の一部を切り落として腐らせたような匂いだ。
佐倉律が、ふと足を止めた。
視線が絡む。
彼は完璧な角度で口角を上げ、微笑んだ。
精巧なビスクドールのような、一分の隙もない笑顔。
けれど、その瞳の奥は暗い井戸の底のように、光を一切反射していなかった。
「隣、いいかな」
彼が俺の前の空席を指差す。
拒絶の言葉を喉に詰まらせている間に、彼は鞄を置き、優雅な動作で椅子を引いた。
風圧と共に、濃厚な死臭が俺の鼻先を掠める。
脳髄が痺れ、視界が明滅する。
「……君、顔色が悪いよ。保健室、連れて行こうか?」
心配そうに覗き込む顔。
その美しい仮面の裏側で、悪臭は音を立てて渦巻き、俺の生存本能を逆撫でする。
俺の視線が、彼の胸元に吸い寄せられた。
ブレザー越しに、奇妙な違和感がある。
心臓のあるべき場所が、そこだけ不自然に窪んで見えた。
まるで、大切な何かを無理やり引き抜いたかのような――空洞。
俺は確信した。
この「完璧な転校生」は、取り返しのつかない何かを犠牲にして、ここに立っている。
第二章 完璧な喪失
佐倉律が学校という生態系の頂点に立つのに、三日もかからなかった。
数学の試験では、教師さえ舌を巻く解法で満点を叩き出す。
体育のバスケットボールでは、重力を無視したような跳躍でダンクを決め、歓声を独占する。
放課後の美術室では、写真と見紛うほどの精密な油絵を、無造作に仕上げてみせた。
誰からも愛され、誰からも称賛される存在。
生徒たちは彼を『天才』と呼び、遠巻きに崇めた。
だが、俺にとっての彼は『歩く汚染源』でしかない。
「……ぐ、ぅ」
屋上のフェンス際。
錆びた金網に指を食い込ませ、俺は胃液を吐き出していた。
佐倉と同じ空間にいるだけで、内臓がねじ切れるような苦痛が襲う。
限界だった。
「大丈夫か、香月」
背後から、冷ややかな声がかかる。
心臓が跳ねた。
振り返ると、佐倉が立っている。手には未開封のミネラルウォーター。
逆光を浴びたその姿は、神々しいほどに美しい。
だが、その足元には、相変わらずドス黒い瘴気が渦巻いている。
「水、飲む?」
「……近寄るな」
俺は喉を引きつらせて後ずさった。
風に乗って、あの甘ったるい腐敗臭が鼻孔を侵犯する。
佐倉は傷ついた様子もなく、ただ小首を傾げた。
感情の抜け落ちた、ガラス玉のような瞳。
「僕のこと、嫌い?」
「嫌いとか、そういう次元じゃない……」
俺は口元を袖で拭い、荒い息を吐く。
これ以上、誤魔化せない。
俺の体が、こいつの匂いを拒絶している。
「お前……胸のそれ、何だ」
俺は震える指で、彼の心臓を指差した。
佐倉の無表情な顔に、微かな亀裂が走る。
「……見えてるの?」
「匂うんだよ。お前のその傷跡から、腐った臭いがダダ漏れなんだ」
俺はポケットから、いつもの空の試験管を取り出し、彼に向けた。
ガラス越しに見る彼は、歪んで、ひどく脆そうに見えた。
「『後悔の棘』……そう呼ぶらしいな」
俺の言葉に、佐倉の目がわずかに見開かれる。
「……おとぎ話じゃなかったんだ」
「棘は、後悔の結晶だ。それを抜けば、痛みから解放されて才能が開花する。だが、その代償に……」
俺は一歩踏み込んだ。
吐き気を堪え、彼の空っぽな瞳を睨みつける。
「お前、何を捨てた? 何を犠牲にして、その完璧さを手に入れたんだ」
核心を突いたつもりだった。
佐倉はふっと笑った。
それは、あまりにも空虚で、見ていて痛々しい笑顔だった。
「犠牲? そんな大層なものじゃないよ」
彼はフェンスに背を預け、遠くのグラウンドを見下ろした。
歓声を上げて走る生徒たち。その輝きから、彼だけが切り離されている。
「僕はただ、完璧になりたかっただけだ。みんなが望むような、誰の期待も裏切らない人間に」
「そのために、心を殺したのか」
「殺してないよ。ただ……」
佐倉は言葉を濁し、自分の胸元を強く握りしめた。
爪が生地を裂きそうなほどに。
その瞬間。
彼から発せられる悪臭が、爆発的に膨れ上がった。
もはや匂いではない。痛みだ。
鼻の奥が焼け爛れるような刺激臭。アンモニアと硫黄を煮詰めたような劇薬の気配。
「嘘だ!」
俺は叫んだ。涙目で、咳き込みながら。
「お前からは、死んだ匂いがするんだよ! お前が封じ込めた『後悔』が、中で腐って悲鳴を上げてるんだ!」
佐倉の動きが止まった。
彼はゆっくりと俺の方を向き、焦点の合わない目で言った。
「……悲鳴?」
「ああ、聞こえないのかよ。お前は今、泣き叫びたいくらい後悔してる。完璧であることの裏で、何かを取り戻したいと藻掻いてる」
佐倉の仮面が剥がれ落ちた。
美しい顔が、苦悶に歪む。
「……分からないんだ」
ポツリと、彼が漏らした声は震えていた。
「完璧な絵を描いても、満点の答案を見ても、何も感じない。歓びも、達成感も、安らぎも。全部が砂みたいに指の間をすり抜けていく」
彼は膝から崩れ落ちるように蹲った。
初めて見せる、人間らしい弱さ。
「思い出せないんだ。僕が、どうして完璧になりたかったのか。誰に見せたかったのか。誰に、褒めてほしかったのか」
彼の瞳から、透明な雫がこぼれ落ちた。
だが、その涙さえも、どこか作り物めいている。感情の伴わない生理現象のように。
「『棘』を抜いた時、僕は……一番大切な『動機』を置き忘れてしまった」
あの人の顔。あの温もり。
彼を突き動かしていたはずの「原動力」。
それを失って手に入れた才能は、燃料のないエンジンと同じだ。
空回りして、摩擦熱で心を焼き尽くし、ただ焦げ付いていく。
それが、この悪臭の正体か。
『目的を忘れた努力』の成れの果て。
『愛を失った才能』の腐敗臭。
「助けてくれ、香月」
佐倉が床に額を擦り付ける。
「このままじゃ、僕は空っぽのまま、壊れてしまう」
第三章 空の試験管、満ちる時
その日の放課後。
美術室のある北校舎は、異様な空気に包まれていた。
廊下まで漏れ出す悪臭。
生ゴミと、焼け焦げたプラスチックと、鉄錆の匂い。
生徒たちは本能的な恐怖を感じたのか、誰一人として近づこうとしない。
俺はハンカチで鼻と口を二重に覆い、意を決して美術室の扉を開けた。
「思い出せ、思い出せ、思い出せ……ッ!」
佐倉がそこにいた。
彼は狂ったようにキャンバスに向かっていた。
パレットナイフではなく、素手で絵の具を叩きつけている。
赤、黒、青。色が濁り、混ざり合い、汚泥のような塊となって画面を埋め尽くす。
「佐倉、やめろ!」
俺の声など届いていない。
彼の手は傷つき、爪の間から血が滲んでいる。
絵の具と血が混じり合い、キャンバスの上でグロテスクな模様を描く。
部屋中に充満する匂いは、もはや致死レベルだった。
吸い込むたびに肺が痙攣し、視界が白く明滅する。
「描かないと……描けば、思い出せるかもしれないんだ。あの人の笑顔を、あの温もりを!」
「無理だ! それ以上やったら、お前の心が砕ける!」
俺は駆け寄り、彼の血まみれの腕を掴んだ。
佐倉が振り向く。
その目は血走り、瞳孔が開いている。人間のものではない、追い詰められた獣の目だ。
「触るなあああ!」
佐倉が腕を振り払う。
恐ろしい膂力だった。俺の体は軽く宙を舞い、イーゼルをなぎ倒して床に転がった。
「邪魔をするな! 僕は完璧でなきゃいけないんだ! そうしないと……そうしないと僕は、自分が何者かも分からなくなる!」
佐倉が叫び、再びキャンバスに爪を立てる。
ガリガリと、布が裂ける音が響く。
その背後で、目に見えない巨大な「不在」が、彼自身を飲み込もうとしていた。
棘を抜いた痕の空洞がブラックホールのように広がり、彼の自我を削り取っていく。
このままじゃ、こいつは「完璧な天才」という名の怪物になって、人間としての輪郭を失う。
俺はどうする?
逃げるか?
こんな悪臭、これ以上嗅いでいたくない。
俺は自分自身の後悔さえ直視できない、空っぽの臆病者だ。
他人の人生に責任なんて持てない。
『香月くんは、いつも綺麗だね。何も持ってないから』
いつか誰かに言われた言葉が、脳裏をよぎる。
そうだ。俺はいつも一歩引いて、汚れないように生きてきた。
人の後悔が臭いから。関わりたくないから。
傷つくのが怖いから。
制服のポケットで、試験管がカチャリと鳴った。
中身のない、空っぽのガラス管。
何も掴めない、何も残せない、俺の心そのもの。
(……ふざけるな)
奥歯を噛み砕くほど強く食い縛る。
目の前で、同い年の人間が、血を流しながら壊れようとしている。
そのSOSの「匂い」を、世界でたった一人、俺だけが知覚している。
ここで逃げたら。
一生、俺自身から「あのドブ川のような匂い」が消えない気がした。
一生、この空っぽの試験管を抱えて、独りで生きていくことになる。
「やめろって、言ってんだよ……ッ!」
俺は床を蹴った。
恐怖を、嫌悪感を、理性を、すべて置き去りにして。
「離せ! 殺すぞ!」
「うるせえ!」
暴れる佐倉の背後から、俺は彼を羽交い締めにした。
直撃する悪臭。
至近距離で嗅ぐそれは、もはや暴力だった。
胃の中身が逆流し、涙と鼻水が止まらない。
臭い。苦しい。気持ち悪い。
全身の細胞が「離れろ」と叫んでいる。
それでも、俺は腕に力を込めた。指が白くなるほどに。
「お前が忘れたなら! 俺が覚えててやる!」
佐倉の耳元で、喉が裂けんばかりに怒鳴る。
「お前は今、泣いてる! 誰かのために必死だった自分を、取り戻したくて足掻いてる! その痛みだけは、絶対に嘘じゃない!」
「香月……う、あぁ……」
佐倉の抵抗が弱まる。
彼の体は、小刻みに震えていた。熱い。火傷しそうなほど熱い。
「思い出せなくてもいい! 今、ここで、お前が苦しんでることは、俺が全部知ってる! だから……もう自分を傷つけるな!」
それは、俺の人生で初めての「暴露」だった。
自分の殻を破り、不快感や恐怖をねじ伏せ、泥だらけになって他人の心に踏み込む。
その瞬間。
バキンッ。
俺の胸の奥で、硬質な音が響いた。
心臓を覆っていた分厚いガラスが、粉々に砕け散る感覚。
鋭い痛みが胸を貫き、そこから熱い血液がドクドクと全身へ駆け巡る。
「が、はっ……!」
俺と佐倉は、もつれ合うようにして床に倒れ込んだ。
絵の具と汗と涙にまみれ、俺たちの境界線が溶けていく。
視界が、眩い白に染まった。
第四章 未来の雫
気がつくと、悪臭は消えていた。
いや、消えたのではない。
匂いの質が変わったのだ。
佐倉から漂っていたあの腐敗臭は、雨上がりのアスファルトのような、切なくも静謐な匂いへと変化していた。
冷たいけれど、どこか懐かしい。
それは「後悔」が浄化され、「受容」へと変わろうとする匂いだった。
そして、もっと驚くべきことが起きていた。
俺自身の体から、匂いがする。
古びた図書館の、陽に焼けた紙とインクの匂い。
埃っぽくて、不器用で、でも静かに物語を紡ごうとする匂い。
これが、俺か。
ずっと「自分がない」と嘆き、世界を隔てていたガラスが割れ、初めて自分自身の輪郭を感じることができた。
「……香月?」
腕の中で、佐倉が呆然と俺を見上げている。
顔中絵の具だらけで、酷い顔だ。
でも、その瞳には光が戻っていた。ガラス玉ではない、濡れた人間の瞳。
「ごめん。僕、どうかしてた」
「ああ、酷い顔だぞ。イケメン台無しだ」
俺は笑おうとして、顔をしかめた。
胸の奥が、ジンジンと熱い。
これが、殻を破った痛みか。それとも、他人の人生に触れた代償か。
カラン、と乾いた音がした。
床に転がっていた試験管を、俺は拾い上げた。
蛍光灯にかざし、息を呑む。
「……あ」
空っぽだったはずの試験管の底に。
一滴だけ、青白く発光する液体が溜まっていた。
それは、夜明け前の空を凝縮したような、凛とした色。
『未来の雫』
ふと、そんな言葉が浮かんだ。
俺が、他人のためになりふり構わず行動した代償として、砕けた殻の隙間から溢れ出した可能性の欠片。
試験管を透かして、佐倉を見る。
さっきまでの歪みは消えていた。
代わりに、彼の背後に幻影が見えた。
苦しみながらも絵筆を握り続け、泥臭く生きていく、数年後の彼の姿が。
決して「完璧」ではない。
悩み、傷つき、誰かを羨み、それでも前を向く、人間臭い姿。
そして、ガラスに映り込んだ俺自身の顔。
鼻水と涙でぐしゃぐしゃだ。
でも、その目は今まで見たことがないほど、強く、鋭く光っていた。
「見えた気がするよ」
俺は試験管を強く握りしめ、佐倉に言った。
「お前の失くした記憶は、戻らないかもしれない。棘を抜いた穴は、塞がらないかもしれない」
佐倉は身体を起こし、汚れた手で涙を拭った。
「それでも、生きていけるかな。こんな空っぽのままで」
「空っぽなら、これから詰めればいい」
俺は彼の手を取った。
絵の具と汗で汚れたその手は温かく、確かな脈動を伝えていた。
「俺たちがこれから作る記憶で、その穴を埋めていくんだ。嫌になるくらい、たくさんな」
佐倉が、くしゃりと笑った。
作り物ではない、不格好で、最高に人間らしい笑顔だった。
「……臭くないか? 僕」
「ああ、臭いよ。人間だからな」
俺たちは顔を見合わせ、泥だらけの美術室で笑い合った。
窓の外では、夕日が街を茜色に染め上げている。
試験管の中の雫が、その光を受けて、一瞬だけ黄金色に輝いた。
後悔の棘は、もうない。
でも、その傷跡は一生消えないだろう。
風が吹けば痛むし、雨が降れば疼くだろう。
それでも。
この「未来の雫」がある限り、俺たちは大丈夫だ。
俺は佐倉の肩を叩き、立ち上がった。
足取りは重いが、視界はクリアだ。
さあ、行こう。
悪臭と希望が入り混じる、この騒がしい世界へ。