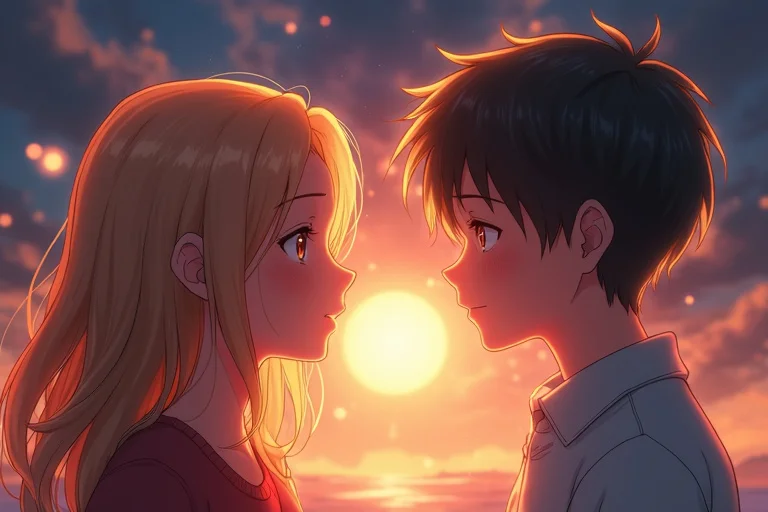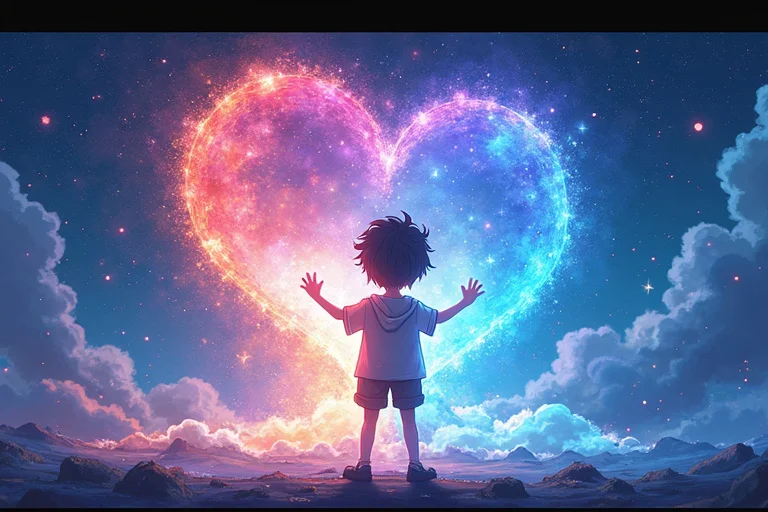第一章 ファインダー越しの未来
埃っぽい部室の隅で、俺、水島湊は祖父の形見である古いフィルムカメラを弄んでいた。ずしりと重い金属の感触。カチリ、と鳴るシャッター音だけが、退屈な放課後の空気に小さな穴を開けていく。写真部に所属しているとはいえ、俺には撮りたいものなんて何もなかった。ただ、ファイン-ダーを覗いている間だけは、ぼんやりとした未来への不安から少しだけ逃れられる気がした。
「湊、またそれ?骨董品いじりもいいけど、たまには撮ってこいよ」
部長が呆れたように言う。俺は曖昧に笑って、カメラを鞄にしまった。
その帰り道だった。なんとなく、踏切のそばに咲いていた紫陽花にレンズを向けたのは。特に意味はない。フィルムがもったいないとは思ったが、シャッターを切った。現像はいつも、駅前の古い写真屋に頼んでいる。数日後、出来上がった写真を受け取って、俺は息を呑んだ。
紫陽花の鮮やかな青紫の奥、ピントの合っていない背景に、何かが写り込んでいた。赤い自転車が、線路脇の柵に倒れかかっている。その時は、よくある光景だと気にも留めなかった。だが翌日、学校からの帰り道で、俺は全く同じ光景を目撃した。小学生の男の子が運転を誤り、赤い自転車がガシャンと音を立てて柵に倒れかかったのだ。写真と寸分違わぬ光景。背筋に冷たいものが走った。
まさか。偶然だ。そう自分に言い聞かせたが、胸のざわめきは収まらない。週末、俺は半信半疑のまま、今度は人の多い公園でカメラを構えた。噴水の前に立つ、見知らぬ家族。シャッターを切る。
そして数日後、現像された写真を見て、俺は確信せざるを得なかった。写真には、噴水の前で風船を飛ばしてしまい、泣きじゃくる少女の姿が写っていた。それは、まさに今日、俺が公園で目撃した光景そのものだった。
このカメラは、未来を写す。
非現実的な結論に眩暈がした。これは一体何なんだ。俺はこの力をどうすればいい?恐怖と、ほんの少しの興奮が入り混じった奇妙な感覚。そんな時だった。教室の窓から校庭を眺めていると、転校生が落とした画材を拾い集めているのが見えた。朝比奈陽菜。太陽みたいに明るい笑顔で、いつもクラスの中心にいる、俺とは正反対の人間。
衝動的に、俺は彼女にレンズを向けた。カチリ。乾いたシャッター音が、やけに大きく心臓に響いた。
第二章 太陽とシャッター音
写真に写っていたのは、階段の踊り場で、陽菜がスケッチブックを派手にぶちまける姿だった。撮影してから、三日後の未来。俺は、その瞬間が訪れるのを、まるで共犯者のように息を潜めて待った。
そして、運命の日の放課後。階段を駆け下りてくる陽菜の姿を認め、俺はさりげなく彼女の前に回り込んだ。「あ、危ない!」と声をかける。驚いた陽菜は足を止め、その拍子に抱えていたスケッチブックの紐がほどけた。しかし、俺がとっさに手で押さえたおかげで、中身が散らばることはなかった。
「あ、ありがとう!助かったー」
屈託なく笑う陽菜に、心臓が大きく跳ねた。これが、俺と彼女の最初のまともな会話だった。
「水島くん、だよね?写真部なんだって?」
「あ、うん……」
「すごい!私、絵を描くのが好きなんだ。今度、水島くんの写真、見せてよ」
太陽に真正面から向き合ったみたいに、目が眩んだ。
それから、俺たちの距離は急速に縮まっていった。俺はカメラの力を使って、陽菜に降りかかる小さな不運を、まるで予知能力者のように回避してみせた。雨に降られる前に傘を差し出したり、彼女がなくしそうになるキーホルダーを先回りして見つけたり。陽菜は「水島くんってエスパーみたい!」と無邪気に笑った。俺は真実を言えない罪悪感を抱えながらも、彼女の笑顔が見られるなら、それでいいと思っていた。
いつしか俺のカメラは、陽菜の姿ばかりを追うようになっていた。屋上で空を見上げる横顔、絵筆を走らせる真剣な眼差し、友達と笑い合う一瞬の表情。彼女をファインダー越しに見つめるたび、モノクロだった俺の世界が、鮮やかな色彩を帯びていくのを感じた。撮りたいものが、初めてできた。
「湊くんの写真、すごく好きだな」
ある日、現像した写真を見せると、陽菜はそう言って微笑んだ。
「なんていうか……そこにあるはずのない、未来の光まで写っているみたい。キラキラしてて、あったかい」
ドキリとした。彼女には何もかもお見通しなのかもしれない。俺は言葉に詰まりながら、ただシャッターを切り続けた。この輝くような時間が、永遠に続けばいいと願いながら。未来を写すこのカメラがあれば、きっとどんな困難も乗り越えられる。俺たちの未来は、きっと明るいものになるはずだ。そんな、根拠のない自信が芽生え始めていた。
第三章 夏祭りの夜、写ってはいけないもの
夏休みに入り、俺は陽菜を近所の夏祭りに誘った。人混みは苦手だったが、彼女と一緒なら、きっと最高の思い出になる。浴衣姿の陽菜は、夜店の灯りに照らされて、いつも以上に輝いて見えた。りんご飴を頬張る顔、金魚すくいに夢中になる姿。俺はそのすべてを、愛おしく思いながらフィルムに収めていった。
神社の裏手、少しだけ人の少ない石段に腰を下ろして、二人で夜空に咲く花火を見上げた。ヒュルルル、と音を立てて昇り、パッと開いては消えていく光の粒。その儚い美しさに、なぜか胸が締め付けられた。
「綺麗だね」
隣で陽菜が呟く。俺は、花火の光に照らされた彼女の横顔に、そっとレンズを向けた。この瞬間を、永遠にしたくて。
カチリ。
いつもと同じシャッター音。しかし、その時感じた胸騒ぎは、今までとは全く違う種類のものだった。
数日後、現像された写真を受け取った俺は、写真屋の前で立ち尽くした。そこに写っていたのは、夏祭りの陽菜ではなかった。白いシーツ。点滴のスタンド。そして、そこに力なく横たわり、青白い顔で眠る陽菜の姿だった。
血の気が引いた。手足が震え、呼吸が浅くなる。事故だ。いつ、どこで?俺はパニックに陥りながら、この最悪の未来を回避することだけを考えた。それからの俺は、まるでストーカーのように陽菜に付きまとった。道を歩くときは車道側を歩かせない。階段では必ず手すりを持つように言う。彼女の行動一つ一つに口を出し、危険から遠ざけようと必死になった。
当然、そんな俺の態度は陽菜を困惑させた。
「ねえ、湊くん。最近どうしたの?なんだか、すごく過保護だよ」
「そんなことない。心配だから……」
「心配って、何を?私、そんなに危なっかしいかな」
彼女のまっすぐな瞳から、俺は逃げるように目を逸らした。真実を話すわけにはいかない。だが、このままでは彼女との関係が壊れてしまう。未来を変えるための行動が、今を壊していくという皮肉。俺は苦悩の末、すべてを打ち明ける決心をした。
放課後の教室で、震える声でカメラの秘密を話した。未来が写ること。そして、病院のベッドに眠る彼女の写真を撮ってしまったこと。荒唐無稽な話だ。信じてもらえるはずがない。だが、陽菜は黙って俺の話を聞いていた。そして、俺が話し終えると、困ったように、でも、どこか穏やかに微笑んだ。
「そっか……未来、見えちゃったんだ」
そして彼女は、俺の価値観を根底から覆す、驚くべき事実を告げた。
「あのね、湊くん。私、生まれつき心臓に病気があるんだ。お医者さんには、もうそんなに長くはないって、ずっと前から言われてる。だから、多分その写真に写ってたのは、事故じゃなくて……病気が、悪くなった私だよ」
頭を殴られたような衝撃だった。じゃあ、俺が回避しようとしていた未来は、そもそも回避不可能なものだったのか。未来を変えるための力だと思っていたこのカメラは、ただ、変えられない残酷な運命を突きつけるだけの道具だったのか。俺は、陽菜の運命の上で、無力に踊らされているだけだったのか。
「ごめん……ごめん……」
俺は、それ以外の言葉を見つけられなかった。
第四章 永遠の一瞬
絶望に打ちひしがれる俺に、陽菜は静かに言った。
「謝らないで。むしろ、ありがとう」
「……え?」
「だって、未来が分かるなら、残された時間を最高に楽しいものにできるじゃない。やりたいこと、全部できるよ。湊くん、手伝ってくれる?」
その笑顔は、あまりにも強くて、眩しかった。俺は自分の無力さと、彼女の強さの前に、ただ涙を流すことしかできなかった。運命を呪い、未来を恐れていたのは俺だけだった。彼女はずっと前から、自分の運命と向き合い、今を懸命に生きていたのだ。
その日から、俺たちの最後の日々が始まった。
俺は決めた。未来を予知するためじゃない。変えられない運命に抗うためでもない。かけがえのない「今」を、陽菜という存在がこの世界にいた証を、永遠に残すためにシャッターを切ろう、と。
「海が見たい」「制服でプリクラが撮りたい」「屋上で一番星を見つけたい」。陽菜のささやかな願いを、俺たちは一つずつ叶えていった。俺はそのすべてを、写真に焼き付けた。ファインダー越しに見る彼女は、時折苦しそうに胸を押さえることがあっても、いつも最高に輝く笑顔を見せてくれた。もう、写真に未来の悲劇が写ることを、俺は恐れなかった。大切なのは、レンズの先にある彼女の、今の笑顔だけだった。
季節は巡り、文化祭の季節がやってきた。俺は写真部の展示で、一つのコーナーを借りた。そこには、陽菜の写真だけを並べた。笑う陽菜、怒る陽菜、泣きそうな顔で空を見上げる陽菜。たくさんの陽菜が、そこにいた。写真展のタイトルは、二人で決めた。
『永遠の一瞬』
その後の陽菜がどうなったのか、俺は誰にも話したことはない。ただ、文化祭の最終日、誰もいなくなった展示室で、彼女は俺の写真を一枚一枚、愛おしそうに指でなぞり、「ありがとう、最高の宝物だよ」と、今までで一番綺麗な顔で笑った。
それから、しばらく経ったある晴れた日。俺は久しぶりに、あのカメラを手にした。空に向けて、ファインダーを覗く。そこに写っていたのは、未来の光景ではなかった。ただ、どこまでも広がる、青すぎるほどの青空が、あるがままに切り取られているだけだった。
カメラは、もう未来を写さない。役目を終えたのかもしれない。それとも、俺がもう、未来を写してもらう必要がなくなったからだろうか。
俺はカメラを静かに下ろした。ファインダーを覗かなくても、俺の目には、陽菜と過ごした輝く日々が、未来へと続く確かな光となって見えている。悲しみも、切なさも、すべて抱きしめて、俺は自分の足で歩き出す。
彼女がくれた「永遠の一瞬」を胸に、これから先の、長い長い時間を。